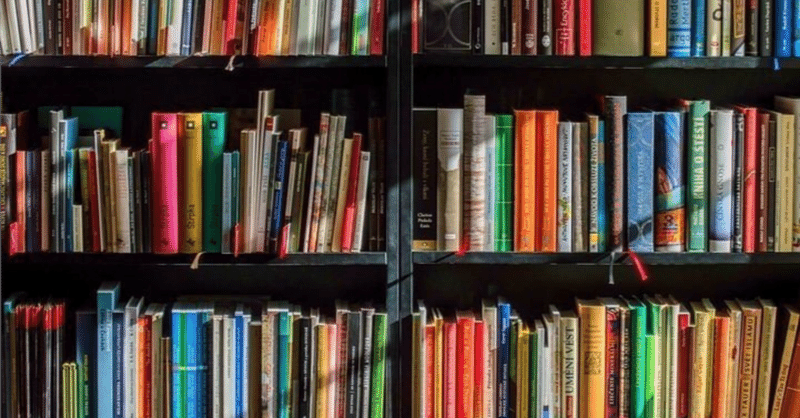
私の読んだ本のおすすめ(随時更新)
このnoteでは読んだ本について感想を述べていくよ。
Twitterでもおすすめしてるけど、こちらの方が感想長め。
気になったらみんな読んでみてね。
読んだ本のコメントとかくれたら嬉しいな。
1)コンテナ物語
船の上とか電車で運ばれている鉄の箱。
あの何の変哲もない金属の箱が世界の物流革命を起こしたものとは知らなかった。
コンテナ出現前後で世界の物流は指数関数的に増えているし、またこれにより世界の製造業のあり方までひっくり返ったとはこの本を読むまで想像もつかないだろう。
特に日本は島国でありコンテナなしでは生きていけない国だ。
そしてこのコンテナ輸送によって国の盛衰が決まる可能性がある。
私もシンガポールやドバイなどはこのコンテナ輸送で今日の地位を確立したことは知らなかった。
日本の未来を憂う人が多いが、私は米中対立により日本の製造業は再度盛り上がる可能性があると思っている。
ただ日本人は物流を軽視しがちだと思っており、この考えを変えないと再興の可能性は低くなると思う。
みんなに物流の大切さを知ってもらうために読んでもらいたい1冊だった。
合わせて読んでほしいおすすめ
コンテナ物語の中ではコンテナ輸送がベトナム戦争に与えた影響が書かれていた.戦争には輸送が欠かすことのできない最も重要といってもいい要素だ.そんな戦争と物流に関して説明してくれる本も合わせて読んでほしい.
専門的なことは書かれておらず,読み物として読むとちょうどいいと思う.
2)失敗の科学
「人は過ちを繰り返す」
この言葉は大好きなゲーム、Falloutで使われている名言だ。
この名言の通り人は間違いを繰り返してしまう。
間違いを犯すことは仕方ない、でも繰り返さないようにすべきだ。
ではなぜ失敗は起こるのだろうか?
人間が起こす失敗の原因とその対策を説明した本をお勧めしたい。
この本で取り上げられている失敗例で比較的ポジティブなものは、航空業界での失敗例だろう。
航空業界の歴史は血で書かれている。
航空機の事故は黎明期のみならず、近代でも多数起こっている。
ハドソン川のバードクラッシュなど覚えている人も多いだろう。
しかし航空業界は数々の失敗を乗り越えて改善を繰り返し安全性を高めてきた。これからもずっとそうだろう。
対してネガティブに書かれている業界がある。
医療業界だ。
この業界では航空業界のように失敗が人命につながるが、失敗に対するフィードバックが上手くいっていないと批判されている。
この指摘には医師の端くれである自分にも思い当たる節が多かった。
ただ当の医師達はこの問題に気づいていないと感じている。
私と同じ医師は特に航空業界の失敗に対する姿勢は、この本を読んで学んでいくべきだと思う。
読み物としても面白いのでオススメ。
合わせて読んでほしいおすすめ
同じ作者の『の科学』シリーズ.
昨今多様性の大事さが叫ばれているが,なぜ多様性が大事なのかを詳しく説明してくれている.
人類が現在の地位を確立した要因の一つに多様性があるとも述べられている.
この作者の本はすべて面白いから大好きだ.
3)Science Fictions あなたが知らない科学の真実
科学は人類の発展に欠かせないものだったし、これからもそうだろう。
しかしこの科学の発展に暗雲が立ち込めている。
科学は論文として出版されることで透明性を担保されてきた。
しかしこの出版プロセスに問題があると筆者は述べている。
科学雑誌が採用する論文は話題性がある結果を出したものだけであり、多くの「とるに足らないつまらない」論文が闇に葬られている。
この「つまらない」論文も科学の発展には大変重要であり、その分野の評価に寄与しているのに関わらず。
また学術界の問題もある。
有名な雑誌に掲載され、その論文が引用されることで科学者の評価は高まるが、逆に言えばその評価に科学者が翻弄されている。
その評価を高めるために質の低い論文を乱造したり、酷い場合には捏造を行うことすらある。
加えて喜ばしいことに科学者の数は増えており、その論文数も倍増しているが、科学の透明性を指示するための再現実験がほとんど行われていない。
著者は特にこの「再現性の危機」を危惧している。
私も『再現性』に関しては常日頃疑問に思っていた。
医師は論文を根拠に治療方針を決定するが、根拠の論文の再現を行なっているのかと。
ただこれらの危機に対する科学界の対応とこれからの展望も述べられている。科学は人類に不可欠なものであるが弱点もある。
この科学の弱点を知ることは、科学の恩恵に預かるためには必要だ。
エセ科学に騙されないためにも。
科学に携わる職業、また学生には読んでほしい。
合わせて読んでほしいおすすめ
サイエンスフィクションの中で意図的に研究結果を偽装する科学者の話が出てきた.科学者のいうことを盲信してはいけない.
さらに数字は嘘をつかないが,詐欺師は数字を使って騙そうとしてくる.
どうやって詐欺師が人を騙すのかを心理学者が解説してくれる一冊だ.
この作者は『見えないゴリラ実験』で有名だ
一度動画を見てみるといい.
あなたもきっと騙される.
4)サイコロジー オブ マネー
新NISAが話題になっており、日本の投資人口も増えてきている。
Youtubeなどでは「オールカントリー(略してオルカン)を買っとけばいい」とか「脳死で積み立て」とかの意見が多い。
私も概ねそれらの投資方法には賛成している。
リスクを低くしながら株式のリターンを得られるし、一度設定したあとはすることがほとんどないため、他に余力を向けることができるからだ。
だけど暴落は必ずくる。
十年に一度は暴落が来ると言われており、前回の暴落(2019年)から五年が経った。
新NISAから投資を始めた人は多いと思うし、次にくる暴落が初めての暴落となるだろう。
そんな時、今の方針を維持し続けることはできるだろうか??
この本は投資の説明というよりは「投資における心理学」を説明した本だ。
中にはお金についての考え方(マインドセット)が書かれており、暴落が起きた歴史とその際の人々の心理などが説明されている。
「暴落?ガチホしとけばいいっしょ!!」と考える人は多い。
だが暴落時に起こる心の乱れは想像以上だ。
冷静を保てる人は少ないと思う。
この本を読むことで得られることは、大多数の人のお金に関する心理学であり暴落が起こった際の「自身の心の揺らぎ」を予想することが出来る。
この本を読むかどうかで投資に対する心構えがずっしりと安定したものになると思う。
また来るべき未来の暴落で心が揺らいだ時、この本は精神安定剤になりうるだろう。
5)JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則
上で紹介したサイコロジーオブマネーより少し踏み込んだ内容の本。
かといって難しくなく端的に分かりやすい。
具体的にライフサイクルに沿って説明してくれるので、自分に合った資産形成の参考になる。
とはいえ一番重要な内容は題名にあるように「株または債券を買い続ける(Just Keep Buying)ドルコスト平均法」だ。
上述のサイコロジーオブマネーと比べるとデータ分析を重点としているので、しっかりとしてデータベースの投資としてのドルコスト平均法を理解することができるだろう。
将来にわたって参考になる本だと思う。
6)「モディ化」するインド―大国幻想が生み出した権威主義
米中対立が悪化していく昨今、日本を含む西側諸国が急接近しているインド。
ただ私たち日本人はインドのことをほとんど知らない
インドではヒンドゥー至上主義が蔓延しており、それに伴い司法が政府の言いなりになっている。
そしてこのヒンドゥー至上主義を牽引するために神格化されているのがモディ首相だ。
モディ首相率いる与党BJPはイスラム教徒への宗教的弾圧を行なっており、民主主義国家から中国やロシアのような権威主義国家に緩やかに移行していると筆者は警告している。
日本のメディアはほとんどインドのことを取り上げていないと思う。
このまま権威主義化していくようであれば、インドは西側諸国と協調していくのは難しいかもしれない。
私もインドのETFを購入しているが、この本を読んで購入量を減らしていこうと思った。
7)ロングゲーム 今、自分にとっていちばん意味のあることをするために
人は短期目線で考えすぎている.
これは悪いことではないが,人生は思ったより長い(ロングゲーム).
目先の出来事に振り回されずに長期の目線で物事を考えることの大事さを教えてくれる本だ.
自己啓発書にありがちなちょっと説教臭い面はあるかもしれない.
ただ長期の人生計画の立て方やその維持の仕方をこの本から通して学ぶことができると思う.
とくに私が納得したのが「人生は一つのことで満足できるものではない」ということだ.
会社で成功した人でも,その過去の栄光にすがるだけでは満足することはできない.だからこそどんな人でも新しいことにチャレンジし,そのチャレンジをし続けなければならない.
仕事が忙しくて新しいことなんてできない,そういう人もいるだろう.
そのような日々の出来事に追われている人は特にこの本を読んでほしい.
人生は長い,ただ無駄なことをしている暇はないんだ.
日々の雑用に忙殺される人生はこれを機会にやめよう.
8) 科学的根拠に基づく最高の勉強法
最初本を開いたときは「全然中身なくてスカスカじゃん!」と思って買ったことを後悔した.
でも作者の勉強法として,気になったことや学んだことは本に書いていくことを推奨しているので,そのための余白なんだと気付いた.
またあくまでも勉強法の紹介なので,この本は軽く読めるほうがいい.だから分量が少なくても問題ないと読みながら納得した.
肝心の勉強法だけど,はっきり言って珍しいものではなく普通に行ってるものだと思う.
ただ注意しなきゃいけないのは,ほとんどの人が勉強法を間違ってやっているということだ.
私は自分で勉強法を調べていたし,進学校から医学部に入ったため周囲はみんな勉強ができる人だった.
そのような環境にいた自分には当たり前の内容だが,そうでない人にとっては目からウロコの内容かもしれない.
学校は勉強は教えてくれるが,勉強法は教えてくれない.
無駄な努力で勉強が嫌いになるまえに,正しい勉強法を学ぶためにこの本を読むことをおすすめする,特に学生には.
9)「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論
現代社会は生産性を高めることに追われすぎている.
Twitterなどでも『朝活』や『仕事終わりの筋トレ』,『マルチタスクのライフハック』などが溢れている.
現代社会は人々に休むことなく働き続けることを強いている.
この状況にNOを突きつけるのが本書だ.
現代社会で「怠惰」とみなされていることは,本来人の生活に欠かせないものであり卑下されるものではないというのが作者の主張だ.
「だらだらベッドでスマホをいじってしまった」
「職場でぼーっとしていたら時間が過ぎていた」
「何もする気が起きず,学校の課題に手がつかない」
これらの状態は決して甘えからくる見下すべき行動や衝動などではなく,体が必要としている欲求なのだという.
たとえば本書ではネットで時間つぶしをすることはいい面もあると述べている.疲れ切った脳を休息させる効果があるのだ.
人間は連続して集中することなどできない.
にもかかわらず現代では「8時間座って仕事に集中すること」が当たり前だと思っている.
その考えを正すことで,むしろ生産性が上がることすらあるというのだ.
日々仕事に忙殺されている人は,この本を読んで欲しい.
自信を持って「ダラダラ」することができるようになると思う.
合わせて読んでほしいおすすめ
むしろ集中しすぎることでアイデアがわかなくなるという内容が書かれている.単純作業だと集中することも大事だが,新しい発想を行うときなどは集中しないほうがいいと私も思う.
散歩してるときとかにいいアイデアが浮かんできたりするしね.
怠惰を否定し働き続けることで身体と心に本当に必要な休息ができないとどうなるか?
注意散漫になりミスが起こりやすくなるんだ.
このようなミスで医療業界などで起こると致死的な状況に繋がり兼ねない.
しかし以前として医療業界では医療ミスにつながる超過労を続けている.
『失敗の科学』では,どのようにして人は失敗を起こすのか,そしてその対策の歴史を述べている.
この作者のシリーズは読みやすく,誰にでもおすすめしたい.
詳しくは上にもかいてあるよ.
怠惰を否定し,生産性を高めるために利用されている技術がある.
「ゲーミフィケーション=ゲーム化」だ.
これはあたかも貴方をRPGの主人公のように数値化することで達成感を与える手法だ.ランニング30日達成でメダル授与したり,新記録を出したらSNSで広めて皆からの称賛を浴びたりさせることで新たな報酬系を作り出す手法だ.
もちろん全てが悪いわけではないし,この手法を使うことで楽しく勉強をすることもできる(Duolingoなど)
でもこれは行き過ぎると貴方から「必要な怠惰」を奪いかねない.
ゲーミフィケーションに支配されず,逆に利用するためにはこの新しい手法を学ぶ必要がある.
よろしければサポートをお願いします。 いただいたサポートはビールと焼肉になり筆者の血と肉になります。
