
PDCAサイクルとは?トップセールスが徹底解説!
営業の皆さん、新入社員の皆さん。『PDCAを回しなさい』この言葉を
日頃先輩や上司から言われて、戸惑っていませんか?
・詳しく教わってないのに何言ってるんだろう、、、
・どういう意味なんだろう、、、
・実際そうすればいいんだろう、、、
本記事では、営業の皆様が感じている疑問を解消するために
日頃、新人営業マネジメント、管理職マネジメントなど専門にして
活動している私が【PDCAサイクル】について徹底的に解説していきます。
そもそもPDCAとは?
PDCAとは、そもそも
「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」
のそれぞれの頭文字を取ったものになります。企業の業務改善や業務効率化、それによって生産性向上を図るための考え方です。
PlanからDo、Checkと順に続けて行い、最後のステップであるActionまで終わったところで、また最初のPlanに戻ります。
これを『PDCAサイクル』と言います。
PDCAの各ステップですること
1,Plan/計画
2,Do/実行
3,Check/確認
4,Action/改善

PDCAを回し、成果を上げるには何をすればいいのか。それぞれのステップで、どのようなことに注意し、実行していくべきなのか解説します。
1,Plan/計画
Plan/計画
PDCAのスタートとなるPlan(計画)は、PDCAサイクルの成否を担う重要なステップです。課題認識や策定した計画が間違っていたり、現状分析の視点に偏りがあったりすると、PDCAを回す効果が薄れてしまうからです。この計画がPDCAの重きを占めます。
Planでは、下記の項目を検討します。
✅Planで検討したいポイント
現状の分析
目標と現状のギャップを洗い出す
対処すべき課題の検討
課題の数値化(KPI:重要業績評価指標)
実行計画の策定
現状のギャップの洗い出しや課題を検討する際には、「ロジックツリー」や「5W1H」などのフレームワークを有効活用して要素に分解し、課題を見える化しましょう。漏れなく、なおかつダブりがないように課題を抽出することがポイントです。
また、注意したいのは、目標数値が高すぎて現実的ではないケース。PDCAによる業務改善が実現しにくくなってしまうので、自社にとって適切な目標であるかどうかの検討が必要です。
補足:良くない例のPlanの立て方
例)『今月は300件電話して30件の来店確約をもらう。』
・なぜ良くないかの解説
30件の来店確約をもらう。→これは『結果』
この場合のPは『今月は300件電話する』になります。
これを理解していない上司、先輩が多いから『結果管理』になってしまい
プロセス管理が出来ない。
『今月は300件電話する』←ここに重点を置いてPDCAを回せば次工程への
ステップに転換することが可能になる。
2,Do/実行
「Do」では、計画を実行します。ここで注意したいのが「やりっぱなし」にしないことです。Checkの段階で、実行した内容を客観的に評価できるように、必要なデータを記録しておきましょう。ここでの記録は、いくつかの指標を選んで数値化しておくと評価者の主観が入り込まず、客観的な評価を下すことができます。
✅Doで注意したいポイント
計画をすぐにタスクレベルに落とし込み実行する
プロセスや結果の「事実」を記録する
計画と現実のギャップを把握する
実行するだけでは、Checkのステップで評価がしにくくなってしまうおそれがあります。重要なのは、Doで行った実行のプロセスや結果の活動内容を必ず記録しておくこと。記録すべきは「事実」のみです。
そして、成功したことだけを記録するのではなく、計画どおりにいかなかったもの、生じた課題などもすべて正確に記録しておきます。これはすべて、計画と現実のギャップを把握するためのもの。可能な限り数値化し記録しておけば、Checkのステップでより正確に客観的な評価ができるはずです。
3,Check/確認
「Check」では、実行した結果を評価します。なるべく数値を用いた、具体的な評価を行いましょう。一見、数値化できないような項目でも、アンケートや行動に関して発生する数値を用いれば、間接的な数値化が可能です。Checkの精度が高いほど、Actionにおける改善効果も期待できます。
✅Checkで注意したいポイント
計画どおり実施できたか(定量的な確認)
計画は妥当だったか
どんな成果があったか
評価は、単に「できた」「できなかった」と判断するだけでは何の意味もありません。「なぜそのような結果になったのか」の要因を分析し、気づきを得ることのほうが重要なのです。定量的なデータがあると、より有効な気づきが得られるでしょう。
要因分析によって、次のステップであるActionから、Planの再検討へとつなげていきます。
4,Action/改善
「Action」では、目標達成を実現する、あるいはさらに高い成果を生み出すために活動内容を改善します。改善点がまとまったら、Planに戻って改善点を取り入れた新たな計画を策定します。
✅Actionで注意したいポイント
改善策が複数あるときは、優先順位をつけて絞り込む
良かった点をもとに考察し、次の計画に活かす
悪かった点は改善案を検討し、次の計画に反映する
PDCAがうまく回っていても、目標を達成するため、さらに高い成果を出すためには計画や行動の改善が必要となるでしょう。行動の改善はもちろん、良かった行動をさらに伸ばすことも視野に入れます。一方で、改善の見込みがない場合は、計画そのものの中止という判断も必要となります。
ここで考察した改善のための仮説をもとに、再びPlan(計画)に戻り、PDCAサイクルをさらに回していくのです。
今ではPDCAサイクルは古いという声などもありますがまずは一歩ずつ
自分自信に仕組みを取り入れてルーティン化することが大事です。
日頃の営業活動の基盤になる部分ですのでしっかり仕組み化していきましょう。
PDCAが営業活動にもたらすメリット・デメリットとは?
PDCAが営業活動にもたらすメリット
営業活動の業務や事業そのものを改善できる
PDCAの最大のメリットは、企業がPDCAサイクルを着実に回し続ければ、営業活動などの業務、ひいては事業そのものを改善できるようになることです。
それらを改善させていくためのポイントは、Actionのステップで「うまくいった点」「うまくいかなかった点」をそれぞれ細かく要素に分解し、定量的に分析すること。これによって、根拠を持った仮説が立てられますので、新たなPlanから始まるPDCAにスムーズに移行できるはずです。
KPIやタスクを明確にできる
企業の営業活動においては、目標が明確でなければ具体的にどのような行動をすればいいかわからず、営業担当者のモチベーション維持も難しくなるでしょう。そこで、PDCAを活用し、計画やKGIを立てれば、ブレイクダウンしてKPIや日々のタスクが明確になっていきます。一人ひとりが「自分は何をすべきか」を理解し数値目標に向かって行動できるため、モチベーション維持も可能となるのです。
適切にPDCAの運用ができれば、常に目標(KPI)やタスクを更新し、営業担当者のモチベーションを維持し続けられるはず。
PDCAが企業の営業活動にもたらすデメリット
PDCAが形骸化する
PDCAは、業務改善など目標達成のための手段です。しかし、PDCAサイクルを運用し、慣れていくうちに、PDCAを回すこと自体が目的になっているケースがよく見受けられます。
PDCAが形骸化し、手段が目的化してしまうのは、PDCAの本来の意味や真の課題を理解できていないのが原因です。本質的な課題を理解しないままPDCAを回しても、業務改善にはつながりません。「目標や課題は何か、そのために何をしなければならないのか」を意識した上で、PDCAを回している意味を理解することが重要です。
イノベーションが生まれにくい
PDCAは、前例や過去の定量データなどの資料をもとに、Plan(計画)のステップから始めます。一巡目のPDCAが終われば次のPlanに移りますが、これは過去(一巡前)のPDCAから導かれたものです。
PDCAサイクルはPlanからActionまで、さらに次のPDCAへと連続することに強みがあります。つまり、「継続的な改善」にこそ価値があるのです。裏を返せば、PDCAは無から有を生み出すような新規事業開発などでの活用には向いていません。
イノベーションを生み出すようなフレームワークとしては、後述の「OODA」のほうが向いているといえるでしょう。

次のパートは企業の営業部門がPDCAサイクルをうまく回して成果を得るために、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。ここでは、PDCAを成功させる3つのポイントを解説します。
PDCAを成功させるための3つのポイント
1,「見える化」して計画を確実に実行する
2,「習慣化」して定期的に評価する
3,「仕組み化」して無理のない計画にする
1 「見える化」して計画を確実に実行する
PDCAにおいて、いかに完璧なPlan(計画)を立てても、次のDo(実行)が伴っていなければ、成果にはつながりません。PDCAのDoのステップにおいては、Planの実行が極めて重要なポイントになるのです。
計画どおりに実行できなければ、次のステップであるCheckで正当に評価できないどころか、Actionでの分析や仮説を立てることも、そして次へ続くはずのPDCAサイクルも回せなくなるでしょう。「実行しなければ成果が出ないなんて当たり前じゃないか」と思われるかもしれませんが、それほど「計画倒れ」に終わるケースは多いのです。思うように計画を実行できないときには、一人で抱え込まずに上司や先輩、同僚に相談・共有する体制を作ってみてください。第三者視点が加わると、「実行しなければならない」という緊張感が生まれるからです。
また、PDCAサイクルのDoに関して、プロセスや現状の課題などをデータとして記録するルールを設ければ、次のステップであるCheckで定量的に分析しやすくなります。このようなPDCAの見える化が、成功の秘訣のひとつです。
2 「習慣化」して定期的に評価する
PDCAを活用し生産性を上げるためには、進捗の定期的なCheck(評価)、Action(改善)が重要になります。定期的に各ステップの進捗確認や評価をすれば、PDCAサイクルのスピードを落とさずに、行動の精度を高めていけるはずです。また、日々のタスクもより明確なものになるでしょう。
うまく進捗できていない場合には問題点を洗い出す必要がありますが、日々の業務に追われている営業担当者は、CheckやActionのステップを後回しにしてしまうかもしれません。実は、CheckやActionをしなくても、仕事自体は回ってしまうのがPDCAの落とし穴なのです。
そこで、「毎週末の展示会後、30分間はPDCAの振り返りをする」など、スケジュールの固定化をおすすめします。CheckやActionを重点的かつ定期的に見直す機会を設け、細やかに検証、改善すれば、スムーズにPDCAを回せるようになり、成果も上げられるようになるはずです。
3 「仕組み化」して無理のない計画にする
PDCAの失敗の多くは、Planのステップで起きています。これは、計画や目標を立てるときに、理想が大きくなり、現実を踏まえていないものになってしまうことがあるからです。ともすれば、計画は机上の空論となり、実際の行動につながりにくくなります。さらに、目標が高すぎると営業担当者のモチベーションも上がらず、成果を上げること自体が難しくなるでしょう。
最初の目標は、無理のない範囲で「少しがんばれば達成できる」程度にとどめ、PDCAサイクルを何度も回していく中で目標を上方修正していく、また誰でも実行できるタスクにする、見える化・習慣化できるようにするなど、PDCAが回りやすい仕組みを構築することが成功への近道です。
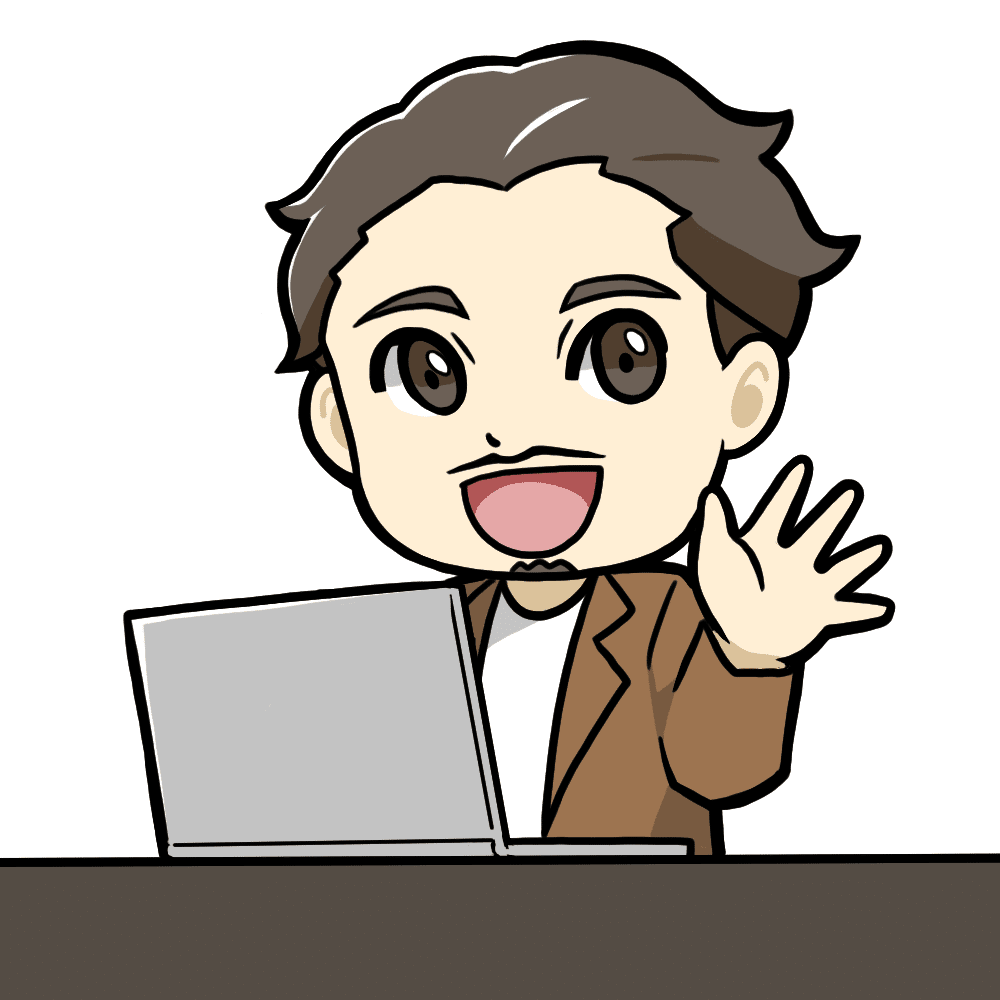
次のパートでは課題解決のためのフレームワークであるPDCA。しかし、PDCAを導入しても失敗することがあります。ここでは、PDCAの各ステップにおける、失敗しやすいポイントについてご紹介します。
PDCAの失敗要因とは?
1,Planの失敗要因
2,Doの失敗要因
3,Checkの失敗要因
4,Actionの失敗要因
1,Planの失敗要因
Planのステップでは、成果を追い求めるあまり「高すぎる目標を設定する」失敗が起きます。目標が高すぎると、営業担当者が「そんな目標はどうせ達成しない」とあきらめたり、モチベーションが下がってしまったりしてDo(実行)の精度が下がり、結果としてPlanが計画倒れになってしまいます。
評価者も高すぎる目標が基準では、担当者の営業活動を適切に評価できません。高すぎる目標によって気持ちが削がれると、高い成果も望めなくなりますので、計画に携わるメンバーは注意したいところです。
計画=やらされ感、にならないようにすることも大切です。
この時点でPlanが『絵に描いた餅』にならないよう気を付けましょう。
2,Doの失敗要因
Doステップでよくある失敗要因は、Planで設定した目標に対し「現場の取り組みが不十分なこと」でしょう。これは、トップダウンでPDCAを導入したケースで起こりやすく、営業現場でPDCAの重要性や目的が十分に理解されていないと、Doの部分がおざなりになってしまうのです。まずは営業担当者に、「なぜPDCAに取り組む必要があるのか」を説明し、理解した上で注力してもらうことが重要です。
また、行動記録の管理方法が担当者ごとにバラバラだったり、記録されるべきものが欠けていたりすると、良質なDoが行われていても、Check以降のサイクルの質が低下してしまうおそれがあります。操作が扱いやすいCRM/SFAなどを準備し、営業活動とそれに関連する行動を短時間で記録できる環境構築も重要といえるでしょう。
3,Checkの失敗要因
CheckはPDCAで、最もつまずきやすいステップです。よくある失敗の要因は「振り返りをしないこと」「評価基準があいまいなこと」が挙げられます。PDCAなのに振り返りをせず、やりっぱなしにしてしまうのは最も不毛な行為です。しかし、仮に振り返りをしたとしても、管理者のあいまいな評価基準では「全体的によくやっている」などの評価が下されたり、評価がバラバラになったりしてしまいます。また、評価基準がしっかり定まっていても、自部門の評価だけではどうしても評価が甘く、意図的でなくても改善点を見逃してしまうこともあります。
Checkは「評価」といいつつも、意味合い的には疑心暗鬼になって行われる「検証」と捉えるべきでしょう。売上や訪問件数などの目標は定量的に目標数値を設定し、目標に対する達成率を出すなどして冷静かつ客観的に評価を行う必要があります。厳密性を求める際には、他部門の評価者を交えて二重チェックを行うとより効果的です
4,Actionの失敗要因
Actionのステップでは、「改善の視点が少ない」ことによる失敗が挙げられます。業務改善においては「ECRS(改善の4原則)」があるとされています。ECRSとは、「Eliminate(排除)」「Combine(結合と分離)」「Rearrange(入れ替えと代替)」「Simplify(簡素化)」です。このように、少なくとも4つ以上の視点が必要となるのですが、営業担当者などの直感・経験や社内の前例のみでなんとなく改善策を導き出してしまうと、本質的な解決に導くことができなくなってしまうおそれがあります。
Actionでは、顧客目線や取引先目線なども含めた、あらゆる側面から分析します。そして、DoとCheckの内容・結果から、「なぜうまくいったのか」「なぜうまくいかなかったのか」をそれぞれ論理的に分析しなければなりません。最終的な目標達成に向けて何をするべきか、そのアプローチを検討していくと、当初は考えられなかったような新たな課題が出てくる可能性もあります。

1.PDCAとは?
「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」
のそれぞれの頭文字を取ったものになります。企業の業務改善や業務効率化、それによって生産性向上を図るための考え方です。
PlanからDo、Checkと順に続けて行い、最後のステップであるActionまで終わったところで、また最初のPlanに戻ります。
これを『PDCAサイクル』と言います。
PDCAが営業活動にもたらすメリット・デメリットとは?
メリット:
1.営業活動の業務や事業そのものを改善できる
2.KPIやタスクを明確にできる
デメリット:
1.PDCAが形骸化する
2.イノベーションが生まれにくい
PDCAを成功させるための3つのポイント
1,「見える化」して計画を確実に実行する
2,「習慣化」して定期的に評価する
3,「仕組み化」して無理のない計画にする
補足:計画の立て方
→時系列ごとに立ててPDCAを回すこともおすすめします。
例)
・デイリー計画
・ウィークリー計画
・マンスリー計画
日々の積み重ねが週の実績に繋がる
週の積み重ねが月の実績に繋がる
こういった捉え方ができればその都度修正を加えて日々の活動にも変化
が出て、モチベーション維持にも繋がるので繰り返し実行してみて下さい。
本記事も最後までお付き合い頂き有難う御座いました。
皆様が普段、悩んでいること、職場では聞けないこと、なんでも構いません
もし、日々の営業活動の中で足踏みしていることがありましたら
お気軽にお声掛け頂ければと思います、精一杯お力添えさせて
頂きますので、楽しんで自分だけの成功へのルーティンを作り上げましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
