
DJ Boonzzyの選ぶ2023年ベストアルバム トップ10(完結編)
今年も年内ギリギリのタイミングになってしまった「DJ Boonzzyの選ぶ2023年ベストアルバム」、ここまでのランキングはお楽しみ頂けたでしょうか。今年は昨年に比べてややメジャー寄りかな、とは思いますがそれでも皆さんがまだ聴いてなかったアルバムで一つでも興味を持ってもらえて、かつ楽しんでもらえたものがあれば最高ですね。では第4コーナー回って最後の10枚、トップ10をどうぞ。
10.AURORA - Daisy Jones & The Six (Atlantic)

このアルバムも、毎週の「全米アルバムチャート事情!」の記事をアップしていなければ多分アンテナに引っかからずスルーしてしまっていた可能性大だったんじゃないか、そんな作品。というのも、このデイジー・ジョーンズ&ザ・シックスというバンド、実在のバンドではなく、今年の3月から10話完結のミニシリーズでアマゾン・プライム・ビデオでストリーミングされたドラマ『Daisy Jones & The Six』の主役の架空のバンドなんです。もともと2019年、アメリカの作家、テイラー・ジェンキンズ・リード作の同名小説を映像化したもの。70年代にLAから登場して世界的なビッグバンドになりながら、その人気の絶頂に解散してしまうという、なかなかロックファンには胸躍るストーリーなんですが、このバンドのモデルになってるのが明確に『噂』期のフリートウッド・マックなんです!自分もこのアルバムに出会ってからすぐ、このミニシリーズを一気見してしまいましたが、スティーヴィー・ニックスに当たるデイジー・ジョーンズ役をライリー・キーオ(今年亡くなったリサ・マリー・プレスリーの実娘)と、リンジー・バッキンガムに当たるビリー・ダン役のサム・クラフリンの主演の二人がリアリスティックな体当たり演技で見応え満点。このアルバムはそのグループがリリースして全米ナンバーワンになった架空のアルバム、という設定ですがもちろん使われている楽曲もマックを大いに意識して書かれたものがほとんどで、アルバム2曲目の「Let Me Down Easy」なんて、イントロのドラムフィルから前のめりのギターリフが入って行くところ、そして2人がコーラスで絡むあたりなんて、ホントまんまマックやん!って感じ。これ、無茶苦茶褒めてます。
そんな今回のこのアルバムの楽曲全曲を共作・プロデュースしているのが、アラバマ・シェイクスのプロデューサーの仕事で知られるブレイク・ミルズ。共作者としてはマムフォード&ザ・サンズのマーカス・マムフォードが関わっている他、自分お気に入りのマディソン・カニンガムやジャクソン・ブラウン、そしてブレイクが初期に在籍した、これも自分大のお気に入りのバンド、ザ・ドーズのテイラー・ゴールドスミスなども制作に参加しているという、今のLA音楽シーンの蒼々たるメンバーを中心に作り挙げられた、単独のアルバムとしても素晴らしい出来になってます。ハイムやジェニー・ルイスといった、いわゆる「Rumours Children(マックの『噂』に影響されたアーティスト達)」のファンであれば間違いなく、そうでないあの頃のマックに夢中になったシニアの音楽ファンも絶対持って行かれる作品だと思うので、是非聴いて見て下さい。このシリーズのために1年間バンド練習を重ねたという、ライリーとサムの主演の2人が劇中も、そしてこのアルバムでも一切吹き替え無しで演奏してますが、なかなかの実力でそれがこのシリーズと作品に更に現実味を加味してます。ハイライトはドラマのクライマックスで、スタジアム満杯の観客を前に演奏する全米ナンバーワンヒット(という設定の)バラードで始まり、サビで一気にカタルシスに達する「Look At Us Now (Honeycomb)」。このミニシリーズ、まだアマゾン・プライム・ビデオで視聴可能なので(邦題が『デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃』というまるでイケてないのがイラッとするのですがw)こちらもお正月にでも是非。
9.Hackney Diamonds - The Rolling Stones (Polydor / Geffen)

今年は往年の大御所バンドの「新作」が2つ続いてリリースされた。一つがビートルズの「Now And Then」。そしてもう一つのこのストーンズのアルバム。「Now And Then」の方は賛否両論あり、往年のビートルズファンが喜ぶのも理解できるし、一方でジョン信者のファンが「あれはジョンの曲でビートルズじゃない」というのもまあ理解できるところ。ただ個人的には冷静に聴いてみて正直さほど感動やインパクトを感じるものではなかったですね、申し訳ないけど。でもこのストーンズのアルバムは全く違っていて、現役感満点で(まあ一応バンドは解散してないから当たり前といえばそうだけど、今の現役バンド感が凄いということ)聴いてて興奮を掻き立ててくれたのには、自分としても意外でしたね。もともと自分は中学生だった70年代前半にビートルズから洋楽に入って一時期はどっぷり浸かっていて、同時期に最初の活躍期を迎えていたストーンズは名盤『Let It Bleed』(1969)や『Exile On Main Street』(1972)も含めてほとんど当時通過しなかった、というのもあって、ビートルズに比べて感情移入度がまるで低いバンドでした。その後70年代後半に『Some Girls』(1978)『Tattoo You』(1981)といった名盤を相次いでリリースした第2期絶頂期には「おおなかなかいいではないか」と思ったけど、その後は正直あまり興味を持って新譜を追いかける対象ではなくなってたんですよね。
そのストーンズが自分の中でぐっと比重を増したのは、皮肉にも全曲彼らの出自の一つである古いブルース・ナンバーをカバーしたアルバム『Blue & Lonesome』(2019)で伝わって来たその圧倒的なパワーとバンド演奏を楽しんでる雰囲気。それでも今回のアルバムは聴くまでそんなに期待してた訳ではなかったんです。ところがところが!オープニングの「Angry」のカッコいいギターリフを聴いた瞬間にもう完全に持って行かれて、そのままアルバム全12曲、アップの曲もスローの曲もテンションを下げることなく一気に走り去ってしまうような彼らの演奏とミックのボーカルを聴いて、80歳前後のバンドのやってるレコードとは俄に信じられないパワーに「すごい。参りました」とつぶやいてましたね。もちろんミックとキースの年を知らないパワーもさることながら、このアルバムのもう一人の殊勲者は今回プロデュースに参加している、ポスト・マローンやマイリー、オジーなど今のポップ・ロック作品のヒット作を多く手がけているアンドリュー・ワットでしょう。ストーンズのバンドとしての揺るぎないミュージシャンシップを、コンテンポラリーな音楽シーンのコンテクストにフィットするような微調整をやってるのは彼に違いなく、その仕事が、ちょっと聴くと『Tattoo You』の頃のストーンズそのままに聞こえるけど、全くサウンドが古臭く感じられないという結果につながってますよね。こんなアルバムだされると、次のアルバム、真剣に期待しちゃいます。
8.Cousin - Wilco (dBpm)

ウィルコは、自分が数人の洋楽仲間と洋楽サークル「meantime」の活動をやっていた1990年代後半に『Being There』(1996年73位)で鮮烈にブレイクし、自分の音楽嗜好の二大軸の一つがアメリカーナ/ルーツ・ロックだと確信させてくれた(もう一つの軸はR&B/ファンク)自分にとっては大事な意味を持つバンド。その後名盤『Yankee Hotel Foxtrot』(2001)で、『Being There』で見え隠れしてたサイケデリックな感じが彼らの本質の一つであることを教えてくれて、更に彼らの音楽(というかリーダーのジェフ・トウィーディーの音楽)に惹かれる度合いが一気に増したものだ。ただその後『A Ghost Is Born』(2004)『Sky Blue Sky』(2007)と力のこもった意欲作を次々に出してくれてたものの、2009年の『Wilco (The Album)』(通称「ラクダアルバム」)の後リリースされる作品に対しては、初期ほどの興奮と共感を覚えきれずに来ていた。むしろその間ジェフがプロデュースしたメイヴィス・ステイプルズの3部作や、息子のスペンサー君とトウィーディ名義でリリースした『Sukierae』(2014)といった作品の方がいいな、と思う時期が続いていたので「ウィルコとしての活動も曲がり角かな」と思っていたところ。コロナを経て昨年リリースされた、思いっきりカントリーに寄せたアルバム『Cruel Country』もかなり地味な内容だったので、そういう感じがいっそう強くなったものだ。
で、今年届けられたこの『Cousin』。まず冒頭の「Infinite Surprise」でいきなり炸裂するノイズの嵐に、あの『Yankee Hotel Foxtrot』を思い出して思わず興奮してしまった。その後も久しぶりに聴く親しみやすいメロディのカントリー・ロック「Evicted」、ドラムマシーンの刻むビートとギターやベースなどバンド楽器の生音が不思議なゆらぎを造り出す中でジェフのたゆとうようなボーカルが魅力的な音像を造り出す「Sunlight Ends」、インディロック然とした曲調が新鮮なタイトルナンバー、アコギのシンプルなアルペジオのイントロから、シンフォニックなSEが一気にサイケデリックな世界観を提示する「Pittsburgh」などなど、各楽曲のサウンドのアイディアや提示のしかたにいろんな工夫の跡が見えるのに、全体が拡散したとっちらかった状態になっておらず、不思議な一体感を造り出していて、個人的には2009年のラクダアルバム以来純粋に楽しめるウィルコのアルバムになった。そしてここでも今回新たにプロデュースを担当した、ケイト・ルボンが提案したという「アルバムをスタジオ・ライブでレコーディングするんじゃなくて、一人一人の楽器の音を別々に取って、それを組み立てる」というアプローチがとっても有機的に機能してる気がする。デビュー以来完全にバンド以外のプロデューサーにアルバムを委ねたことのない彼らが今回トライしたアプローチが機能して、またウィルコの魅力が新たに感じられるようになったという意味でも、このアルバムは自分にとって今年大事なアルバムの一つでした。
7.Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd - Lana Del Rey (Interscope / Polydor)
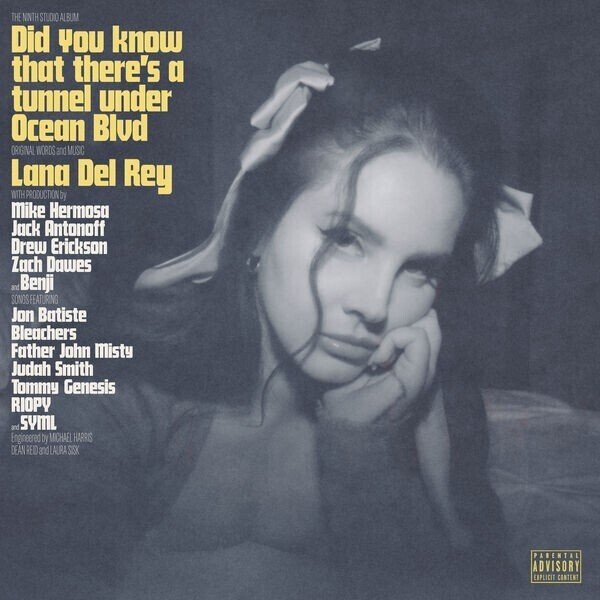
前々作『Chemtrails Over The Country Club』(2021年2位)ではケムトレイル説(飛行機雲が白いのは、燃料が燃える煙ではなく、化学物質が排出されているという陰謀論)に言及し、今度はカリフォルニアのロングビーチにあると言われる封鎖された地下トンネルにヒントを得たというタイトル。ラナのアルバムって、毎回タイトルだけでもいろんな想像力を刺激してくれるね。そんな今回のアルバムは、エレクトロ/ヒップホップに寄り添っていた『Lust For Life』(2017年1位)、メインストリームなロック路線の『Norman Fucking Rockwell』(2019年3位)、フォーキッシュなシンガーソングライター・スタイルの『Chemtrails〜』から今度はとても多様なスタイルとアレンジの楽曲がオモチャ箱のように詰め込まれた作品になってて、『Lust For Life』以降ラナとタッグを組んでるジャック・アントノフがテイラーやSt.ヴィンセント、クライロといったいろんな他のアーティストとの仕事から得た視点やアイデアをかなりインプットしたんじゃないか、そんな感じを受けるアルバム。
今回も『Norman〜』に続いてグラミー賞の最優秀アルバム部門にノミネートされてるけど、加えてソング・オブ・ジ・イヤーにノミネートされてる「A&W」なんて前半アコギ中心のフォーキッシュなポップ・ソングなのに後半急にトラップ・ポップに変貌するという、ある意味プログレ的展開の7分超の大作だし、ここ数年話題のジョン・バティーストをフィーチャーした叙情的でドリーミーなピアノ・バラードの「Candy Necklace」の後の「Kintsugi」「Fingertips」「Paris, Texas」などはミュージカルの一場面でのヒロインのモノローグを思わせるようなピアノをバックに歌うラナの存在感がじわじわ増してくる展開。それも含めてアルバム後半は彼女のここ数作のスタイルである、浮遊感たっぷりのサウンドスケープにラナのドリーミーなボーカルで彼女一流の世界観を作り上げてる。そしてアルバム最後はドリーミーポップな前半から『Norman〜』で評価を集めた「Venice Bitch」の初期バージョンを含むオーケストラ・トラップ・ポップとでもいうべき壮大な後半にこれもプログレ的に展開する「Taco Truck x VB」で幕を閉じるこのアルバム、聴き終わった後のラナの存在感の残像が半端ない。静かに静かにやってきて知らない間に聴く者を包み込んでしまう、そんな感じで今回もラナにやられました。
6.But Here We Are - Foo Fighters (Roswell / RCA)

フーファイのこのアルバムを一言で言い表すとすると「テイラー・ホーキンスが亡くなったことへの悲しみと喪失感がそこら中に刻み込まれたアルバム」。そもそもタイトルからして「それでも僕らはここにこうしている」という、バンドの存在意義(レゾン・デートル)確認の表明だし、アルバムの第一弾シングルでアルバム冒頭を飾る「Rescued」も「今僕らは救われるのを待っている」と、このやりきれない状態からの救いを求める内容だ。でもしかしだ。その「Rescued」にしても、「いつか君のことから抜け出すよ」と叫ぶ、次の「Under You」にしても、ここ数作のフーファイの作品で感じられなかったような勢いと、感情のほとばしりが強く感じられる演奏で、しかもキャッチーな楽曲でストレートにこちらの胸に飛び込んでくるのがたまらない。哀愁たっぷりのギターリフに始まる、今回初めてデイヴと娘さんのヴァイオレットとの美しいデュエットが実現した「Show Me How」も「君は今どこにいるの?君をどうやって見つけたらいいか、誰が教えてくれるの?」と切々と訴える歌詞だが、あくまでバンドの演奏はタイトであり、テイラーを失ったことに対してバンドが前を向いて歩んでいこう、という決意がちゃんと感じられる、そんな曲だ。
このアルバムのレコーディングはテイラーが亡くなった後だったので、全曲デイヴがドラムスを叩いているというのも、アルバム全体のサウンドが久しぶりにタイトになっている要因なのかもしれない。しかしちゃんと後任のドラマーは、ガンズやパーフェクト・サークルのドラマーだったジョッシュ・フリースがアナウンスされて、今年の7月のフジロックで2日目のヘッドライナーを務めた彼らの素晴らしいライブでもジョッシュが全曲渾身のパフォーマンスを見せてくれていた。「All My Life」でパワフルにスタートしたそのライブでも、このアルバムから「Rescued」「Under You」をやってくれたが、つまるところはテイラーの件に折り合いを付けるために一番重要なのがこの2曲だということなんだろう。そしてこのアルバムはテイラーの死を悲しむと同時に、それにも関わらずバンドは前に進んで行くんだ、という決意表明のアルバムなんだろうと思う。だからこそ、フーファイのファースト・アルバムの頃を想起させる、ストレートで、力強く、直接胸に響いてくる演奏と歌で聴く者の感情を掻き立ててくれるんだろう。新たなフェーズに踏み出したフーファイを今後も見守って行きたい、そう思わせてくれるアルバムだ。
5.Jaguar II - Victoria Monét (Lovett Music / RCA)
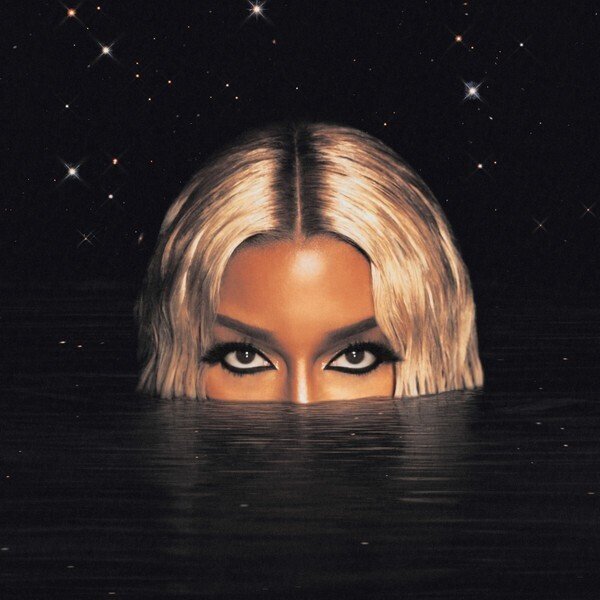
今回の第66回グラミー賞のノミネート発表でも例年どおりいくつかのサプライズがあったが、その中でもことに目を引いたのが、R&Bシンガー、ヴィクトリア・モネのレコード・オブ・ジ・イヤー(「On My Mama」)、新人部門、最優秀R&Bアルバム部門を含む7部門ノミネートだろう。昨年の第64回でジョン・バティーストが11部門ノミネート(うち最優秀アルバムを含む5部門受賞)した時のように「誰?」という洋楽ファンも多いだろうけど、ジョン同様、ヴィクトリアもこれまでシーンではアリアナ・グランデの「Thank U, Next」の共作などでソングライターなどの実績を積み上げて来た実力者で、グラミー・アカデミーのメンバー(アーティストやプロデューサー、ソングライター達)はちゃんとその辺を知っていて彼女のこのデビュー作と、その優れた内容にちゃんと反応したということなんだろう。もちろん彼女の歌唱も素晴らしいし、アルバム全体をプロデュースしてるDマイル(ご存知シルク・ソニックのプロデューサー兼仕掛け人の一人)も手堅く、いい仕事をしているからこそ出来上がった作品。この年間アルバムランキングで再三「最近のブラック・ミュージックのいいやつはUKから来ることが多い」と言ってるけど、今年アメリカ発のR&Bレコードの中では、クリス・ブラウンの新作などと並んで数少ない質の高い作品の一つだと思う。
もちろん全曲の歌詞を書いているのも含め、全曲彼女自身が共作してる全11曲はいずれも70年代のソウルが輝いていたころのオーラをまとった曲ばかりで、我々のようなソウル・ラヴァーとしてはたまらないところ。いきなり自分ご贔屓のラッキー・デイをフィーチャーしたコンテンポラリーなナンバー「Smoke」で始まるアルバムは、70年代半ばのミニー・リパートンやヴァレリー・シンプソンといった先達達を彷彿とさせる素晴らしいバラード「How Does It Make You Feel」、そして母親であることをポジティブにこれまた70年代ソウル風トラックに乗せて高らかに歌う「On My Mama」で一つのクライマックスに達して、その後自らの愛娘のヘイゼルをエンディングにフィーチャーして、何とアース・ウィンド&ファイヤのヴァーダイン・ホワイトをコーラスに迎えた「Hollywood」では正に『Gratitude』の頃のアースのメロウなサウンドを思わせるような、ドリーミーなメロディでシニアなソウル・ファンなら昇天すること間違いなし。グラミー賞本番でどの程度検討するか大いに興味をそそられるところだけど、今年のR&Bレコードの中で一、二を争う作品であることは間違いない。
4.Stick Season - Noah Kahan (Mercury / Republic)

クリス・ステイプルトンのところで「今年はアメリカーナ/ルーツ・ロック系、特に若いアーティスト達にいい作品が多かった」と言ったけど、このノア・カーン(日本ではノア・カハンという表記になってるみたいだけど、彼のインタビュー動画などを見ると「カーン」と言ってるのでこの表記にします)もそんなアーティスト達の中でも特に今年強い印象を与えてくれたアメリカはヴァーモント州出身のシンガーソングライター。このアルバムはもともと昨年10月リリースなのだけど、オリジナルの14曲に7曲のボートラを追加(ポスト・マローンとのデュエット・ヒット「Dial Drunk」を含む)した『Stick Season (We’ll All Be Here Forever)』バージョンが今年6月にリリースされているので、実質今年のアルバムということで選ばせてもらっています。彼は基本フォーク系のシンガーソングライターなんですが、明らかにボン・イヴェール以降の21世紀的オルタナ・音像ロックや、マムフォード&ザ・サンズ、ルミニアーズあたりの伝統の香りを感じさせるアメリカーナ・フォーク・ロックあたりの影響を強く感じさせるアーティスト。曲の題材としては自分が住むアメリカ北東部の、特に秋から冬にかけては荒涼とした自然をバックにしているものが多いのに、聴いていると彼の歌う情景が鮮やかに脳内に広がってくる、そんな感覚を持たせてくれるものが多いのです。
このアルバムがブレイクしたきっかけは、今年半ばにTikTokにアップしたヴァーモントの自然のことを歌ったタイトル曲(「Stick Season」というのはハロウィーンの後、雪が降り始める前の時期、あたりが枯葉が落ちた木々だけになってしまう時期のことを呼ぶ地元ニューイングランド地方の表現だそう)が、なぜかアイルランドでバズって現地で7週間1位を記録するというヒットになったことがきっかけで、全米でもオルタナティブ・アルバム・チャートやアメリカーナ/フォーク・アルバム・チャートなどで首位を獲得、そこに6月のデラックス・バージョンのリリースとポスティをフィーチャーした「Dial Drunk」(最高位25位)のヒットも重なって全米アルバムチャートでも一気に3位に昇るブレイクとなりました。マムフォードを彷彿とさせるスケールの大きいフォーク・ロック「Northern Attitude」や「She Calls Me Back」など、それだけでも魅力的な楽曲が詰まったアルバムなのですが、今年後半はこれらの曲に他のアーティストをフィーチャーしたバージョンをリリースする(前者はホージャー、後者はケイシー・マスグレイヴス)など、プロモーションにも怠りのないノア。こういう間口の広さもトラディショナルな音楽スタイルにもかかわらず、今時のアーティストのいい面を存分に発揮している気がします。今後の成長と次の方向性がとっても気になる、来日したら是非観に行きたいアーティストですね。
3.The Record - boygenius (Interscope)

さていよいよトップ3。これくらいの順位になると正直どれを取っても今年最高に気に入っていたアルバム、ということになるのですが、敢えて順番を付けるのであれば、ということで3位に選んだのは、既によくご存知の方も多い、フィービー・ブリッジャーズ、ジュリアン・ベイカー、ルーシー・ダカスの3人の強力なインディ・ロック系シンガーソングライター達によるスーパーグループ、ボーイジニアスのデビュー・アルバム『The Record』です。そもそもフィービーもジュリアンも、しばらく前からそれぞれの作品に強く惹かれていて、フィービーの『Punisher』(2020)はその年の自分の年間6位、ジュリアンの『Little Oblivion』(2021)は10位とこれまでも自分のランキングに入れてきたわけで、その彼女らが束になってかかってくるこのボーイジニアスというグループが好きにならない訳がないわけで、彼女達が2018年にリリースしたEP『boygenius』もかなり繰り返し聴いていました。今年2月には念願のフィービーの来日公演にも出かけていって彼女の芳醇な作品の世界を堪能したのですが、このグループの素晴らしいのは、基本全曲3人の共作なのに曲ごとにそれぞれのスタイルを感じさせるような微妙な違いがあって、それでもボーイジニアスとしての作品としての統一感は維持されてる点でしょう。
その3人が一体となって紡ぎ出した典型的な楽曲で、3人のアカペラコーラスの「Without You Without Them」で始まるこのアルバムは、ジュリアンがボーカルを取るパワフルなバンドサウンドの「$20」、シンプルな演奏にドリーミーなフィービーのボーカルが乗る、いかにもフィービーの世界観という感じの「Emily I’m Sorry」、インディーロック王道といった感じのルーシーの「True Blue」、ジュリアンがポール・サイモンにインスピレーションを得たという「The Boxer」を思わせる「Cool About It」、そして今回第66回グラミー賞のレコード・オブ・ジ・イヤーにノミネートされた、90年代インディー・ロックの香りを湛えた、3人が交互にボーカルを取る「Not Strong Enough」とアルバム前半まで流れるように3人のスタイルと世界観が見事に渾然一体となった楽曲が続きます。アルバム後半もレナード・コーエンをトリビュートした「Leonard Cohen」や、自分達の最初のEPの曲の一節を含んでいて、清冽な美しさで静かにアルバムの最後を飾る「Letter To An Old Poet」などの楽曲でその統一感というか、静かなテンションを維持したままアルバムは完結します。ボーイジニアスとしてのツアーもこのアルバムを受けて今年アメリカでは行われたみたいなので、是非来年はボーイジニアスとして来日してくれるといいんですが。絶対素晴らしいライブになること請け合いです。それまではこのアルバムを聴いて心待ちにすることにします。
2.Zach Bryan - Zach Bryan (Belting Bronco / Warner)

正直今年の1位と2位はどっちをどっちにするかかなり悩みました。結局最後の決め手は今年そのアルバムやアルバムの楽曲を聴いた回数くらいしかなく、今年8月にリリースされたこのザック・ブライアンのセカンド・アルバムがそれでも本当の僅差で今年の自分の年間2位、ということになりました。昨年『American Heartbreak』でメジャーシーンにブレイク、そのハートランド・ロックな匂いをプンプンさせながら、アメリカの保守層が強い地域であるオクラホマから出て来た若者が、赤裸々に自分の内省的な感情をストレートに表現し、矛盾や問題だらけの今のアメリカに白人として暮らすことの忸怩たる思いと怒りを静かに表現する、その等身大のスタイルのカッコ良さにシビれた人は多かったんだと思うし、自分も「Something In The Orange」を聴いた時にビビッと来た一人。スタイルはカントリー・フォークながら、明らかにその表現手法はロック以外の何者でもない、そんなザックは70年代にスプリングスティーンがニュージャージーでやろうとしていたことを、21世紀の社会に住む若者のセンシビリティで、しかもアメリカ中西部でやってることにも大きな意味があると思う。そうそう、彼が沖縄生まれというのも彼にシンパシーを感じる結構重要な要素の一つ。
そのザックが、前作の『American Heartbreak』がまだロック・アルバムチャート首位(トータル21週1位)から落ちてわずか1ヶ月、アメリカーナ/フォーク・アルバムチャートでは首位(トータル61週1位)から落ちた翌々週に、切れ目なくリリースしてきたのがこのアルバム。前作が、ザックがこれまで書きためてきた私小説のドラフト集的なたたずまいを見せる飾りのないシンプルな楽曲集、的なイメージだったところから、今回は収録されている楽曲が一段存在感と説得力を増したように思えるのはやはり彼自身今回の成功とそれに対する周りの反応を受けて一段成長した、ということもあるんだろうと思う。アルバムオープニングの「Fear And Friday’s (Poem)」アコギ一本をバックの武骨なザックの語りから、正しくハートランドなロックナンバー「Overtime」になだれ込んでいくあたりを聴くと、スタイルはスプリングスティーンの『The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle』(1973)なんだけどそのスケールの大きい表現力は『Western Stars』(2019)の壮大さすら感じさせて、これだけでもザックの才能の奥深さが充分感じ取れるんじゃないかな。あと、前回はザックがアコギか自分のバンドだけでやってたけど、今回はサザン・ソウル・デュオのザ・ウォー&トリーティや、アメリカーナのルミニアーズなど、いくつかのアーティストとの共演もやってるあたりは、ザックの懐が一つ広くなったと言う点で歓迎すべき展開だと思う。特にケイシー・マスグレイヴスとのデュエット「I Remember Everything」でのためらうようなザックの剛とパッと光を放つようなケイシーの柔のぶつかり合いが起こす化学変化の雰囲気は、往年のウェイロン・ジェニングスとジェシー・コルターのデュエットを思い出さずにはいられなかったな。先日友人が今年オープンした某70年代ルーツ系ロック中心のレコード・バーにこのアルバムを持参してかけてもらっていたら、カウンターにいた見ず知らずの同年代のお客さん数人が「これ、カッコいいな!」と言ってくれたのが何だか無性に嬉しかった。そうだよな、今の若い洋楽ファンももちろん聴いて欲しいけど、70年代のロックやソウルを通り過ぎてきた同じくらいの世代の洋楽ファンにこそ、ザック・ブラウンを聴いて欲しい。きっと胸に響いてくるものがあるから。
1.SOS - SZA (Top Dawg / RCA)

そして2023年のDJ Boonzzyが選ぶ年間アルバム・ランキングの1位は、SZAの『SOS』でした。先ほど「1位と2位の差は聴いた回数の差くらいしかない」と書いたけど、昨年12月にデジタルとストリーミングのみでリリースされたこのアルバム、5月に待望のヴァイナルとCDがリリースされた、という媒体のリリーススケジュールも大きくこのアルバムの自分の(そして多くの洋楽ファンの)今年の作品群の中での位置づけを大きなものにした、結構重要な要素だったように思う。一通りこのアルバムに親しんだところで、新たなメディア(自分の場合ヴァイナル)で再度このアルバムをよりよい音楽環境で再体験できたわけだから。また、リリース当時から、このアルバムの楽曲群がエレクトロなサウンドスケープを基調にしながら、オーガニックなR&Bの雰囲気満点のトラックをバックに、涼しげな歌声を響かせるSZAの存在感が圧倒的で、それが彼女が前作からのこの5年間で書きためた数々の楽曲の魅力を増幅させていると感じていた。このアルバムがリリースされた直後の昨年の年末年始は、スポティファイでこのアルバムをエンドレスにプレーしながらいろんな仕事や執筆作業をする、というのがある意味自分のワークスタイルに定着してしまったというのも、このアルバムが2023年の自分のサウンドトラックとして欠かせない作品となった理由の一つかな。
アルバム自体は、「Kill Bill」「Snooze」の2大R&Bヒットが代表するようなコンテンポラリーなR&Bスタイルの楽曲に加えて、フィーチャーされたトラヴィス・スコットがただの歌伴ラッパーになってしまっている「Open Arms」では90年代〜2000年代王道R&Bの香りが強烈に感じられるボーカルを堪能させてくれたり、我らがフィービー・ブリッジャーズをフィーチャーした「Ghost In The Machine」では今時の女性シンガーソングライターの浮遊感溢れるインディロック的トラックをフィービー共々軽々と乗りこなしてみせ、ビョークとオール・ダーティ・バスタードというある意味両極端のサンプリングを駆使した「Forgiveless」ではメロディック・ラップもこなすなど、SZAの楽曲とパフォーマンス力の高さを証明するショーケースにもなっていて、聴けば聴くほどのめり込んでいける造りになってる。そしてこのアルバムに魅了されたのは自分だけでなく、うちの末娘もスポティファイのプレイリストに組み込んでて、今年一年を通じてことあるごとにSZAの曲を流していたくらいなので、もう我が家の今年のサウンドトラックの一部として完全に機能していた感がある。大方の予想通り、今度の第66回グラミー賞では最優秀アルバム部門や最優秀プログレッシヴR&Bアルバム部門など9部門でノミネートするなど、名実共に2023年アメリカ音楽シーンの顔に飛躍した感のあるSZA。アルバム部門はテイラーやオリヴィア・ロドリゴ、ラナ・デル・レイそしてボーイジニアスといった蒼々たる面々との史上希に見る激戦が予想されるけど、このアルバムの完成度と圧倒的な存在感からいって、SZA受賞の可能性は充分あると思ってます。その辺はまた年明けから始めるグラミー賞各部門大予想ブログの方で。
ということで何とか大晦日には間に合った「DJ Boonzzyの選ぶ2023年ベストアルバム・トップ40」いかがでしたか?いつものことですが、ご紹介したランキングが皆さんの今年の洋楽のふり返りや、新たなアーティスト・アルバムとの出会いにお役に立てばうれしい限りです。今回も昨年に続いて、今年のトップ40アルバムから一曲ずつ選んだSpotifyのプレイリストをラストに付けておきますので、お正月のサウンドトラック等にお使い頂ければ幸いです。
では次は年明けにスタートする第66回グラミー賞各部門大予想のブログでお会いしましょう。皆さまどうかよいお年をお迎え下さい!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
