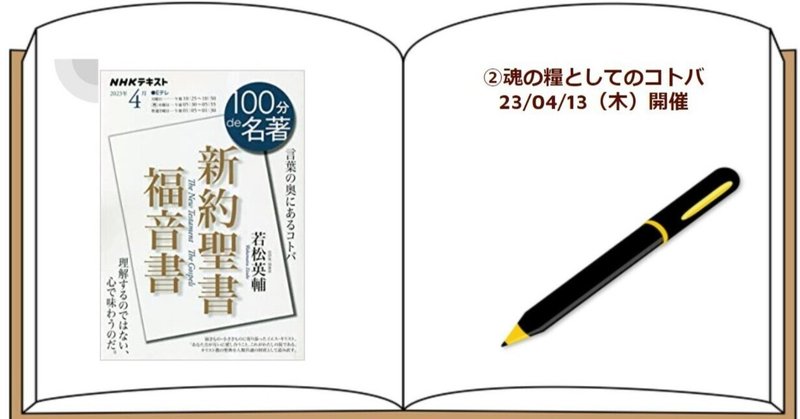
【100分de名著を語ろう】2023年4月度『新約聖書』福音書②魂の糧としてのコトバ
こんにちは。
23/04/13(木)21時から、clubhouse「100分de名著を語ろう」ルームで使う「レジュメ」をお届けいたします。番組をご覧になれなかった、テキスト未読等であっても、概略がつかめるようにしたつもりですので、ぜひお目通しください。
今回のポイントは、主として情報をやりとりするツールとしての「言葉」の奥、あるいは背後にある、意味の顕われとしての「コトバ」があるということだと思われます。この使い分けは、若松英輔さんの思想を読み解こうとするときにもキーとなる概念だろうと思います。聖書の「言葉」を、その字義通り情報として受け取ろうとすると、非合理と判断されてしまいますが、その奥や背後にある「コトバ」を探ろうとすれば、豊かな世界が開けてくるように思われます。
1)言葉とコトバ
コトバが、いかに人間に届きにくいかということが語られているのです。
忘れがちですが、私たちもまた、自分の世界をコトバでつくっているのです。
一つのコトバをそこに与えるだけで、その存在どころか周囲との関係まで変えてしまう。そんな力をコトバはもっているのです。
2)「ただ、お言葉をください」
皆さんにあることを試みていただきたいのです。それは言葉を重層的に読むということです。
石が「パン」になる、とは、役に立たないはずのものが、この世の価値あるものに変わるということです。
だからこそ、彼は部下に永遠なるものを届けたいと願った(略)イエスのコトバこそ朽ちることのないものであることを熟知しているのです。
3)なくなることのないパン
しかしイエスは、それだけに終わらない何かを、私たちは深いところで求めている、自分で感じているよりも深く、真実味のあるものを希求している、というのです。
ここで注目したいのは、イエスの与えるコトバは、渇きを癒やすだけでなく、その人自身の中に泉を湧き出させる、と述べられている点です。
ここでの「水」は、神のコトバです。それもまた、誰かと分かち合うべきものであって、自分だけのものにしてはならないとイエスは言うのです。
しかし、奇跡を、絶対に起こり得ないこと、と感じるのは、それを文字として、言葉としてだけ読んでいるからかもしれません。その奥にあるコトバをともに読むとき、その奇跡の物語が何を象徴しているかが見えてくる。
4)コトバを届けるということ
「たましい」の糧であるコトバの比喩だとしたらどうでしょう。「たましい」に渇きを覚えた五千人の人たちをイエスのコトバが癒やす、というkとは十分にあり得ることなのではないでしょうか。
つまり、イエスの弟子になるということは、人々に食べ物を、すなわち言葉を届けることなのだと言明したのです。
5)あなた方には、すでにコトバが宿っている
イエスは弟子たちに「あなた方には、すでに豊にパン=コトバが宿っているのに、なぜ『持っていない』といって論じ合うのか」と言うのです。
弟子たちは、自分たちは無力で何もできない、いつも誰かから与えてもらわなければならない存在だと思い込んでいます(略)自分で生み出せるはずのものを誰かに与えられるのを待っているのです。
弟子たちはすでに、与えれれるだけの存在ではなく、与える主体でもある、ということです。
まず、自分の中にある「泉」に気が付くこと、そして、そこから湧き出る水を誰かと分かち合うこと、そして、その「泉」は、誰の内面にもあることを互いに確かめ合うことが大切だというのです。
永遠に残るのは、姿、かたちのある「わたし」ではなく「わたしの言葉」である、というのです。
6)語らない人たちの言葉に、耳を傾ける
ここでの「石」は、語ることを奪われた人たちの象徴としても読むことができます(略)彼は「石」の声、つまり、虐げられた人の声にならない呻きをけっして聞き逃さない、というのです。
7)追記
関連した個人ブログを作成いたしました。仏教との間に見出せる「共通性」について考察しています(約3300文字)。ご一読くださいますとうれしいです。
https://mori-to-seiza.hatenablog.jp/entry/2023/04/12/060712
今回のレジュメは以上となります。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それでは!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
