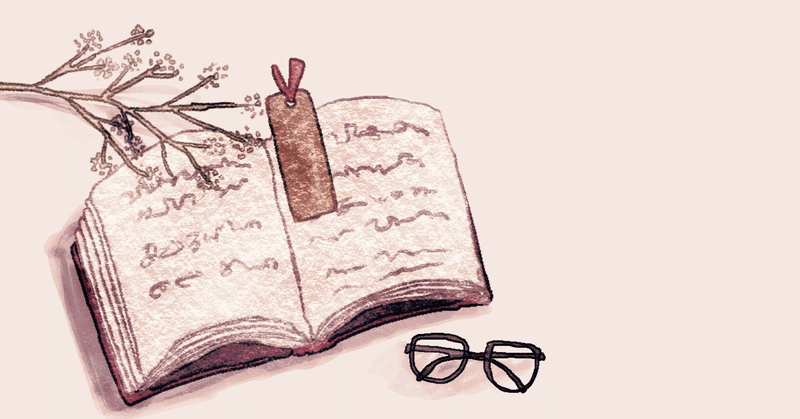
【杜のラボ】「読書会という希望」を語る・序
こんにちは。5月18日(水)08:12です。数日の間、ひんやり感じる日が続きましたね。
ぼくが開くオンラインでの読書会が「続く」ようになって、少なくとも3年半ほどになるかと思います。断続的に開催してるのを加算すれば、もっと遡ることができるのですが、さしあたって2018年10月を起算の月としておきます。
この間、ぼくはずっと、読書会が充実することに「あこがれ」を抱いていました。今回のnoteでは、ぼくは読書会を続けることで「何」をめざそうとしているのか、少し考えてみようと思っています。おつき合いくださいますと幸いです。おそらく、ぼくにとって読書会が続き、充実していくのは、希望の灯をかかげるのとほぼ等しいと述べてみたいのだろうと、今は考えています。
ぼくにとっての読書会の原体験とは、学部生時代のゼミであったと考えています。少人数で、特に制限を設けずに語り合う。あるいは、一冊の書物について論じあう。授業や講義ではなく、少単位での学習が行われること。これは実に楽しい経験でした。
また、ぼくが属する団体において、「座談会」という形式で、信仰体験を語り共有することも、ある時期までのぼくには重要なことでありました。これらの経験を通じて、ぼくは聴き、語ることが重要であると感じる端緒に着いたのだと感じています。その後、コールセンターで就労していたり、カウンセリングの勉強をしていたりということで、「聴き、語る」についての考えを深めてきたつもりですし、それらについては、既に述べてきているはずです。
ですので、今までのところで言うと、「聴き、語る」ことを通じて他者を見出し、つながりあうことを、ぼくは希求してきたのだろうと思うのです。そこで語られる話題として、ぼくは本と読書を選んだということなんだと思います。場合によっては、音楽であったり映画であったりしてもよかったのでしょうが、ことによると、本と読書とを「敢えて」選んだ。むしろそう考えたいと思います。
なぜ、本と読書を「聴き、語る」際の話題として、あるいは他者を見出し、つながりあう際のツールとして選んだのか。これを考えるべきでしょう。これについては、事後的に見出したことですが、「書く」こととのシームレスなつながりがあったからなのだと思うようにしました。なぜならば、音楽について言えば、ぼくは楽器を弾けないどころか、音符も読めないし、映画については創作ができない。料理も作れないし、スポーツもダメ。消極的ではありますが、読む=「享受」することに対応する「書く」ことであればできる。そういうことなんだろうと思います。つまり、享受と創出との双方ができる。読む=書く=聴く=語るが、それぞれに相補的に関わり合い、深め合ってもいる。これはとてもよい循環をもたらしているはずです。
と、今日はここまでとしたいと思います。機会を改めて続きというか、発展させて書いてみようと思っています。お読みいただきまして、ありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
