
なぜ選択的夫婦別姓に賛同するのか。ビジネスリーダーたちの声
ジネスリーダー(経営者・役員)として、なぜ選択的夫婦別姓の法改正に賛成なのか。いただいたコメントをご紹介します。
共同呼びかけ人
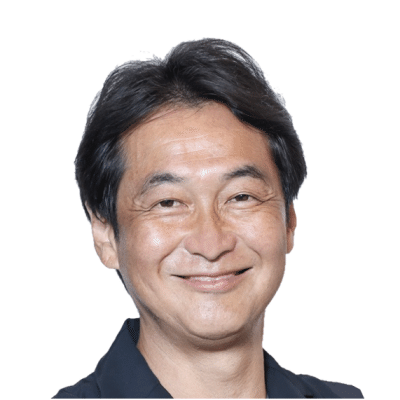
共同代表:夏野剛 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
女性活躍がこれだけ重要視される中で、結婚によって姓を変えているのがほとんど女性という状態。しかも姓を変えることでの不利益はキャリア形成上大きいので、早く法改正すべき。当たり前のことを当たり前にできないことが日本の生産性の低さにつながっています。身近な問題から変えていきましょう!
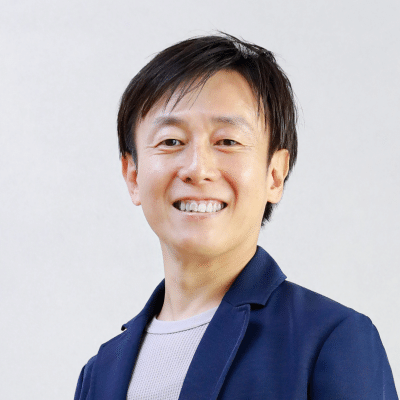
共同代表:青野慶久 サイボウズ株式会社 代表取締役社長
現行制度は、名字の変更や使い分けに対する負荷をビジネスの現場に押し付けており、企業の生産性を下げる一因となっているから。次代を担う社員たちの願いを受け止め、ぜひご賛同をお願いいたします。

冨山和彦 株式会社経営共創基盤(IGPI)グループ 会長
既婚、未婚を問わず、今は個人が個人として輝くことがすべての経済社会活動の基本です。そこで大事なことは個としてのアイデンティティーを何よりも尊重すること、そしてそのための選択肢を個人が持つことであり、選択的夫婦別姓はより多くの人々にとって豊かで幸せな社会を作る上で当然の制度であり、個人からみればこの選択権は憲法上、最も尊重されるべき人権の一つです。現代社会における家族的価値は、こうした個の尊重、個の確立があって相互に助け合うことによって持続的に実現するものだし、これは日本国憲法を含む自由と民主主義を共通の価値観とする現代のまともな立憲主義憲法の国においては、個々の国柄の固有性や伝統の個別性を超えた普遍的原理です。

田代桂子 大和証券グループ本社 取締役執行役副社長
自分がキャリアを積んでいる間に使った大切な名前を、結婚時に強制的に変えさせられている現状の早期改善を強く希望します。通称という中途半端な対応ではなく、正式な形での選択制にしないと様々な場面でストレスを伴う交渉がこれからも発生してしまいます。無用なストレスから女性を解放し、明るい世界の将来のためにパワーが発揮出来る環境を整備しましょう!!
賛同者の皆様
坂光信夫 株式会社ミアルカ 専務取締役
私たちは夫婦別姓のために事実婚を30年間続けています。選択的夫婦別姓制度の成立をずっと待ち望んでいます。妻も私もそれぞれ自分の名前を出して事業を営んでいますので、改姓するととても不便です。仕事の都合もさることながら、対等な個人としてパートナーでありたいという想いから夫婦別姓を望んでいます。生まれた時からの名前を結婚してからも使うことができるというのは、人として当たり前の権利だと思います。多様な夫婦のあり方を許容する社会の方がより豊かであると信じています。
和久井香菜子 合同会社ブラインドライターズ 代表
私の周りには、「結婚したくない」「結婚のメリットが感じられない」という女性が何人もいます。SNSには「離婚して本当に幸せ」という声もあふれています。
私が離婚した時代にSNSがあったら、同じように開放感に包まれて喜びを語ったことでしょう。
そしてその感覚が決して特異なものでないことは、近年の非婚率の高さを見ても納得がいきます。
私たちは、親を見て育ち、家族観を学びます。誰かに我慢を強いたり、片方だけが努力をする結婚で幸せなのは、我慢や努力を必要としない側の人たちです。
人はそれほど強くはありません。我慢した圧力は、目の前の弱者……子どもに向かってしまう恐れがあります。その結果が、結婚にネガティブな印象を持つ私の周囲の人々を作ったのだと感じます。
結婚したい、家族になりたいと思える相手と出会えることは、たいへん貴重です。そうした方々が「生まれ持った名前で生きたい」と望むだけで法的サポートが得られないのは、不平等であると同時に、とてももったいないことです。
合同会社ブラインドライターズは、障害のある方たちで構成された会社です。起業の際にはこんな理念を掲げました。
「『できない』を『できる』に変える方法を考え、だれもが自信を持てる、自由で、便利な社会を目指します。」
私はこの理念のもと、選択的夫婦別姓制度の導入を強く望みます。
高祖常子 NPO法人ファザーリング・ジャパン 理事
自分らしく生き、働くために選択できることが必要です。選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
水上駿 DIGGLE株式会社 取締役CTO
通称利用推進に伴うシステム改修は極めて非効率であり、二重・三重氏名がセキュリティリスクを高めることは明らかであると技術責任者の視点から断言します。日本の生産性を高めるためにも、選択的夫婦別姓の早期実現は必要です。
讃井康智 ライフイズテック株式会社 取締役(最高教育戦略責任者)
次世代の子どもたちの「生きづらさ」を少しでもなくすためです。多様な考え方を持ち、将来の姓の選択についても考え始めている中高生がすでに沢山います。姓について思考を通し、自分で意思決定し、別姓・同姓を選択することは権利であると同時に、非常に重要な学習の過程でもあります。自分の意思で選択したことが、古い制度や理不尽な思考停止で阻害されることは、本人の成長・学習上の大きなマイナスであり、ひいては生きる上での障害です。なるべく早くこの「生きづらさ」が解消されることを望みます。なお、同姓を選択したい人たちの権利が守られることも同時に望みます。
田中美乃里 特定非営利活動法人 地域魅力 理事長
この署名に参加する機会を与えてくださったことをうれしく思います。
アイデンティティでもある名前の一部を変えることは、物理的、心理的、経済的に大きな負担がかかります。一方で、好んで姓を変えたい方々の自由を制限することはまったくありません。
今後未来にわたり、苦痛や負担を強いられている人々が解放されるような、制度の適正化を求めます。
野澤武史 一般社団法人スポーツを止めるな 代表理事
その人がその人らしくあれるよう、ルールは変わって行くべき
島田卓 株式会社フェニックスバイオ 代表取締役社長
女性であれ男性であれ、結婚によって生まれたときの姓を名乗り続けられなくなることは、実の親との関係を絶ち、家族を分断することではないでしょうか。私と私の配偶者もそうですが、姓名を個人のアイデンティティと考える人は少なくないと思います。
高橋鉄平 株式会社ティー・ティー・シー 代表取締役社長
選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
「望む人だけが改姓し、望まない改姓はゼロにする」という理念にも強く賛同します。
僕とパートナーは同じ「高橋」同士の結婚でした。彼女が僕をパートナーに選んだ理由が「改姓を避けるため」だったとは思っていませんが(笑)改姓せずに活動できるメリットをたくさん実感している様子です。
中井照大郎 株式会社百森 代表取締役
誰もが等しく生きられる世界を願っています。選択的夫婦別姓はそこに通じる制度です。
喜多村若菜 株式会社fruor 代表取締役社長
慣習が故にどちらかの姓が消えてしまうことと、現状その96%が女性が担っていることを考えると目指すべき男女平等からはかけ離れた実態があることから、選択的夫婦別姓に賛同します。
新井紀子 一般社団法人教育のための科学研究所 代表理事・所長
従業員が結婚前の姓を通称として仕事上利用し続ける際、様々な場面で本人を確認する書類の提出が必要となり、本来不要な労務コストがかかるため。
赤松佳幸 株式会社播磨屋茶舗 常務取締役
姓を変える側になれば平日に煩雑な手続きに追われ、姓を変えない側になったとしても、パートナーに苦労をかける心苦しさを感じる。
こんな事が起きてしまう現状は、早く解消されるべきだと思います。
河合通恵 SREホールディングス株式会社 取締役不動産本部長
通称ではあまりに実生活に悪影響が大きい。個人の名前を選択できることは基本的人権であると考える。
麻野一哉 テクテクライフ株式会社 役員
そもそも名前を自分で決定できないことがおかしい。名前自決権の一歩として。
中村大樹 株式会社バリューブックス 代表取締役
先頭に立って呼びかけていただいた皆様、ありがとうございます。
個人個人が自分らしさを失うことなく、活躍できるように、夫婦別姓の選択の自由が早期に実現することを望みます。
神裕之 株式会社あそぶ 代表取締役
私自身、青野さんと同じように妻側の苗字に変えた一人です。女性が苗字を変えて当たり前という風潮の中に、多くの場合で女性側に手間や費用などの実害がある中で、結婚後も苗字をそのままにするという選択肢を否定するということは、非常におかしいと思っていますし、理屈が通らないと思います。
私たちが求めるのは、強制ではなく、あくまで選択制です。これは、ジェンダーに関わる問題だと強く訴えます。
藤本あさこ 株式会社フジモトソーシャルラボ 代表取締役社長
会社を立ち上げる際に、旧姓で登記できないことに衝撃を受けました。勤めていた企業でも、社員登録名と業務時の名前が異なるため人事手続きで何度もエラーが発生しました。このアンフェアな状況で経団連役員が「女性がトップ層に居ないのは能力が足りないから」と平然と言ってしまうことを恥じてほしいです…
山田敦子 インバイトジャパン株式会社 代表取締役
社会を世界を良くするために活動をしているのにもかかわらず、瑣末な旧姓などの処理に煩雑な作業を求められ、無為に時間を奪われる現状を変えたいです。我々の有限な時間を最大限に価値を生むことに使わせてください。
伊藤美也子 株式会社ミアルカ 代表取締役社長
なぜ女性だけが人生途中から名前を変えなくてはならないのか。ネットで友人の行方を探すこともできない。女性だけ行方不明。アイデンティティとしても当たり前に大切だと思う。結婚においても独立した人間として、対等に夫と共生できる精神の基盤になる。
榊原美紀 フューチャー株式会社 取締役(監査等委員)
海外では常識。世界中で同姓を強制しているのは日本のみ。反対の立場は、選択的別姓にすると「家族が崩壊する」というが、それが本当なら、世界中の家族が崩壊しているの???
高比良歩 株式会社kataribe 代表取締役社長
選ぶという自由があるからこそ、自分と家族の将来を真剣に考えることができる
佐藤啓一郎 株式会社フィラメント 取締役CXO兼CHRO
社会の見えないルールを変革して多様な社会を実現しましょう
木村祥一郎 木村石鹸工業株式会社 代表取締役社長
選択的夫婦別姓に賛同します。むしろ選択できないことが異常で、選択できることが当たり前だと思うのです。当たり前のことが当たり前にできる社会にしたいです。
堤雄史 TNY国際法律事務所 代表弁護士
これ以上見苦しい言い訳をして世界から遅れた状況を維持するのはやめましょう。夫婦別姓を強制するわけではなく、選択的夫婦別姓であれば、同姓を維持したい人にとっても不利益はないはずです。もっと個人の意思を尊重できる社会を目指しましょう。
小澤克年 株式会社東京藤屋 代表取締役
夫婦がどちらかの戸籍に強制的に入らざるをえない今の制度は、基本的人権を侵害するものと考えます。
他者に迷惑をかけない限り、できるだけ自由な社会の実現を望みます。
藤田修嗣 西部商工株式会社 代表取締役
多様性が求められる社会で、女性も男性も過ごしやすい日本という社会のありかたに賛同します。
生まれながらに持ち続けた姓を名乗れる社会を作りましょう。選択できるという社会の実現を望みます。
矢本 真丈 株式会社10X 代表取締役社長
私たちが没頭する技術やプロダクト、事業の本質というのは「制約を開放し社会に選択肢を増やすこと」だと考えています。誰もが自分らしさを発揮できる選択ができる社会を目指す、という点において「選択的夫婦別姓」にも強く共感し、賛同したいと思います。
天野 妙 合同会社 Respect each other 代表
19年前、結婚して姓を変えました。その時の自分は姓を変えることが当たり前だと思っていたので、何の迷いも躊躇もなく、むしろ一人前になるような、誇らしい気持ちでした。手続きはもちろん面倒で、今もまだ名前を変えていない口座がありますが、今の姓に何の疑問を持っていません。なので、もしも仮に離婚してもきっと私は今の姓を選択すると思います。
でも、それは私の価値観であり、他の人の価値観が同じとは限りません。
選択的夫婦別姓とは「選択的」であり選べることなのです。
「選択」ができることは幸福度を高めます。これは多くの研究が証明しています。各個人が幸せになる「選択できる」社会であるべきだと考え、選択的夫婦別姓に私は賛成します。すべての日本人に幸せを。
種市孝 【NPO】IRI理論物理学研究所 所長
性別により社会での役割が限定・強制される社会は時代遅れ。自らに手かせ足かせをはめるようなもの。あらゆる選択肢が、性別に寄らず、個人の手にゆだねられることが社会の、ひいてはその構成員たる我々一人一人の充実と幸福につながる。そのためにも選択的夫婦別姓は必要です。
寺尾伸一 テラオ株式会社 専務取締役
経営者一族に婿入りしました。改姓自体には特に心理的な抵抗はありませんでしたが、旧姓での社会との関係性が薄まる事、改姓に伴う各種手続きの煩雑さを考えると、パートナーとの同意のもと、旧姓も選択できるとありがたかったです。
結局は旧姓で通しています。
角田尭史 株式会社midnight sun 代表取締役
大事なのは慣習ではなく、自分が生きやすいかどうか。だから、選択的夫婦別姓に賛同いたします。
福本博之 フロービス株式会社 代表取締役
選択的夫婦別姓は、多様な生き方を認め合える社会実現のための第一歩です。
川端伶実 株式会社Sai. 代表取締役社長
家族の姓が一致しないことで家族の絆が壊れ、子供に悪影響が及ぶという懸念もあるようですが、私自身は父親が外国人であり、父母の姓が異なる家庭で育ちました。しかしながら私は家族に絆を感じますし、別姓が理由でなにか悪影響があったとは全く感じておりません。
現状パートナーのどちらもが姓を変える選択肢を持っていますが、現実の日本社会では、夫の氏を名乗る女性は96%、夫が妻の氏を名乗るのはたったの4%です。
女性の社会進出を推進し、性別に関わらず全ての人が自分の人生をいきいきと生きられる社会を目指すのであれば、片方に負担を押し付けることなく自分の意思で選択ができる、選択的夫婦別姓が間違いなく必要なのではないでしょうか。
刻一刻と時代は、生き方は変わっています。選択的夫婦別姓に強く賛同いたします。
西川朋子 一般社団法人ヨコグシ 代表理事
同姓を強制することの合理性はもはや見当たりません。ならば選択できる社会へ。
森岡貴和 サイボウズ株式会社 営業本部副本部長 兼 取締役
選択的夫婦別姓の法制化が、日本の未来を創る上での重要な一歩になると信じています!
浦田悠宇 株式会社ウラタ薬局 取締役
自身が結婚する際も別姓を選べるなら選びたかった。ぜひ実現してほしい。
小林直樹 泉金物株式会社 代表取締役社長
生まれたときから名乗ってきた名前とはそんなに軽いものでは無いと思います。私自身、妻に姓を変えてもらいましたが、手続きの煩雑さにも驚きました。様々な考えが有るかもしれませんが、選べないことが問題だと考えています。子供たちにも選べるタイミングをしっかり作ってほしい。いち早い実現を望みます。
市川圭介 株式会社インターメディカル 代表取締役
ファミリーネームに対する考え方は、人それぞれで違って当然だ。
結婚するカップルが異なる姓を名乗ることを選んだときに、誰かに迷惑をかけるだろうか?
二人が同じ姓を名乗りたければ同姓を選択する。二人が今までの姓を名乗りたければ別姓を選択する。それで良い。
多様性のある社会において、選択する権利が認められることは当然の基盤だ。
こと私自身は夫婦で同じ姓を名乗りたいと思うのだが、選択的夫婦別姓は私のような考え方を否定する制度ではない。
選択する権利を認めるための制度である。
西村創一朗 株式会社HARES 代表取締
夫婦別姓を強制するわけではなく、選びたい人は同姓を選べる選択的夫婦別姓なのだから、認めない理由がないから。選択的夫婦別姓が認められていないのは、日本のダイバーシティがいかに遅れているかの象徴。
若宮和男 株式会社uni'que Founder/CEO
「選択的夫婦別姓」の重要なことは「選択的」ということ。制約や負担の多くを女性にだけ「強制的」に負わせてきた「強制的夫婦同姓」制度を改善し、個人が人生を「選択」し暮らし働いて行ける社会にするため、賛同・応援します!
山本遼 株式会社R65 代表取締役社長
常に変化する社会や文化に、フィットする制度を応援します。
菅原譲 有限会社菅原靴店 専務取締役
ファーストネームで呼び合う文化の方が離別した際にも何事もなく日常を過ごせ心理的安全性を保てるため。
伊藤聡 青山社中株式会社 取締役COO
姓によらず、心から信頼し合うことで生まれる「本当のパートナーシップ」が、日本社会に溢れますように。
田村啓 GJC Myanmar Ltd. Managing Director
夫婦同姓を義務付けるいかなる理由も見出せません。この議論があること自体が不思議です。夫婦同姓、夫婦別姓、自分らしい選択肢を誰もが選べる社会に!
TomikoYazawa Synetre, LLC 代表取締役社長
自分の生まれた時の姓名で人生を生きたい。そういう選択肢を認めてほしいだけです。
山本和奈 WAYVX SpA 代表取締役社長
夫婦同姓であろうと、別姓であろうと、誰に何の迷惑がかかるのでしょうか。そもそも外国人パートナー結婚をする場合、自動的に夫婦別姓になるのであれば、相手が外国籍でなくても別姓が可能になって良いはずです。
山谷武範 株式会社山谷産業 代表取締役
仕事上・生活上大変なことが多すぎる。どちらかの姓にしなければならないよりも姓を変える変えないの選択できることが必要と思う
近藤美文 株式会社Five Technologies 代表取締役
賛同します。大半の女性が姓を変えざるを得ないという状況によって、女性を男性の庇護対象とする価値観の強化につながり、女性の経済的自立やキャリア形成を妨げています。こういった価値観を無くしていくために、法改正の早期実現が必要です。
宮﨑雄 株式会社バンソウ 取締役・ボードゲームデザイナー
ルールというものは、ゲームをスムーズに進行したり楽しくするためにあるべきものだと思います。私達がプレイしているゲームでそれが適いやすいのは、選択的夫婦別姓の方だと考えています。
米井 亜紀子 シンコーストゥディオ株式会社 代表取締役
選択する自由を日本の未来のためにも!
有田歩 合同会社オフィスA'mu 代表社員
国民が望むことを当たり前にする社会の実現を目指しています。なぜ選ぶことすら出来ない制度のままなのか理解できません。
久次米美奈 株式会社ARTISAN 代表取締役
いつか選択的夫婦別姓に法改正されることを信じて私は事実婚を選択しました。多くの女性は結婚する事と名前が変わることはセットになっていますがそうではない人もいますし、仕事のために結婚を諦めたり結婚のために仕事を諦めている人もいます。何かを諦める結婚がゼロになる世の中にしたいです。
瀧本裕子 イノベーションブリッジ合同会社 代表
小学校の時、3度苗字が変更した同級生がいました。親の都合で子どもがふりまわされることがないようにと思います。
伊江玲美 一般社団法人スローフード インターナショナル日本オフィス 代表理事
やるべきであると思ってます
竹原司 インフォグリーン株式会社 代表取締役
女性が仕事をする場合、結婚後も名前が変わらない方が有利だと思えるからです。
村上達志 一般社団法人ダイアローグ1st 代表理事
遅れている日本の人権意識を前に進めましょう。
長谷川暁子 株式会社日動画廊 専務取締役
外国人と結婚したばあいは夫婦別姓が許され、日本人同士では許されないのは不平等であるし、選択する余地もないのはおかしい。
松岡恭子 株式会社大央、株式会社スピングラス・アーキテクツ 代表取締役社長
変化激しいビジネス界に立ち続け、経営し、社会に向けて発言してきた一人として、名前は変えることのできない自分のアイデンティティであり、併記や通称で機能がカバーされるから、といった方法論でその喪失を補えるものではありません。パートナーも同様です。
企業の代表はその社会的責任から氏名や住所も登記事項であるだけでなく、一切の書類に掲載されている代表者の名前は、その責任の重さを示すもので、それは本名であるべきです。
婚姻の喜びと仕事の喜びの間に、ストレスのない社会を次世代のためにも実現する必要があります。
神沢 學 アルー株式会社 監査役
人間は生まれながら差はなく、全員平等であります。結婚すると女性が男性の姓を名乗らなければならないのは、我国の伝統と称するも、女性は男性に従属する存在とする過去の我国の男尊女卑の社会意識のあらわれで、女性を理性を持った自由な人格として認識してこなかった因習の残滓であります。少子高齢化が急速に進む我国に於いて、因習に捉われず、能力と努力の意思があれば、性別に拘わらず全員平等に扱われるべきであります。今回の(選択的)夫婦別姓制度はその一歩を進めるもので是非とも法制化を実現すべきと思います。
田辺直子 NPO法人ゆたかなビレッジ 理事長
私は「実家の名前を継ぎたい姉妹の会」にて活動しています。
私はペーパー離再婚し、日本人の4%である、夫が妻の名字を選び婚姻しました。
介護支援専門員、介護福祉士、など福祉の資格は名字変更が必要でキャリアアップの弊害になります。
さらに、私は女系家系のため田辺を継ぐ人間がおらず、愛された祖父母を始め想いを繋ぐためにも田辺で生きたいと思い、名前を継ぎました。
全ての人が結婚しやすく生きやすい生き方ができるよう、今後も活動していきます。
長岡善章 株式会社アーティスティックス 代表取締役
「選択的」というところが重要です。多くの人が夫婦同姓のほうがいいと思っているし、その考えを尊重します。しかし、夫婦別姓のほうがいいと考えている私たちのことを、制約する理由にはならないと考えています。通り名は法律的には偽名。ビジネスや手続きの上で活動の制約となっています。多くの人の夫婦同姓の考えを私たちが尊重するように、私たちの「選択的」夫婦別姓の考えも尊重していただけることを、切に願います。
小野田幸子 株式会社クロスメディア・ランゲージ 代表取締役
経営者として通称使用を続けていて不自由を感じる面は多くあります。登記簿、銀行口座、社会保険等、代表取締役として通称使用(通称併記)をするために多くの時間を割きました。認められず、涙をのんだことも多々あります。私がそのような手続きに時間を費やしている間に、姓を変えないで済んできた他の経営者たちは経営に集中しているのかと思うと、悔しい気持ちです。実務の問題として不自由な思いをしている経営者もいることを知っていただければ幸いです。
石﨑節子 JAIWR(国際女性の地位協会) 事務局長
国連の女性差別撤廃委員会からの勧告を無視し続け、多くの女性たちに不便を強いているのは、男女不平等の極み!「選択」できることが大切!!
新田香織 社会保険労務士法人グラース 代表
同姓一択のシステムよりも、結婚したら同姓or別姓を選択できるシステムの方が、当事者の納得感を高めます。家族の在り方やアイデンティティについて考える機会にもなります。
浪川舞 合同会社PeerQuest 代表
別企業の経営者である彼ともうすぐ入籍します。これまでに姓を選択する上でお互いの家族を交えて何度も検討を重ねました。日本人女性の多くが選択してきた男性姓になるという覚悟、それを当たり前としてしまう習慣や偏見と初めて向き合う一年となりました。とても長かったです。
最終的には私の姓を選ぶこととなりましたが、本来であれば法律婚している事実と、名乗るべき姓は切り離して考えたかった。それを実現できる取組みに賛同いたします。
真鍋康正 ことでんグループ 代表
個人・家族によって価値観が異なるのは自然なこと。それぞれの人が、自分らしく生きるために、選択肢を用意できる/用意しようとする社会でありたいと思います。
浅野(中静)透 国立研究開発法人森林研究・整備機構 理事長
私自身も旧姓「中静」を通称として使用していますが、理事長業務には通称が使えず、不便に思っています。
田中浩 一般社団法人日本森林技術協会 業務執行理事
私自身、法改正を待ち、事実婚のまま26年が経過しました。
改姓をしていないため、自分自身の研究や業務の上での不便はありませんでしたが、周辺の研究者や専門技術者(主に女性)が改姓により苦労する様子を多数見てきました。
通称利用の許容が研究の場面では徐々に増えてきたものの、様々な不便や不都合は根本的には解消されず、ダブルネーム使用による弊害も問題です。
研究者や専門技術者(特に女性)の活動をエンカレッジするためには、
選択的夫婦別姓制度の導入が必須であると考えています。
新井仁 Arai & Associates LLC 代表
結婚に際し同じ姓となり、新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦の方が圧倒的多数であることを論拠に選択的同姓制度に反対する意見があるが、これはつまり少数派、マイノリティの抑圧である。この意識は少数派差別に他ならず、選択的に別姓とすることはその少数派の問題を解消する一歩であり賛同する。
光畑由佳 有限会社モーハウス 代表取締役
「私」が「私」であり続けるために、自らの姓を選んでいけることが必要です。働き続けること、生き方を選べることなどの自由の前提でもあると思います。個人的には、30年前から課題と思い、仕事上別姓を続けていました。ようやくうねりが来ている今こそ、変化の時。心から賛同します。
小栗ショウコ 認定NPO法人あっとほーむ 代表理事
どちらかの姓に統一したい人はそれを選択し、夫婦別姓を使いたいならそれを選択する。
それに賛同します。
尚、夫婦別姓を選択した場合、改名による個人と社会システム上の手続きの負担がなくなり、働いている場合は企業での通称と戸籍上の氏名の二重使用の負担がなくなります。これは女性の事であると思われがちですが、男性でも同じです。
また、子どもにとって両親の姓が違うことに精神的負担があるのでは?と反対する人もいますが、長年子育て支援をしてきた私の見解としては、子どもが精神的負担を感じるのは、周りの大人がそれがいけないことだと思い込ませるからです。
個人の選択を尊重する社会になることを切に願います。
古市克典 Box Japan 代表取締役社長
別姓にすべしということではなく、別姓か同性かを選べるようにしましょうということで、個人や家族が主体的に納得感を持って暮らせるようになると思う。
猪原健 医療法人社団敬崇会 理事長
押し付けではなく、みんなが選べる世の中にしていきたいです!
神永英義 一般社団法人HALOMY 理事
多様性のある社会、選択できることが当たり前であって欲しいです!
戸田佑也 株式会社あらまほし 代表取締役
「それぞれの価値観に基づいて選べる選択肢が多いこと」が豊かさではないかと思います。
Kawabata Hitomi 株式会社 薩摩太良院 代表取締役
私は実家に伝わる製法を受け継ぎ企業した立場上、仕事上の名目は旧姓、様々な書類は夫の姓と使い分けており、大変手間もかかります。そもそも一人娘であったために、夫を養子に迎えるか私が嫁に出るかの選択を迫られたからです。それはどちらの家族も大切にしたいのに、どちらかを選べと言われているようなものでした。案の定、結婚後は姓を理由に、「お前は◯◯家の人間であり、◯◯家(実家)の者ではない」と両家から言われることになり、仕事上も相続でも非常に苦労しました。しかし結局、親の介護等は両方の肩に掛かる問題でした。
少子化が進んだ今、同じように悩む人々はもっと増えるでしょう。どちらの家の者であるかの選択ではなく、個人として立ち、力を合わせて解決して行く形を取らなければ、家のために結婚やひいては社会で活躍することも諦める女性が増えることでしょう。それは女性がそのセンスを生かして活躍している現在の世界情勢からますます取り残され、日本経済の再浮上の妨げにしかならないと考えます。
浜口智洋 株式会社フューチャーデザイン 代表取締役
反対する理由が全く理解出来ません。男性が持つ既得権を手放したくないっていうようにしか思えないです。今の時代にくだらない既得権にしがみつく情けない男にはなりたくないものです。
東上征司 JBCCホールディングス株式会社 代表取締役社長
極めてシンプルに考え、選択出来る事が極めて自然です。
樋口泰行 パナソニック株式会社 代表取締役専務執行役員
ジェンダー平等の観点で、議論の余地なく、当然のことと賛同致します!
岩崎由夏 株式会社YOUTRUST 代表取締役
弊社に入社してくる既婚女性のほぼすべてのメンバーが雇用契約の段階で「すみません、実は戸籍上の名前はこちらで…」と申し訳無さそうに修正を申し出てきます。私も含めて彼女たちは過去の信用が化体している姓のまま仕事をしたいという意思を持っています。
使っている名前と戸籍上の名前が異なると、手続きは俄然ややこしく、かつ申し訳無さそうに毎度修正を申し出てくれます。使っていない書面上だけの名前になんの意味があるのだろう、と私自身思います。大切にしてきた信用が化体している名前を不本意に捨てる必要がない社会になることを強く望みます。
寺澤順子 特定非営利活動法人NINJA Project 理事
離婚時に子のために旧姓に戻しませんでした。戻すためには、子が成人し再手続きが必要。審判手続きの簡略化を希望します。
林田香織 ワンダライフLLP代表 代表
姓名は自分らしく生きる権利の象徴でもあると思います。選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
宮永麻代 株式会社グローバルプロデュース CMO
名字を変えないといけない、という足かせのために「であれば結婚したくない」とさえ思っていたので強く同感しました!
江角和沙 COM-MA Laboratory株式会社 代表取締役社長
ビジネスは旧姓を使用していた流れから、会社登記においても旧姓を選択しようとしましたが、本籍名のみでということで驚愕しました。偽名ではなく旧姓のまま活動したいというだけで、様々なハードルが存在します。必要な方は夫婦別姓を選択出来る、名前で苦労しない、世の中になることを望んでいます。
合田文 株式会社TIEWA 代表取締役
より自分たちらしい方を堂々と選べることで、もっといきいきと活躍できるできる人がこの社会にはたくさんいる。そう思うと賛同以外無いと思っています。
中里聡一郎 いろどり株式会社 代表取締役
従業員が働きやすい環境を整備するために姓がハードルになってはいけないと思います。従業員それぞれの価値観に従って姓を選択できるようになったら、ダイバーシティ促進の一助になるのではないでしょうか。
工藤英之 新生銀行 代表取締役社長
反対する論理がそもそもよくわからない。
渡邊民人 有限会社タイプフェイス 代表取締役社長
現状では一方の権利を奪い、かつ、ただ選択できるようにするだけの制度の議論に30年以上費やしているにも関わらず結論がでていない。反対派は情緒面以外での反論しかできない。ロジックはゼロ。こんな無策を放置しているのは看過できません。
村木真紀 認定NPO法人虹色ダイバーシティ 理事長
日本で婚姻の平等が実現し、同性同士も結婚できるようになる未来がきたら、同性パートナーを持つ人もこの問題の当事者です。太郎さんと太郎さん、花子さんと花子さんで結婚したら、同性同士で同姓同名になってしまい、大きな社会的混乱が予想されます。そんなややこしい事態にならないよう、選択的「ふうふ」別姓に賛同します。
永田京子 NPO法人ちぇぶら 代表理事
私たちは、全ての人が自分らしく充実した日々を過ごせる社会を実現するために、選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
白石実果 株式会社M&Company 取締役
社員それぞれの自由な生き方を大切にするために、環境を整えたいと思っています。
村崎加代子 株式会社 むらさき ジャパニーズ インスティテュート 代表取締役社長
むらさき ジャパニーズ インスティテュートという日本語学校を経営しています。村崎(むらさき)さんが経営している日本語学校だから、むらさき ジャパニーズ なのに、他の姓になったら、なんの意味もありません。よって、結婚当初は別姓法案が通りそうということで、籍を入れていましたが、結局は抜いて離婚(同居婚、法的には内縁関係というらしいですね)にしました。
山田浩司 boundaryspanner株式会社 代表取締役社長
個人のエンパワーメントが進むべき社会において、選択的夫婦別姓がなぜできないのか不思議でなりません。生きづらいという人が少しでも少なくなるような社会を望みます。
白石達史 株式会社M&Company 代表取締役社長
選択できることが本来あたりまえであって、今までがそうではなかった。希望者のみが別姓を選べる権利の主張は、賛成反対の対立構造を超えたアンサーだと思います。
大東信仁 株式会社あみだす 代表取締役社長
検索で情報を抽出する今の時代、強制的に、婚姻によって苗字が変わることは、以前の苗字と別の人間になることであり、婚姻前のポートフォリオ(実績)を見つけることが困難となる。現実に、この問題に直面して困っているクリエーターも多い。つまり、ネガティブな影響しかない。
平本沙織 株式会社wip 取締役
生まれ持った姓を捨てることを強要することのない社会を共につくりましょう。ソーシャルアクティビスト平本沙織
野崎奈緒子 株式会社WOMENOMCS 代表取締役社長
海外での事業展開をしており、自身が代表を務める海外会社の氏名変更手続きは想像を絶するほどの大変さであった。パスポート、就労許可証、ビザ、法人登記書、法人銀行口座、各種数え切れないほどの契約書の氏名変更が必要で、それらを全て行うのに膨大な時間とコストがかかった。これらの負担が多くの場合、女性にのしかかっていることに不公平感を感じるとともに、女性が責任ある立場に立つことの弊害要因の一つになっていると感じているため、選択的夫婦別姓の導入に賛同します。
三好拓朗 株式会社パーク 代表取締役
夫婦別姓を選ぶ人も、夫婦同姓を選ぶ人も、それぞれの想いと決断を尊重できる社会になるといいなと思います。
選択肢があることで、逆に夫婦について考える機会が一つ増えて、より良い関係の夫婦が増えるんじゃないかなー。
平野歩 OurPhoto株式会社 代表取締役
夫婦別姓は、アイデンティにも関わる問題です。より自由で働きやすい社会、環境を作るためにこの活動を応援したいと思います。
吉田大樹 特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト 代表理事
家族のあり方は多様。自分自身も名字の異なる子どもと生活しているが、名前が違うからと言って、愛情が変わることなんてない!一方の名前しか名乗ることができない現行制度では、逆に選択されなかった名字が存在できなくなるのではないだろうか。
松本知華 株式会社松本機械製作所 代表取締役社長
会社を経営する上で名字の変更による不利益、不便さを痛感しました。名字が変わることを前提に社長就任前に結婚して名字を夫の方に変更しましたが結婚後2年とたたずに夫が他界。名字を戻す際にも手続き的に大変で、名字が変わるのでプライベートが公になり理由を聞かれるなど精神的にも苦痛を感じる場面が多々ありました。また、両親がつけてくれた松本知華という名前の画数がとても良かった分、亡くなった夫の名字に変わってからの私の画数が最悪になってしまったことも夫の死に繋がってしまったのかと思い悩むこともありました。親族夫婦同性が良い方は同性に、自分の姓を使い続けたい方は自分の姓を使える自由を望んでいます。
松田陽子 城山ふとん店 店舗責任者
賛同します!
川戸裕佑 株式会社グローカリズム 代表取締役
選択的夫婦別姓に賛同します
佐貫葉子 株式会社メディパルホールディングス 社外監査役
多様性の尊重を掛け声だけではなく、具体的に実現してほしいと願います。
池田祐輔 アルー株式会社 取締役
夫婦別姓にするのも、同姓にするのも、個人の選択の自由であるべきだと考えます。
阿部龍治 株式会社ダクグループ・ホールディングス 代表取締役
当社女性社員も入社後に結婚された場合は社内では旧姓のまま、新たに入社した女性社員は選択制を採用しております。また当社のビジネスパートナーは女性の方が多いですが、旧姓のままビジネスをされている方が大半のようです。インターネット環境が整い、オンラインでの検索スピードもますます早まるなか、次世代に継承すべきルールへの改正は随時進めるべきであると考えます。世界の動きや男女平等などを考慮した改善には賛同致します。
吉田浩一郎 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長
時代とともに社会制度も変化していくべきだと考えています。
現在は仕事であればリモートワーク・オフィスワークに分かれ、性別はジェンダーフリー、LGBTなどの多様な在り方が受け入れられ、食はビーガン、人工肉、完全食など思想や嗜好性によって分岐が進んでおり、急速に個人の価値観が多様なものになっています。そのような中で、それぞれを1人の個として扱い、多様な価値観全体を受け止める包摂性が求められていると感じています。
そういった観点からも一人一人が選択的に姓を選べる仕組みに賛同いたします。
住田涼 一般社団法人Nancy 代表理事
「強制的夫婦同姓」では、それまで仕事でも使ってきた姓を変更する側に大きな負担が強いられます。免許証やマイナンバーカードへの旧姓併記によって解消された部分は大きいものの、証券口座の開設や保険関係などまだまだ旧姓併記によって解消しない部分は多く、そもそも旧姓併記の手続きを平日の日中に仕事を止めて役所へしにいく必要があります。それらの負担が一方に押し付けられてしまうことは、平等とは言えません。だからこそ、婚姻関係は結ばずに事実婚にとどまる方も一定数存在しております。多くの方々にとって人生の選択肢をより広げることは結婚や出産へも繋がり、少子化解消の一因に繋がることも十分考えられます(もちろんそれだけで少子化が解決するわけではないにしても、社会課題は複雑に絡まっている糸のようなものなので、その1つを解くことには繋がるのではないでしょうか)。日本国民がより生きやすい国へと成長するために、選択的夫婦別姓に賛同いたします。
東賢 インフラジスティックス・ジャパン株式会社 代表取締役・シニアUIアーキテクト
選択ができるようになることになんらの影響もなく、選択ができない状況が不利益を生むと言うだけで賛同しない理由が見つからない内容です。文化が壊れることもなく、問題もない。弊社ワールドワイドで見れば至極当然のことと思えますし、早々に本件が良い方向に進んでいくことを望むばかりです。
堀田実希 合同会社みきほし 業務執行代表社員
結婚・改姓後、まだ個人事業主で、国際送金で「名前が違うから送金失敗」というトラブルが2回ほどありました。私自身は「堀田実希」として国際的なキャリアを切り開いてきたので、自分の法律名とビジネスネームが違うことで、様々な手続きでエラーを引き起こしているのが残念だと思います。
岡山史興 70seeds株式会社 代表取締役編集長
「姓は大事だ」「姓なんて大した問題じゃない」どちらの立場も肯定できる制度が生まれることを否定する理由などあるでしょうか。
友斉照仁 トモナリ衛生材料株式会社 取締役
「家」に所属することに意味があり、それを示すために姓を揃えることが必要だった時代が、かつての日本にはありました。いわゆる家制度ですが、しかしそれは70年以上前に廃止され、現代では結婚に対する考え方、家族の在り方は多様化しています。
外部環境の変化に合わせて制度を変えるのは経営において当たり前のことですが、政治においても同様になりますように。
鏡照美 株式会社せいじつ会計 代表取締役
私たちの社会は様々な技術発展をし、いろんな選択肢を持てるようになり、個性を表現し自分らしくいきることができる時代になったのに今の法律が合っていません。自分の生き方を選択できる社会の実現のため、選択的夫婦別姓に賛同します。
佐野泰喜 株式会社HAMIGAKI 代表取締役
何がいいとかではない。一個人の選択の自由はあるべきだと思います。
平岡純 株式会社シャドウウィングス 代表取締役
名字を変えるメリットはないし、生まれる生産性もない。変える・変えないで家と家に争いを起こすこともあるし、変えることで発生する各種手続きはただ時間だけを浪費するだけ。認めないことで失っている生産性と発生している無駄がなくなればいいと思います。
野崎綾子 株式会社ソルシェール 代表取締役
名前は一つのアイデンティティです。私自身姓が二度変わり、その都度それまでのキャリアやキャラクターがゼロクリアになるような違和感がありました。アインデンティティの喪失と新たなキャリアとキャラクターを創り上げることは、本来エネルギーをかける必要のないことだと思います。たかが姓ですが、されど姓。改姓をしない自由も認められる社会であってほしいと願います。
諸藤優子 株式会社スイートクラス 代表取締役
子供が生まれたのをきっかけに9年前に入籍しました。夫は私が改姓するのが当たり前と思っていたらしく、私が変えたくないというと「は?」というように私を軽蔑したような扱いをしました。私も自身の姓と名の組み合わせが気に入っていたので変えたくなかったです。
女性が姓を変えないといけないという暗黙の了解のようなものが男性の中にあるのではないでしょうか。女性を下に見ているということだと思います。
通称ではクリアできないことが山のようにあります。4人こどもがいますがこどもたちは私が通称を名乗っていること「別に人の自由だよね、なんで夫婦一緒じゃないといけないとか言う人いるんだろうね」ととても理解を示してくれています。こどもが悲しむとか子供が苦労するとかそんなことはありません。それは選択的夫婦別姓を取り入れたくない自民党の議員たちのちょうどいい口実にすぎません。ああいえばこういう、今から社会で活躍していくのはあなたたちではなく、若い世代の人たちです。若い世代の声を聞いてほしいです。選択的の意味がわかっていらっしゃらない方が多いのでしょうか。ただ、選択できるだけです。変えたい人、変えたくない人どっちもいます。お好きなように選択してください。ただそれだけなのに、何でお堅い頭の方は柔軟にならないのでしょうか。
一日も早い実現を願っております。
石橋伸子 弁護士法人神戸シティ法律事務所 代表社員弁護士
平成元年から選択的夫婦別姓制度の実現を待っています。子どもの世代が結婚する年齢になてきました。もう、待てません。
通称使用制度の拡大は、問題を解消しません。誰でも見ることができる会社の登記簿に、結婚して改姓したこと、改姓前の姓、改正後の姓、改正前の姓を通称として使用していること、の全てが記載されます。個人情報であるのに。
アイデンティティである姓名を変更しなければならないのは苦痛です。不便などという問題ではありません。
この苦痛を次の世代にも強いるのですか、と国会議員に問いたい。
通称ではなく、正式の姓名として、自分の姓名を名乗りたいのです。
平田はる香 株式会社わざわざ 代表取締役
現在の日本では結婚によって苗字が変わることにより、沢山の労力がかかることを、どちらか一方が負担しなければなりません。選択的夫婦別姓が実現すれば、結婚による負荷を少なくすることができる選択肢が一つ増えることになります。同じ姓を名乗りたいという思いも、違う姓でいたいという思いもどちらも尊重される世の中になってほしいです。時代に伴い法律を柔軟に変えていくことができる国であってほしいと切に願います。
藤俊久仁 株式会社truestar 代表取締役社長
個人の意思決定を尊重する『選択的』夫婦別姓に強く賛同します。
業務上においても、利用するシステムによって旧姓と新姓が混在してしまうこと、結婚というプライベートな情報が本人が望まない場合でも社内に公開されてしまうことは大きな問題であると捉えています。
田口智章 株式会社あぶらび 代表取締役
私が妻と再婚した時のことです。
妻は私の姓になりましたが、当時妻の子供はまだ中学生だったため姓の変更を望まず当時の姓のまま受験期を迎えました。
妻の旧姓ではなく再婚前の男性の姓であったため、学校や役所に書類を提出したりする段階で妻と子の親子関係を証明することが非常に困難でした。
その後、妻の出産を機に妻の実家に引っ越しました。
そこでは妻の旧姓の家族と、別の姓のままの子供と共に暮らしてきましたが、姓が異なることで家族関係に問題があったとは思えません。
現在も子供とは同じ家で別の姓のまま生活をしています。
私たちの間にできた子供とも妻側の血縁関係はありながら兄弟で姓が違っていますが、現在も仲良く暮らしています。
このことによっても、姓の違いが家族の関係に影響を与えるのではなく、あくまでも個々の人間関係が原因で、姓の違いが原因ではありません。
これらのことを自分たちは経験してきているので、反対派の意見が自分たちが経験もしていないで、想像でだけで言っているのに過ぎないことがよくわかります。
別姓になることで問題が発生するのは、役所等の事務をする側の問題だけで、家族間の問題ではありません。
選択的夫婦別性が実施されることで、再婚の場合には夫婦間だけでなく、子供にとっての選択肢や可能性が増えることも大きいと考えます。
一日も早くこの時代遅れな制度を解消し、不幸な人を減らしていけるように願っています。
島本敏 株式会社エーディエフ 代表取締役
自身の結婚式で両親への花束贈呈をした際に、妻のご両親が悲しそうにしている姿は“嫁にやる”という風習が残っているように感じました。姓を変えないことで名字が残るなら、そのような間違った感覚が失くせるのではないかと考えます。現に私の父が「嫁をもらう、ではなく、婿に出す気持ちです」とスピーチして妻側の親戚が拍手喝采でした。
竹田綾夏 株式会社Mirary 代表取締役
ダイバーシティ&インクルージョンという観点から、またアジア諸国でも選択的夫婦別姓が主流となる中、日本が今すぐに取り組むべき課題です。ジェンダーや様々なちがいによって起こる不利益をなくすには、不可欠なアクションと考えます。
山崎繭加 エムスリー株式会社 取締役監査等委員
願いながら半ば諦めていたこと。立ち上がってくださったみなさまに心から感謝しております。
斎藤聖美 ジェイ・ボンド東短証券株式会社 代表取締役社長
強く賛同します
太田彩子 一般社団法人 営業部女子課の会 代表理事Founder
選択的夫婦別姓に賛同します。姓そのものは、その人がキャリアを積み上げたアイデンティティで、自ら選べることは人権の一つです。私自身も、初婚時には相手の姓に合わせた、そして再婚時には夫が自分の姓に合わせた、という経験者です。
大家望 有限会社おおやデンキ 取締役
現実は、女性が名前を変えないといけない、結婚は男性の家に入ることということが一般的であるという考え方が強い中、結婚に対する幸福度やメリットを考えられない女性が多いと思います。人は家庭やプライベートが平等の環境のもとで安心充実できたときこそ、仕事への活力となり、また社会への貢献度が上がると思います。
柳川裕美 Spready株式会社 共同創業者, 取締役
法律としては夫婦どちらかの姓とするとしながら、実態は結婚する夫婦の96%が男性の姓を選択しています。ほぼ慣習といっていい数字です。
古い日本固有の慣習にとらわれることなく、女性が姓を選択する権利があることを望みます。
小浦ゆきえ mog株式会社 代表取締役社長
仕事上旧姓を名乗っています。登記で旧姓併記できるようになっても、不便さは解消されていません。一方で、子ども達は私が旧姓を名乗っていても混乱する様子はありません。別姓を「選択」できることを希望します。
ワーママはる(尾石晴) ポスパム 代表
「あれ?結婚しただけなのに、なんで私だけが社内の名前変更手続きや、旧姓使用申請がいるのかな」最初は小さな気づきですが、そこから大きく夫婦の価値観の違いや、家庭内ジェンダー問題が始まる。結婚前に、2人で話して「選択」できていたら・・・そう思い、いちワーママですが賛同しています。
杉浦加菜子 じょさんしONLINE 代表
多様な価値観、多様な生き方がある現代、個々の選択を尊重できる社会になることが真の意味でのダイバーシティだと思います。
国際化社会になり、より一層多様性が増す中、選択的夫婦別姓は社会の変化のほんの一歩にしかすぎません。この一歩が踏み出せなければ日本は国際化社会の中で取り残されてしまうのではないでしょうか。
多様性が尊重され、それぞれが幸せになることをあきらめないで良い社会にするための一歩として、選択的夫婦別姓に賛同いたします。
宮浦晃一 城北板金機械株式会社 代表取締役
多様性に富んだ働きやすい環境を自分自身で選択できる
こんな素晴らしい事はない
是非、選択的夫婦別姓を実現して欲しい
東和浩 株式会社りそなホールディングス 取締役会長
人それぞれに様々な生き方、輝き方があり、家族の在り方もまたそれぞれの選択肢があっても良いと考え、応援いたします。
塚原 綾子 株式会社アカデミック・ロード 代表取締役社長
次の世代のためにも今実現して欲しい!
今田素子 株式会社インフォバーングループ本社 代表取締役CEO
自身も、ビジネス上、旧姓を変更することに抵抗や違和感があり、実際に様々な場面で苦労もありました。また、女性が変えるのが当たり前という風潮にも疑問が残ります。同姓にしたい人も別姓を名乗りたい人も、誰もが選択する権利を持てるようにするべきだと思います。
赤池円 有限会社グラム・デザイン 代表取締役社長
ひとりひとり、家という単位から切り離されたひとりであっても輝ける日本であってほしいです。待ち受ける厳しい未来を切り開き、みんなで乗り越えていくために、自由を。
小林博之 株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント 代表取締役社長
男女共同参画基本方針で「指導的地位にある人々が性別に隔たりない社会となることを目指す」こととされており、指導的地位としての経営者ポジションを、中小企業における事業承継での女性承継を増やすことによって実現を図ることが、社会全体の活力向上に資するものとなるはずです。
それにもかかわらず、現在女性社長はわずか10%。
多くの女性後継者(予定者も含む)との意見交換を重ねる中で、「結婚して配偶者の姓に合わせること、また離婚して姓を変えることが、女性が経営を行っていく上で、物理的にも心理的にも障害となっていることが非常に多い」との思いに至りました。
女性の事業承継支援を通じて、女性がイキイキと自信をもって経営に臨むことを通じて、日本社会がより働きやすく創造性あふれるものになるべく貢献していきたいと考え、本取り組みに強く賛同いたします。
日下拓 (有)酒田屋 常務取締役 兼 SAKATAYA1793 代表
クオーター制の導入にも賛同しておりますが、この取り組みが「はじめの一歩」一里塚となります事を切に願っております。
鈴木裕二 あんしんプランナー 代表
現在、ひきこもりや就職氷河期世代、障害者の支援を行っております。生き方の多様性が認められないことが、当事者の「はじめの一歩」を躊躇させてしまう結果にも繋がっています。多様な生き方が受容される社会の象徴的な存在として「選択的夫婦別姓」の実現があると思います。
山田理 サイボウズ株式会社 副社長
選択肢を増やすことで幸せになる人しかいない。反対する人は幸せになれる人の機会を奪うことの責任についてどう考えているのだろうか。
バルアビジョイ アプライドエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長CEO
別姓を選択できることは男女が双方活躍する社会において当然の権利で、如何なる場合も選択できないことによる不利益を受ける人々がいてはならない。時代に合わせた柔軟な対応できる法体系が必要と考え、本運動に賛同いたします。
丸山祥子 株式会社フェリタスジャパン 代表取締役
30代で家業(創業90年の建設会社)を父から継ぎました。代表になってから自身の結婚があり、姓が変わることで創業家ブランドが損失されること、取引先や金融機関、建設業許可等の各種届出の煩わしさや二重管理の手間が大きく懸念されました。結果的に、入籍を遅らせることになり、企業経営とパートナーシップの両立に悩みました。
ただでさえ、経営もパートナーシップも問題は尽きません。せめて夫婦別姓を選べることで損失(時間、手間、関係性など)を防ぎ、本来やるべきことに集中できる環境づくりを望みます。
小阪翔 メトロエンジン株式会社 取締役COO兼チーフデータサイエンティスト
キャリアを積む妻の夫として、2人の娘を持つ父として、また、女性が活躍する会社の役員として、選択的夫婦別姓に賛同します。古き悪しき慣習が一つずつ撤廃されていくことで個人としての自由が真の意味で尊重される時代になることを希望します。
行徳未来 合同会社両筑デザインプランツ 代表
仕事は旧姓ですが法人登記は夫の姓です。早くこのねじれを解消したいです。
安森一惠 株式会社クレディセゾン 常務執行役員
同姓を望む2人は夫婦同姓を、別姓を望む2人は夫婦別姓を。
強制しない・選択できる・あたりまえの社会の実現を望みます。
江口晋太朗 株式会社トーキョーベータ 代表取締役
あらゆる人が尊厳をもち、行動するこれからの社会に向けて。
対等なパートナーシップを持って関係を築き、時には、次世代を育む場としての家族のあり方も多様化してくる現代において、選択的夫婦別姓とは、「選択的」に別姓も同姓も選べる社会であるという、自由のもとに選択的な意思決定ができる社会の一つとして、あるべき姿だと考えています。
私自身も、選択的夫婦別姓や対等なパートナーシップの関係づくりをするため、現行の法制度を変えるべきだと考える立場のもと、「事実婚」夫婦として契約に関する契約書や遺言書を作成し、子どもも育てる立場でもあります。
男性も女性も、すべての人が仕事も家庭も充実して過ごすとともに、男女の区別なく、優秀な人材登用や人材投資、そのための働く環境の充実を図る一つとして意味のある施策であり、こうした動きが起きることに心から応援・賛同しています。
鳥居希 株式会社バリューブックス 取締役
呼びかけてくださった皆様、ありがとうございます。選択的夫婦別姓は必要な自由だと思います。法律のアップデートを望みます。
女性の社会進出が進んでいる今、多くの女性が、結婚後に改姓することによって生じる不利益を感じています。アイデンティティ、プライバシー、キャリア、また、女性の事業承継において問題が生じている現状から女性を解放するために、法改正を望みます。
小松智子 小松建設工事株式会社/ケーアンドエス株式会社 取締役
女性であれ、男性であれ、姓名を個人のアイデンティティと考える人は少なくないのではないでしょうか。選択的夫婦別姓は、誰もが自分らしく生きられる社会の実現において、大きな意味を持つと考えます。
ノダマコト 有限会社グラナーテ 代表取締役社長
次の世代のためにもぜひ選択的夫婦別姓の実現を希望します。
金卷朋子 株式会社チクタク 代表取締役社長
離婚した際に苗字が変わったのですが、会社の名義変更で手間と金銭がかかったため
安渕聖司 アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
一人ひとりが自分らしさを追求できるインクルーシブな社会の実現に向けて、私は選択的夫婦別姓制度の法律化に賛同します。
竹内麗子 (有)ライブハウジング 専務
ダイバーシティ推進のために女性の尊厳を守ることが重要。その一歩目は選択的夫婦別姓が認められることです。
平山 香緒利 有限会社まいらいふ 代表取締役
選択肢があった方が良いため
川本明 アスパラントグループ シニアパートナー
「男女共同参画社会」の理念の基本に関わります。抑圧的な旧習を次世代に残してはならないと考えます。
染矢明日香 NPO法人ピルコン 理事長
仕事や研究において、旧姓を使っています。しかし、書類上は本名でなければならなかったり、大学院の受験や学生生活において、改姓・旧姓使用の手続きの煩雑さを女性ばかりが負わなければいけなかったりするのは、不平等であると感じています。大学院の旧姓使用申請の書類には、「旧姓使用は社会制度上整備されておらず、不利益を生ずる可能性がある」「国家試験や資格取得は戸籍上の本名が求められ、氏名が一致しないことによる不都合が起こることが考えられる」等という注意書きが添えられていました。国家公務員、看護師、医師、教員、公認会計士など、あらゆる分野で旧姓と本名のギャップに苦しんだり、不利益を被っている人が今もたくさんいます。新姓を仕事上で使いたい方は、どうぞ使っていただき、結婚をしてもそれ以前からの本名である旧姓を使いたい人が使えるような世の中になるよう、選択的夫婦別姓に賛同します。
柳福女 株式会社オフィスRyu 代表取締役
女性の社会進出に向けての一助になればと思います。
澤円 株式会社圓窓 代表取締役
選択肢がない、という異常さにそろそろ気づかないといけません。自分らしくありたい人生を送るために、姓を大切にするマインドセットも尊重される必要があります。
櫻田謙悟 SOMPOホールディングス株式会社 グループCEO 取締役 代表執行役社長
選択的夫婦別姓は多様性を尊重する制度のひとつであり、すべての人が自分らしく生きられる一要素になると考え賛同します。多様性は、社会の持続的発展につながるイノベーションを生み出し、新たな価値創造に結びつけるための原動力になります。これらの取組みが、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会の実現に繋がると確信しています。
酒井香世子 損害保険ジャパン株式会社 取締役執行役員
私自身が旧姓使用をしており、ビジネス遂行上の様々な面で生産性を阻害されることをまさに実感してきました。選択的夫婦別姓が法制度化されることで当たり前のことが当たり前に選択できる世の中になることを願っています。
中山淳子 Domani 代表
この署名に参加する機会を与えてくださってありがとうございます。選べる自由。夫の苗字でも、妻側の苗字でも、夫婦別々の苗字でも。いろんな選択があるということ。それこそが真のダイバーシティだと思います。選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
森林育代 株式会社シーズプレイス 代表取締役社長
なぜ選択的夫婦別姓に「反対」するのか。その理由が「個人を尊重」し「日本の未来」を考えているように思えないからです。
賛同理由はきっと多くの皆さんのご意見と同じです。
敢えて賛同理由を述べるまでもないくらいの、人としての生活の話です。
イデオロギーの問題にしてはならないです。
青野さんが作って下さったこのムーブメントを機に改正へ向かうよう、私も事業活動を通して後押ししていきます。
髙橋英二 味の素企業年金基金 事務長
選択の自由やダイバーシティーの観点でも大切なことかと思っています。
小野﨑悠介 Pathfinder株式会社 代表取締役
子を持つ親として、子供の将来において姓で悩むような事なく、自己実現して欲しい。
氏名非公表 所属先非公表
海外で働く人にとって、パスポートに旧姓が表記されても、現地の社会保障番号などの制度ではそもそも、「夫婦別姓」が認められているため、旧姓表記のシステム自体が存在せず、泣く泣く戸籍名を使用することになってしまいます。
また、アーティストとして本名を用いて国内外で仕事をしてきた私にとっては、あえて本名を表に出して仕事をしてきた誇りがペンネームになってしまうという仕事上の不便/精神的苦痛が伴いました。
海外のアーティスト仲間は大半が別姓で仕事をしていますし、家族も幸せに溢れています。
今年入籍した際も様々な追加書類であったり、窓口での心ない対応に会う、戸籍変更が変更完了しないとマイナンバーカードと住民票の旧姓併記ができず、その2点どちらかがないと婚姻届受理証明書などは認められず、運転免許の併記新規発行がすぐできないなど行政の不備も沢山残っています。(新姓であれば即日できると、窓口で暗に新姓を使うことを促されました)
これらの苦労は、夫婦別姓が当たり前に認められれば一切発生せず、対応するたびに落胆をして家族に心配をかけることも起こりません。
一刻も早く選択的夫婦別姓を願います。
砂川裕子 株式会社フォーモスト 代表取締役
選択肢があること が思考停止の防止になればと願う。
藤田徳子 株式会社フェアリー・テイル 代表取締役
私自身も、旧姓及び「家」ということにすごくこだわりを持っていて、願わくば旧姓のままにしておきたかったです。
私が結婚する25年前の当時は、そんなこと、取り上げてもらうこともかないませんでした。
堀江敦子 スリール株式会社 代表取締役社長
2年前に結婚し夫の姓になっています。
登記簿謄本もマイナンバーも免許証も、旧姓併記にしていますが、戸籍や銀行口座が新姓であるため、実際は書面上は全て新姓にする必要があり、旧姓併記の意味は全く意味がありません。経営層やアカデミックの指導的役割にも女性が増えていく上で、選択的夫婦別姓は効果的な方法だと考えます。
また、「2度前の姓に戻れない」という規定や、LGBTQの家族などから、家族全員が違う姓の家庭が、実態として増えています。選択した人だけが実施ができるという形を取れば、現行の戸籍の仕組みでも問題なく対応できます。
日本しか実施していない、強制的夫婦同姓を是非世界水準へ変革していきましょう。
横田響子 株式会社コラボラボ(女性社長.net企画運営) 代表取締役
誰もが選択の権利を持ち、他者の選択を阻害しない。個々人を尊重する社会を望みます。
小宮仁至 ファンシップ株式会社 代表取締役
もはや、選択的夫婦別姓に反対する理由が、皆無なので諸手を挙げて賛同します。
宮田賀生 宮田コンサルティング 代表
賛同します
鍋嶋洋行 大橋運輸株式会社 代表取締役社長
時代と共に社会の価値観も変化します。多様性を受け入れる社会として、選択的夫婦別姓も必要と感じます。
田頭倫子 株式会社ナニラニ 取締役
仕事では当然旧姓を継続して使っていますが、そちらがずっと本来の自分であり、プライベートや子供周りで使用する結婚後の姓は本来の自分ではない感覚がずっとあります。結婚して15年ですが、変わりません。
子供たちにとって、お父さん・お母さんの、苗字も含めた名前がそれぞれにあることが当たり前、と早くなってほしいとずっと願っています。国際結婚で生まれた子供が性を両親両方から取っているように、日本人同士でもそうなれば良いのではないでしょうか。(便宜上どちらかを選択して使うでも良いかもしれませんが。)
籍を抜く、入れる、という日本古来の制度にも同様に抵抗がありますし、選択的夫婦別姓制度が試行される際はそこも議題に上がることではないでしょうか。併せて議論できれば良いと思います。
竹内香予子 平安伸銅工業株式会社 代表取締役
選択的夫婦別姓に賛同する理由に、自身の経験が影響しています。
私は、結婚時に夫の姓になりましたが、数年は旧姓を通名として仕事をしていましたが、最終的には仕事でも戸籍名を使うように変更しています。
このことから、通名を使う不便さ、改姓することの喪失感、両方経験し、その際に「改姓せずとも、婚姻関係が成り立つ方法はないのか?」と疑問を感じました。
この解決策として、「選択」を提示しているのは、非常に画期的なことと感じています。それは改姓を望む人、望まない人、それぞれの意思を尊重できるからです。
選択的夫婦別姓の実現は、家族の在り方を議論しているようで、実は日本の社会を変える大きな一歩になるのではないでしょうか?望まない改姓をなくすことは、結婚後も仕事を続ける女性が増える中、女性の活躍を後押しする効果があります。また、改姓についての選択肢を増やすことは、多様性に対する価値観を社会に根付かす一助にもなると思っています。
以上のことから、過去のルールにとらわれず、改姓する人改姓しない人ともに尊重される、そんな社会の実現を望みます。
吉田耕太郎 所属先非公表 代表取締役社長
誰もが幸せな暮らしができる社会の実現を目指してください
伊藤毅 CREリートアドバイザーズ株式会社 代表取締役
生まれた時から慣れ親しんだ姓を強制的に変更させられることは、自らのアイデンティティの1つを傷つけられるようなものです。そうした理不尽は見直していくべきものと考えます。
もちろん、夫婦で同姓を希望するカップルもいらっしゃるでしょうから、選択的夫婦別姓により「望む人だけが改姓し、望まない改姓はゼロにする」ことが実現すれば、各人の考えを尊重できる素晴らしい制度になると期待しています。
大垣伸悟 株式会社ギガスリート 代表取締役
多様性の高い社会の実現へ
堀内文雄 株式会社クラベス 代表取締役
外国では両親の名字を引き継いでいたりしますよね。家系の両方からの血が見えることは良いことだと思いますし、「選択できること」は大事だと感じています。
高塚苑美 株式会社グローバルセールスパートナーズ 代表取締役
個人の権利、アイデンティティとして夫婦別姓は認められるべき。世界の中での日本を客観的に見つめ、グローバル社会に対応してほしい。
中村真広 株式会社ツクルバ 代表取締役ファウンダー
開かれた選択肢があり、そのなかで自律的な判断をしていくことは、現代において個人に委ねられた幸せな「余白」であると思います。そして、その余白を広く肯定できる社会であってほしい。選択制夫婦別姓もその一つだと考え、本声明に賛同致します。
坂東愛子 合同会社マム・スマイル 代表社員
結婚時名前の変更によってビジネス上対顧客や関係者などに新しい姓をを覚えてもらうのが大変だったり書類の手続き変更が多いため女性だけにとても負荷がかかり不公平さを感じておりました。
選択的夫婦別姓に大賛成です!!!
堀潤 NPO法人8bitNews /株式会社GARDEN 代表理事/CEO
100人いれば、100通りの生き方が認められる懐の深い社会に。そして、制度として誰かに負担が偏るアンバランスさを是正するために、賛同します。
大洲早生李 Global Stage Inc. Founder & CEO
夫婦別姓であっても家族は家族です。同姓にすることにより、会社やコミュニティでどれだけ女性が苦労してきたのでしょうか。同じ苦労を味わった人間として、賛同します。
椎野和久 株式会社上組 取締役
相続問題など別姓を選択できれば解決出来る事が多々あるので
高橋烈央 ラグスタ株式会社 取締役
多様性を理解し、認め合える社会へ
石黒不二代 ネットイヤーグループ 株式会社 代表取締役社長CEO
社会的信用を築いた名前を使い続けることを選択できる権利は、基本的人権であると考えます。姓を変えることに伴う諸手続きは煩雑で、往往にして、女性だけがその負担を負っている不利益を解消する必要があると思っています。
伊東正仁 日本地震再保険株式会社 取締役社長
選択肢を広げることが、コミュニケーションや考える機会にもなり次世代にとってもプラスと私は考えます
浜田恵美子 所属先非公表 取締役
研究者時代より一貫して旧姓を使用してきましたが、多くの場面で不都合な状況に直面してきました。パスポートの旧姓併記により、国外での活動などで解決できたことも多くありましたが、個人の権利に関わる場面(特許等)、また個人の責任が問われる場面(契約等)において、旧姓の通称使用には限界を感じます。
また、すでに30年以上、旧姓を使用してきましたが、学生時代のネットワークなどを失わずにこれたのは、旧姓使用の大きなメリットであることを実感しています。
さらには、還暦を過ぎて自身の経歴を振り返り、現在の自分の存在がひとつの名前で表わされていることの意味を強く認識しています。すべての経験や人との関係が繋がって今日の環境を形作っているからです。旧姓を使い続けてきて本当に良かったと思います。
それだけに、本人の意思に反して未来に大きな不利を被る方を生まないために、選択制の実現を強く要望いたします。
竹下小百合 三共ビジネス有限会社 代表取締役社長
私たちのアクションで、未来を担う次世代の人たちに自由な選択を!
有明三樹子 株式会社りそなホールディングス(りそな銀行) 執行役(常務執行役員)
結婚した瞬間に旧姓で作っていた実印が無効となった不条理に愕然とした経験は今も忘れません。「女性は苗字じゃなくて下の名前で実印を作ったらいいんですよ」と区役所の方。免許書、金融機関、健康保険証、クレジットカード、、、、仕事では旧姓が使えたものの、なぜこんなことに手間暇をかけなくてはいけないのかと感じたことが昨日のことのようです。
中川祥太 株式会社キャスター 代表取締役社長
意味の無い強制は必要無いかなと
本山晴子 有限会社コ・リード 代表取締役
通称使用による公的署名や契約書、国家資格証明書など、まだできないものもある。個人番号カードや印鑑証明書に旧氏が併記されるようになったのは、よいことだが、根本的に別姓での戸籍登録を可能にし、個人の尊厳の最大化を図ってほしい。
伊藤久美子 株式会社パソコンレスキューサービス 代表取締役
女性がますます社会進出していく時代において、結婚により「姓」を変更しなくてはいけない社会の風潮では、女性が社会進出していくためにはきわめて非効率だと思います。これからの日本の女性進出を高めるためにも、選択的夫婦別姓の早期導入を願います。
加藤陽太郎 アップハーツ株式会社 代表取締役
姓はアイデンティティだ。
塚原月子 株式会社カレイディスト 代表取締役
生まれた家の姓を持ち続けること、配偶者と同じ姓になること、どちらも自分の姓名への真摯な向き合い方だと思います。自分と家族が心から望んで選んだ名乗り方が法的に保護されることは基本的かつ重要なことだと思います。
森山貴士 一般社団法人オムスビ 代表理事
現代では、社会構造によって決められたジェンダーロールによって女性だけではなく男性も含めて苦しい思いをしていると考えています。選択的夫婦別姓は一方に寄せられていた負担を平坦にしていくという意味で、社会の生きづらさをなくしていく一歩になっていくと考えています。
田原悠西 株式会社Nexedi 代表取締役社長
自分の氏名をどうするかは自分自身で自由に決められるべきです。
匿名希望 団体理事
私自身海外生活が長く、日本の結婚の姓制度に違和感しかありません。結婚で姓が変わることに抵抗があり、私も結婚せずにいます。選択制は誰にも不自由をさせることがない制度と思います。女性が生きやすく、世界的にみてスタンダードな国になるために、今こそ変わるべきと思います。
村山利栄 株式会社新生銀行 取締役
実際に不便なのです。 私も属する会社も。 結婚前の姓を通称として仕事上利用し続ける必要があり、そうしていますが、様々な場面で本人確認書類の提出が必要となり、多くの関わるスタッフおよび本人にとって負担となっています。 選択する権利が与えられないことが永年疑問でした。今回は署名のチャンスを頂き、感謝しております。
豊田圭一 株式会社スパイスアップ・ジャパン 代表取締役
選択の自由がある現代において、姓の選択ができないことによって、結婚したものの、仕事においては通称という形で旧姓を名乗っているという実態はナンセンスだと思います。選択的夫婦別姓に賛成です。
徳原康成 株式会社TEGOS 代表取締役社長
結婚する二人が別姓にしたいというなら、みんなで二人の決定を応援する世の中になって欲しいと思います
小川貴弘 創販株式会社 代表取締役
自分の裁量で選択肢の中から決定するという次の文化を創る。女性が活躍してきている現状で女性蔑視で政治家等がものすごく叩かれる時代になった。しかし、夫婦になった際に強制的に女性は男性の姓を名乗らなければいけないという古い文化との矛盾を無くしていくことが大事だと思います。
金春利幸 アールスリーインスティテュート 取締役 Chief Innovatoin Officer
経営者として従業員が働きやすい環境を作るのは当然の責務と考えています。その中で多様な選択肢を提供することは非常に大切だと考えています。選択的夫婦別姓も当然の権利だと考えられ、従業員をはじめすべての人の生活上の負担を取り除くべく、本活動に賛同いたします。
船戸大輔 株式会社アートフル 代表取締役社長
時代に合わせて豊かで働きやすい世の中がどうあるべきかという点で非常に重要だと考えています。個々人の状況に合わせて希望する姓を選択できる世の中に。
仲村薫 デロイト トーマツ グループ CHRO (人事担当執行役員)
当グループでは、公認会計士や税理士、弁護士などの士業従事者を含む多くのプロフェッショナルがクライアント・社会へ価値を提供すべく日々活躍しています。
社内システムとしては旧姓を使用できるように対応済みではありますが、改姓に伴う実務的・精神的負荷のすべてを軽減できるわけではありません。
「結婚しても改姓しない」という選択が法的に尊重される、誰もが働きやすいインクルーシブな社会へ向け、人事担当執行役員として、また一人の女性リーダーとして、ジェンダーに関わらずすべての人が活躍できる環境構築を推進していきたく思います。
溝口晴康 株式会社アントレッフェン 代表取締役社長
選択肢を増やしたほうが一人ひとりに向き合う幸せにつながり、持続可能な世の中を実現できそう
松野絵里子 H.U.グループホールディングス株式会社 社外取締役
仕事上の名前で銀行口座もカードもつくれず、不便です。多様な家族の形の選択ができる社会が望ましいと思います。
堀江誠 有限会社オフィス五円玉 代表取締役社長
個の尊重は人権の基本であり、自由で開かれた民主社会成立の基盤です。
宮平貴子 株式会社ククルビジョン 代表取締役社長
選択性に反対の人のなかには「家族制度を崩壊させる」という意見があるが、「生まれ育った家の姓を受け継ぎたい人」は男女問わず多くいらっしゃり、それこそ家族を存続させ、守りたい気持ちを無視している。また名字の変更にともなう煩雑な手続き、対価も女性側にだけ強いられる慣習は、少子化対策・女性の活躍といった国の政策とも矛盾しており非合理的に思う。早急にアクションが必要で、次世代に受け継ぐべきものではない。
黒田由貴子 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー
結婚して名前を変えることによる経済的損失を証明せよ、なんて話を聞きますが、そんな次元のことではなく、人権に関わる問題と考えます。自分自身、旧姓を通称として使っていますが、そもそもそんなことをしなくてはいけないことに苦しみます。
伊藤数子 NPO法人STAND 代表理事
伸び伸びと自由に社会活動ができる社会を実現したいです。
脇野真梨江 株式会社クラインベスト 代表取締役
私自身も夫婦別姓が認められない日本で入籍を諦めた当事者です。
名字を変えたくないという事を当時のパートナーに伝えたところ「養子になれとでも?男が名字を変えるなんて恥ずかしくて職場の人に言えない」との事。
女性が男性の名字に変えるのは「当然」とされ、その逆だと「恥ずかしい」となる現状に男女の不平等さを痛感しました。
名字が変わる事で自身のアイデンティティまで失うような喪失感に襲われ、同時にこれまで受け継がれてきた名字を自分の入籍により途絶えさせてしまうかもしれないと考えると父親に非常に申し訳ない気持ちになりました。
「望む人は夫婦同姓、望まない人は夫婦別姓」と、日本が個人の考えと人権を尊重する社会となる事を願っております。
脇野真梨江 株式会社クラインベスト 代表取締役
私自身も夫婦別姓が認められない日本で入籍を諦めた当事者です。
名字を変えたくないという事を当時のパートナーに伝えたところ「養子になれとでも?男が名字を変えるなんて恥ずかしくて職場の人に言えない」との事。
女性が男性の名字に変えるのは「当然」とされ、その逆だと「恥ずかしい」となる現状に男女の不平等さを痛感しました。
名字が変わる事で自身のアイデンティティまで失うような喪失感に襲われ、同時にこれまで受け継がれてきた名字を自分の入籍により途絶えさせてしまうかもしれないと考えると父親に非常に申し訳ない気持ちになりました。
「望む人は夫婦同姓、望まない人は夫婦別姓」と、日本が個人の考えと人権を尊重する社会となる事を願っております。
生田明子 合同会社あやとり 代表社員
自分自身、旧姓の生田を名乗って会社経営しております。登記や税務、契約書など、戸籍名の北條を名乗らざるを得ず、不都合不便、アイデンティティの不一致に苦労しております。
三浦恭平 株式会社グース 代表取締役
選択できないことで、迷い、苦しむひとがいるという状態を変えたいです。
さらには、それぞれが、自分とはなにか、パートナーとの関係はどういう関係か、家族とはどういうチームか、平等とはなにか、考えて決めていくきっかけづくりにつながっていければいいなと考えています。
記野直子 カイオス株式会社 代表取締役
結婚して25年ほどになりますが、仕事をする意味ではずっと旧姓で続けています。しかしこの旧姓使用は「非公式」であり、会社登記、その他公的なものはすべて本名(結婚後)での記載を強いられていたため、実際に私が私として社会に認識されるにはかなりの細工が必要でした。これらの詳細を述べれば語りつくすのに何日もかかりそうです(笑)。
私たちは、男女別姓を基本にして欲しいのではなく、男女別姓の「選択肢」が欲しいだけです。決して男女同姓に異論を唱えるものではありません。ココがどうしても正しく理解されていない気がします。
伊藤久美 4U Lifecare株式会社 代表取締役社長
自分は結婚していないから興味がない、自分は旧姓使用で困っていない、姓を変えても嫌ではない、という消極的な理由でこのテーマを捉えている方も多いのではないかと思います。でも必要なのはそれぞれの個人が自分らしく生きたい、それを支える社会であることではないかと思います。姓を変えることに大きな犠牲が伴う、喪失感がある、いろいろな理由で生まれたからの姓をそのまま使いたいと思う人の気持ちに寄り添って、誰もがニコニコ生きていける社会を作ることに賛同します。
西田涼輔 株式会社natn 代表取締役社長
ビジネスネームとして旧姓を使っているのですが、登記や銀行、契約書は現在の姓を使うのは、混乱もあり大変です。
夫婦別姓も選択できるようになることを強く希望します。
石倉秀明 株式会社キャスター 取締役COO
私には5歳の娘がいるのですが、娘が結婚する時に自らの姓を自らの意思で選ぶことができない社会を残したいとは思いません。
1人の親として、そして多くの子供たちがこれから生きる社会を作る社会の一員として、自らの意思で自らの姓を選ぶことが当たり前になることを強く望みます。
浅山理恵 三井住友銀行 執行役員
本質的な解決ではないと思いながらも、ビジネスネームと称し、自分の姓を通してきました。単一企業の施策やルールでなく、ようやく誰もが選べる社会に近づいてきたと感じています。誰もが個として自立し働き社会と関わっていける時代になりますよう、そして日本の女性がもっと輝けますよう、切に願っています。
村田明音 株式会社しらかべ企画社 代表取締役社長
旧姓で積み上げたキャリアがあるため、結婚後も旧姓の名刺で仕事を続けています。法人化をするにあたり、定款上は「現姓◎◎(旧姓◎◎)」という表記にしましたが、銀行口座などの表記は現姓のみの表記となっています。融資や契約の際など重要な場面でも、必要となるのは現姓のみ。定款上で旧姓と現姓を併記した意味が全くない状態です。表記ひとつの話ですが、自分がこれまで築いてきたものを他人に明け渡しているような感覚にさえなります。結婚というのはプライベートな領域です。結婚相手の戸籍に入るのも喜ばしいことですが、仕事には関係ありません。どうか、選択的夫婦別姓が叶いますように。
南部陽介 株式会社レヴィ 代表取締役
「名前」とは何でしょうか?3.1415926... という数字の羅列を人は「円周率」と呼びます。そもそも1,2,3,...という数字も、数を比較するために、人が作り出したものです。わり算という計算を覚えた人が、1を3で割ったときの答えを表そうとして困り、「1/3」という名前の分数を生み出しました。方程式を覚えた人が、その解を表現する術に困り、平方根や複素数といったものを生み出しました。人の知性は、未知の概念に名前を付けることで、発展してきたように思います。
社会は、人の認知の重ね合わせで出来上がっています。人の認知は、名前付けに大きく依存します。名前の付いた概念は理解しやすく、そうでない概念は理解が難しい。
人を表す名前も同様です。名前があること、名前を知ることによって、自己や他者の認知は格段に高まります。ここでいう名前は、特に自己認知にとっては、当然、姓名一体のものです。姓を変えた瞬間に、自己を表す概念は変わります。
良い悪いという話ではなく、変わります。
その変化を肯定的に受け入れる人もいれば、そうでない人もいるでしょう。自己の概念は、自分のものです。だからこそ、そこに大きく介入する名前に、法的な拘束は極力設けるべきではないと思います。男女問わず、人は自身の名前を保持する権利を持つべきと思います。
本竜晋 社会福祉法人野の花会 業務執行理事 双葉保育園園長
姓が変わることで、アイデンティティを失う思いをした人達の思いを代弁します。
私も職場では別姓で働いていますが、それがあたりまえの世の中になりますように。
森下麻由美 エポックシード株式会社 代表取締役社長
一人ひとりが自律したキャリアを築ける環境づくりと、選択肢の広がりが生み出す多様性とその豊かさの実現のために、私は選択的夫婦別姓制度法制化の推進に賛同します。
私は、いずれの性別によらず、それまでのアイデンティティやキャリアの実績を刻んできた自分の姓について、選択の自由とそれに対する理解ある社会づくりが大切だと考えています。
私自身、幼少期に姉が父親の姓でいじめにあったのをきっかけに、夫婦別姓という選択肢がなかったため、両親が父方親族に説明にまわり、実態は家族でありながらも、子どもたちの姓を変えるために離婚し、父方親族が鬼籍に入るまで、事実婚の形式をとらねばならない環境で育ちました。今ほど一般に事実婚の認知がないなかで、学校へ事実婚の理由を説明をするたびに「苗字のために、家族なのに何故」と違和感を覚えていました。
また、結婚のときには、個人だけでなく会社にまつわる手続きの煩雑さに、大変苦労しました。特に、パートナーの理解もあり、ビジネス上では旧姓で通しているため行った登記の旧姓併記手続きで「国が旧姓を載せるのを認めてくれただけです」と言われて、旧姓併記の意味について改めて考えました。
社会は、様々な事情を持つ人たちが、集い、寄り添いあっているできています。だから、多様性を活かす制度設計により、一人ひとりの力を引き出すことができると信じています。ぜひ、この声が少しでも状況改善につながればと願っています。
最後に、社会を変えていく扉を、不断の努力で押し広げようとしてくださっている先人の皆様、ありがとうございます。
中川寿子 生活協同組合コープこうべ 常勤理事
自分らしく生きるために別姓を選んだ人が、不利益を被る現状はおかしいと思います。
早期の法制化を願っています。
横山真也 ヨコヤマ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役
戸籍があるために婚外子を産めないのが出生率が増えない原因の一つ。世界的にも稀有な戸籍制度はこれからの時代には合わない。
石橋正朗 石橋製油株式会社 代表取締役
賛同します
中島努 Nippon Wealth Limited Chief Executive Officer
組織や家から個人の時代になって来た今日、日本が規範を示す時だと考えます。
瀬戸川礼子 合同会社リバーオフィス 代表社員
呼びかけ人、とりわけ青野さんの多大なるご尽力に感謝します!
中村暁 所属先非公表 CTO
結婚にあたって夫である私の方が姓を変えました。婚姻という平等なパートナーシップの制度において、どちらか一方が不利益を被る自体は改めるべきです。
松岡克政 株式会社かたちえ 代表取締役社長
「おかしい」ということも検討しないままに当たり前になっていることが世で認知、認識され始めてくる時代になりました。
どれも大事。でも一つずつ。
しっかり考えて、「本当の当たり前」に気づける自分でありたいし、そういう社会を人を育む一員でいたいと思います。そういう点でも先駆者の皆様に大いに賛同いたします。
ありがとうございます。
佐藤仙務 株式会社仙拓 代表取締役社長
強制されるより、選択肢のある社会の実現を。
野坂哲史 株式会社吉田正樹事務所 取締役COO
何事も、選択できない不自由さはとても恐ろしいです。
西綾 株式会社輝く羽 代表取締役社長
形の意味合いはあるとは思いますが、個々に選ぶ自由は大切な事だと思います。特に女性は、姓が変わる事による苦労はたくさんあります。
宮城直 司法書士宮城事務所 代表司法書士
単なる要望ではなく、戸籍制度の変更案まで納得出来るものだったので、実現可能と判断し賛同致します。
井上拓磨 株式会社はたらクリエイト 代表取締役
自分らしさを尊重し選択できる社会になることを願っています。
牧山嘉道 フィルミネーション株式会社 取締役
個人の尊厳・尊重の点からは、選択的夫婦別姓は自然なことだと思います。夫婦同姓が良い人は同姓を選択すればよいし、夫婦別姓が良い人は別姓を選択すればよいので、この点、個人の自由でよいはずでしょう。ちなみに、海外では、夫婦両姓を名乗る人(例えば、巨匠指揮者のハンス・シュミット=イッセルシュテットなど)もいます。
土橋一夫 株式会社デトリタス 代表取締役
同姓の強制により、実態としてたくさんの女性に大きな経済的負担や面倒を押し付けている、と感じています。婚姻率や出生率の低下の一因にもなっているように思います。選択的夫婦別姓に賛同します。
桂Jasmine茉利子 MODALAVA株式会社 代表取締役
結婚や離婚という個人情報と仕事や社会との関係が必ず連動しなくても良いとずっと思っていました。これを気に「自分が選んだこと」に偏見の色がつく感情的慣習が薄れてくれればと思います。前職で10年在籍させて頂いていたフューチャーを率いていた金丸さんが先導されていて嬉しいです!
長友佑樹 株式会社マーサリー 代表取締役
同姓でも別姓でも選択できるようにすればいいのだと思います。結婚して別姓でも、二人の愛情には何の問題もありません。
杉山亨 所属先非公表
多様性が当たり前の時代となりましたが、法律が追い付いていないように思います。この法改正をきっかけに様々な分野で時代に則した法改正が為されていくことになると良いかと思います。
高瀬和哉 株式会社YELLOWPARKS 執行役員 営業部長
意味のない伝統や習慣は柔軟に変化すべきどと考えています。この活動の支持いたします。
永瀬文昭 所属先非公表
事実婚当事者です。妻を私の税法上の扶養に入れ、年末調整で配偶者控除を受けるため、毎年年末に婚姻届を提出し、年が明けてすぐに離婚届を出しています。そのため、会社の労務、総務に過剰な負担をかけており、心苦しい限りです。早期の選択的夫婦別姓制度の法制化を望んでいます。
四宮琴絵 株式会社ジョイゾー 取締役COO
同姓になることも別姓でいることも尊重される制度を望んでいます。
伴野卓磨 有限会社北海道新聞永田販売所 代表取締役社長
同じ姓でいたいという思いと同様に、別姓でいたいという思いも尊重されるべきです
小林健伸 株式会社サラ 代表取締役CEO
法制審答申から25年を経過しても未だ閣議決定をためらい続ける理由はどこにもない。明治民法で初めて出来たにすぎない夫婦同姓制度は日本の伝統ではない。マイナンバーが普及し社会が大きくパラダイムシフトする時代に世界唯一の制約に固執するようでは、そのことだけでも我が国がグローバルな潮流から遅れていくことになるだろう。
江渡公則 株式会社ユニークワーク 代表取締役社長
国が選択という他者の自由を認めないのであれば、多様性を認めていないことと同義と考えます。慣習に捉われずに実現していただきたいです。
根上春 数学カフェ 代表理事
まさにこの春、法人設立手続きを通じて旧姓使用の様々なハードルを経験し、夫婦の片方にだけ過剰に負担がのしかかる制度の不便さ・理不尽さを痛感しています。婚姻に伴う改姓手続きの際には旧姓を戸籍・住民票に付記できるという選択肢が提示されなかったため、旧姓が付記された身分証明書を得るために別途役所に足を運ばなくてはなりませんでした。また、登記名に旧姓を記載する場合の正しい手続き方法の仕組み化や担当者への周知が不完全なために事務手続きに手戻りが発生し、書類を訂正し再提出しなければなりませんでした。旧姓利用が進んでいるとは言いますが、銀行口座や法人の登記など高い法的根拠が求められる場面では、本名でないという事実があるために多くの障害に直面しています。このような負担は創造的な思索に使う時間を奪うものです。
私個人が夫婦別姓を希望する理由は、旧姓の方が珍しいので覚えてもらいやすい、本名を使うと結婚前からの仕事と紐付けられなくなる、夫と共に団体運営をしているので本名を使うと他の人からの識別性が低くなる、旧姓に愛着がある、などです。各種調査でも選択的夫婦別姓を支持する人の割合は年々高まっております。選択的夫婦別姓の早期実現を望みます。
黒田浩史 黒田精工株式会社 代表取締役社長
結婚をした場合でも社内外の業務利便性や効率上旧姓を使い続けるニーズは高い。社会の多様性重視の観点からも、姓を変更するかどうかを選択できることは合理的と考える。
満間摂子 ソダテキカク 代表
姓を変えることで、社会的にも経済的にも、そして個人としても蒙る不利益は大きい。
だが、姓を変えることで新しい自分を見つけることも可能かもしれない。
だから、夫婦同姓か夫婦別姓かを選択できることにメリットはある。
同じ姓でなければ家族の結束力が弱まるのであれば、それは記号的家族でしかないだろう。
五嶋耀祥 一般社団法人ファミリー支援INV協会 代表理事
ビジネスネームの改名による女性活躍の制限やリスクから解放されるためにも、男女共同参画への第一歩です。実現することを強く望みます。
森暁彦 ENECHANGE株式会社 取締役
結婚して働く大人(多くの場合は女性)がビジネスや社会の現場にてハンデキャップのないように、そして何より名前という個人が最も大切とするアイデンティティを尊重する社会を作っていきたいと思っています。
木浦幹雄 アンカーデザイン株式会社 代表取締役社長
私達ひとりひとりが尊重されるインクルーシブな社会の実現に向けて、選択的夫婦別姓制度の法律化に賛同します。
井出有希 株式会社シェアダイン 共同代表
あらゆることが選択できる社会の実現に向けて、選択的夫婦別姓に賛同します。
石原彰太郎 株式会社 コスモス・プラン 代表取締役
この活動に賛同致します
川嶋治子 ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社 代表取締役
選択的夫婦別姓は、望む人のみが夫婦同姓となり、望まない改姓をゼロとする、全ての人が自分らしく望む人生のあり方を実現する選択肢を生み出すものです。これまで、選択肢がなかった日本に選択肢が生まれます。
学生時代、私が大人になる頃には日本でも別姓が選択できるようになるだろうと思っていました。しかし、今尚実現に至らず2021年を迎ています。
私は自らも結婚しビジネスリーダーとなった今、10代の頃から望んでいた未来を早期に実現して、次世代にバトンを手渡していきたいと考えています。
この署名はその意思あるビジネスリーダー等が賛同するアクション。これまでも、意思ある先人等が社会課題を一つ一つ解決してきてくれました。私達が現役世代でいられる間にどれだけ社会を前進させられるかは私達一人一人の意思ある選択によるものだと思います。真の多様性ある社会を私は現役世代の間に実現したいと考えます。
難波昇平 株式会社AAIC Japan 代表取締役社長
日本と新興国の成長を支援する弊社として、日本での多様性のある社会の実現は、新興国における選択の自由や多様な社会のあり方を示し、後押しする上でも必須であると考えています。仕事や生活の中での不自由をなくし、平等な社会の実現のための当然の手段として、個人の意思を尊重し、選択的に性を選択できる本案の実現に賛同します。
岡坂泰寛 株式会社ロイター板 代表取締役社長
同姓にするか別姓にするか、夫婦が自ら考え自由に選択ができるというのが、本来あるべき姿だと思います。
城谷弘明 みんなのIT協会 代表理事
旧姓利用に関して、離婚を経験した母の苦労を生の目で見て来ました。最高裁判所は強制的夫婦同氏制という考え方自体に否定的な考えが多数派な判決を下しましたが、伝統に名を借りた不合理は国民の手で令和の世で終わりにするべきです。
原繭子 原公認会計士事務所 代表
私自身旧姓で仕事しておりますが、同時に仕事上においてどうしても戸籍名も必要な場面があり、煩雑です。
仕事、アイデンティティ、どちらの面から考えても、選択の自由があることを望んでいます。
河野一美 有限会社リバー&ブリッジ 代表取締役
選ぶ権利を否定する理由がありません。そして、賛同しない方々は、別姓を採用している国の方々に対してどう考えているのか知りたいです。
鈴木直子 株式会社グリーンズ 取締役人事本部長
選択的夫婦別姓に賛同します。これまで数社の経験がありますが一貫して旧姓をビジネスネームとして使用しております。数年前、歴史あるメーカーに転職した際に、転職の条件に旧姓使用を認めてもらっていましたが、入社当日、労務事務の女性社員に『例がないので認めません』と言われ、泣く泣く旧姓利用をあきらめました。ですが、数年後、自分が人事部門の管理職になり、そのルールを変え、旧姓利用第1号になりました。するとその後、多くの女性社員が旧姓利用をはじめました。たったこれだけのことですが、非常にパワーも抵抗勢力もあった記憶があります。たまたま私は変えたいという気力とタイミングがあったため突破することができましたが、これは誰もができることではないとも思います。現在、上場会社の役員を務めておりますが、私は離婚時に旧姓には戻らず離婚前の姓で戸籍をつくり、子どもたちを自分の戸籍に入れました。役員登記は旧姓併記ですが、独身であることがわかると、先方に説明するのが非常に難しいです。またもしも、今後再婚するようなことがあった場合、相手の戸籍に入ってしまうと、一生旧姓には戻れないので、ビジネスネームで仕事してもそのバックボーンがなくなるのは説明もつかないし、悲しいとも思います。(予定はありませんが・・・笑)選べる時代が来ますように。
頼母木俊輔 株式会社コルクラボギルド 代表取締役
令和にもなっていまだに選択的夫婦別姓に反対する政治家がいるのは、理解に苦しみます。時代遅れな法律は速やかに改正しましょう。
村上誠典 シニフィアン株式会社 共同代表
選択的夫婦別姓制度への早急に移行すべきだと考えています。名前は大きなアイデンティティの一つです。生まれてから常に共に時間を過ごし、人生やキャリアも名前と共に刻まれていきます。社会人となった後、結婚や離婚という極めてプライベートな事象と名前の変更という極めて形式的な事象が同列に扱われ、それによりアイデンティの毀損とプライバシーの守秘性が危険にさらされることになります。LGBTや外国人など考えるべきダイバーシティの問題は多数ありますが、少なくとも女性の社会進出がこれだけ進み、また女性の活躍が大きな社会的価値を生み出すことが明らかな現在において、アンマッチな制度だと考えています。アイデンティとプライバシーに対する感度が低い方にとっては理解し難いかもしれませんが、感度の高い方にとってはこの問題は非常に大きな悩みの種となっており、社会活動を減速させる一要因となっていると感じています。今、我々人類は「個」の時代を生きるようになってきています。これまでの家族や社会といったつながりを尊重しつつも、それにより少し蔑ろにされてた「個」の尊重に対して、もう少し寄り添うべき時代が到来したのだと思います。
成井隆太郎 ヤマト運輸株式会社 執行役員
誰もが自分らしく生きることができる社会こそが、本当の意味で豊かな社会であると信じています。
村上太一 株式会社リブセンス 代表取締役社長
選択的夫婦別姓制度が実現することで、別姓を希望して結婚に躊躇していた人たち、諦めていた人たち、事実婚という選択をした人たちは、大きな希望を得ることができます。
夫婦別姓という「選択肢」が増えることは、同姓でも別姓でも自らの意思で選ぶ自由と権利を得るのであって、夫婦同姓を望む人の選択肢を奪うことでも、別姓を強いることでもありません。
多くの人が選択的夫婦別姓制度の実現を望んでいるいま、その実態と乖離した不合理なルールは、見直されるタイミングにあると考えます。
結婚を望む人の障壁を取りのぞき、より多くの人が納得した選択をして、喜びにあふれる社会をつくれるよう、私も選択的夫婦別姓制度の実現に賛同いたします。
平野洋一郎 アステリア株式会社 代表取締役社長/CEO
Gender Equality のためにも、女性活躍のためにも、選択的夫婦別姓は大きな効果が期待できます。当社(アステリア株式会社)の全ての既婚女性社員は旧姓を名乗っています。その理由は、姓が変わることによる社内や取引先とのコミュニケーションの阻害要因を無くし、積み重ねてきた個人のアイデンティティを活かすためで、個人個人が選択した結果としてそうなっています。一方で、法的文書や行政文書は戸籍上の新しい姓しか認められないために、不便を被っています。一日も早く選択的夫婦別姓が認められることを願っています。
鳥海智絵 野村證券株式会社 専務執行役員
商業登記における旧姓併記の実現に微力を投じた経験から、それを超えた選択制の導入に強く賛同いたします。
平田仁志 株式会社M4CH 代表取締役社長
夫婦となるふたりの判断で別姓にメリットがあるのなら、別姓を選べる自由と権利は当然のものだと思います。
渡辺由美子 NPO法人キッズドア 理事長
日本の子どもの貧困という社会課題は、女性の貧困と直結しています。女性の貧困は、女性の地位が低いことがあるのは間違いありません。選択的夫婦別姓制度の導入は、ジェンダーギャップの解消に必須だと考えます。
大川哲郎 株式会社大川印刷 代表取締役社長
人にはそれぞれ様々な事情があり、柔軟な対応と多様性を互いに認め合える社会の実現が求められると考えるため、賛同します。
藤岡英二 株式会社ソルネット 代表取締役社長
今は法律と言う枠組みの中で強制的に同一の姓にされているのが現状であり個人の権利と言う観点や世の中の動向を勘案しても無理がある。またSDGs的観点から見ても世界的にジェンダーギャップが大きくとりわけ日本は最低の評価である。改善すべき点であると考える。
荒畦朋子 一般社団法人ヨコグシ 代表理事
登記時の姓を、アイデンティティのないほうの姓でしなくてはならないのは苦痛です。選択できる社会を実現しましょう!
蓮本智仁 JBCC株式会社 取締役常務執行役員
選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
「望む人だけが改姓し、望まない改姓はゼロにする」という理念にも強く賛同します。
どちらを選択するか?は家族の問題・夫婦の問題であり、法規制すること自体に合理性を見出せません。国際化・ダイバーシティが当たり前の世界の中で、個人の選択が認められることは極めて当たり前だと思います。
吉松正三 JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 代表取締役社長
様々な価値観と選択肢が提供されている中、何を選択するのかは個人の判断です。多様性の積極的な肯定は、人類、全ての生命の持つ強みを生かすことそのもの。個人に選択権のない現制度は明らかに生存力、競争力、生産性を阻害するものです。心から選択的夫婦別姓に賛同します。
松崎耕介 株式会社フジシール 代表取締役社長
ビジネス上当然のことなので。
岩城慶太郎 アステナホールディングス株式会社 代表取締役社長CEO
賛同しない理由が見当たらない
大西譲二 野原住環境株式会社 代表取締役社長
特に仕事上では長く使ってきた姓名というのは非常に大事なことであり、私たちの国では主に女性が結婚した際に姓名を変更することが残念ながら慣例となっております。
これからの多様性の社会の中では、女性であっても一生涯働き続けることを目指す方もどんどん増えてくると思いますし、時代にあっていないこのような制度は早く変えるべきだと思います。
近藤俊次 株式会社ソルネット 取締役執行役員
それぞれの人が、自身の望める豊かな生活を送れる社会をつくりましょう。
落合順子 有限会社シグネチャ 代表取締役
全ての人が一人の個として自立し続けるために、自分の名前は自分が選択したものであるべきです。
清水宏美 株式会社アギラス 代表取締役
女性です。
幼い頃からずっと、自分の姓への愛着により、婚姻時に姓を変えること抵抗を感じていました。
現在ではそれに加え、暗黙の了解で女性側に改姓を強いる空気に加担したくないという思いを強くしています。
そのためには法律婚を避けたいとすら思い、実際に、事実婚を受け入れてくれる生命保険を選び加入もしました。
どのような制度が敷かれているのかにはその国の思想が表れていると思います。
もうそろそろ、変えるべきだと、強く思っています。
薮下真平 JBCC株式会社 取締役副社長
選択肢があって良かった!、事は多くあります。
選択肢が無くて困った、、事はもっとあります。
古島忠 株式会社ASPREAD 取締役
自分の姓にアイデンティティーを持っていても、婚姻による強制的な改姓を強いられ、それによる手続きの煩わしさやストレスがある。女性家系で姓を存続させるためにマスオさん(婿)を迎えるなんて事もある。
平良和久 合同会社うるま農場 代表社員
生きやすい社会の実現の為に
境順子 株式会社マスコール 代表取締役社長
選択肢のない世界は本当にもったいない。
それぞれの私らしさのために賛同します。
境和彦 東芳紙業株式会社 代表取締役
弊社でも別姓のために事実婚の社員が2人います。社会保険の手続きなど、非常に面倒です。
逆に、結婚のために改姓すると本人が非常に苦労するのは、皆さんのおっしゃる通りです。
希望する人は別姓を選べるように、法改正を求めます。
匿名
私はシングルマザーです。小さな頃から婿養子をもらうよう言われて育ちました。前の夫は、幸い婿になってうちの姓になってくれました。再婚の話しがあった時も、婿に入ってくれる事が条件でした。シングルマザーで再婚してくれるだけでもありがたいのに、婿にきてくれるという条件をつけられたら、素敵な人とは再婚できません。娘にも婿をもらってほしいとは言いたくありません。娘が幸せになれる人と結婚してほしいです。しかし親や姉は、この姓を300年繋げてほしいと願っています。皆の願いを叶えるために、選択的別姓に賛成です。
御厨志郎 AIG損害保険株式会社 執行役員
みんなが活き活きと活躍できる社会の実現
宇田直人 AIGジャパンホールディングス株式会社 執行役員兼チーフ•ヒューマンリソース•オフィサー
それぞれのアイデンティティを尊重するのは当たり前のことであり、今の時代に全くそぐわない法律は改正すべきであると思います。
池谷英悟 有限会社池谷製作所 代表取締役社長
姓は個人のアイデンティティの一つであり、結婚により望まぬ改姓を強制することは権利の侵害であると考えます。
また、諸外国の例を見る限り、夫婦別姓が離婚を助長するという主張の根拠はないものと思われます。
家族の絆は、別姓によって妨げられるものでは決してありません。
すべての夫婦が、同姓・別姓を自主的に選択できる社会になることを望みます。
中西康治 株式会社WOW WORLD 専務取締役
今の時代に合っておらず、夫婦同姓を強制している国は、先進国の中では日本だけであり、男女平等の観点からも選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
平塚ひかる 株式会社Cheer 代表取締役
私も結婚というライブイベントで過去に仕事で名乗る時は旧姓、事務手続きは改姓したものを使用すると言う煩雑さに困惑した時代もありました。世の中の人が自由な選択ができる世界になればと選択的夫婦別姓に賛同します。
平田麻莉 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事
選択肢があり、自ら意思決定できることが、人間の幸福度に大きく関係するという研究結果があります。選べることが大切だと思います。
近藤浩計 株式会社うるる 取締役CFO
婚姻後に姓を変えるのは96%が女性であるという現状を踏まえると、男女平等な制度とは言えないと考えています。
男女平等な世の中を実現していくためにも、選択的夫婦別姓の実現を望みます。
西見勝也 株式会社ロングリリーフ/一般社団法人ISHIKETTEI 代表取締役/代表理事
性別がある前に、誰もが同じ一人の人間です。自らアイデンティティを確立して、そのアイデンティティを持ち続ける権利も平等だと考えます。世界を見渡しても、夫婦別姓であることが普通です。そして、より「個」が光る時代となっていくからこそ、選択的夫婦別姓が認められることを支持します。
稲田亜美 thomas株式会社 取締役 CTO
日本でのダイバーシティ推進において、個のアイデンティティでもある自分の姓を選択する権利が与えられることは必要不可欠だと感じています。選択的夫婦別姓は、決して同姓でありたいという方々を否定するものではなく、別姓でありたいという方々を許容する制度です。誰しもが個々の多様な考え方を受容し尊重しあえる社会の一歩となると信じ、この制度の実現に賛同いたします。
最相友貴 株式会社STORY ABOUT 代表取締役
単純に名前を変えなければならない理由が思い当たりません。一個人としてのアイデンティティを失うかのような喪失感、非効率で無駄な手続き。
会社の代表として活動しているため旧姓を通称として使えるよう手続きを進めていますがすでに時間の無駄を感じずにはいられません。
これからは前ならえの時代ではなく、自らの人としてのブランドを築きあげ、自由に活動できる平等でオープンな時代になっていくと思います。そのためにも選択的夫婦別姓の早期実現を願います。
上野篤志 上野行政書士事務所 所長
姓の選択権を認めないのは日本国憲法が保障する基本的人権を否定するものです。
小林有佳 アシアル株式会社 取締役
夫婦別姓を選択するか、同姓を選択するかは、個人の意志によって、自由に選べる権利だと考えます。
個人の自由意志によって選べるように、法が改正されることを望みます。
甲斐田万智子 認定NPO法人 国際子ども権利センター 代表理事
共同声明も活動も素晴らしいです。衆院選に向けて法制化の実現頑張ってください。
岡本真 アカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg) 代表取締役
変えたい人は変えられる、変えたくない人は変えなくていい。そういう当たり前を実現していきましょう。
古藤総一郎 ソウ合同会社 代表社員
自分自身通称で旧姓を使っているが結婚離婚で姓の変更を体験。変更自体が離婚強いがかかなり難しく簡単ではない。選択的別姓であれば最初からこう言った問題は起きにくい。
吉谷愛 株式会社あいふろいで 代表取締役社長
主人と起業した際「同じ姓だとお客様が困られるから」という理由で私が旧姓を使うことになり、最終的には私が代表になってビジネスをすることになりました。その際旧姓は通称でしかなく、銀行口座開設や融資および行政等との契約では新姓しか使えない事実に何度もぶち当たり、色々と大変苦労しました。
小松遊気 株式会社IT Coach 代表取締役
うちの両親が、まさに選択的夫婦別姓を行ってきました。
そのため、私は母・弟とは別姓で、父とは同姓です。
こういった形態を、今の法律は家族と認めていません。
このことは、当事者として、素直に嫌ですし、おかしいと思っています。
少しでも早く、選択的夫婦別姓制の導入を願い、取り組みに賛同させていただきます。
田中 純子 マーガレットこどもクリニック 院長
医師は、姓の変更に際して医師免許の書き換え、保険医登録の書き換え、電子カルテの登録名の変更、処方箋印鑑の変更など、業務に関わる沢山の変更が必要でとても大変でした。また、プライベートなことを患者さんに知らせる必要もあります。
そもそも、自分のアイデンティティを、変えるのが当然であるという社会の風潮に強い違和感を個人としても感じてます。
牧野隆志 株式会社アットウェア 代表取締役
創業間もない頃、妻にも事業を手伝ってもらっていましたが、同姓での活動は面倒なことも多く彼女は旧姓で仕事をしてくれました。いわゆる通称。わざわざ通称と本名を使い分けなければならない労力はとても馬鹿らしく思いました。逆に私が旧姓を使わなければならなかった事態を想像するとても憂鬱。姓の変更を受け入れ、通称との併用という労力を払ってくれた妻に感謝です。
橋本正徳 株式会社ヌーラボ 代表取締役
自己決定度の高い人が幸福度が高い傾向にあるそうです。幸福な人の多い社会を実現するために、姓を選択できるようにして欲しいです。
渋谷 雄大 株式会社MOVED 代表取締役
選択肢を増やし、多様な価値観を受け入れる社会を作り広げることこそ、今必要なアクション
奥野昭光 株式会社エクスペリエンス 代表取締役社長
私も夫婦別姓を選択して生活しています。以前から日本では何故だめなのか調べており、何かしらお力になるのであればと思い、寄付行為など他の団体でもしておりました。今回、岸田総理のニュースから御会を知り、賛同した次第です。
利根川裕太 NPO法人みんなのコード 代表理事
同一の姓になりたい夫婦は同じ姓を、それまでと同じ姓を名乗りたい夫婦はそれぞれの姓を名乗れる社会になるべきです。
坂本真子 IFS株式会社 代表取締役
自分自身、結婚、離婚を通して、圧倒的な不便さを感じました。
後の世代に、子供たちに、こんな不自由で不便で理不尽なルールは残せません。
堤亜紀子 所属先未公表
免許証、パスポート等旧姓併記をしても銀行口座一つ開設が出来ないです。以前の会社ではトップの一声で旧姓使用出来なくなりました。そんなあやふやな状態ではなく、きちんと自分の名前を名乗りたいです。
小野朋江 株式会社ASIA Link 代表取締役
経営者にとって、名前は看板でもあります。簡単に変えたくありません。
もちろん、経営者になる前も、自分の名前は大切でした(結婚して姓を変えてしまいましたが)。
結婚や離婚によって、どちらかが姓を変えなければならない制度は、誰も幸せにしないのではないでしょうか。
同姓にしたい2人は同姓を、別姓にしたい2人は別姓を。
「選択」できる社会を早期に望みます。
和光良一 株式会社日興電機製作所 代表取締役社長
強制的夫婦同姓に反対します。結婚して姓を変えるも変えないも当人の自由であるべきです。
須永由美子 株式会社山野楽器 執行役員広報部長
働き始めてから40年近く旧姓で仕事をしています。もちろんSNSも旧姓登録しています。仕事で得たネットワーク全てが旧姓前提。資格取得、出張時の宿泊や交通機関の予約、業務での契約、大学院進学など、全てが旧姓と本名との間で、どちらを立てればどちらが不利益という中途半端な状態が続いており、常にペーパー離婚が頭によぎる状況です。
「選択的」とは、不利益を被っている、望んでいる人だけが選ぶ仕込みです。望まない人は選ばない自由があります。「選ぶ」ことができる自由の早期実現を望みます。
由利孝 テクマトリックス株式会社 代表取締役社長
ダイバーシティ推進の上で、選択的夫婦別姓を実現することは必須だと思います。
松田憲幸 ソースネクスト株式会社 代表取締役会長&CEO
賛同します
保坂梨恵 株式会社グローバルフィールド 代表取締役社長
今、正にこの問題に直面しています。代表に就任してから一度離婚をしており、その時の苦労は同姓を強制する方々には分からないでしょう。金銭的負担もありますし、以前の名前での実績は引き継がれることはありません。
出会いに恵まれ、新しいパートナーとの子供も妊娠しています。別姓を選べることで、女性の社会進出の後押しができるものと信じております。
三浦崇宏 株式会社GO 代表取締役
いつか選択的夫婦別姓が実現するまで、結婚しません。
それまでは、待ちます。
小安美和 株式会社Will Lab 代表取締役
ひとりひとりが自分のあり様を選択できる多様性を認める社会に向けて、また、ジェンダー平等社会に向けて、選択制夫婦別姓の早期実現は、その起爆剤になります。逆に言えば、今は、ひとつの足かせになっていると言えます。
私自身も法改正を待ちながら、16年間、事実婚を余儀なくされています。
自身のあり様に従い法律婚を選択しなかった結果、子どもを持つ/持たないというライフフェーズにおいて、事実婚では不妊治療が受けられない病院があったり、特別養子縁組の機会も得られなかったりと、事実婚のままでは得られない機会があります。
超少子高齢化の未来を見据えれば、これまでの固定的な役割分担、制度を見直していくことは待ったなしです。ひとりひとりがありたい姿で生きるWell-beingな社会に向けて、趣旨に賛同いたします。
青木水理 一般社団法人日本おひるねアート協会 代表理事
姓を変えるのは大体女性側という事が不自然です。別姓制度が難しいのなら、せめて姓を変える割合は男女半数ずつにしてほしい。男性側の家を途絶えさせない、妻は夫の所有物という風潮に違和感を覚えます。
新谷真寿美 クニヒロ株式会社 代表取締役社長
3世代続く企業経営者です。結婚して主人の名前になり、出産後会社に後継者として入社したため新姓で仕事をしていますが、親族で続いているので旧姓に戻したい。でも、主人も子供もいます。子供の名前を変えるのもかわいそうなので思いとどまっており、現在選択できるのは「事実婚」です。
墓などもどうするのか考えていますが、私は実親の墓に入りたい。
是非、夫婦別姓を!認められないと今後日本の女性活躍はなかなか難しいです。
鈴木省吾 JustCo DK Japan株式会社 日本部門長
ただただ公平を求めるだけ。誰かの不幸せの上に立つ制度なら、変えればいいだけです。
伊藤泰朗 新技術中亜香港有限公司 董事
海外では当たり前の夫婦別姓が、日本で認められない、認めようとしないのはなぜなのか。
この問題には既得権益も何もないはずで、それが認められて困る人は誰もいないはず。
認められないことにより、困り果て、苦しみ、悩む人がますます増えることになる。
経済活動にも支障をきたし、結婚しない若者も増加し、日本社会のシュリンクを加速させることにつながっている。別姓にできず悩み苦しむ日本人が元気を取り戻すためにも、一刻も早く実現させていただきたい。
津曲慎哉 えびの電子工業株式会社 代表取締役社長
私は男性ですが、妻と結婚して、妻の改姓での様子を見て、この伝統をとても不思議に思いました。
『何故、女性だけが名前で結婚の有無が判断されてしまう?』『自分が逆の立場ならどうなの?』
私と妻は、名前で結婚相手を選んでいません。たとえ将来に子供の姓が変わっても、ずっと愛する子供のままです。
伝統を壊したいのではなく、選択により、より良き伝統として、家系について家族で話して考えて選びながら、大切に守り続けてゆけたらと願います。
私の愛する日本で、ジェンダー平等が進むことを願っています。
橋本夕紀子 所属先非公開 常務理事
結婚し、戸籍の名字を変えましたが、職場では旧姓を使用しています。マイナンバーカードなどには旧姓を併記していますが、なんの意味もないことを実感しています。姓を変える前は、結婚するのだから自分(女性)が姓を変えるのが普通かと思っていましたが、姓を変えるとなると、喜びより喪失感や手続きの煩さのほうが大きく感じられ、自分が犠牲になった気分になっています。夫が私の姓を選んだとしても、夫に同じ思いをさせることになると思います。私たちは選択の自由を得るべきだと思います。
飯田光穂 株式会社Backrest 代表取締役社長
少子化や優秀な人材が海外流出することへの対策、もしくは女性活躍や生産性の向上。
それらの理由ではなく、現状の人権侵害への抗議として、賛同します。
子供がいなくても、優秀でなくても、労働で活躍できなくても、活躍したくなくても、生産性が低くても、すべての人に、自分が望む名前で生きる権利があります。
朝尾直太 株式会社オープンパワー 代表取締役
20年前に結婚したときに私(夫)の姓を選んでもらいましたが、それ以来、妻には不便と負担をかけていると感じています。妻は仕事などでは旧姓を使っています。結婚するときに片方だけがこのような不便・負担を引き受ける必要がない制度を望みます。
江幡哲也 株式会社オールアバウト 代表取締役社長 兼 グループCEO
選択制とすることで、様々な方の人権が守られ、不利益を排除し、個人の嗜好も満たされ、このことに限らず当たり前のことが実現できる社会の一助となるはずです。
伊村采那え 株式会社ブレイン 代表取締役社長
1日でも早く認められる事を望んでいます
匿名 Y.M
20代の頃からすでに30年以上も期待し待ち望んでいる選択的夫婦別姓制度ですが、個人的な実績を積んで来た今、娘の時代に生きづらさを残さないためにも、私も行動を起こします。企業を経営していますが、少子高齢化のあおりで人手不足に苦しんでいるのは、これまで日本社会が女性の存在を軽んじ、能力を過小評価し、意見を聞えないふりし、声を封じ込み、意思を無視し、女性は我慢して当然、それが美徳、虐げられても当たり前と捉えて扱ってきた結果です。日本での結婚、妊娠、出産を望まない日本女性が増加したのは、日本社会に対する女性たちの無言の反乱だと感じています。
ぜひ、日本の制度に疑問を持つ者同士が一致協力し合って、まずは選択的夫婦別姓の実現から始めて、ありとあらゆるジェンダー格差を是正していきましょう。
石井智康 石井食品株式会社 代表取締役社長
少子化社会においては、それぞれの背景を尊重し合い気持ちよく働ける環境づくりが、より多くの方が自分の力を発揮し働ける前提となり、すべての企業にとって必須となっています。
そのためには、個々の状況に基づき個人が判断・選択できるということが重要だと思います。選択的夫婦別姓もその一つだと考えており、女性活躍を推進する大前提だと考えます。
社会状況が変わる中でルールを変えていく、という変化の時代の中で重要なことがこの問題についても実施されることを切に願います。
内山幸樹 株式会社ホットリンク 代表取締役社長グループCEO
「個人」よりも「家」を中心に社会制度が作られていた時代から、「家」よりも「個人」を尊重する時代に変わっています。
時代に合わせて、法律は変わるべきだと思います。
浜田和子 J.フロント リテイリング株式会社 取締役
誰しもが、自身のルーツを選択できる自由があってよいと思います。
長田志織 ヤンマーホールディングス株式会社 取締役CSO
女性が社会的に活躍するための大きなハードルの一つがなくなり、みなが自分の意思で自分のことを選択できる社会になって欲しいと思います。
西松千鶴子 株式会社JTB 執行役員サステナビリティ推進担当(CSuO)
個々人の”らしさ”を発揮して生きることが大切です。そのため、選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
尾崎由紀子 野村ホールディングス株式会社 CHRO 兼 CHO(健康経営推進責任者)
自分らしく生活し、働く環境においても、自身の願う姓を選択できることが必要です。無駄を無くして、より良い社会を目指します。選択的夫婦別姓制度の法制化に賛同します。
田中稔哉 株式会社日本マンパワー 代表取締役会長
当然の権利だと考えます。
甲斐 暁子 株式会社フィグメント 代表取締役
私は起業・法人設立にあたり、旧姓併記での登記をしましたがいざ金融機関や公的手続きを行う際に旧姓では認められなかったり、郵便物がわざわざ「○○(主人の姓)様方」と付けて送られてきたりと、登記で認められている旧姓の使用が認めてもらえない理不尽に日々出くわしています。旧姓併記は、夫婦別姓の代替案にならないどころかパスポートやクレジットカード、銀行口座開設に際してマネーロンダリングの温床にすらなり得るため厳しい目で見られます。ただ自分の姓を名乗りたいだけでそのような視線を浴びることの不条理は、味わった者にしか分からないと思います。一日も早くこの人権問題が解消され、気持ちよく誇り高く自らの名前を名乗って生きていける社会を待ち望んでいます。
加藤 茜愛 アカネアイデンティティズ株式会社 C.E.O / 株式会社SUMCO 社外取締役 / 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
明治時代の家制度の名残に縛られ、強制的に姓を統一しなくてはならない現状はビジネスシーンでの自らのアンデンティティを守ることへの足枷になっています。多様性を重視し性別を問わず働き続けることを自分の意思で選択する現代において、結婚によって姓の変更を法律で強要されることに違和感を覚えます。未来を担う若い世代のためにも、一刻も早く選択的夫婦別姓を叶えたいです。
吉岡マコ 特定非営利活動法人シングルマザーズシスターフッド 代表理事
シングルマザーの支援をする中で実感しているのは「多くの女性が離婚時にも苗字のことで頭を悩ませなければならない」という現実です。結婚に際して、男女のいずれか一方が、苗字を改めなければならないという制度を採用しているのは諸外国を見渡しても日本だけであり、苗字を変える側の95%は女性という現実も、日本社会における男女の不平等を物語っています。名前はアイデンティティに関わることであり、自分にとってしっくりくる氏名を使用できることは、大切なことです。誰もが、自分が名乗る名前について、自分らしい選択ができる制度が1日も早く実現するよう期待しております。
井上佳子 ノボノルディスクファーマ株式会社 取締役副社長
アイデンティティの一貫性の実現のためにも重要だと思います。現実的には、心の負担だけでなく、実践的な負担の公的書類や、支払い等の煩雑さも減ると思います。
桑山三恵子 株式会社安藤・間 取締役
日本経済の活性化に必須であると思います
福家 良一 日本労働組合総連合会香川県連合会(連合香川) 会長
選択的夫婦別姓の早期導入を求めます
飯塚盛康 NPO法人 ディーセント・ワークへの扉 理事長
名字を変えることで、その人のキャリアが途切れることは、社会にとってもその人にとっても不幸なことです。結婚しても別姓でいられる社会にしないといけない。
平方亜弥子 NPO法人つながりつながる研究所 代表理事
「家」という箱は、実質的には先にバージョンアップしていて、その箱の中に閉じ込めなくても対等な人と人の関係性によってさまざまな形の家族が生まれ育っています。姓もその一つ。選ぶことができることによって、改めて自分は何を求めるのか、考えるチャンスになる。自由とは、選べること。賛同します。
桜庭理奈 35 CoCreation 合同会社 CEO
この地球上の人間が、らしさを最大限に自由意志で選べる未来を胸に賛同します
荒川正子 株式会社エーエムシーアドバイザーズ 代表取締役 (兼 リコーリース株式会社、株式会社ジーフット 社外取締役、オリオンビール株式会社 非常勤取締役)
名字の変更や使い分けは、変更手続きのみならず、その後も同一本人であると証明するための作業が何度も必要となります。時間とコストの損失とともに、過去の成果や実績も同一人物のものと認識しづらい為の機会損失もありえます。支障は改善していかないと発展もありません。未来を担う次世代のために、多様性を認め、自分で選択できる人生を引き継ぎたいと思います。
鈴木駿 株式会社Smart Lab 代表取締役
選択制であれば反対意見が合理的ではないことは明らか。
ビジネスの現場では旧姓でやり取りすることも多くあり、特に個人事業主や会社の代表であれば登記変更など多くの労力がかかる。
森永一弘 森永計測サービス株式会社 代表取締役社長
誰もが自分らしく生きることを応援できる社会になってほしいと願って、この取り組みに賛同いたします。別姓であっても同姓であっても夫婦や家族であることに何も障害はありません。一方に改姓を強制する制度は煩雑な手続きが求められるのみならず、これまでのキャリアを消失させてしまう恐れもあり、有能な人材を消耗させる結果にもなりかねません。このような旧態依然の制度が日本の国力を下げています。法律の改正を強く望みます
阿部裕 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 取締役 専務執行役員
世界では、日本だけの特別な仕組みであり、結婚して姓を変えることによる不便や不利益を被ることは、平等の観点からも問題であると思います。また、選択制になることで、必ずしも強制でないことも、良いと思います。
山野千枝 一般社団法人ベンチャー型事業承継 代表理事
名前の呪縛が個人の人生を左右してはいけない。
大切なのは自分で選べること。
選択の自由がある世界こそが豊かさだと思います。
氏名非公表
「団体の役員や取締役は男性が多い(だからこそ、女性は男性よりもっとがんばらないといけない)」「結婚したら女性側が改姓することが多い」という、無意識なバイアスによって苦しみ、結婚などのライフイベントを躊躇してきました。
改姓後、旧姓の通称使用は事務担当に多くの手間をかけます。そういった、少しの手間・リスクを避けたいのは、多忙なビジネスパーソンにとっては当然のことです。
例えば、パートナーと結婚を考えていたとしても、お互い改姓を望んでいないため、さらに仕事・居住の場所も離れているため、別居での現在の関係性の維持を選ぼうとしているひとがいます。本当はパートナーとの法律的な関係性がほしいですし、結婚や子どもを持つかどうかについても、法的な関係性をもとに前向きに進めたいのに、です。
自分には夫婦別姓は当てはまらないし夫婦同姓でよい、そう思う人も、
強制的夫婦同姓に悩むスタッフやビジネスリーダーを応援してください。
そうすることで救われる人がいます。
「旧姓使用できるでしょ」「そんなに改姓が嫌なの?」
そういった無意識な言葉で、私は傷ついてきました。
「女性が改姓するのが当たり前」「女性は仕事か結婚かどちらかを選ばないといけないんだよ」、と言われているように感じたからです。
どうか、民法、戸籍法の改正の検討を進める必要性を理解してください。
平澤薫子 株アニマックスブロードキャスト•ジャパン 取締役
業務上旧姓使用継続の希望があるということはそれだけ氏の変更を望まない理由があるということであり、手続きが煩雑だということが取り上げられがちだが、人権を尊重していないあらわれだと考えています。
田代邦幸 合同会社 Office SRC 代表社員
改姓が障害となって多くの(おそらく大部分は女性の)方々の人生の選択肢が制限されてしまっている現状を放置するわけにはいきません。
三宅民子 TMMT合同会社 代表社員
つい最近も法人登記で旧氏表記で追加で書類が必要だったり、新たに銀行口座開設で苦労しました。私が所持しているJALクレジットカードに夫を家族会員にしようとしたら、私と苗字が違うからと拒否され、私の苗字を夫と同一にしない限り受け付けないと言われました。入籍後に健康保険証を頼みもしないのに、変更してきました。
一刻も早く、選択的夫婦別姓になって欲しいです。どうぞよろしくお願いします。
板橋力 アイティビジネスサロン株式会社 代表取締役
選択できる点が大変有意義であり、デメリットはない印象です。
野原裕美 Intermedia合同会社 代表社員
個人が自分の意志に沿って生きられる社会を作りたいです。夫婦別姓は、その一つだと考えます。
遠藤亮介 株式会社EpoCh 代表取締役社長
個が自分らしく「イキイキ」と生きていくためには、一律に与える "平等” ではなく、個々がチョイスできる “公平” なプロセスや仕組み、意識や行動が大切だと実感しております。個がオーナーシップを持って “選択できる“ 機会が創出されることを願います。
松浦千恵 コミュニティ婚活株式会社 代表取締役
婚活世代の結婚観も多様化しています。選択できる社会の実現は生涯未婚率の低下の第一歩と思っています。
長尾円 有限会社ラプラス 代表取締役社長
私の前職はJALの国際線客室乗務員です。かねてより、婚姻や離婚後に姓を変える必要があり、フライトで入国にVISAが必要な国がある為、それらのVISAの改姓手続き完了まで、フライトスケジュールを変更しなくてはならず、夫婦別姓が選択できたらと考えていました。
三浦久美子 株式会社エムズNEXT 代表取締役社長
私が結婚をした40年前、改姓をする事が自分のアイデンティティを否定されるようで、本当に嫌でした。しかも今や離婚再婚などが頻繁にあり、その度に嫌な思いをするのはほぼ女性。これも立派な女性に対する社会的ハラスメントだと思います。
矢下善生 元株式会社樽味屋 代表取締役社長
婚姻関係で姓が変わる事によるキャリアを捨てないで
岡本弘毅 株式会社エデュソル 代表取締役社長、一般社団法人ロボッチャ協会、NPO法人子ども大学水戸、株式会社スコップ
選択肢を増やすことで、より良い社会の実現ができるはずです。日本の古き良き文化は残しつつ、時代に合った制度変化は必要であり、将来の日本が発展していくために必要な制度だと思います。
尾川俊司 株式会社エンターシステム 代表取締役社長
賛同いたします。
なぜ、夫婦が同性でなければならないのか、その意図の明確な説明が必要と感じます。
特に意図が無いのであれば、自由であることが望ましいですね。
青木正幸 医療法人社団竹下内科 理事長
別姓でも同姓でも本人たちが良いと思う選択をするのは至極真当で自然なことです。
浅山理恵 SMBCオペレーションサービス株式会社 取締役副社長
30年以上前の結婚時には、こんなに長い時間がかかる一生を賭けたテーマになろうとは思いませんでした。
やむにやまれず社内で旧姓を使えるようビジネスネーム制度をつくりましたが、利便性がかえって法制面での対応を遅らせていることがあってほしくないと、この活動を強く支援します。
選択肢を増やすことがなぜこんなに困難を伴うのでしょうか。次世代に今より生きやすい日本を残したく思います。
前岡照紀 税理士法人京都合同会計 社員税理士
選択的夫婦別姓制度の導入がなされない国は、もはや日本だけであるという現実を真摯に受けとめるべきだと思います。多くの社会で活躍する女性が困っている声を聞く中で未だにこの制度が導入されないことは恥ずかしいことと感じます。多様性を認める社会を求めます。
川端法子 株式会社HONEST 代表取締役
選択の自由が当たり前の世の中になりますように
萩本はるみ ドリーム北海道株式会社 代表取締役
社会で認知されていた名前が変わることで不利益が生じる人もいると思います。
結婚しても姓が選べる自由がある社会にしたいと思います。
藤本真由海 所属先非公表 代表
今年こそ実現を祈っています!
門口宰子 アバンダンスライフ合同会社 代表
姓名は生命です。選択できない生きづらさを感じることを無くしていきましょう!
村山 淳 一般社団法人トピカ 代表理事
私は結婚して自分の姓を変えることでアイデンティティクライシスが起きることはありませんでしたが、単純に法人代表として戸籍名と旧姓を使い分ける、「村山(立川)淳」という名刺をいちいち説明することに面倒さを感じています。私より深刻な方々のためにも、1日も早く実現して欲しいと思っています。
阿部由美子 株式会社ZABUN 代表取締役
私はオーストラリアで現地の法律に基づいた法的効力を持つ海外挙式を行い、結婚しましたが、選択的夫婦別姓を待っている為、日本では未入籍です。
不妊治療をしていますが、ほとんどの病院は事実婚を受け入れてくれません。
事実婚を受け入れてくれる限られた病院でしか不妊治療が出来ません。
そして、事実婚だと生まれてくる子供は婚外子になってしまいます。
事実婚だと不利益になり、子供を諦める夫婦も多々いると思います。
そう思うと少子化を悪化させているなと感じてしまいます。
早く選択的夫婦別姓が可決され、別姓でも婚姻関係が認められる日本になって欲しいです。
別姓を望む夫婦にとって、早く安心して暮らせる日が来る事を祈っております。
中村香菜子 一般社団法人ぬくぬくママsun's 代表理事
別姓を選択できるようになることは、何のデメリットにもならないと思います。名前が2つあると、不便だと思います。子どもたちの未来のために、今、選択できるようにしておきたいです。
Kay Osekkay株式会社 代表取締役社長
名字が強制的に変わることで、積み上げてきたものが強制的に断絶した感覚がありました。また夫の苗字をつかうことは、別人格にラベリングされた気分にも。私のような感覚の人は少なからずいるので、せめて選択させてほしい。選ぶ権利がほしい。
瀧澤 昌宏 株式会社テクノ中部 取締役 上席執行役員
各人が様々な頸木から解き放たれて自由に選択できることが大切だと思います。
長谷川竹彦 有限会社想いやりファーム 代表取締役会長
常に犠牲を伴う社会の仕組みは、もう転換期に来ています。一部の方の都合ではなく、皆んなが幸せな社会へ。
渡邊弘子 富士電子工業株式会社 代表取締役社長
そもそも夫婦同姓とはいっても、9割は女性の側が姓を変えているのが現状です。現在は、結婚する前に、海外で論文を発表していたり、海外で学位などを取っている優秀な女性が沢山いるのに、そういう方にそれまでのキャリアを捨てさせるような状況を社会が強要している事がおかしいと思います。また家や墓を守る運命を背負った女性もいます。
夫婦同姓にしたい方はそうすれば良いのです。でも上記のような方々は、選べるようにする、というのが、むしろ婚姻、出産するカップルを増やすことに繋がると考えます。
愛知県内20代女性経営者
姓名は自分のアイデンティティに深く関わる部分です。
姓を変えたくない理由は、自分の親兄弟と姓が同じでありたい、自分の姓名に愛着がある、手続きが面倒などいろいろと挙げられます。わたしはこれまでの実績(研究論文や会社関係)が自分の姓名の組み合わせで登録されているため、変えたくないと思っています。
それでも結婚のために仕方なく姓を変える人たちがたくさんいます。
姓を夫側、妻側のどちらにするのかで揉めている方も少なくありません。
また夫婦のどちらが名義を変えるにしろ、姓で変更するために煩雑な手続きに追われます。例えば、この名義を変えるには
先にこの申請をして、
しばらく待たされて、
申請が通って
やっと本当に名義を変更したかったものに申請できる。
これを何度も繰り返すことになります。
しかもその各申請には料金がかかります。
変えたくもない姓を変えた上に料金まで支払わされる。
これを夫婦のどちらかに強制する現在の制度は変えてもよいのではないのでしょうか。
むしろなぜ変えないのかが不思議です。
家族の連帯のためでしょうか?
姓が同じだからと言って必ずしも連帯意識が生まれるわけではありません。結婚して同姓にしても3組に一組は離婚しています。姓は関係ありません。
子どもの姓の選択の問題でしょうか?
生まれたときに親が話し合って決める、あるいは二重国籍の場合のように、22歳までに子供が選択できる制度を作るなど、方法は考えればいくらでもあるはずです。
選択的夫婦別姓制度ができるまでは結婚も子供を持つこともしないつもりだというカップルは一定数います。
性別にかかわらずあらゆる点で機会は公平とされるべきだと言われる現代社会で、結婚という制度を利用することでその一部を強制的に変更させることが社会に則した制度だとは言えないでしょう。
全員が別姓であるべきとは言いません。ただ、私は選択肢、選択の自由が欲しいのです。
河野幸江 株式会社きごろも 代表取締役社長
私が結婚した時、選択的夫婦別姓だったらどれだけ楽だったかと思います。
対外的には旧姓のまま活動はしましたが、公的な書類の変更、今の私は旧姓なのか現姓なのか、意識しなければ呼ばれても気付けないので、意識することにリソースを取られる。など、外からではわからない苦労がたくさんありました。
選択制、早く実現しますように。
岡田恭彦 元富士通株式会社 常務執行役員
当然のこと、と思うから。
夏目知佳子 株式会社夏目製作所 代表取締役
夫婦だけでなく、様々な形でのパートナーシップが事実上存在している社会において、より多くの方が制度に縛られずに幸せな関係を築けます様に。
北山久恵 株式会社荏原製作所 取締役監査委員会委員長
女性の活躍のために早期実現をお願いします。
古家野晶子 弁護士法人古家野法律事務所 社員弁護士
「氏名」の第一義的な機能は、同一性識別機能です。婚姻によって、それまでの氏名が維持できないのは社会生活上大きな不利益となります。旧姓使用の普及で対応しようとしても制度は複雑になるばかりですし、商業登記上の役員登記においては、婚姻で姓を変更した人だけが、婚姻や離婚をしたことが異動日とともに公示されてしまっています。婚姻、離婚等の事実はプライバシー情報であり、一方のみがその公表を強いられる現状は変えなければなりません。
八田圭子 株式会社寺岡製作所 取締役
今の日本の民法では、婚姻の際、夫か妻のどちらの氏を選んでも良いことにはなっているが、実際には96%女性側が氏を変えている。この事実は、家制度の名残りであり、日本における同調圧力の強さを物語っていると感じる。結婚したら片方が強制的に氏の変更手続きをしなければならず、晩婚化している現代、キャリアを積みながら長く大事にしてきた自分の氏を変えることは、アイデンティティの喪失感を強く伴う。旧姓使用では埋めがたい不自由さがあり、特に別姓を認めている海外への赴任や渡航時には(ドイツ等)、氏は一つ、と決められているため、旧姓使用ではトラブルが多い。若い世代は半数以上が別姓を支持している。これからの日本を担う若い世代の意見を尊重すべきではないか。ITが発達した今、別姓で困ることなど殆どないはずだ。D&Iと言いながら、選択の自由を奪っている実態を憂いている。是非とも実現してほしい。
岩田喜美枝 住友商事、味の素、りそなホールディングス 社外取締役
選択的夫婦別姓は、だれにも迷惑をかけない、世界では当たり前のことです。今回は是非実現していものです。
安藤正樹 株式会社リクシィ 代表取締役社長
選択的夫婦別姓の制度実現が結婚の条件という方にとっては、それがないことで結婚という選択肢を剥奪されているといっても過言ではない現実を知りました。1日も早い実現を望み、賛同します。
朱峰玲子 株式会社エム・エイチ・グループ 取締役会長
それぞれの個人の尊厳を大事にする。
小池友紀 at FOREST株式会社 代表取締役CEO
結婚の時も、離婚の時も、名前を変えた方は大変です。仕事への影響も少なくない。男女関係なく、働き続けやすい環境のために、選択的夫婦別姓は必要なことだと思います。
岡崎かつひろ 株式会社XYZ 代表取締役
大事なことは”選択”できること。
夫婦同姓でなければならない時代ではありません。
また現実的な問題として離婚をされるかたも多く、姓を変えた方の苦労の大きさは想像に難くありません。
選択的夫婦別姓に賛同します。
井田芙美子 株式会社いただきますカンパニー 代表取締役
創業後に離婚し、数年間は事業安定のために元夫の姓を名乗っていましたが、やはり自分のアイデンティティを大切にしたいと考え、家庭裁判所に通って旧姓に戻しました。幼い子どもを抱えながらの手続きはとても大変なことでした。通称利用として認めてもらうための期間は戸籍上の姓と通称使用の姓が異なるために正式な契約等で不具合が生じました。改姓してからは会社の登記はじめ様々な改姓手続きがあり、費用も労力もかかりました。今はパートナーがいますが、過去の大変な苦労を考えると改姓は絶対にしたくないですし、パートナーにも同じ思いをしてほししくないため、結婚を考えることができません。改姓使用の推奨は、会社の代表や研究者など社会的権限のある立場に、改姓する側(主に女性)が立つことを想定していないと感じています。どんな職業を選んでも婚姻の自由が保障されるべきと考えるため、私は選択的夫婦別姓に賛同します。
城之尾薫 一般社団法人バンザイ体操アファメーション協会 代表理事
日本が世界に羽ばたくためにも、世界の常識を知り、選択できる余地を作っておくことは、とても大切だと感じています。
江連千佳 株式会社Essay 代表取締役
私自身も、苗字をそのままにしたくて、事実婚を選びました。でも、なぜ私だけが苗字を変えない合理的な理由を求められるのでしょうか。自分の苗字への愛着が素直に認められる社会になりますように。
清水絹子 株式会社トップランナーマーケティング 代表取締役
私は離婚して再婚したので、苗字が3回変わっています。その度に行政や金融機関など、本当に多数の手続きに追われることになり、子どもも小さいため非常に大変でした。今でも元夫の苗字の郵便物が届くたびに憂鬱な気持ちになります。男性が苗字を変えればいいという話では負担を押し付けるだけです。それは希望しておらず、別姓さえ認められればすべて解決します。名前は私自身のアイデンティティを示す大事なものなので、仕事の名前はずっと旧姓です。
河野一郎 ストークグローバル・ジャパン株式会社 代表取締役社長
選択的夫婦別姓に賛同します
鈴木恭男 元栗田工業株式会社 専務執行役
私は、結婚する際に、相手が女性総合職で、お互い苗字を変えたくないので、結婚破談直前まで行き、揉めに揉めて、最終的には、私が苗字を変えました。私が変えたことにより、周りから、養子に入ったのかと毎回聞かれました。養子縁組ではないので毎回説明をするのですが、疲れました。女性が名前を変えないことで、相手の両親からも非難、私の両親からも非難でした(私は長男)。会社では、旧姓で仕事をしていましたが、戸籍上は違っているので、様々な支障が出ました。特に、グローバルの事業を長年やってきましたので、人脈が全て旧姓で認知されて、パスポートと旧姓が違うことによるトラブルが頻発に起こりました。ホテル予約が違っていた。契約書の責任者の名前、サイン等もそうです。その対策として、当時外務省に膨大な資料を提出して、パスポートに旧姓をカッコ付きでいれて貰いました。今はこの方法を女性が使うようになったようです。パスポートの併記で、ドイツ駐在中及び本社責任者として、この併記を正として、契約書類に記載することが出来るようになりました。上場企業の取締役就任の際には、旧姓での記載は問題(違法)があり、私の場合、有価証券報告書には、戸籍上の名前を備考で記載するように、弁護士の見解をもとに対応しました。女性取締役が増える中で、このようなめんどくさい処理は私だけで終わらせて欲しいです。
また、慣例で女性が苗字を変えることに関して、男性は、その苦労が全く分かってあげられない。免許証、カード、等々の変更、旧姓のままで仕事なので、本当に大変。これが日本人だからと言って諦めてはいけません。世界中にいる仕事仲間には、本当に同情されています。海外出張の際も、パスポートの名前(苗字併記)がベタ打ちなので、日本の航空会社のCAに毎回何とお呼びすればいいのですか、と言われます。
次の世代のために。
宮川晶子 株式会社宮川会計事務所 代表取締役
選択的夫婦別姓に賛同します。
原口唯 株式会社YOUI 代表取締役
多くの女性たちのビジネス活動を物理的・心理的に阻害する制度の撤廃を要求します。そもそもなぜ選択的夫婦別姓が認められないのかについて、社会として説明責任が果たされるべきだと思います。
間所加恵 株式会社Nurse&Co 代表取締役
去年入籍して名字が変わったが、法的手続き自体複雑で20箇所くらいに登録しなければならず、繁忙期の仕事に影響があった。また、会社名より個人の名字での外部からの認識があり、ビジネスネームとして旧姓で仕事しているが、公的機関の証明書を出さねば官庁系の手続きが滞るなど、会社の経営体制にも影響があり、不利益となる。
榎本真弓 一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 評議員
平成13年生まれ現在22歳の娘は、「結婚しても名字を変えたくない」と言っています。しかし現状の日本では、結婚すると女性側が変えることが一般的なので、娘にとって結婚のハードルが高くなるでしょう。選択的夫婦別姓が実現され、男女共にどちらの名字を変更するかなどの問題に囚われずに結婚ができる日本になるよう切に願います。
山本京士 株式会社RRR 代表取締役
賛同いたします!
櫻井由美子 ㈱JTEKT 社外監査役、㈱プロトコーポレーション 社外取締役、ダイコク電機 社外取締役
是非とも夫婦別姓期待しております
杉田純 三優監査法人 名誉会長
小生の次女は公認会計士ですが、ビジネス上の名刺だけは旧姓を使用してます。
不便ですね。会の趣旨に賛同します。
角貝恵 オンウェーブ株式会社 代表取締役
製薬業界の人材紹介を運営していますが、転職者の人、主に女性ですが、旧姓で入社できることを条件に会社を選んでいる人も多くいて、社会で活躍している女性ならでは、不便さを解消したい。またエビデンスを求められる論文発表する研究職は結婚によって名字が変わることへのデメリットは大きく、結婚へのハードルを高くしています。
代表取締役として様々な企業と契約をしていますが、代表者の名前が変わることにより、再締結も必要となるため、法律婚はしておりません。名前はアイデンディティーでもあり、平等を毀損している日本の同姓を強制する婚姻制度は強く国に異議を伝えたいです。
仙頭真希子 せんとう法律事務所 代表
実現に向けてご尽力いただきありがとうございます。小学生の娘が結婚するまでには実現させたいです。
重松清美 株式会社太陽産業 取締役副社長
1日も早く実現することを希望しています。
角田朋子 株式会社Lumiere 代表取締役 公認会計士
夫婦別姓を強制するのではなく、同姓が良い人は同姓を選べる、「選択制」です。
この選択権は憲法上、最も尊重されるべき人権の一つです。
実務面でも、通称ではなく正式な形での選択制でなければ、無駄な作業に多くの時間が割かれ、社会全体にとっての大きな損失になるため、一刻も早く解消することを願います。
原田奈美 リンクスシステムコンサルティング合同会社 代表社員
なぜ反対するのか意味がわからない。
小川恭子 女性の法律事務所パール 所長
婚姻したことで、どちらか一方が、生来の「人格の一貫性」を表示できなくなる虞のある改氏強制は、人格権を国家によって侵害する制度というべきである。また、少子化社会の進む中で、従来の家系の維持を重視する立場からも、必須の制度と思われ、どちらの立場からも、早急に変更すべき制度と思われます。また、旧制度のもとで氏を変更した者の救済措置も、是非、実現させたいものです。
美辺香澄 美辺株式会社 代表取締役社長 / 一時お預かり専用託児所はないと 代表
私も法人の設立時は旧姓で起ち上げをし、現在も名刺などすべて旧姓で活動をしております。選択できるようになるとよいなぁと思います。
武井由起子 八重洲グローカル法律事務所 共同経営者
私は、今は弁護士で、前職は総合商社の総合職でした。どちらも仕事に多いに支障があって困りました。通称使用を拡大と言っても、仕事の銀行関係の手続などが全く思うようにいきません。別姓でバリバリ仕事ができるようにして、日本の雰囲気をイキイキとかえていきたいと願っています。
河合奈美 株式会社Two Zone 代表取締役
主人がアメリカ人であり、結婚をした際も戸籍には自分のみとなるので本名の苗字は変えずにきました。しかし、同じ姓でないと家族として認められないという場面があり、家族の在り方を世界基準にしていくにも夫婦別姓が早く認められることを望みます。
横山桂子 西日本電信電話株式会社 常勤監査役
娘たちの世代に宿題を残したくないと思います
高崎信暁 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 代表取締役
結婚する人を増やし、出生率を上げ、人口増でお米の需要を増やすために賛同します。
増子里美 合同会社フォレスティ 代表社員
34年前に夫婦別姓が認められる未来を信じて夫の姓となる同姓婚をしました。実家の事業を承継した11年前、旧姓への改姓を考えましたが既に結婚して23年、旧姓に戻すための手続きの煩雑さ、夫・子供への影響を考えると出来ませんでした。別姓婚が認められる法改正を願っていましたが、速やかな実現性に期待し、別姓婚を選んでも不利益のない制度の整備とあわせて実現を強く願います。結婚によって一方だけが名前が残せる残せないと一喜一憂していては誰も幸せになりません。
藤田淑子 フィランソロピー・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
1.私は、結婚と離婚により2度の改姓を経験しています。姓が変わること度に、自分のアイデンティティを失う感覚を持ちました。キャリアの継続性に支障が出る経験もしました(同一人物であることを認識されず、過去の活動記録が分断されます)。旧姓使用をしていましたが、海外渡航において、社内の通称名とパスポート名が違うため、渡航できないかもしれないという事態にも見舞われたことがあります。手間と不便さを考えると、2度と結婚する気にはなれません。
2.国民の8割が賛成している制度が国会議員によって成立させられないということは、この国で間接民主制が機能していないことの現れです。これはこれで大きな問題です。
「なぜ選択的夫婦別姓に反対するのか」もオープンに議論し、みんなで解決策を考え、選択的夫婦別姓の法制化を進めていきましょう。
長川美里 NPO法人Wake Up Japan 副代表理事
誰もが自分の在りたい名前で、偽ることなく、我慢することなく、のびのびと暮らせますように。
大野勝利 元・株式会社ジェイ・プラン代表取締役 会長
結婚して女性が男性の姓になる前提という慣習からの脱却を支持します!
日高真理子 東ソー㈱ 社外取締役
現行制度は、名字の変更や使い分けに対する負荷を主に女性と企業に押し付けています。旧姓利用が進んでいるといわれ、企業も協力していますが、システム対応や旧姓の括弧書きが必要だったり、氏名を登記等している場合は旧姓ではなく戸籍と同じであることが必須の書類があったり、その不便さは、数え切れません。
選択的夫婦別姓制度の早急な法制化に賛同します。
藤森恵子 ASIMOV ROBOTICS株式会社 代表取締役CEO/公認会計士・税理士
公認会計士では、旧姓使用についてはかなり以前から認められていたものの、身分証明証がないことから、本当に、何度も何度も何度も、繰り返し繰り返し、苦しめられきました。
某メガバンクでは、会計事務所名と戸籍姓が違うことから、事務所の口座が作れませんでした。経費決済のためのクレジットカードも作れませんでした。こんな状態で、どうやって社会で働けというのか・・・この実態を知っていただきたいです。
確かに、ここ10年で、会社役員の登記、パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住民票などなど様々な場所で「旧姓併記」が認められるようになりました。
当時のこと思えば、今は、実務的な面での手間はかなり軽減されてきました。
でも、「旧姓併記」で済ませれば良いという日本という国は、本気で女性の活用を考えているのかと、いつも疑問に思います。
相澤菜穂子 有限会社あいね 代表取締役
女性の意思で、主体的に活躍できる社会をめざすために名前の選択権を求めます。
塚本薫 株式会社きらり.コーポレーション 代表取締役
離婚して既婚時の苗字を利用しております。経営者として名前が変わることはどれだけ大変なことかと実感しております。人から呼ばれる名前だからこそ、別姓選択ができるようになることを心より望んでいます。
髙野孝子 NPO法人エコプラス 代表理事
事実婚32年目です。国際的な活動をしていますが、関わる人たちに日本はまだそうなのと呆れられています。選択肢が増えることは民主的な国に近づくことと思います。
村井曉子 (株)フェニクシー社外取締役、元センクシア(株)社外取締役
日本古来の伝統、というロジックは間違っています。明治時代前は、姓がある人の方が少なく、江戸時代前でも姓がある由緒ある家柄の方々は別姓を保持する場合もありました。選択肢を増やす事です。
楠橋 明生 株式会社ako 代表取締役
応援しています。
渡部瑞穂 株式会社伝 代表取締役
20代の頃、別姓にするためにペーパー離婚しましたが、まさか自分が50代になってまだ法制化されていないとは思いませんでした。今は便宜上、夫が私の姓にしていますが、もちろん夫婦共に不本意であり、できるだけ早い法制化を願います。
池戸淳子 (社福)横浜市福祉サービス協会 理事長
人生100年時代、パートナーとのつながりの形にも多様化を!
伊加井真弓 EY新日本有限責任監査法人 パートナー 金融事業部副事業部長
同姓を強制する理由が全く理解できません。名前は自分のアイデンティティ。誰もがそれを喪失することのない社会を望みます。
三木谷浩史 楽天グループ株式会社 代表取締役社長
基本的な人権だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
