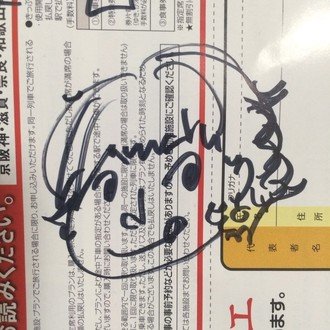むらにつもるこえ
1
発進した二両編成の電車がカーブを曲がり視界から消えたあと、ほんとうにひとのいない無人駅は私の知らない静かさがうるさかった。あたりには草木の青いにおいがたちこめていて、汗が穴という穴から噴き出してくる。
改札らしきものはない。日も暮れかかった夏の午後七時五分、駅の時計の針は私の腕時計と同じ時間を示しているが、秒針は腕時計のほうが十秒ほど遅れている。どっちがあっているのかわからない。両方ともあってないかもしれない。さっき下りた電車は終電一本前で、三時間後の十時五分発が終電だ。どうせ気まぐれの旅なのだったから、今日はここらで泊まろうと思った。
雨曝しになった銅のような色の屋根と、ほとんどの青かったペンキが剥がれた木の色も褪せたベンチがある。ここで野宿でかまわない。でも誰か泊めてくれるひとがいるにこしたことはないから、芸能人が田舎を旅する番組みたいにそこいらの民家に頼み込んでみようかと思ったけれども、外を見渡す限りひとつも街灯がなく、ひとっこひとり見当たらない。たぶん、長く歩いても民家はない気がして、そうするとますます民家を探す気がおきなくなる。かりに民家を無事見つけたとしても泊めてくれる保証はない。そもそも見ず知らずの汚らしい若者の一晩といえ泊めてくれなんて申し出は無理な相談と考えていた方がいいだろう。私なら泊めない。それにただでさえ家の数が少なそうなのに、断られたらすごくへこむ。それに良心あるひとならそんな頼みをされたら断れないかもしれないし、それはそれでこっちの良心が痛む。蚊が首に止まった。つぶそうと思って首を手で勢いよく叩いた。耳元でぷーんと高い音がなった。手には血がついてなかった。夜のとばりがおりた。
ベンチの上に寝袋をしき、そのなかにすっぽり入ると夜空には星が都会や私の故郷よりもたくさんあった。ほんとうはちょっとくらい散策してみたいところだけれども、予想以上に街灯がないし、ひとの気配もないし(まぁ、それがまたいいのだが)、ここらの地図も持ち合わせていないから、歩くにしても朝まで待った方がよさそうだ。それにここまでえっちらおっちら、乗り継ぎに乗り継いで一○時間ぐらい電車にゆられていたのだったからさすがに疲れた。夜の奥底で虫がちちちちちと鳴いた。銃声が遠く響いた。体は睡眠を欲しているが頭は覚醒したままだ。まぶたを閉じる。体と頭を足して二で割ったような心地で起きて眠っていた。まぶたの裏はずっと明るかった。駅の電灯は消えない。暑くて上半身だけ寝袋をぬぐ。
古い軽トラのサイドブレーキを引いたみたいな濁った甲高い音にはじかれて体を起こすと、やはりというか、知覚よりさきに浮かんだ風景とまったく同じに古い軽トラがベンチの横に止まっていた。おっちゃんが運転席の窓から首をのばして、
「にいちゃん、家は?」
と大声で早口にいった。その声で地元の人だと思った。
「ないです」
「泊めたろか?」
「はい、ありがとうございます」
ほとんど条件反射だった。大きく腹が鳴った。
「食うてないんか」
とおっちゃん。私が、はい、と答えると、
「よっしゃ!」
とおっちゃんはいう。大急ぎで寝袋をたたんで助手席に乗せてもらう。荷物は後ろの荷台につませてもらった。荷台でシカが死んでいた。
車のなかではエアコンはついてなくて、ふたつの窓を全開にして走った。おっちゃんはエアコンがくさいから嫌いだといい、私も実家の軽トラのほこりくさいエアコンが苦手で、父もきらいでいつもつけなかった。そして車内のどろくささも好きになれなかったのだったけれども、おっちゃんのとなりに座るいま、それが心地よくすら感じられた。窓の外から流れ込む湿った風が車のなかの空気をかき混ぜ、ふくらませ、運び去っていく。車のにおいが薄れていく。
おっちゃんの家はその無人駅から車で一時間ぐらいの村にあり、県道を三○分、それから舗装されていない山道を三○分。車で一時間とはいえ県道では常時時速九○キロぐらいだしていて、山道でも時速八○キロぐらいだしていた。信号はひとつもなかった。道中、おっちゃんは、
「疲れてるやろ? 寝ててええよ」
といってくれたのだったけれども、大声でずっと話しかけてきて、かと思えば実はただの大きな独り言のようで、黙っていても話はどんどんひとりでに進んでいき、相槌の打ち方がわからず、というよりも相槌を打つ隙すらも与えてくれず、結果、おっちゃんの声が気になって眠れなくて、後半はしょっちゅう曲がりくねって且つかなり凸凹した道だったので激しく車体は上下に揺れ、乗り物酔いはしないほうの私でもさすがに気分が悪くなったほどだった。
「死体かと思ったわ」
とおっちゃんは笑って何度かいった。
「最近死体を捨てに来る連中が多くてな」
というから私は、
「ほんとうですか?」
と一度返してみて、
「嘘にきまっとるやんけ」
とおっちゃんはさらに大声で馬鹿笑いをした。これが道中で唯一成立した会話らしい会話だった。
おっちゃんの家に着いたときは夜の九時。外観は木造二階建ての古き良き日本家屋といった感じだ。他にも似た十軒ほどの家が密集していたのは印象と違う。私の実家もそれなりの田舎にあるが、そこでは一軒一軒の敷地はだだっ広く、家と家の間隔はけっこう離れている。庭に畑があったり田んぼがあったりするというか、ひとまず家と家の間に最低一畝の田んぼを挟む。故郷との違いが目新しくてしげしげと辺りを見回していると、
「なにしてんねん」
とおっちゃんがいう。
「都会の子か?」
「大学は都会ですが、実家は田舎です」
「うちの息子も今年大学行ってなぁ、東京やなぁ」
とおっちゃんはいう。牛の間延びした鳴き声が聞こえて、
「うちの実家も牛を飼ってるんです」
「肉? 乳?」
「肉です」
おっちゃんは満足そうな顔をして、
「ここらやったらマラドーナさんとこが飼うてるな。んで、マラドーナさんとこ、今年、なんや県の牛の品評会で優勝したかなんかでそのお祝いを公会堂でこないだしたんや。わざわざ知事さんも来てくれてん」
といった。
「マラドーナさん?」
さすがに気になって訊いてみると、おっちゃんと同い年の近所のおっちゃんだという。
「日本人ですか?」
「あたりまえやん」
おっちゃんは即答した。
「本名ですか?」
と訊いてみると、
「ちゃうやろな」
と返ってきた。思えばおっちゃんの名前をまだ訊いていなかった。家には表札がなかった。
玄関は引き戸でガラガラと音が鳴る。中学一年のとき新築した私の実家は引き戸だったが音はならず、いまでも滑らかに開く。それ以前の家はここよりちょっと大げさにガラガラと音の鳴る引き戸で立てつけも悪かった。
「おかえり」
玄関からまっすぐのびたフローリングの廊下のわきからおっちゃんの奥さんだろうおばちゃんが首だけ出し、遅れて、
「あらまあ」
という。私は反射的にぺこりと頭を下げる。あいさつをしようとしたが声がでてこない。
「今日この子泊めたってや。駅で寝袋しいて寝とってん。んで、飯も食うてないみたいやから作ったってや」
それを聞いておばちゃんは一瞬視界から消え、ふたたび視界に現れのそのそとこちらへ歩いてきて私のスリッパを出してくれて他人用だろう笑顔をした。そう思った自分の小ささがいやだった。おばちゃんは思ったよりでかかった。たぶん一七○センチはある。
「野宿とかやめときや。イノシシとかクマとかに、あんた、わちゃわちゃにされんで」
このあたりは動物による被害がたえないようで、山からおりてきた獣が畑を荒らすなんてのは日常茶飯、それに関しては村全体であーだこーだ試行錯誤しながらいろいろ罠をしかけてみたものの数ヶ月で獣たちはその攻略法を見いだすものだから、最近はそういうもんだと村の者はあきらめていて、でも獣たちはときとして人も襲うのだから最低限個人でできることだけは怠ってはならないと村人同士で当番を決め、一軒一軒の戸をたたきまわるのだという。死者こそはめったにでないが、毎年五、六人の山の動物の襲撃によるけが人がでるのだと、おっちゃんは背中の古傷を見せ、
「イノシシにやられてん」
噛まれたような傷だった。
「まぁ居間で適当にゆっくりしといて」
とおっちゃんは外へ、おばちゃんは台所へ消えていった。私はつけっぱなしのテレビをぼんやり見る。クイズ番組だったテレビの音声より大きくおばちゃんの声が聞こえて、家の壁をはさんだおっちゃんの声がくぐもって聞こえ、テレビでしゃべっているここ半年ぐらいどのチャンネルでもでっぱなしのお笑い芸人がなにをいったのか聞き取れない。テレビに興味をなくし、だからといって初対面の他人の家のテレビを切るのもなんだか図々しく思え見るともなく見ていた。
おっちゃんとおばちゃんの声はずっと居間に流れ込んできて、おっちゃんの声は流れ込んでくるというより壁を打ち破ってくる。ふたりとも各々の作業をしながら、家の内と外で会話をしている。聞こうなんて思わなくても耳に入ってくるその会話の内容は、知らない固有名詞や耳なじみのない方言、訛りのためにほとんどわからない。ベッカムとかオバマとかメイリンとかそんな名前が頻出した。釈然とはしないが、たぶん有名人じゃなくて近所の人なのだろうと推測した。私の知っているオバマは猟銃を構えない。
会話は途切れることなく一時間ばかり続いて、おっちゃんとおばちゃんは話しながら一緒に居間に現れる。台所脇の勝手口からおっちゃんは入ってきたようだ。おばちゃんは鍋を、おっちゃんは生肉の切り身の乗った皿を持っていた。こんな暑いのに鍋とは意表を突かれた。
シカ鍋とシカの刺身だとおばちゃんはいう。シカの刺身の赤い肉を見ると軽トラで死んでいたシカを思い出し、隣に座ったおっちゃんの手から血なまぐさいにおいがしたような気がした。その手でおっちゃんは扇風機をつける。
シカ鍋の肉は固かくて噛みきるのに大変で、おいしいのかどうかよくわからなかったが、辛子味噌をつけて食べるシカの刺身はすごくおいしい。
「にいちゃん、なんでまたこんな辺鄙なとこに?」
おばちゃんは鍋をよそう。
「まぁ、ふらっとですね」
は? といいたげな顔をおっちゃんはした。
「自分探しの旅ってやつです」
私はとりあえずそう答えておく。あながち間違ってないのだが、べつに自分探しなんていうにはちょっと大げさで、ただ大学生活に疲れて知らない土地へ行ってみたくなったのだった。就職活動を前にして、山のようにある職種を調べていくなか、自分のやりたいことなんてなにもないことに気がついてしまった。もっとも、大学に入る前、そして入った直後は、かねてから切望していた物理学をようやく学べるのだと私はすごくうれしかったのだったけれども、いざ授業がはじまると、線形代数、ベクトル解析などの数学がどうしても理解できず、授業から次第に足が遠のき、気がつけば物理をやりたいという意志もはじめからあったのかすらわからない程度になっていて、文系就職用の応急処置的な言語学のゼミに所属することになった。ゼミには一度も出ていない。
「ほー、どこ行くとか決めてんのか」
おっちゃんは日本酒を私についだ。頭を軽く下げ、小さくありがとうございますという。お猪口に両手を添える。
「いやぁ、まだぜんぜん決めてなくて。気分に任せて、ですね」
「また十月から学校やろ? はよせなすぐ夏休み終わってまうで」
「時間はまぁ、たくさんあるんです」
「そうなん?」
「休学してるんです」
すべてが煩わしくなって逃げ出したかったというのが本音だ。とりあえず一年間は大学や街を離れることにして、でも貯金なんてまったくなかったのだったから、四月の頭から七月の中旬まで毎日派遣のアルバイトを詰め込んで、八月から日本をふらふら回ろうと思った。まだやろうと思ってやっていなかった青春18きっぷでのノープランのひとり旅をとりあえず期限の切れる夏いっぱいやってみようと思い、休学はいい機会だと考えた。しかし中途半端に時間があるときはどうも時間を無駄に使ってしまいがちで、だいたい家でごろごろだらだら過ごし、たとえばネットをさまよい小さいころ好きだったアニメを見るに終始してしまう私の悪い癖も直るとはとうてい思えなかったし、アパートも七月いっぱいで引き払った。これは冬場にこたつのなかでだらだらしてしまうのを直すためにはこたつがなければいいという発想と全く同じだ。こたつ近傍のポテンシャルエネルギーが井戸のよう深く落ち込んでいるから一度入ると出られないとかそういう感覚で、家の扉の内と外でも同じことが起こっているなら家がなければポテンシャルエネルギーの極小に私はトラップされないはずだ。閉じた系ではエントロピーが増大していくのが自然の摂理で、私のなかで悶々としたあれこれが降り積もり、視界が閉ざされていくのを回避するためには系を開くのがいい。扉を開くのがいい。それに、いない家に金を払うのももったいない。
おっちゃんは日本酒をぐいっとのみ、手酌してまたぐいっと飲むと、
「若いってええわー」
と相変わらずの大きな声でいう。私の方を向いていなかった。テレビからどっと笑い声が起こった。
「行くとこないねんな?」
「決めてないですね」
「ここでのんびりしてってもええで」
「あ、それもいいですね」
「なんやねん、それ」
私もそこそこに酔っぱらっていたのだと思う。が、見知らぬ土地の見知らぬ人と生活してみるのもいいことだと、アルコールのない頭でも判断しただろう。私の気まぐれとおっちゃんの気まぐれが起こした、この場所、この時間でしか経験できないことで、そういう機会はもう人生でないかもしれない。私は限定品に弱い。テレビがまた笑った。
「ツジヒロシといいます」
私は姿勢を正し、これまで名前を名乗っていなかった無礼を詫びると、
「そんなんはええけど、それ、本名か?」
とおっちゃんは怪訝な表情で訊き、はい、と答えると、
「そんなん他人にやすやすというもんちゃうで」
と続ける声が少し小さかった。おばちゃんはいなくなっていた。
「どうしてですか?」
「いろいろあんねん」
「いろいろですか?」
「名前は人を縛りよるからな」
私たちは黙った。静かになる。テレビは相変わらずだけれども、外の虫の声が聞こえる静かさだ。
「わし、ボナンザな」
私は驚かなかった。
「それは誰がつけたんですか?」
「自分」
おっちゃんは私をまっすぐ見るのだったから『自分』はおっちゃん自身を指しているのか私を指しているのか一瞬わからなかったけれども、たぶんおっちゃん自身を指していると見て間違いないだろうと思うと、それはそのはずでまちがいようがなく、そもそもなんでそんなことを考えていたのか自分でもよくわからなくなる。
また黙る。おっちゃんは外を見ながら何かを考えていて、ふたたびにこっちを向いたとき、名前をつけろという。私はとっさに、
「コウジ」
と答える。三つ下の弟の名前だった。ええ名前やん、とおっちゃんはいう。コウジ、コウジと連呼しながら私の背中をうれしそうにバンバン叩いたが、それで胃を揺すられて吐きそうになった。
「風呂が沸いたで」
おばちゃんが目の前に立ってにっこり笑っていてびっくりした。こういうのも失礼で申し訳ないのだが、なんだか嫌な気分になった。風呂は風呂自動機能がなかった。おばちゃんをヴィクトリアと呼ぶおっちゃんの声を風呂場で聞いた。
寝床として息子さんの八畳の和室があてがわれ、風呂から上がるとすでに布団がしいてあり、ベッドはなかった。ベッドだけではなく、箪笥と空っぽの学習机を除いて目につくものは何もない。おっちゃんが部屋までついてきて、すぐ寝るか? と訊かれ、はい、と答える。私が布団に潜り込むとおっちゃんは電気を消して廊下に立つと、
「あんたのほんまの名前、わし、もう忘れたからな」
と襖を閉め、私の視界は真っ暗になった。
翌朝、私は外から窓ガラスを打ち破って侵入してくるしわがれた大声で目を覚ました。なにごとかと窓を開くと、家々が密集したこのあたりのちょうど真ん中あたりの広場になったところに立つ腰の曲がったおじいさんが声の主だとわかった。そのあたりにおじいさん以外の人はおらず、遠くの田んぼには人が点々といた。動いていたので案山子ではない。動く案山子がいるなら案山子かもしれない。動く案山子はふつうにいるかもしれない。動く案山子は見てみたい。
私は窓の下のおじいさんに視線を戻し、そのままおじいさんを見ていた。彼の声に起こされたときはあまりの唐突さに目が一気にさめたのだが、じきにまた眠くなる。おじいさんは自分を、私、といい、自分の婚約者の話をしていて、それは現在形で語られた。訛りこそきつかったが、共通語だと思う。おじいさんはたいそう婚約者に惚れ込んでいるようで、彼女の好きな仕草のひとつひとつを詳細に語り、気がつけば禁煙が苦しいという話を煙草を吸いながら話していた。二本目の煙草に火をつけたとき大きくむせて、そのあと涙声になると妻が死んだ話を過去形で話し、ツバメが毎年自分の家の玄関の上に巣を作るのがうっとうしいと語った。都会へ行った息子が帰ってこないと嘆いた。貧困ゆえに幼い息子を殺そうかと迷ったと語った。煙草をやめてから体の調子がいいとうれしそうに語った。村の川でとれる魚はうまいと語った。
朝食のときにボナンザさんに村の川魚について訊いてみたが、そんなものはないという。厳密には、もうない。川がない。曰く、かつては確かに川があったのだが、十五年前の地震のあとに干上がってしまったという。川なければ川魚はいない。そういってボナンザさんは朝食をかき込むと勝手口から外へ出ていく。ズボンに泥がたくさんついていた。
川が干上がったとき村は魚臭くて誰もが鼻を押さえて歩かなければならなかったとヴィクトリアさんは食器を洗いながらいう。地震があってから川は流れなくなり、よどみ、徐々に川幅を狭くしていった。誰も川の草を刈らなかったのだったから川には雑草が青々と茂った。草の間に干からびた魚の死骸がたくさん落ちていた。そのときにはもうとても食べられそうになかった。あのときも夏だった。おじいさんの声が聞こえる。
「あのおじいさんは何者なんですか?」
「ムラやで」
「ムラさん?」
「『さん』はつけへん」
「ムラ」
「そう」
「どうしてですか?」
「名前とちゃうからとちゃう?」
ヴィクトリアさんは質問を疑問符で返し、ムラについて教えてくれなかった。というより、私がムラについての何を訊けばよいのか思いつかなかったから会話がそこで途切れてしまい、ヴィクトリアさんは洗濯物を干しに行ってしまった。行く前に麦茶をくれた。わたしはそれをゆっくり飲みながらムラの声を聞くともなく聞いていた。ムラは休まなかった。
七時半を過ぎるとムラじゃない声もいくつか聞こえるようになる。ムラと同じくらい大きい。私は玄関から外に出ると、ムラと目が合う。しかしムラは自分のペースで話を続ける。私の方を向いているし、ひょっとしたらムラは私に話しかけているのではないかと思ったが、ムラの視線はすぐに私から離れた。また、ムラ以外の声はムラと会話していなかった。そのとき話していたのは納屋で仕事をするボナンザさんと、二軒隣の家の台所から窓を開けて野菜を洗っていたおばあちゃんはメイリンさんで、今年の梅雨は雨があまり降らなかったから田んぼが心配だと話していた。二人は互いの顔が見える位置関係になかった。ムラは空梅雨のときの過ごし方の話を始め、すると夏は山のわき水がとてもおいしいから毎朝汲みに行くのだとムラは語り出す。メイリンさんはわき水をいまは使っていない風呂桶に貯めているのだという。家は去年息子夫婦がリフォームして、段差の少ないバリアフリー仕様らしい。ボナンザさんは早く息子に帰ってきて欲しいのだが、やっぱり息子の人生を田舎に縛り付けることはできないし、自分ができなかったことをしている息子が一番たのしいと思える人生を歩んで欲しいという。ほんまそうやで! と新しい声が飛び込んでくる。逆隣のおじさんはオバマさんだった。その隣の家から牛がモーと鳴いた。あそこがマラドーナさんの家だろう。ムラは井戸の掘り方の話をしている。
「なにか手伝えることはありませんか?」
わたしはボナンザさんのいる納屋まで行ってそうたずねると、
「べつにないなぁ」
といって手を止め、しばらくうーんと唸って考える。そして、
「コウジ、あれやん、実家で牛飼うてんねんやろ?」
と声を張り上げた。納屋全体が揺れたような気がした。
「コウジが牛の世話できんぞー」
とボナンザさんはまた大声でいうと、
「ちょっとわしんとこきてぇやー」
と返事が返ってきた。ボナンザさんはマラドーナさんの家へ行けと私にいう。村人とのコミュニケーションにもなるしそれがいいと理由を付け加える。しかし私は牛の世話などしたことがなかった。父親がしているところを見ていただけで、小さいころに藁をくわせてやったことぐらいはあるが、それは世話というより幼いころの遊びでしかない。牛がまたモーと鳴き、その声のする建物へ歩いて行くと、ボナンザさんより少し若そうなツナギを着たおっちゃんが首から下げた手ぬぐいで汗を拭いていた。どちらかといえば痩せた人だった。
私はマラドーナさんに、
「はじめましてコウジです」
とあいさつをすると、マラドーナさんは、
「知っとう知っとう」
と背中を向けて作業の手をとめることなくいう。そして私はたしかに実家では牛を飼っているが、牛の世話についてはずぶの素人だという旨を申し訳なさを全面に出した声色で伝えると、マラドーナさんはそんなものは全然関係ないと笑い、作業の手を止めて、さっきまでかれがしていた牛のえさに混ぜる藁を鎌で細かく切る仕事を私に与え、
「ほんま、ありがとなー」
という。簡単な仕事だった。牛小屋には牛が五頭だけだった。それでも結構うるさくて、話しかけられても何度か聞き返さなければ私には会話ができない。
マラドーナさんは品評会で優勝したという牛を私に見せてくれて、毛並みがどうとかエサの与え方がどうとかそういう解説をしてくれたのだったけれども、私には当然ながら全然わからなかったし、実家にいる牛との違いもよくわからなかった。デカいことだけはわかった。しかしマラドーナさんは機嫌よく話していたのだったから、彼が時折語尾を上げて私の目を見たときは、できるだけ元気よく、そうですね! と同意した。牛を飼い始めたのはマラドーナさんの父で、マラドーナさんは五年前に父からそれを引き継いだ。ようやく最近コツがわかってきたのだという。父は癌で一昨年亡くなった。その話を聞くと藁を切る手が止まってしまった。マラドーナさんは手が止まっていると注意し、すいません、と謝ると、少し間を置いて、あんまり気にするなといい、そのあとに歯を見せて笑って手ぬぐいで汗を拭く。牛の泣き声と藁を切る音がない、ほんの一瞬にムラの声が潜り込んでくる。
「ムラってなんですか?」
マラドーナさんに訊いてみた。
「手!」
とマラドーナさんはいった。私はすいませんという。
「ムラはなぁ、ムラとしかいえんなぁ」
「村長さんみたいな感じですか?」
「それは違うなぁ」
「ムラになれって言われたらなりますか?」
「そういうことはないけど、あったらやらなあかんな」
「ムラになりたいですか?」
「そういうもんでもない」といったあと、マラドーナさんは思いついたように、「ムラはな、村そのものやねん。漢字の村や」
「村の顔ってことですか?」
マラドーナさんは眉を思いっきりしかめて、
「そんなんじゃなくて、村なんや」
といった。私は、すみませんがよくわかりませんというと、マラドーナさんは諦めたような顔をして、長く村にいたらそれがわかるかもしれないといった。マラドーナさんうまいこというやん! と牛の声の膜を突き破ってボナンザさんの声が聞こえた。せやろ! とマラドーナさんはいい、おいこら手! といった。ボナンザさんは、コウジちゃんと仕事しいやといい、マラドーナさんは昨日のシカの礼をボナンザさんにいう。ムラの声が大きくなり、聞こえてくる単語からムラはシカの仕留め方の話をしているように思われた。そしてその後もムラは日没まで場所を動くことなく語り続けた。
2
医者は女の子が生まれるといったのに、実際に生まれてきたのが男の子だったから、私はまだへその緒がつながったままのぬれた我が子の豆のような男性器を見ながら、かれを埋める場所をぼんやりと考えていた。妻の顔は男の子だと私がいうととても疲れたようで、へその緒を切ってちょうだいといえば眠りにおちた。となりの部屋で寝ていた父はこっちまではってくると、じっと息子を見たあと、やるなら名前をつけるまえにしろ、とぽつりという。
私の仕事の稼ぎの大方は妻の実家へいき、本来、それは私の父が支払わねばならない償いだった。私が結婚するより五年前に父は病に倒れ、働けぬ体になった。金はすぐになくなり、続いて家具がなくなると私の結婚後には父の家はなくなって、それからは私と妻の家で寝る毎日だ。母は私の幼い頃に死んだ。実家には女がいなかった。
村では夫の家が妻の家に財産をみつがねばならず、それは二十年後になくなるのだったけれども、そのとき私たちは後にそれがはじめからなかったみたいに消えてなくなってしまうことを知らないから、自分たちが老いて腰の曲がったあと、息子の嫁の実家に身ぐるみはがされるかもしれなかった。逆に、娘をつくれば私たちは娘の夫の家から私がこれまでに、そしてこれから奪われてしまったものたちを取り戻せるかもしれなかった。十代から街へひっそりとでかけ買い集めた本たちをろくろく本など読みもしない妻の両親に差しだし、案の定、家にあってもしかたないという理由から二束三文で私の知らない街へと売られていったようだった。家族で一番結婚が遅かったのは私で、二つ上の兄と一つ下の弟もまた私と同じく各々の妻の家へ財産と稼ぎを差し出さねばならなかったが、本をしぶった私に、そんなもんだ、お前はぜいたくだ、と異口同音に長いため息といっしょに吐き出した。彼らに欲しいものなどない。体があればよかったのだ。私もじきに欲しいものはなくなった。しいていうなら金が欲しかった。手元に金が残るなら、産湯につけた息子をそのまま溺れさせることだってできる。
男は女を奪うものだ。大人が子どもにそのようにいうから村の誰もがそういう。奪うのは罪で、奪われるのは罪ではない。結婚は罪だ。幼い頃からどんなに奪う罪を説いても、若い男女は惹かれあってしまう。それは教育が悪い。子どもの罪を親が償う。親が罪深いのだ。村人は罪を金で洗うか、その罪をほかの誰かになすりつける。右があれば左があり、男がいれば女がいる。結婚が一対の男女でなされるのであれば、村人はみな奪う者であり、みな奪われる者となった。天国があるから地獄があり、村には地獄もなければ天国もなくて、村にはなにもなくなり、形骸化したしきたりだけが残る。思えば、それもまた消えていくに違いなかった。
兄と弟、そして他の村の男たちと比べ、私がもっとも違っていたのは牛を飼わないところだ。冬場、雪に閉ざされるこの村ではすぐに金になる仕事は限られる。草鞋を編むか、子どものいない老人の家の雪かきぐらいだ。それでも日頃からぜいたくさえいわなければ誰もがかろうじて生活することができ、私と兄弟以外の村の男たちはぜいたくができ、しかし村の外へ働きにでたほうがたくさん稼げたのはいうまでもない。村の男たちは牛によって村につながれていた。私は牛の鳴き声が嫌いだ。
私は私のために父があてがった土地を兄と弟にまかせ、夏のあいだでさえも村の外で働くことを選んだ。妻も私と同様に村の生まれだった。妻と私はおなじ日に生まれた。妻と私はずっといっしょだったから、いつ恋仲になり、いつ夫婦になったのか厳密にはわからない。だからふたりの誕生日にすべてが起こったことにして、八十年もすればこの日に死ぬのだと幼い頃からわかっていた。妻の両親は私たちが生まれたときから楽に死ねるとよろこんだ。結婚の遅いことに腹をたてた。かつ遠くへ妻を連れていくものなら、自分たちを殺すつもりかというだろう。妻は村を出られなかったから、私たちははじめてわかれることになる。
私は月に一度、妻の実家へ償いをするために帰ってき、そのときだけ妻に会うことができる生活だった。私たちはいっしょにおいしいものを食べたかったのだったから、私は猟銃を持って山を歩き、妻は料理に腕をふるう。時間をかけて夕食をとり、時間をかけて交わり、妻のおなかは会う度に大きくなっていく。妻は申し訳なさそうな顔をしたのだったけれども、私はつとめてよろこぶようにし、それはもう不安を微塵も与えないようによろこび、村の川魚を食えば女の子が生まれるといわれていたから、川が凍りついても釣りをするようになる。医者が妻のおなかに女の子がいるといったときに、妻ははじめてよろこんだのだったけれども、どことなく後ろ暗い笑顔のように思え私はそれを見なかったことにすると、妻は総じてうれしそうだったから私もうれしい。妻は子どもが三人欲しいといった。私は微笑んで、あとふたり欲しいねといった。妻は寝息をたてはじめる。息子はずっと泣いている。
妻が子どもを三人欲しいというのは、私もそうであるが三人きょうだいで育ったからで、妻は長女でひとつ下の妹と五つ下の弟がいた。妻は、三人というのは教育的にすごくいいのだと主張し、上もいるし下もいるし上と下のやりとりを少し離れたところから見ることもできるのがなによりいいことだと語った。しかし妻の弟は八歳で亡くなった。生まれつき胃腸が弱かった。
妻もまた胃腸が弱い。病気というわけではないが、三日に一度、夜になると腹部が苦しくなって、私に背中を圧してと頼む。布団にうつ伏せで寝た妻の背中を、腰のあたりを、私は妻に馬乗りして圧す。そのとき、このあたりが痛いのだと、むかし、弟がいっていたの、と妻は不意になんでもない口調でいうのだったから、私は言葉を奪われ、その八歳で亡くなった弟のことを思い出さねばならなかったが、かれの顔を思い出せず、そのことが私を悲しくさせるのと同時に楽にしてくれるのだった。
しかし妻はそんな私を見透かしたようにくすっと笑って、十五年も前のことなのだから、十五年も経ってしまえば、死んでいるひとは生きているひとと同じに扱っても悲しいことなんて何もないのだ、という。泣いていない、とても穏やかな声でいう。十五年前の妻は妻でなくサエちゃんだった。
サエちゃんの弟と遊んでやったことが度々あって、でもかれはやっぱり体の弱い子だったのだから、家のなかで遊ぶことしかない。家の外では同世代の子どもたちが黄色い声をまき散らしながらおにごっこやかくれんぼをするが、もしサエちゃんの弟が缶蹴りなどすれば、かれはずっとオニのまま缶のまわりをうろうろしなければならなかっただろう。缶蹴りというのはなかなかにひどい遊びで、逃げる側が隠れることをやめて団結し、いっせいに缶に向かって走り出せばオニはそれを阻止することが物理的に不可能になる。健康な子でさえそうであるのだから、泣かされるのだから、体の弱いサエちゃんの弟も泣くに違いなかった。子どもはそれほどに残酷なのだ。でも、サエちゃんの弟はおそらくかれの体がたとえ健康であったとしても、家で遊ぶことを選んでいたような気がする。かれはトランプ遊びが好きで、ババ抜きや七ならべ、大富豪とか、すごく楽しく何度も遊んだ。とくに「ざぶとん」という遊びがお気に入りだった。「ざぶとん」は場をみなで囲んで1から順番に2、3、4、と各人数字を出していく遊びで、数をいいながらカードを伏せて場に出し、ときどき数は嘘かもしれなくて、嘘だと思ったらカードを出さなかったひとが「ざぶとん!」と叫ぶ。ほんとうに嘘だったら「ざぶとん!」と言われたひとは場にあるカードをすべて手札に加えなければならず、嘘でなければ叫んだひとがそうしなければならず、いちばん先に手札のなくなったひとが勝ちだった。サエちゃんの弟はざぶとんがとても強い。私はかれほど強くない。私は「ざぶとん!」といいたい。サエちゃんは、そんな無鉄砲にざぶとん! ざぶとん! とあんたばかりが連呼するのはつまらない、と不平をいう。サエちゃんの妹は曖昧に笑う。サエちゃんの弟はカードを出すのが楽しい。かれは必要なとき以外にほとんど声を出すことなく静かににこにこしている。かれが強かったのは、嘘をつく必要がなかったからだった。かれはそのことをよく知っていたのだと思う。サエちゃんはざぶとんが弱い。
妻はサエという名前をやめてからもざぶとんは弱いままに違いなかった。しかしかれがいなくなってから、私と妻と妻の妹はざぶとんはおろか、トランプ遊びをすることをやめたのだったから、ひょっとしたら強くなっているかもしれなかったが、それでもやっぱり弱いだろう。妻はとても大事にお腹を撫でさすり、妻のそうしているところを見ている間、私はここに私がいないことのほうが正しいような気がして、私は妻のお腹が大きくなりはじめてから、妻のお腹の大きさにあわせて私の不在が私のなかで膨張するような、そんな心地がしていて透明で真っ白だった。うごいた、と妻がいう。うごいたの? と私がいう。うん、と妻がいって手招きをする。私は妻のお腹に耳をあてる。かれが向こうから蹴る。どんと蹴る。怒りか、それとも恐れか、私を拒絶している蹴りだった。私は追い立てられるように村を出た。
街で私は妻のお腹のなかにいるかれが、じつは私の子ではないんじゃないかと思う。結婚して以来、私と妻が会うのはせいぜい三十日あるひと月の一日ぐらいしかないし、交わらない月もあったし、よくよく考えると、それが妻の排卵と重なっていたのかどうかわからない。私が村にいないあいだ、妻は家でひとり目覚め、食事し、家事をし、私の父の面倒をみ、風呂に入り、眠る毎日だった。大方は縁側で田を眺め、時のムラの声に耳を傾けて過ごしていた。そこに、村の若い男がよってきたのだったら、いったい妻はどうしただろう? それ以上、考えないようにした。肉体労働なのがよかった。地面を掘っては埋め固める工事現場の仕事は、役所が予算を使い切るためだけの意味のない仕事なのだと同僚は語った。その同僚はヤマオカという、私のふたつ上の子どものいる独身の男だった。そのとき私はキョウジという名前を使っていて、ヤマオカはヤマオカシンヤという名前しか使ったことがなかった。私はそれは怖くないかとたずねると、ヤマオカはそんなことを一度も考えたことがない。ヤマオカは先祖がつけ、シンヤは親がつけ、生まれたときからあったそれはヤマオカシンヤの好きでも嫌いでもない空気だ。ヤマオカだけではない。他のひともみんな名前はひとつだけだ。私を含めて村の人みんなにとって、名前は着ては脱ぐ服だった。名前は私たちの体を通り過ぎて、やってくる。その周期はひとによってまちまちで、季節ごとに着替えるひともいれば三年以上同じ名前を着続けるひとだっている。名前を着替えないひとは、着替えないの? とまわりに訊かれ、そこにはいつも「どうして」がついてまわる。名前を着続けることには理由が必要で、逆に名前を脱ぎ捨てることには何の意味もないのだと、ヤマオカを見て私はそのときはじめて知った。ヤマオカは子どもの名前をつけることすらできなかった。子どもと会ったことがない、とかれはときどき語っては悲しく安い焼酎を飲んで、私はたびたびそれに付き合った。あのときはたしかヤマオカの借りていたアパートで私とヤマオカとキジマとヒロセの四人で飲んでいて、それもかなり飲んでいて、それはたぶん私たちは年が近く一番上から一番下まででみっつしか違わず、また、みんな田舎から街にやってきたという共通点もあったからに違いなかった。私たちの地元はまったく違った。けれども酒が入るとそれぞれがそれぞれの方言で自由に話し始める。聞き慣れない発音や知らないことばがあふれている。ヤマオカの部屋はとてもこざっぱりしていて、必要最低限どころか必要なものすらも切り捨てられていて、机もちゃぶ台も本棚もなければ冷蔵庫も調理用具もなく、ひとつあるタンスと万年床を囲む酒瓶ぐらいしかない。その四段あるタンスの一番上の引き出しは左右二つにわかれていて、その左側をキジマが勝手に開けたときにトランプを見つけて、暇つぶしにそれをしようとなったが、じゃあ大富豪をしようかと私がいうと、それは大貧民というのだとヤマオカはいった。キジマは大貧民で、ヒロセも大貧民だった。それを受け、続いて私はざぶとんのことをいうのだったけれども、やはりみんなざぶとんというときょとんとし、互いに目を見合わせたあとに私をのこして暗い笑いをもらす。それはダウトというのだとヒロセがいうとキジマもヤマオカもそれに同意した。私だけが違った。そこで大貧民ではなくダウトをしたが、私だけざぶとんといわないといけないルールでそれは行われた。私が一番よわかった。キジマも、ヒロセも私より強かった。最も強かったのはヤマオカで、それは妻の弟とはまったく対極にある強さだった。だてに子どもをひとり捨ててないよ、とかれは笑う。そして私が一時的に村へもどり、またこの街にやってきたときにはヤマオカもキジマもヒロセも、この街にはいなかった。もう会わなかった。
十代のころだ。毎月すこしずつ貯めた小遣いを片手に、中学の寮をスネルと名乗っていた友達といっしょに忍び出て、格安の4列シートの夜行バスでこの街に本を買いにはじめてやってきたときの私は、いずれこの街に住むだろうというかすかな予感めいたもの感じていないわけではなかったが、村人であると自覚する私がその予感をすぐに否定し、降り立った駅をのろのろと歩いているとすれ違った女の子のランドセルはてらてらと黒かった。私はスネルに、黒いね、というと、かれも、黒いね、という。次にすれ違った女の子のランドセルは茶色い皮のくすんだ色で、赤じゃないね、とかれはいって、それっきり私たちは黙ると足音がたくさんあった。街は違う位相にあった。だからどうしたこともない。違うものは違うものとしてそこにあるだけだ。私たちは街ではできるだけ声を発したくなかった。駅の裏にある細い路地のシャッターがたくさんおりたところにあった車は見えないのに走る音だけ表から忙しく流れ込んでくる古本屋に私とスネルはその店が開いてから閉まるまでいた。街はひとも建物もなにもかもの背が高かったのに、そこはちいさい本屋だった。店主はおじいさんで、タツタ書店だったからタツタさんで正しかったのが不思議で笑えたので、でもおおっぴらに笑うのは失礼だとわかっていた私たちは店の外にでてこっそり笑った。いま思えばとても迷惑だっただろうに、店に一日中いる子どもが珍しかったからかタツタじいさんは嫌な顔ひとつせずにずっといることを許してくれて、昼にはごはんと味噌汁とおかず一品をだしてくれて、ときどきお茶もくれて私たちはうれしかった。私たちがどこから来たのかを聞くことはなかったけれども、私たちの話す声を聞いて、遠くからやってきたのだとわかっていた。大人になってこの街で働き出すと、一言しゃべれば田舎から来たのだろうといつも訊かれた。ヤマオカとはじめてしゃべったときも訊かれた。ヤマオカといちどこの書店のあった前を通っていると、そこはずっと降りたシャッターになっていて、「タツタ書店」の字もかすんで読めなくなっていた。位相が変わっていた。
ヤマオカの話にはいつもどこかに嘘が忍び込んでいたが、子どもの話を私にするとき、ヤマオカはどことなく違う口調になる。どこがどう違うのかをいうのは難しく、どことなくたどたどしくなる。それがヤマオカでないひとだったなら、嘘をつくときのたどたどしさと考えるのが普通だが、ヤマオカの場合は嘘をつき慣れているから、いちばん悟られたくない嘘を隠すために日頃から嘘をつき続けていたのかもしれない。私の知っているヤマオカは誰よりも長くまじめに働く男だが、かれのいうに元来そういうたちではない。この街にくる前の別の街にいたときに二年ほど女と同棲していて、そのときかれは働いておらず、ずっとふらふらしていて、もっぱら女が稼いでいた。女は大学を卒業していた。有名な会社に勤めていた。良い稼ぎだった。なんでそんな女がヤマオカと付き合っていたのか。どちらから惚れたのかと訊いてもヤマオカは知らない。恋愛なるものが発生する過程なんて過ぎてしまえば忘れてしまう。そうかもしれないと私は自分を省みて思った。
子どもができたとわかったとき、ヤマオカは即座に捨てられた。夜中、知り合いと飲んでから帰った朝に子ができたと女は告げ、私はこの子と生きていくのだから、ふたりはとても養えないのだから、あんたは必要ないのだから、今すぐ荷物をまとめて出ていってくれないか、とまだ大きくなってもいないお腹を撫でながらいう。ヤマオカの荷物はすでにいくつかのダンボール箱に積められていて、出て行かなければならなかったし、こうなった以上ふたりの関係の修復はもはや手遅れで、女のこの毅然とした態度はもう前々からこのときを待ちわびていたことを物語っていた。このときヤマオカは子どもなどできていないのだと、それは女の嘘なのだと、これ見よがしに腹を撫でさする女を見ながら考えていた。そしてヤマオカは出ていった。玄関に積まれたダンボール箱はそっちで捨てておいてくれと女にいい残した。引っ越しをするのは身軽なのがいい。次にどこへ行こうか。故郷に帰ることも考えたが、そこへ帰るには遠くに来すぎてしまった。
しかしほんとうに子どもができていたのかもしれない。ヤマオカはそんなことを思うことがあって、それは主に夢のなかだった。ヤマオカは滅びたかれの故郷のひび割れたかたい土の上に立っていて、そこにはなにもない、だれもいない、木もない、川もない、雨もふらない、雲もない、ただ空虚な晴天が果てしなく地平線の向こうまで続いている荒れ果てた土地だ。そこに地面の割れ目から無数の赤子が湧いて出る。まずは耳から視界に現れ、続いてそこに手が生え足が生え、他の器官が遅れて形成されると胎児が地面に転がり泣き声を上げる。そして成長を続け、地面につながったへその緒を伸ばしたまま、おぼつかない足取りでヤマオカのもとへとすり寄ってくる。男でもあり女でもある子だった。かれらはなにもいわない。ひとりの子どもがヤマオカの裾にふれたとき、ヤマオカは目が覚める。ヤマオカは自らの子どもが男なのか女なのか、それとも存在しているのかを知らない。依然として知らない。知らない方がいいんだよ、その方が楽なんだ、どうせもうあの女との連絡も途絶えてしまった、知りようがない。
妻の腹のなかにいる子は私の子ではなく、他の村の男の子にしか思えなくなってきた私は、お腹のなかの子が女の子だと医者がいったあとに明るくなった妻のちょっとした笑みですら私をあざわらっているとしか見えなくなる。妻は最近私の話し方が変わってきたという。ほんとうはちょっと前から気になっていたのだけど、いまじゃもうぜんぜん違う、あなたはすっかり街のひとだ、そう妻がいうとき、私はヤマオカと名乗っていた。私は街の話し方をしてなにが悪いのだと怒鳴る。お前は村人だもんな、ずっと、これからも村人で、村人でしかなくて、その腹のなかにいる誰のものかもしれない子もまた村の牛につながれて、ここで一生朽ちていくのを待つんだろう、おれは村の人間ではもうなくて、いまじゃもうはじめから村の人間じゃなくって、土地も牛も持っていないし、撒いた種も実らなかった、本も奪われた、話す言葉も失われてしまった、次に村を出るときはきっと、もう村に帰れない、帰らない、これからずっと遠くへ行くことになるだろうから、その腹の子の顔を見ることもできない、見るべきではないし、見る意味もない、というと妻は私に死ねという。私は妻を平手で打つ。妻はもう一度私に死ねといい、私はもう一度妻を打ち、一度目よりもはげしく妻を打ったが、妻は何度でも私に死ねという。妻ははげしい目をしていた。私は妻を殴るのに疲れてやめてもまだ妻ははげしい目で、死ね、死ね、というけれどもそれはだんだん弱くなっていって、知らぬ間に消えたと思ったら寝ている。次の日の朝、妻の声が聞こえて目覚めると、それはまったくいつもと変わりなく、私が起きたのに気がつくと、子どもは三人欲しいねと笑うのだったから、やっぱり私は昨日妻を罵倒したりしなかったし、殴ったりはしなかったし、怒りの痕跡はどこにもなくて、妻のお腹の子も私の子だとすんなり納得できるようになって、あとふたり欲しいね、と答えて見た妻の笑う顔にはくっきりと痣がある。痣はいま布団の上で寝息をたてはじめた妻からは消えているはずなのに、ずっと前に消えているはずなのに、火照った妻の頬の赤いのが、たしかに赤いのに青く見える。妻のとなりに横にさせた泣きやんで静かになった息子の濡れていたのを拭ってやる。とても柔らかい頭をしていたのだったから、豆腐みたいにくにゃっと曲がり、あるいはぼろぼろと崩れ落ちそうな体の部位だったから、そのままひとつずつそれらをひっぱってはがしていけるんじゃないかと私は思った。まったく憎らしい子だった。そんな息子も中学になると赤いティーシャツを前を全開にした学ラン前のなかに着て、乱暴なことばを使い、家の軽トラを勝手に乗ったりして、高校も途中でやめてもうずいぶん長いこと村へ帰ってきていない。息子のいない間に妻は死んだけど私は生きていた。妻は私たちの誕生日に死ななかった。妻と私はやっぱり違った。妻の命日は私たちのふたつめの記念日になってはじめて誕生日にお祝いをするのは自分の命日を祝えないからなのか、と妻の十回忌が終わった後にひとり仏壇の前で思った。
3
村をずっと前に出ていったきり帰らないかれのケータイがもう通じない。
どうやらソフトバンクだと圏外らしいということを甲子園中継のラジオを縁側で聴いていた隣のオバマさんから聞いた。私はドコモだったから圏外じゃなかった。なんでオバマさんはソフトバンクだと圏外だと知っていたのかひっかかった。オバマさんのケータイはドコモのガラケーだ。オバマさんだけでなく、私の会った村の人のケータイはみんなドコモのガラケーで、私が来てから村の外から村へ訪れたひとは私以外に私は知らない。そういえば、ケータイはドコモにしとけ、と吹聴する声をいつか聞いた。
「どうして知っているんですか?」
「なにを?」
「ソフトバンクが圏外だってことを」
「ほんなん、ソフトバンクのケータイが圏外やったからに決まっとうやん」
「みんなドコモじゃないですか?」
と私は訊くと、
「ドコモちゃうアホがおったからやん、アホか」
と納屋にいるボナンザがいって、牛小屋で作業しているマラドーナさんのばか笑いが牛の鳴き声を押し退けて響き、私はアホ呼ばわりされて腹が立ったのだったけれども、腹を立てるほどに馴染んできている私に気がついて、それはなんだか撮った写真に私の後ろ姿が紛れ込んでいるのを見つけた気分になっている。
そこへ、
「小学校の先生でソフトバンクのひと、おってん!」
とヴィクトリアさんが台所の窓を開ける。そんなかれもいまはドコモらしい。こっちに赴任しての最初の土日は、一泊二日で街に行ってケータイのキャリアを変更するのに使わなければならなかったとかれはいった。
村にある学校は小学校がひとつだけで、民家がある場所から離れたところにあって、まわりは田んぼに囲まれている。全校生徒は十人いるかいないかがここ十年ぐらい続いていて今は八人で、中学校も同じ敷地にあったのだけれども十年程前に廃校になって、そこはいま、大部分は村人共有の農業機械や収穫の保管場所とかになっていて、一部は赴任してくる教師の職員寮として使われている。
赴任してくる教師は全員が村の出身じゃなかった。これまでもそうでこれからもそうだろう。場所が場所だけにかれらには僻地手当が与えられるらしいが、与えられたところで使うことがないから貯まる一方だと誰もがいう。職員は若い人が多く、でも若い人ばかりじゃない。家族を持っている人は例外なく単身赴任で盆、正月、ゴールデンウィーク、シルバーウィークと季節に一度のまとまった休みを使って家族の元へ帰っていく。若い家族を持たない人は最初こそ逃げるように街へ行ってしまうのだったけれども、次第にそれすらも億劫になり、通販を使って本だの酒だの取り寄せては、じぶんひとりで楽しめる趣味に没頭するようになる。
そのソフトバンクのケータイを持ってきていた先生は私とそう歳の変わらない若い先生で、たぶん二十四くらいで、ケータイをドコモに変えてからもソフバンとまわりから呼ばれていて、仕方がないから名前をソフバンにしていた。
「悪意があるよね」
とソフバンはいう。村の出身でなく、かつ二十代という共通点はけっこう強く互いの気を惹いたみたいで、たとえば私がマラドーナさんの牛を連れて村を歩いているときによくすれ違ったのだけど、そういうときには長く立ち止まって話をした。
「悪意ですか」
ソフバンは妙なプライドの高さを持つ男というか、きっと小さいころガキ大将にいじめられてたんだろうなぁと想像せずにはいられないようなしゃべり方をする男で、学費が高いことで有名なそこそこ名門の私立大学の出身だった。
「村のひとはぼくをバカにするんだ」
「そうですか?」
「ソフバンとか勝手にいうし。たぶんぼくが若いからだ」
「ぼくはソフバンさんより若いですが、べつにバカにされては……いないと思っていますが、まあそれも、愛情のようなもんじゃないっすか?」
こういう会話を数回したことがあって、職員寮のソフバンの部屋に呼ばれてふたりで酒を飲んでいるときは、
「ぼくは! 名前すら自分でつけれなかったんだぞ! みんなは自分で好きにつけてるのに!」
と怒鳴りだし、深夜だったからその声で起きてしまった先輩の教師に廊下に正座させられて、ちくしょうちくしょうと泣くのだから、もう帰っていいですかと訊いても返事はないし、そのまま黙って帰ってきた。
「この村から出してくれ!」
とソフバンの泣き叫ぶ声が聞こえた。それがすごく呆れたというか、悲しかったというか、だからそれ以来、私はソフバンになるべく関わりたくないなぁと思って、このごろはすれ違っても軽い会釈で終わる。
手持無沙汰な時間に私はスマホでSNSサイトにアクセスし、
「牛の世話からの一服なう」
とつぶやくと、
「いまどこ?」
と私の所属している軽音楽サークルの友だちがバイト中に返信をよこし、
「すげぇ田舎。パネェ!」
というとそれから返事はない。しばらくして今度はサークルの後輩から、
「今度のライブのリハするんですけど先輩これますか? って訊こうと思ったんですけど、無理っすよね」
ときて、
「うん」
と返せば、
「しかして生きてるんですね! よかったです!」
ときて、またしてもそれっきりだなぁと思いながらスマホをいじくっているとマラドーナさんが、
「なにをヌルヌルしよんねん! はたらけー。働かざる者食うべからずや!」
と怒鳴る。
私が牛を引き連れて歩くのはマラドーナさんが、
「牛もストレスたまるんやから、小屋やのうて、広いとこを走りまわしたらなあかん」
というからで、学校近くにマラドーナさんは土地を持っていて、まわりは他の家の畑か田んぼのなか、マラドーナさんだけが牛専用の庭みたいにしていて、
「最近はすっかりみんな、牛育てんようなったなぁ」
とぼやいていた。私は牛をそこまで連れていくと、あとは牛が逃げ出したりしないように牛を牛の庭に放しているあいだ見張っておく仕事をもらっていた。
「牛が逃げ出したらどうしたらいいんですか?」
「捕まえようとか思ったらあかんで、ぜったい」
「だめっすか」
「あかん。まぁ、無理やし。あぶないし」
というわけで牛が逃げ出したら私はマラドーナさんに知らせるだけでよくて、牛は庭から逃げ出すことはいままでに一度もなく、だから私はすることなどひとつもなかったのだった。
「そういえばあの優勝した牛は?」
「ああ、もう売ったよ」
「肉にしちゃうんですか?」
「ちゃうちゃう。種牛にすんねん。ちゃんとした牧場に移したっちゅーわけ」
私は肉になる牛のことを考える。かれらはむやみやたらに太らされたあげく精肉工場で解体されることが生まれる前から決まっていて、ただただ食べて寝るだけの毎日だ。『牛は柔らかに草を食み』といったところか。そして大方は異性と交わることを知らずに死んでゆく。そこらの草を食む牛のバックショットを見ながらそんなことをよく考えてしまうのだが、私も男ということで特に雄に感情移入して考えてしまう。牛の睾丸がゆれる。
かれらは私たちのいうところの美男子コンテストで優勝するぐらいのイケメンじゃないとセックスできない。いや、優勝してもダッチワイフを使って種を搾り取られるだけで、結局他の牛同様に雌を知らずに死んでいくのだっているということをなんかの本で読んだことがある。種牛になれるのって何頭に一頭なんだろうと思いながら、数億分の一の競争率の精子のことを連想する。ひとつの精子が種牛になれる確率は、牛が種牛になれるのが百頭に一頭だとすると数百億分の一だ。そう考えるとなんだか生きているってすばらしくなってくる。 そして種牛になると、自分のいるあたり一帯の牛小屋から生まれてくる子どもはすべて自分の子どもになる。集落の次の世代の子どもたちがみんな自分と同じ顔をしているとなると、さすがに私ならノイローゼになりそうだ。自分の豊かすぎる生命の輝きに目が眩み、逆に生きた心地がしないだろう。私はゆっさゆっさと体を緩慢に揺らしながら歩く牛の顔を見る。五頭連れてきたが、どれも同じ顔をしていた。これは遺伝子のせいだろうか? それとも人間には牛の顔の違いを認識できないだけか? そうならば牛にとって人間はみんな同じ顔をしているように見えているのか? 牛が鳴く。学校のチャイムがなる。しばらくすると八人の子どもが学校から出てくる。
「ただいま!」
と子どもたちは叫びながら通学路を通る。その両脇には田んぼや私のいる牛の庭。学校を出た直後からこの「ただいま!」の声は連呼され、村人たちはそれにたいして、
「おーう」
と作業を続けながら一応の返事はするようで、そこからなんらかの会話が続くことはなく、子どもたちはずっと「ただいま!」を連呼するばっかりで、村人も声が聞こえる度「おーう」と返事をする。そして視界のこっち側から現れた子どもたちが視界のあっち側に消えていくと知らない間に「ただいま!」「おーう」の声はなくなっている。横目で見ている(というか聞いていると)なかなか珍妙な光景で、私もしないといけないのかと思って「おーう」と子どもたちに返事をしてみると、子どもたちは声を出すのをやめ、立ち止まり、私の目をじっと見る。そして視線を私の目から離さずに後ろ向きでじりじり歩いたあと、ばっと走って黒や赤の各々のランドセルをカパカパ鳴らして逃げていった。その夜、ボナンザさんに、
「悪かったなぁ」
と謝られて、何がかれの責任だったのかよくわからなかったが、
「いいっすよ」
と答えると、
「明日からいけっから」
とボナンザさんがいう。そして、次の日から子どもたちに「おーう」と返事すると、子どもたちは私を無視して通り過ぎていくと、私はすごく嬉しかった。
秋が来ると私も米や野菜の収穫に駆り出されるようになり、朝から晩まで田んぼや畑で働く毎日で、時間はそれまでと変わることなくおだやかに過ぎていく。私の実家も兼業農家で、マラドーナさんやボナンザさんや他の村人の土地よりもずっと小さい。幼いころは何もかもがめずらしかったのだから、特に忙しい籾撒きや収穫時期はよく祖父母や両親、そして弟と一緒に畑や田んぼの仕事を手伝っていた気もするけれども、中学以降はほとんど手伝った記憶がない。手伝えと言われても部活が忙しいと逃げ、高校へ上がると勉強が忙しいと逃げ、大学へ入ってひとり暮らしを始めるとその時期に実家へ帰らないという手段をとった。
この時期はなにより風呂が嫌いで、さんざん働いて汗や泥にまみれたあと、風呂に入ろうとすると湯が汚れている。白く濁って浴槽の底が見えず、黒か茶色かの固形物がところどころに浮いている。それを見つけるたびに風呂桶で水面に浮かぶ固形物を取り除いてから私は浴槽につかったが、思春期のころには風呂が汚れているとシャワーだけですますようになった。当時はそれが自分の家だけのことだと思っていたのだけれども、この家でもそれは同じで、汚れた湯にそれを不潔に思う自分がうつり込むたび自分自身を嫌悪し、やはりシャワーだけですませた。
ヴィクトリアさんはそれに気がついたのか一番先に風呂に入ることをすすめてくれるようになった。しかし、透明な底の見える湯をいざ見ると、私の体から出たもの落ちたものがこの湯を濁してしまうことが怖い。シャワーでていねいに体を洗い、髪の毛を洗い、もう一度体を洗ってから湯船に入る。実家は去年の冬にオール電化になって、夜中に貯めた湯が次の日に使う湯になるのだと母は私にいった。風呂自動機能の操作パネルに『追いだき』のボタンがあったけれども、それはほんとうに追いだきをするのではなくて厳密にはたし湯なのだと母はいった。むかしから私の風呂は遅かったから、母ははやく風呂へ入れとうるさかった。弟は、
「母さんは風呂の湯の残りの量をずっと考えている、風呂の湯が一日のなかで一番重要な問題で、風呂の湯が母さんのすべてなんだ」
といって笑い、母は、
「うるさいよ。あんたらの将来のことだって考えてるのだから、家計も苦しくてあんたら、はやく働いてくれないかなぁって」
と大げさなため息をついていった。
「それもまたひとつの楽しみなのよ」
ともいった。
「それってどれ?」
と弟が訊くと母は、
「ぜーんぶ」
といって笑った。
村の収穫は村ぜんたいで行われる。村には若者が少なく、中年や老人、小学生が主で、青年と呼べるものは学校の教員だ。村の大人たちは日が昇ると同時に仕事をはじめ、学校が終わると小学生が加わり、休日はそこに教員が加わる。私やソフバンら若い男は若いという理由で、力仕事の大方を割り当てられ、村の人々はとても喜んだ。
最後の田んぼの収穫が終わるとバーベキューをする。収穫祭とみんなはいう。それは毎年のことだとマラドーナさんはいう。『収穫祭』と呼ぶようになったのはここ三年くらいのことだ。カラーコンテナのイスにベニヤ板のテーブル。コンクリートブロックの上に網をしいてその上にイモやらナスやら並べて焼く。牛やらシカやらイノシシの肉も焼く。そこには当然酒もある。みんな気持ちよく酔っぱらう。私も気持ちよく酔っぱらう。何人かが名前を着替える。マラドーナさんはボローニャさんになる。ソフバンはアオイという名前に着替えたがみんなソフバンと呼び続けるからソフバンだった。泣き上戸のソフバンが泣き出して、かれはたしかにいじめたくなるほどかわいかった。次の日にボローニャさんの小屋の牛が一匹減っていた。名前をつけていなかった。つけていてもよかったかもしれないと思ったが、ボローニャさんは、
「それは素人のやることだ」
といった。
「温暖化ってやつか」
ボナンザさんは窓の外を見る。私は、
「そうかもしれませんねぇ」
と口を合わせると、
「ようわからんけどな」
とボナンザさんはつぶやく。
雪の積もる年末の村には藁を編む大人たちの姿がたくさんある。そこに中高生が村へ帰ってくる。かれらは家の手伝いをすることなく、大人たちもかれらに手伝いを求めなかった。今年の雪はすくないとみんな口々にいった。
子どもたちは小学生から高校生までで二○人ぐらいいて、毎日朝から晩まで缶蹴りをして大方楽しく遊んでいる。オニになるのはいつも中学生で、みんないっせいに缶に向かって走り出すから一度オニになるとその日はずっとオニだった。夕方になるオニは半ベソをかきだす。それでも子どもたちはいっせいに缶に走り出しては缶を蹴る。次々に蹴る。最後は茂みのなかに蹴り込む。そして蜘蛛の子のように散っていく。そして次の日になるとまた新しいオニを決め、同じことを繰り返した。昨日オニで泣いていた子は、次の日になると笑顔で走る。かれらは缶を蹴るのが楽しい。
中学まで村の子はみんな同じ学校へ通い、高校になるとそれぞれにわかれるということになる。わかれるといっても選択肢がたくさんあるわけでなく、みんな公立の高校に通うのだったから、せいぜい選べてみっつよっつで、普通科高校ならほぼ一択だ。だから通う高校もほとんどみんな同じだということが往々にして起こるのだが、一学年に一人ぐらいの子どもしかいない村だから、村出身の同級生はいない。クラスの数も中学のときの倍以上になる。中学のときは村以外の子どもは村より少し大きい町などの出身者ばかりだったけれども、高校になるとそれよりも大きい町の子どもも集まる。かれらが一番多い。町の子は村の子を「村の」と呼ぶ。それはいじめではなく、単に村の子の特徴としてつけられたあだ名以上でも以下でもなく、みんなのなかに自然に溶け込める。しかしことば使いや、たとえば名前のことについての喧嘩ともいえないちょっとした認識の不一致が起こると、村やもんな、ということばが会話の節々に適宜挿入された。子どもたちは高校を出るとより大きな街へ出た。男は三十を過ぎたころ妻と子どもを連れて戻ってくることがある。女は戻ってこない。
「都会に行ってみたい、だから都会に行く、という気持ちはあながち嘘じゃないのだけど、みんなそういうけれども、ほんとうはみんなが都会に行っているから、そうしなくちゃならない気がしているだけかもしれないのかなぁって」
ボナンザさんとヴィクトリアさんの大学生のひとり息子もまた帰ってくる。
私はなんとなく浅黒く体格のいい青年だと思っていたけれども、かれは身長こそ私と同じくらいだという予想は当たっていたが、意外にもひょろりとした色白の青年だった。眼鏡をかけていて、ヴィクトリアさんは、
「インテリに見えるから村ではそれを外しておきなさい」
という。かれは目が悪くなかった。ヒロシといった。私はヒロシに部屋を借りていることと、秋服と冬服を借りていることの礼をいう。かれは、
「それは母から聞いているから気にしなくてもいいです」
と微笑む。
ヒロシは村ではじめての大学生で、東京の大学で文学部に所属している。村ではボナンザさんのところの息子はたいそう賢いらしいという噂は何度か聞いたことがあった。会話の続け方がわからなくて、噂を何度か聞いたことありますよ、といえば、あいまいな顔をしてなにもいわなかった。
「村に図書館をつくりたいなぁって」
かれは夢があるとすればそれが夢だという。『つくりたい』が村のイントネーションを引きずっている。かれの部屋にも、この家にも活字が一冊もない。かれは村にいた小学生の頃までは本なんて教科書以外に読んだことがない。
「お金かかるね」
と私はいうと、ヒロシはえっと驚いて、それはそんなことを一度も考えたことなどないといった表情で、それから、
「そうですね」
といい、遅れて吹き出すように笑うから、私もそれにつられて笑った。外は雪がしんしんと降っている。私は少し考えて、
「つくろうか」
という。
「お金、ありませんよ。本を買うお金すら」
私はバックパックのなかからノートを三冊とりだして、ヒロシとともに勝手口から外へ出て、その向かいにあるもう使っていないという裏座敷のがたぴしの戸を引いたら、埃がふわりと舞って雪に混ざる。
「ここを図書館にしたらいいんじゃない?」
ヒロシはひさびさに裏座敷に入ったといった。むかし、まだかれが小学生で祖父母が生きていたころ、かれと父と母はここで寝ていて、いま居間に置いてあるソファはここにあったもので、それを出したのは中学二年生のときだった。暗闇のなかで電燈のスイッチを探る。電気はちゃんとついた。かれは懐かしい。豆電球の光を受けて埃がしずかに踊っていた。日に焼けた畳が六畳と十畳の二間あって、玄関手前の六畳間の奥には湿気でしわしわになったダンボールがうずだかく詰まれている。十畳間にはなにもなくて、西側はタンスが置いてあったのか四角い痕が畳に残っていて、部屋の真ん中にむかって少しへこんでいる。隙間風が冷たい。かれはそれもまた懐かしい。私は床脇に手に持っていた三冊のノートを立てかける。ヒロシはそれを手に取ってパラパラめくり、
「いいですね、やっぱり」
と呟く。息が白かった。
居間は筆ペンでたくさん名前の書かれた広告が散乱している大晦日で、ボナンザさんとヴィクトリアさんが炬燵に入っていて、テレビは紅白歌合戦で、
「来年の名前を考えとうねん」
とひび割れた指で蜜柑を剥き、皮を広告で作った小さなくずかごのなかに入れた。
「今年一年無事に過ごせておおきになーっちゅう意味を込めてここで名前を脱ぐんや」
というとボナンザさんはてらてら白い広告の裏に筆をさらさら走らせ、私の視線が筆を追っていることに気がつくと恥ずかしいと広告を隠したとたん、
「決めたかー?」
とメイリンさんの声が壁を破ってやってきて、
「まだじゃー」
と返し、ヴィクトリアさんは私に白いお札を一枚渡して、
「ここに古い名前な」
という。古い名前は年が明けると同時に焚きあげる。今年は白組が勝った。ボナンザさんは炬燵から出て、ウインドブレイカーとマフラー、ニット帽と厚着をし、勝手口で背中を丸めて靴を履きながら、
「お前らも、はやく」
といって、ドアを開ける。冷気が流れ込んでくる。ボナンザさんはすーすーと口の隙間から息を吐く音を鳴らしながら小走りで出ていく。続いてヴィクトリアさんも出ていく。私とヒロシは上着とマフラーを部屋にとりに行く。
雪はちらちら降っていた。ボナンザさん夫婦以外にもすでに五、六人ほど外にいて、たき火に背を向け四角く囲み、延びたり縮んだりしながら時々さむいさむいと相変わらずの大声で叫ぶ。みんな赤い耳だった。少し離れてムラがいる。黙っている。
子どもたちも出てくる。みんな厚着をしている。ダウンの袖口からパジャマがはみ出している子どもがあくびをする。眉毛のほとんどない丸坊主の中学生が不機嫌そうな表情を崩さない。
「なんだかあぁいった子を見ると、たとえばあぁいった子とすれ違うとき、殴られるんじゃないかって思うんだよね、いまでも」
と私はつぶやくとヒロシが、
「わかります、それ。むかし学校の廊下でヤンキーっぽい子が向こうから来るときに同じこと考えてました、いつも」
「いつも?」
「はい。どうやって逃げようかを同時に考えていましたね」
「どうすんの?」
「相手が来るなって思ったら、そのまま真っ直ぐダッシュです。相手の横をうまくすり抜けると、相手はぼくを追いかけるためにはいったん振り返らなくちゃならなくて、そのときのタイムロスでぼくは逃げきれるはずなんです」
「足払いされたら?」
「そのときはそのときです」
「だめじゃん」
年が明ける。一斉に古い名前の書いたお札をたき火に放り込む。ヒロシのお札は風に煽られヒロシの足下まで返ってき、拾ってもう一度投げると踊る火の中に消えていった。ボナンザさんはフレネルさんになる。ヴィクトリアさんはマーガレットになる。ヒロシはコウジになる。私はヒロシになる。
ムラが初語り始める。
その日の真夜中、女の泣き叫ぶ声に起こされ、なんだと思って広場にでると、若い夫婦の派手な喧嘩だった。私が一番はやくに駆けつけたようで、少し遅れて他のものも眠気眼を擦りながら広場にぞろぞろと出てくる。わめく女の夫は女をなだめようといろんなことばを手当たり次第に投げかけていたがいっこうに落ち着かず、まるでたちの悪い子どもで、村人が全員そろうとぴたりと泣きやんで、広場はきまりの悪い静けさに包まれる。そして女は夫の手をふりほどいて、ゆっくりと口を開く。が、このとき私はこの女が男の呪いの名前を口にするつもりだと直感し、とっさにアーッ! アーッ! と叫びながら女のほうへ走っていき、発語よりもさきに女の口を押さえた。どうにか間に合った。女は激しく暴れ、口を押さえる私の手に噛みつき、傷を残した。
フレネルさんは眉間に皺をよせ、お前、いいのか、その名前、と耳元でささやき、このヒロシはほんとうのヒロシじゃないからセーフですよ、たぶん、と答えたらお前には呆れたが、まぁええんちゃうかと私の背中をぽんと叩いた。
「この話の結末、わかりますか?」
とコウジがいう。
「女が村人みんなに両手両足を縛られ、猿ぐつわをはめられ、家に監禁されるんだ」
喧嘩は男の浮気が原因だった。元々男は子どもが欲しかった。しかし、一緒になって五年経っても子どもはできなかった。女は子どもがいなくてもかまわないという。男と暮らしさえできればいいという。しかし、男はよそに女をつくり、その女が妊娠したら妻とわかれるつもりだった。しかし、女は許さなかった。
「それから?」
この男に、考えうる限り一番苦しい死を与えたかった。名前の呪いは
「その人間をその人間として縛り付けることにある。男はそれからずっと監禁した女のそばにいた。女は飲まず食わずで皮がみるみる干からび、たれ流した糞尿は小蠅を引き寄せ、黒く長かった髪は真っ白になった」
それから一週間後に起こった日食で、男も女も跡形もなく消えてしまった。誰も彼らがいたことを思い出せなかった。村人たちは海まで探しにいった。
「まったく、めちゃくちゃな話だ」
「いいムラになれますよ」
「ならないよ」
「冗談ですよ」
メイリンさんだったアキナさんは、むかしはこんな前の名前をたきあげるなんてことはなかったという。じゃあいつからですか、と訊けばアキナさんは知らない。彼女の生まれるずっと前から年明けとともに名前を焼く習慣はあって、けれどもそのはるかむかしの村で生きたひとたちも知らなかった。村のある文脈で体を通り過ぎる名前が通り過ぎたままなのが悲しいひとがいた。ひとりだけいた。そのひとはいった。海がみたい。海はとても広い。海のなかでは一○○○年前に死んだ魚が生きて泳いでいる。私の実家は海沿いの町だった。ここは山ばっかりだ。私の故郷では不良はだいたい漁師の子どもで、農家の子どもは基本的に温厚だった。そのことを思い出して、
「ここは漁師なんていないし、漁師の子どもなんているはずないのに、不良がいるんだね」
というと、コウジは一瞬ぽかんとなったあと、
「なんのはなしかわからなかったですよ」
といい、
「なんのはなしかいまはわかってるの?」
と訊けば、
「わかんないです」
というから、
「不良は漁師の子どもと相場が決まっている」
といったら、
「そんなはなし初めて聞きました」
という。
「こんなはなし、はじめてしたよ」
たき火に手をかざしながら、その揺らめきのなかで火が踊るのを見るのが楽しい幼かった私を大人の私が見ていると、幼い私はいなくてコウジだった。どうして幼くみえたのか。コウジは私の弟と同い年だ。小学生のとき、雨が降ったら母の車を図書館で待つ私と弟はいっしょに本を読んで過ごす。火星にいきものがいるかもしれないと本にあった。弟は学校の国語の時間に宇宙人を本でみた。宇宙人はスペースシャトルで文明のない地球に来て、文明を置いて帰っていく。それは弟にとって火星人かもしれなかったのでかれは、
「火星になにがいるの?」
と私に訊いてきて、
「岩石のなかに小さくいるよ」
と親指と人差し指をすごくくっつけるジェスチャーをすると、弟は火星人もいなくて火星のスペースシャトルもないのが悲しかった。火星の次のページには並行宇宙について書いてあった。むずかしくて、母が来るまでに読めなかった。読むのに三年かかった。中学生になっていた。もっとも近い私でない私は10の10の28乗メートル先にいると書いてあり、私たちの世界と同じことが起こっている半径100光年の空間が10の10の118乗乗メートル先にあると書いてあった。コウジは指数を読めなかったから、
「どれだけ?」
と訊くから私は困って、
「ゼロをひたすら地面や海に書いていって、それで地球をぐるぐる巻きにしてもまだたりない、全然足りない」
と答えると、
「それは遠いね。大きいね」
とコウジはいった。私は数字はことばだという手ごたえを感じた。はじめてのことだった。そうだったなぁと思った。ずいぶん遠くまできてしまった。帰れるかなと思った。帰れない気がした。急に怖くなった。帰るには遠くに来すぎてしまった。
「高校のとき、図書館の澱みたいなやつっていわれてたんです」
となりのコウジが白い息を吐きながらいった。私はほんとうに10の10の118乗メートル離れた並行宇宙に迷い込んでしまったのかもしれなかった。
「中学から本を読むのが楽しくなって、高校のころにはバカみたいな話ですけど、この世にある本をすべて読みたいって本気で思っていたんです」タツタじいさんはいう。本を読めば良くも悪くも時間がとまる。しかし本を閉じ、顔を上げたとき時計の針は進み、日は沈み、あるいは昇っている。本の世界にいる間に、お前は世界に置き去りにされたのだ。忘れるなよ、記述された過去の重みで沈んでいく澱となってはならないのだから。「高校の三年間かけても全部あるうちの一割くらいしか読めなくって、いや、一割も読めなくって、時間がほしいなってなんだか思ったんです」
「なんでもそうだよ」と私の口はいっていた。「すべての理想は無限の時間と無限の広がりの上に成り立つんだよ」
「なんかすごいですね」
「自然科学のはなし」
「すごいですね。ぼく、数式のおもしろさが、いままでわからなかったんですよ」
「あれは未来を記述することばなんだよ」
「好きなんですね」
「むかしはね」
すべてのものは無限の時間をかければ位相空間のすべての点を通りすぎる。いま私が存在しているということは、私という原子配列、電子状態の存在可能性を保証していることに等しい。私が物理的に存在できるのだから、私と同じ原子配列や電子状態を持つものが複数あってもおかしくない。もし、宇宙が無限に広いのだったら。揺れる火に奪われた意識のあった空白のぼんやりとした空間のなかをたゆたう心地に私はあった。
「むかし、宇宙人が地球に来るはなし、ありませんでした?」
「そんなの、ありすぎるだろ」
「あれです、小学校の教科書で、です」
「あったね」
「あれ好きなんです」
「わかる」
「物語は、ことばは未来からやってきて、ひとの口を通り抜けて過去に積もっていくんです。そんな気がするんです」
コウジは続ける。
「語られた未来は過去なんです。もうご存知だと思いますが、この村には過去しかないんです。語る未来がなくなってしまうと、語られた過去が語られます。でもかつて自分の発したことばでさえ、一字一句間違わずに発語しなおすことはできないから、すでにある過去は偽りの過去になってもう一度村にやってくる。そして過去と、起こらなかった過去がこの村に雪のように降り積もっていくんです」
フレネルさんはコウジの隣に立った。
「お前がもしもほんとうにムラの話すことをウソだと思っとんやったら、お前はだからむかし『図書館の澱』とかなんとか呼ばれたんやと思うで」
コウジは少し俯いたように見えた。
「なぁヒロシ、わしはな、むかしムラに語られることが、たぶんこいつもそうやと思うねんけど、それがごっつい怖かってん。でもな、いまはそうとちゃう。いまのカカさんのマラドーナさんやったときに、あのおっさんが牛の品評会を優勝できたんがうれしかったんやから。ほんまにな。ムラはそのことを今年語るやろうな。そしたらカカさんはまた牛の品評会で優勝するかもしれんやん。そしたらまたうれしいやん、カカさんも、わしも、みんな」
私はいう。
「同じことのくりかえしでも?」
「それはちゃうで。歳とった人間が集まると知らん過去が増えすぎるんやけども、それがあっから先がある。若いもんには語る過去が、語られる過去がなすぎっから、過去にとらわれんねん。すぐぜんぶ語られてしまう不安があんねんな。なぁ、カカさん!」
と叫ぶと、
「せや!」
とカカさんは酒で顔が赤い。私とコウジに紙コップを渡し、酒をつぐ。
「コウジは十九ですよ」
「知らんがな」
私たちは酒をちびちび飲む。たき火が弱くなると、
「寒いなぁ」
とみんな口々にいって、そこらをふらふら歩きまわって寒さをごまかす。
「ムラにしゃべられてしまう程度やあかん、もっと過去を集めなあかんで」
「よくわかりません」
「結局は過去のないやつに未来はない、っつーこった!」
フレネルさんは私の背を二回叩き、私はむせてみんな笑う。ムラも笑った。私と目が合う。ソフバンはまだソフバンだった。名前をかえなきゃいけないんでしょ? とかれはいう。気にすんな、こんなん形だけのやつやから、と村のひとはみんなかれにいった。雪がやんでいた。
「そういや、図書館、なんでつくりたいの?」
とコウジに訊くと、
「考えたこともなかったです」
といって酒をなめた。
「いいね、それ」
「ヒロシさんってけっこう適当なひとなんですね」
「適当なんだよ」
「いいですね」
スマホを見るとみんな、
「あけましておめでとう!」
といっていた。
庇から雪解け水が滴る。
翌朝、コウジは荷物をまとめると昼過ぎには街へ帰るといった。フレネルさんとマーガレットさんは正月ぐらいゆっくりしていけばいいのにと、多忙な息子を心配するというより、はやくに出て行ってしまうことが不満らしい顔をした。コウジの「街へ帰る」ということばに違和感がなかった。
私が駅まで送っていった。フレネルさんの軽トラを借りる。コウジが引きずるキャリーバッグが踏み固められた黒い雪の上を転がる。荷台に乗せる。しかし私はフレネルさんほどこの道を走り慣れていない。駅まで一時間半かかった。車を降りる。空を仰ぎ見る。10の10の28乗メートル先の薄く青い空のずっと奥の漆黒の彼方から私の声が降ってくる。
その無人駅にはほんとうにひとがいなかった。改札らしきものはない。寒々とした晴天の冬の午後二時五分、駅の時計の針は私の腕時計と同じ時間を示しているが、秒針は腕時計のほうが十秒ほど遅れている。どっちがあっているのかわからない。両方ともあってないかもしれない。電車が来るまで四○分ある。
私は、
「ごめん」
と両手を合わせ、コウジは、
「いえいえ、急いでないんで、すみません」
となぜかあやまる。雪が昼の陽をうけて溶けていた。屋根の影にぴったり雪が残っている。
私たちはだまって電車を待っていた。静かだった。心地よい静かさだった。
電車の近づく音が遠くから響いて、
「ヒロシさんはいつここを出るん?」
とコウジはいったあと恥ずかしそうに、
「ですか?」
を付け加え、私はふきだして、
「いいよ、タメで」
といってからとけた雪の上にぶちまけた笑いが静まると、
「うん。もうすぐ。たぶん」
電車がやってきて、とまる。コウジはキャリーバッグの取っ手をひっこめ持ち上げるとなかへ入る。私に頭を下げる。そんなのいいよ、と私はいう。すみませんとコウジはまた照れくさそうにあやまる。
「本、買えるくらいは稼げよ」
「ヒロシさん、ちゃんと村を出なくちゃ、ですよ」
「せやな」
「また適当なことを」
「手持ちのノートがなくなったらいくよ」
「あと何冊?」
「知らない」
ドアががこんと音をたてたあと、ゆっくりと息を吐くように閉まる。鉄の軋る音が甲高く響く。発進した二両編成の電車は徐々に速度をあげ、視界から消えていく。
(了)
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。