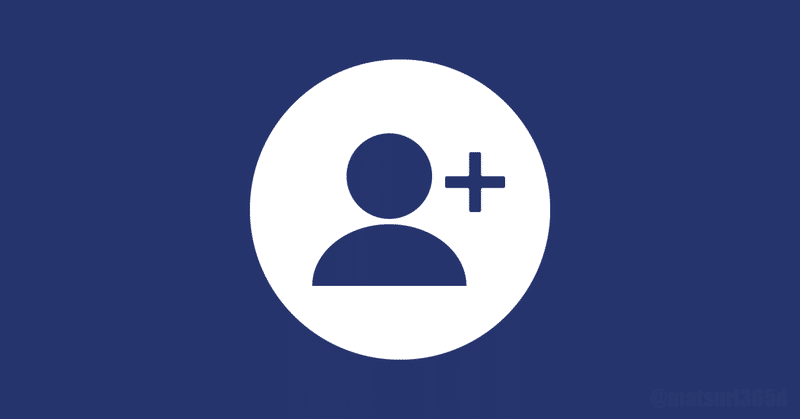
アートボットとフェアユース 美術と著作権について知っておきたいこと(4)
アートボットとは何か
これまで美術品の画像利用に関わる著作権の話をずっとしてきたが、今回は実際にネット上でどのような画像利用が行われているかについて書いてみようと思う。
Twitterアートボット界隈、というものがあるのかどうかは知らないが、Twitterにはアートについて定期的につぶやくボットアカウントが多数存在する。私が運営している日本美術史botもその中の一つだ。
bot(ボット)とは、プログラムによって動作するアカウントのことだ。あらかじめ設定されたツイートを一定の条件で、たいていの場合、1時間に1回など定期的につぶやくことが多い。そしてアートボットはその中でも美術品の画像を自動的につぶやくアカウントを指し、作品情報と画像だけのものから、画像に解説が付されたりする丁寧なものまでさまざまある。
ボットと聞くと一般的には業者がスパムメールを送りつけてきたり、政治的な主張を拡散させようとしたりする怪しい存在を想像するかもしれない。だが、なかには有益な情報を提供するボットもある。Twitterがそうした「良いボット」の存在を認め、好意的に扱い始めたのはごく最近のことだ。
Twitterでは2022年にそうしたアカウントがボットであると一目でわかるようなラベルが設定可能になった。そして、制作者のアカウントとも紐づけられるようになり、ボットが誰によって運営されているのかも明示できるようになった。悪質なボットは自らの素性を明かさないまま人々に近づこうとするが、良いbotはこうした機能を積極的に活用して素性を明かすことで人々の信頼を得ようとするはずだと考えたわけだ。
Twitterは仕様の改悪ばかりしているとはよく言われることだが(実際そうであることは限りなく多いが)、ボットについてのこれらの仕様に関しては素晴らしいと思う。ユーザー同士の情報交換や信頼の構築を手助けするシステムデザインが私は好きだ。
日本のアートボット
Twitterに対して良いボットを認知するように働きかけたのはアンドレイ・タラシュク氏というロシア出身で現在アメリカ在住のアーティスト兼ボット開発者だった。彼は、すでに亡くなっているアーティストの作品や、美術館のコレクションをつぶやくアートボットを500以上運営している。
Twitterに良いbotの代表例の一つとして扱われているアートボットであるが、それらのツイートを分析すれば、ネット上で美術品の画像がどのように二次利用されているのか、その実態の一端をみることができるだろう。
なお今回取り上げるのは、日本語で運営されているアートボットに絞ることにする。著作権法は国ごとに異なっているため、対象を日本で運営されているアートボットに限定することで、日本の著作権法が二次利用のありようをどのように規定しているかわかるはずだ。
たとえば先ほどのタラシュク氏が作ったアートボットは、そのほとんどがパブリックドメインとなっている作品の画像を扱っているが、なかにはまだ著作権が有効なものも含まれている。だが、アメリカの著作権法ではフェアユースという概念があり、著作者にとって不利益にならないような「公正な利用」であれば許諾がなくてもいいことになっている。アートボットのように非営利で、作品の市場価値を損なったり競合したりしないような利用であれば適法である可能性が高い。
フェアユースという考え方は、日本の著作権法では採用されていない。なので日本人がアートボットを運営するのであれば、作品の著作権が有効である時点で二次利用することは原則として不可能になってしまうのだ(引用という体裁が成り立つならまた別だが)。
さて、日本語で運営されているアートボットは、数えたところ29あった。活動歴がほとんどなさそうなものや作家の名言集、あるあるネタがメインのボットなどは除外した。継続的に毎年いくつかのアートボットが誕生しているので、直近にできたばかりのものは見落としているかもしれない。他にあったら教えてください。
ジャンル別に内訳をみると、西洋美術を扱うボットが16と圧倒的に多く、日本美術が5つと少ない。両方扱っているボットは4つあった。画像を利用せず美術史にまつわる書籍から抜粋したり、用語解説をするアカウントは3つほどあった。

アートボットには大別して、定番の名作を集めた総合型アートボットと、作品の主題、ある国や地域などを絞ってキュレーションするテーマ型アートボットの2つがある。
数の上でも、フォロワー数で上位を占めているのもテーマ型アートボットが多数派だ。なお、テーマ型の中でもアーティストの名を冠したボットがほとんどなかったのは意外だった。
ボットを作成する側にとっても、自身が好きな作品の傾向やジャンル、国や地域といった具体的な対象があったほうがアートボットを作る動機になりやすいと思われる。ただアートの魅力を伝えたいといった漠然とした考えだと、取り上げるべき対象が広がりすぎて収拾がつかなくなってしまう。総合型と違ってテーマ型のほうが他のボットと競合しないのも利点だろう。
とくに耽美、退廃、幻想、ゴシック趣味、象徴主義といったように、総じてデカダンス的な趣味によってキュレーションするアートボットの人気が高い。「耽美なる絵画とモノ」(21.1万)と「薄明かりの絵画」(11.7万)がもっともフォロワー数が多く、同様の趣向として「余白の詩学」や「甘美な少女の絵画bot」といったボットがフォロワー数上位に続いている。
日本美術には人気がない?
そしてここからが本題だが、リストを一瞥して明らかなように、日本美術系よりも西洋美術系のアートボットの数が3倍以上も多い。これはなぜだろうか。
第1に日本美術より西洋美術のほうが人気があるという身も蓋もない事実があるようだ。
日本美術において総合型は私の運営する「日本美術史bot」のひとつしかない。テーマ型は仏像に特化したボットが2つあり、西洋美術も扱う「余白の詩学」、作家名を冠したボット、国立館のコレクションデータベースから画像をツイートするボットが1つずつで、合計5つ。これが日本美術をメインに扱ったアートボットのすべてであり、西洋美術の総合型アートボットが5、テーマ型が11もあるのに比べると層の厚さの違いを感じざるを得ない。
第2に、日本より欧米のほうが作品画像が比較的容易に手に入ることが参入のしやすさにつながっていると考えられる。これは欧米の美術館のほうがデータのオープン化が整備されているからで、日本では後を追うような形で近年ようやく整備されてきた感がある(ただ前回の記事で取り上げたように、著作権の処理をめぐってはいまだに混乱がある)。
これは私個人の経験で語るしかないのだが、日本美術の作品画像を集めようとするとネットでは入手しにくい作品がかなり多いのが実情だ。美術史の通史において言及されることの多い作品であってもサムネイルサイズの小さな画像しか見つからなかったり、色味がまったく異なる品質の低い画像しかなかったりする。そうした環境が日本美術を扱うボットが少ない理由にもなっているのではないかと思う。
第3に海外の作品のほうが著作権の制約を受けずらいかもしれない。少なくとも日本美術を扱うよりはリスクがあまりなさそうにみえる。
海外の権利者が、日本で、しかも非営利で画像を利用しているような事例をわざわざみつけてきて訴えるようなことは、相当悪質な利用でもない限りは労力の無駄でしかなく、あまり現実的ではないだろう。著作権の侵害は権利者が訴えることで初めて罪に問われるわけだから、訴えられる心配がなければ著作権法を詳しく調べてリスクを吟味する労力を割かずに済む。それが良いことなのか悪いことなのかは別として、それだけボット運営のハードルは下がるにはちがいない。
日本の著作権法がフェアユース規定を採用していないことは先ほど触れた。そのために日本美術を扱うアートボットが著作物の利用に際してなにかしらの対処を余儀なくされてしまう。そして、アートボットが著作権という制約にどのように対処するかは運営者によって方針は異なっている(実際には著作権に無頓着なボットもあるのだが、それは今回は置いておこう)。
絵画作品よりも立体作品のほうが著作権法上の扱いが難しいことはこれまでの記事で指摘してきた。立体作品の場合、その画像が撮影した写真家の作品として扱われる可能性があるため、原作品と写真作品両方の著作権をクリアしなければ二次利用ができない。絵画作品だけを扱うなら保護期間が過ぎているかどうかだけを気にしていればいいのでそれほど難しくはないが、立体作品を扱おうとするならそれなりの知識をもって対処法を考える必要がある。
引用の要件
対処法としては引用の体裁をとるのが一般的だ。
著作物を利用するには原則として権利者の許諾が必要になるが、著作権法では一定の例外を設けて著作権を制限している。引用は、著作権者の許諾の必要のない利用方法として認められている例外のひとつとして、著作権法32条1項において「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と規定されている。
条文では、①公表された著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③目的上正当な範囲であること、という3つが引用が成立する要件として示されている。これだけならシンプルに思えるが、実際の判例ではさまざまな基準が混在しており、そうした実情を踏まえて成立要件を要約することは難しい。
引用の要件として長らく有力視されてきたのは、1985年のパロディ・モンタージュ写真事件において最高裁が示した明瞭区別性と主従関係を考慮する二要件説だ。明瞭区分性とは「引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること」であり、主従関係とは「引用して利用する側の著作物が主、引用されて利用される側が従という関係があること」である。
仮にこの二要件説に従うならば、立体作品の画像をアートボットで引用する場合、①ツイート本文の内容が十分な量であること(これは実務上、分量の問題になりやすい傾向にあるためだが、量の問題ではなく批評など価値判断を伴う言及になっているかどうかを重視する判例もある)、②画像が独立して鑑賞に堪えないレベルにまで画質を落とすこと、つまりサムネイルサイズの画像だけを利用すること、③画像の権利者や出典を明記することが必要と思われる。
しかし、ここまでしたとしても、アートボットがそのコンテンツの性質上、たとえサムネイル画像であってもそれを示すこと自体が目的であると評価されれば主従関係は成立していないと判断されてしまう可能性はある。引用の体裁をとるアートボットであっても引用が成立しているかはわからず、権利者に著しい経済的な不利益を与えるわけではないので黙認されているのが現状だろう。
であれば、あくまでグレーゾーンでの行為ということで権利者の不利益にならないようにしながら波風を立てないように運営していくのが一番の解決策なのかもしれない。そう考えると、権利者や出典の明記は、黙認している権利者にとって逆に迷惑になる可能性も考えられるので、あえて明記すべきかどうかは微妙な問題だ。引用が成立すると思うなら出典の明記は必須であるし、それが疑わしいと思うならどうせ侵害するなら黙って侵害した方が見逃してもらいやすいと考えることもできる。
この二要件説は現行著作権法32条1項の要件とどのように対応しているのか明確ではないこと。主従関係の成立において考慮される要素がさまざまあり、引用著作物と被引用著作物との関係性を逸脱していることなど、批判が根強くある。
そこで最近では、二要件説には直接言及せずに条文から引用の要件を再構成する判例もみられるようになっている。
2010年の美術鑑定書事件は、美術鑑定書に鑑定対象である絵画のカラーコピーを貼付する行為が著作権侵害に該当するか争われた。判決では二要件説を採用せず、現行法に基づく独自の解釈によって引用の成立を認めた。
しかしこの判例の場合、適法判断がケイスバイケースすぎて権利侵害であることの予測可能性が低くなりすぎてしまうといった批判や、そこで示された引用の成立要件の判断基準を論理化するとフェアユース規定に近い基準が導き出されるため、現行法を逸脱するのではないかという批判もある。逆に著作権法が権利者側にとって都合が良いものになりすぎてしまうバイアスを司法判断によって柔軟に対応して是正するべきであるという立場からは、そのことが積極的に評価される。
もしフェアユース規定に近い法解釈が成り立つのであれば、アートボットが引用によって画像を利用できる可能性も高くなると考えられるが、現時点でこの解釈を採用するにはまだ判例が積みあがっていないように思う。
https://innoventier.com/archives/2022/11/14321
日本版フェアユース規定があれば
私のボットでは写真としての著作権もクリアした画像だけを利用することで立体作品を扱っているが、そこまでして著作権がない画像の使用にこだわるアートボット運営者は他にいないようだ。現行法においてはこれが一番リスクが少ないのだが、この対処法を採用するには著作権について相当調べる必要がある。
そこまでしなければグレーゾーンで、もしかしたら訴えれられるかもなんて不安が常にちらついているようでは、日本美術を扱うアートボットの新規参入は今後も増えることはないだろう。だがもし美術鑑定書事件判決で示唆されたような日本版フェアユース規定の法整備がなされれば、こうした現状は改善するはずだ。
ここから先は
¥ 100
Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi
