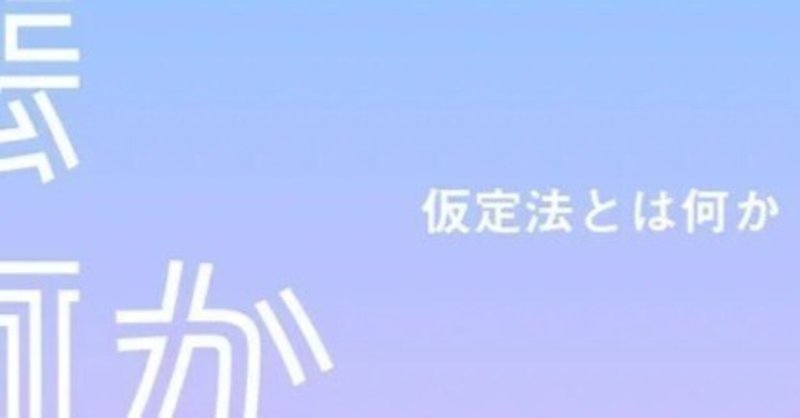
余白1:主張はするけど命題的でない文としての形容詞文
1. 主観を述べる文と命題は相容れない
1-4 では触れずにおいていた一群の文がありました。それは、形容詞を伴って何かを主張する文のことです。これらが、直説法の平叙文で述べられるときにも、命題と呼びうるかという論点についてはひとまずおいておくことにしていたので、1-5に入って行く前に、ここで取り扱いたいと思います。なお、仮定法の説明からは少し外れた内容になりますので、番外編(余白)としてコラム的に、全体の中に組み込むことにします。
論理学では、通例、形容詞を用いる判断文(主観的な事柄)については、命題としては考えないようにします。こうした立場は、野矢茂樹氏が2020年に書いた論理学の入門書でも取られています。野矢氏は、「マクドナルドのフィレオフィッシュはおいしい。」という文をもとに、次のように述べています。
フィレオフィッシュというのは、白身魚のフライをはさんだフィッシュバーガーで、おいしいという人もいれば、そうかあ? と首を傾げる人もいる食品かもしれません。「おいしい」というのが個人の感想にすぎないなら、真偽は言えないと考えた方がよさそうですが、客観的においしいとかまずいとか言い切れる場合もないわけではありませんから、絶対に真偽は言えないかどうかは微妙なところです。
このように述べた上で、野矢氏は、主観的な文を「微妙なケース」として排除して、命題を扱っていくという方針を取っています。(※1)結局のところ、フィレオフィッシュがおいしいかおいしくないかは、「人それぞれ」だということでしょう。このような方針は、論理学においてはとりあえず採用してしまって問題ないでしょう。しかし、私たちはここでどちらかといえば言語学をやっていて、1-4では言語について探究するなかで全てを命題的に還元しようとする愚について述べました。ですから、ここでは命題的に扱えないからといって形容詞の判断文を考察の対象から外すことはできません。
続いて、言語学のテクストを繙いてみます。『日本語の時制とアスペクト』(1989)における町田健氏の記述を見てみます。
「花子は美しい」という文は、発話者にとっては真であるが、別の話者にとっては偽であるかもしれない。ところが、「花子は走っている」という文は、それが発話者にとって真であれば、同じ世界に属する他のすべての発話者にとっても真である。
ここは状態動詞を形容詞と関連づけて述べている文の注釈にあたります。ここでは状態動詞と形容詞は共に、「話者の信念の領域内で真であると判断されている事象」(同上、65頁)を述べるものとされています。
真偽を厳密に命題におけるものとして捉えるならば、人によって真であったり偽であったりすることはありません。それゆえ、上の引用文中の例でいえば、「花子は走っている」について命題として真偽を問うことはできるものの、「花子は美しい」については、先のフィレオフィッシュと同様に、「人それぞれ」の価値観次第といったところがあります。ですので、「「花子は美しい」という文は、発話者にとっては真であるが、別の話者にとっては偽であるかもしれない」と言われるときの真と偽は、もはや命題的な観点から離れた別の意味で使われると解釈しなければなりません。
「マクドナルドのフィレオフィッシュはおいしい。」「花子は美しい。」というような文によって、話者は何を言わんとしているのでしょうか。もちろんそれは、「おいしい」「美しい」ということの主張をしている。では、そのような主観的な信念を主張することで、話者は何をしようとしているのでしょうか。命題的な価値とは別の価値が、そこにはあるはずです。
2. 言葉の脳内的使用と公共的使用
結論へ急ぐ前に、少しだけ寄り道をしましょう。今から述べることを読んでからの方がきっと深く理解できると思うからです。やや時事的な言及になりますが、とても身近な例を取り扱いたいと思います。
近頃の価値観における多様性を歓迎する傾向の中で、次のように言われるのを聞いたことがないでしょうか? 曰く、「自分の美しさは自分が決める」。これが私にはよくわからないのです。もちろん、その言いたい「気持ち」はわかります。いまはテレビだけでなく、どこに行ってもスクリーンと向かい合っているようなメディア環境になっています。電車に乗っていて「脱毛0円」「二重手術29800円」(!!)のようなバナー広告まみれのSNSフィードからやっと目を離し、次の停車駅を確認しようとドア上のモニターを見れば、今度は中村アンなんかがニカーッと整った白い歯を出して何某かの「美しさ」を顕示しており、そこから目を話したところでドアの隣にはミュゼプラチナムの広告があり、電車から降りればMEN'S TBCのローラと井上尚弥がドアップで……というような環境では常に「あなたには未だ何かしら美的にまだ足りていないところがある」というメッセージを送られ続けているに等しく、自分の身体に関する自尊心ないし自己肯定感などというものは損なわれるべくして損なわれるのだと思わざるをえません。
現代におけるそういった広告の類が向けてくる「暴力」などに対して、「自分の美しさは自分が決める」と言って抵抗する、という気持ちはわかります。あるいは、広告だけではなく、SNS上で湧いてくるヘイター達への捨て台詞として言うのもわかります。しかし、「自分の美しさは自分が決める」というような文は、あくまでその抵抗の効用的な(パフォーマティブな)側面からのみ評価されるべきであって、「自分の美しさは自分が決める」という決意がいつの間にか「自分の決めた美しさ(こそ)が美しさ(というもの)だ」という述定的な価値にすり替わっていて、それを勝手に「真である」と見なして、自尊心なり自己肯定感の担保にするというのは違うのではないか、と思うのです。
なぜかと言えば、そうした態度は、独善的になりがちだからです。「自分が決めた美しさ」というのは、そう考える人の頭の中にしかありません。独善的になった美というのは、もはや醜いことの方が多いのに、たとえそれを諫める人が現れても、「自分の決めた美しさこそが美しさだ」と信じる当人にとっては「知ったこっちゃない」で、単に独りよがりになってしまっているということはないでしょうか。
そもそもなぜ、ある人が「自分の美しさは私が決める」などという信念をいだくことになったのかと問えば、それが規範とされる「美しさ」に対するアンチテーゼとしてあったはずです。「自分は一般的に美しいとされる要素を持ってはいない。けれどもだからといって自分が美しくないとは言えない」そういう思いから「自分の美しさは私が決める」という抵抗を示したくなったはずなのです。「美しさ」は、初めは自分の外、言い換えれば、公共的な次元に見出されていたのです。しかし、抵抗しているうちに、いつのまにか「美しさ」(「美しい」とされるもの)を自分の頭の中にコピペして、そのコピーの中身を自分に都合のいいように勝手に編集してしまう人が中にはいます。「自分の決めた美しさが美しさだ」という抵抗を示しているうちに、意固地になって、ファイル名にこそ「美」とついているものの、ダブルクリックでその内実を覗けばハタからみれば「ただ醜い」というしかないようになってしまっても、ただ独り自分だけの「美」は疑わないような人がいます。もはやその人にかける言葉があるとすれば「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」と言うしかないという状況すら生まれることだってあります。
こうした独りよがりに陥らないためにはどうすればよいのでしょうか?
そのためには、価値を戦わせることが重要です。「美しさ」というのもまたひとつの価値で、価値を掲げる以上は、脳内に留めておくのではなく、他者とのあいだでその言語を使わなくてはなりません。戦わせるとは申しましたが、ここに勝ち負けはありません。先の例で言えば、メディア等が押し付けてくる規範的な「美しさ」を打倒することが、私の「美しさ」を主張することの目的なのではありません。他者とのあいだで言葉を使う以上、「美しさ」であれば、あなたの考える「美しさ」というのはその実践の中で磨かれていきます。そうして、やがてあなたは、規範とされるものもまたひとつの「美しさ」に過ぎないのだ、それと同じように私もまたひとつの「美しさ」を持つのだ、という気づきを得ることでしょう。「美しさ」はあなたの中で掴まれるのです。もちろんそれは、花に止まる蝶のように束の間のことかもしれない。けれどもそれは、生きている限り、折に触れて確実に掴まれるものなのです。
3. 命題的でなく論争的な価値を持つ
と、まぁ、だいぶ話が逸れたので戻します。「花子は美しい」というような形容詞の判断文をどう扱うべきかという話でした。ここまでに確認してきたことは、(1)主観的な文については真か偽かを問えない(命題として見做せない)と考える、(2)純粋に論理学をやっているわけではないので、非命題的だからといって形容詞文を排除することはできない、という2つの点です。
命題的に扱えないとした時点で、論理学的な価値は失っています。しかし、私たちはどちらかといえば言語学をやっています。言語の問題として考えたときに、主観的な判断文を述べることで話たちは何をしようとしているのか、そしてそれはどのような価値を持つのか、という観点からこの文章の残りを書いていきます。
ここで、例文を「花子は美しい」から、「小松菜奈は美しい」に変えます。「花子」は抽象的であまり実感がわきませんので、より身近な例として小松さんに登場してもらいます。
「小松菜奈は美しい」と誰かが言ったとして、その文が正しいかは小松菜奈さんに来てもらって、小松菜奈さんをつぶさに観察したところでわかりません(これは上で述べた(1)主観的な文については真か偽かを問えないということに関わっています)。検証の余地があるとすれば、「小松菜奈は美しい」と述べた当人がなぜそう思うのか、という当人の価値観が問題となるでしょう。「小松菜奈は美しい」と思わない人がこの主張を聞いたとすれば、「なぜ君は「小松菜奈は美しい」なんて思うの?」「え? じゃあ、君はぼる塾のはるかも良いと思うわけ?」などと尋ねるでしょう。このとき反論している人は、相手が何をもって「美しい」と言っているのかという、「美しい」という言葉の遣い方に対して尋ねているのです。
ここで何が始まっているかと言えば、ひとことで言えば論争です。話者は価値判断を含む文を述べるとき、「真」であることを述べようとしているのではなく——言葉遊びになるのを許してもらえば——、「信」であること(信じていること)を述べようとしているのです。
形容詞を用いた主観的な判断文が持っている価値とは、このような論争的な価値です。つまり、その文を元にしてあーだーこーだ言い合えるようになるのです。他者と対話できるようになるというのも文のひとつの価値なのです。これが本論考における形容詞文の位置づけとなります。
注釈
※1「おいしい」という例をどう考えるのかは意見が分かれるかもしれません。例えば、どんなに空腹になっても、木の皮や落ち葉を食べる人は滅多にいません。それは木の皮や落ち葉が「おいしい」とは言えない、という共通理解があるからで、その上では「おいしい」にも客観性がある、と主張できる気がしないでもありません。しかし、ここでよく考えてみれば、落ち葉は、「おいしい/おいしくない」の問題以前に、食用と見なされ得るのか、という問題があるように思います。なので、落ち葉のようなまず人が食べないとされるものについては、「おいしい」delicious かどうかでなく、「食べられる」edible かどうかの問題として扱われなければならないでしょう。
この文章全体への注
* 形容詞について扱っておきながら、「美しい」しか検討していないことがこの文章の欠点となっているかもしれません。もちろん、形容詞も色々で、「赤い」であれば、「美しい」と同様に扱えないところもあるでしょう。ここでは「美しい」を主観的表現を表す形容詞の代表として扱いました。
* これを推敲しているあいだ、主観的な叙述について、predicate of personal taste(個人的嗜好述語)として研究があることを知りました(『はじめての語用論』29頁)。しかし、今からそちらについてのサーベイをする余裕がないのと、本筋から外れてしまうことを考慮して、「仮定法とは何か」では取り扱いません。
(以上、13枚/合計102枚)
参考文献
田島正樹『読む哲学事典』(講談社現代新書、2006)・・・牽強付会の謗りを免れないかもしれないが、論争的価値についてのアイディアは、この本から着想を得ている。むろん著者の田島氏が用いている文脈は私のものとは異なっている。
野矢茂樹『まったくゼロからの論理学』(岩波書店、2020)
町田健『日本語の時制とアスペクト』(アルク、1989)
なお、参考文献としてはあげませんが、この文章の全体の論旨に影響を与えているのは、橋本治とニーチェです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
