
!T-37-基本情報技術者試験〈後編〉-
はじめに
今日、基本情報技術者試験の過去問を初めてやりました!
60点中の半分以下でした。なので、今回は、自分が間違えた問題について更に復習をしたいと思います。(前回のぶんもインデックスにあるので、ぜひ一緒に勉強しましょう!!)
問題
https://www.ipa.go.jp/news/2022/shiken/gmcbt80000007cfs-att/fe_kamoku_a_set_sample_qs.pdf
問45
サービスマネジメントのプロセス改善におけるベンチマーキングはどれか。
アITサービスのパフォーマンスを財務,顧客,内部プロセス,学習と成長の観点から測定し,戦略的な活動をサポートする。
イ業界内外の優れた業務方法(ベストプラクティス)と比較して,サービス品質及びパフォーマンスのレベルを評価する。
ウサービスのレベルで可用性,信頼性,パフォーマンスを測定し,顧客に報告する。
エ強み,弱み,機会,脅威の観点からITサービスマネジメントの現状を分析する。問46
ディスク障害時に,フルバックアップを取得してあるテープからディスクにデータを復元した後,フルバックアップ取得時以降の更新後コピーをログから反映させてデータベースを回復する方法はどれか。
アチェックポイントリスタート
イリブート
ウロールバック
エロールフォワード
問48
情報セキュリティ監査において,可用性を確認するチェック項目はどれか。
ア外部記憶媒体の無断持出しが禁止されていること
イ中断時間を定めたSLAの水準が保たれるように管理されていること
ウデータ入力時のエラーチェックが適切に行われていること
エデータベースが暗号化されていること
問49
テレワークで活用しているVDIに関する記述として,適切なものはどれか。
アPC環境を仮想化してサーバ上に置くことで,社外から端末の種類を選ばず自分のデスクトップPC環境として利用できるシステム
イインターネット上に仮想の専用線を設定し,特定の人だけが利用できる専用ネットワーク
ウ紙で保管されている資料を,ネットワークを介して遠隔地からでも参照可能な電子書類に変換・保存することができるツール
エ対面での会議開催が困難な場合に,ネットワークを介して対面と同じようなコミュニケーションができるツール
問51
国や地方公共団体などが,環境への配慮を積極的に行っていると評価されている製品・サービスを選んでいる。この取組を何というか。
アCSR
イエコマーク認定
ウ環境アセスメント
エグリーン購入
問52
コアコンピタンスの説明はどれか。
ア競合他社にはまねのできない自社ならではの卓越した能力
イ経営を行う上で法令や各種規制,社会的規範などを遵守する企業活動
ウ市場・技術・商品(サービス)の観点から設定した,事業の展開領域
エ組織活動の目的を達成するために行う,業務とシステムの全体最適化手法
問54
IoTの応用事例のうち,HEMSの説明はどれか。
ア工場内の機械に取り付けたセンサで振動,温度,音などを常時計測し,収集したデータを基に機械の劣化状態を分析して,適切なタイミングで部品を交換する。
イ自動車に取り付けたセンサで車両の状態,路面状況などのデータを計測し,ネットワークを介して保存し分析することによって,効率的な運転を支援する。
ウ情報通信技術や環境技術を駆使して,街灯などの公共設備や交通システムをはじめとする都市基盤のエネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。
エ太陽光発電装置などのエネルギー機器,家電機器,センサ類などを家庭内通信ネットワークに接続して,エネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。
問55
ロングテールの説明はどれか。
アWebコンテンツを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツに,統合的・体系的な管理,配信などの必要な処理を行うこと
イインターネットショッピングで,売上の全体に対して,あまり売れない商品群の売上合計が無視できない割合になっていること
ウ自分のWebサイトやブログに企業へのリンクを掲載し,他者がこれらのリンクを経由して商品を購入したときに,企業が紹介料を支払うこと
エメーカや卸売業者から商品を直接発送することによって,在庫リスクを負うことなく自分のWebサイトで商品が販売できること
問57
製品X及びYを生産するために2種類の原料A,Bが必要である。
製品1個の生産に必要となる原料の量と調達可能量は表に示すとおりである。製品XとYの1個当たりの販売利益が,
それぞれ100円,150円であるとき,最大利益は何円か。
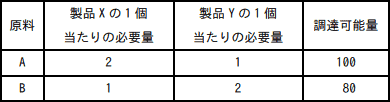
ア5,000
イ6,000
ウ7,000
エ8,000
問58
令和2年4月に30万円で購入したPCを3年後に1万円で売却するとき,
固定資産売却損は何万円か。
ここで,
耐用年数は4年,減価償却は定額法,
定額法の償却率は0.250,残存価額は0円とする。
ア6.0
イ6.5
ウ7.0
エ7.5
問59
売上高が100百万円のとき,変動費が60百万円,固定費が30百万円掛かる。変動費率,固定費は変わらないものとして,目標利益18百万円を達成するのに必要な売上高は何百万円か。
ア108
イ120
ウ156
エ180
解説&解答
問45
ベンチマーキングは、自社の製品・サービスなどを
定量的・定性的に測定し、
それを同じプロセスに関する業界内外の成功事例(ベストプラクティス)と比較することで、
自社の良い点や悪い点を評価する分析手法です。
分析によりベストプラクティスとの差異が明らかになった後は、
ベストプラクティスを参考にして目標や実行計画を設定することで業務改善を進めていきます。
ITサービスのパフォーマンスを財務,顧客,内部プロセス,学習と成長の観点から測定し,戦略的な活動をサポートする。
バランススコアカードの説明です。業界内外の優れた業務方法(ベストプラクティス)と比較して,サービス品質及びパフォーマンスのレベルを評価する。
正しい。ベンチマーキングの説明です。サービスのレベルで可用性,信頼性,パフォーマンスを測定し,顧客に報告する。
サービスレベル管理の説明です。強み,弱み,機会,脅威の観点からITサービスマネジメントの現状を分析する。
SWOT分析の説明です。
問46
ロールフォワードは、前進復帰と訳され、
データベースシステムに障害が起こったときに、
更新後ログを用いて今まで処理したトランザクションを再現し、
システム障害直前までデータベース情報を復帰させる処理です。
ディスクの媒体障害が発生した際には、新しいディスクに入れ替えた後にフルバックアップデータからデータを復元し、続いてバックアップ時点から障害発生時点までのトランザクションの内容をロールフォワード処理でデータベースに適用します。
チェックポイントリスタート
チェックポイントリスタートは、トランザクション障害やシステム障害から復帰するときに、直前のチェックポイント((データベース処理とディスク内容の同期ポイント)まで戻ってから再開する方法です。リブート
リブートは、システム障害などから回復するためにマシンを再起動することです。ロールバック
ロールバックは、トランザクション障害やシステム障害の発生でトランザクションが正常に終了しなかった場合に、更新前ログを用いてデータベースをトランザクション開始直前の状態に戻す処理です。ロールフォワード
正しい。ロールフォワードは、更新後ログを用いてコミット済のトランザクションを再現し、データベースを障害発生直前の状態に回復する作業です。
問48
可用性(Availability)は、情報セキュリティマネジメントで維持管理すべき要素の一つで、利用者が必要なときに必要なだけシステムを利用できる度合いを示します。
障害が発生しにくく、障害からの復旧時間が短いシステムであるほど可用性は高くなるので、MTBFや稼働率が可用性の評価指標となります。
可用性に機密性と完全性を加えた三つは、情報セキュリティマネジメントで維持管理すべき三要素として位置付けられています。
機密性(Confidentiality)許可された正規のユーザだけが情報にアクセスできる特性を示す。
JIS Q 27000では「認可されていない個人,エンティティ又はプロセスに対して,情報を使用させず,また,開示しない特性」と定義されている。
完全性(Integrity)情報が完全で、改ざん・破壊されていない特性を示す。
JIS Q 27000では「正確さ及び完全さの特性」と定義されている。これを踏まえて、選択肢の事例がどの特性を維持管理するための管理策であるかを考えます。
問49
VDI(Virtual Desktop Infrastructure,仮想デスクトップ基盤)は、
サーバ内にクライアントごとの仮想マシンを用意して仮想デスクトップ環境を構築する技術です。
利用者はネットワークを通じてVDIサーバ上の仮想デスクトップ環境に接続し、
クライアントPCにはVDIサーバからの操作結果画面のみが転送される仕組みになっています。
この仕組みにより、クライアントがインターネット上のサイトと直接的な通信を行わなくなるので、クライアントPCをインターネットから分離できます。もし、利用者の操作により不正なマルウェアをダウンロードしてしまったとしても、それが保存されるのはVDIサーバ上の仮想環境ですので、クライアントPCへの感染を防げます。汚染された仮想環境を削除してしまえば内部ネットワークへの影響もありません。
問51
グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。
我が国においては、2001年(平成13年)にグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。
この法律は、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、
地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています(環境省HPより引用)。
CSR
Corporate Social Responsibilityの略。企業活動において経済的成長だけでなく、環境や社会からの要請に対し、責任を果たすことが企業価値の向上につながるという考え方です。エコマーク認定
エコマーク認定は、生産から廃棄までを通じて環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品を認定する制度です。認定された商品はエコマークを表示することができます。環境アセスメント
環境アセスメント(環境影響評価)は、主として大規模開発事業等による環境への影響を事前に「調査する」ことによって、予測、評価を行う手続きのことです。グリーン購入
正しい。グリーン購入は、環境負荷の少ない製品、環境保護に取組む企業から優先的に購入する調達方針です。
問52
コアコンピタンス(Core Competence)とは、
成功や競争優位の源泉となるその企業独自のノウハウや技術などのように、競合他社には真似できない「企業の核となる能力」のことです。
事業を展開していく上では自社のコアコンピタンスを正しく認識し、
その強みを生かせる分野に展開していく経営手法をコアコンピタンス経営と言います。
ある能力がコアコンピタンスであるかどうかは、模倣可能性(他社に真似される可能性はどの程度か)、移動可能性(他分野への適用ができるか)、代替可能性(他のもので代替される可能性はあるか)、希少性(希少価値が高いか)、耐久性(継続的に競争優位を保てるか)の5つの点を考慮しなければなりません。コアコンピタンスの例としては、Googleの検索エンジン、アップルのハードウェア開発技術、トヨタ自動車の生産プロセスなどが挙げられます。
問54
HEMS(Home Energy Management System:ヘムス)は、
住戸で使用されるあらゆる家電や電気設備をネットワークに接続し、
エネルギー使用状況を可視化しつつ積極的に制御を行うことで、
省エネやピークカットの効果を目指す仕組みです。
政府は2030年までに全ての住宅にHEMSを設置することを目指しています。
したがって「エ」が正解です。
工場内の機械に取り付けたセンサで振動,温度,音などを常時計測し,収集したデータを基に機械の劣化状態を分析して,適切なタイミングで部品を交換する。
予知保全の説明です。自動車に取り付けたセンサで車両の状態,路面状況などのデータを計測し,ネットワークを介して保存し分析することによって,効率的な運転を支援する。
ADAS(先進運転支援システム)の説明です。情報通信技術や環境技術を駆使して,街灯などの公共設備や交通システムをはじめとする都市基盤のエネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。
スマートシティの説明です。太陽光発電装置などのエネルギー機器,家電機器,センサ類などを家庭内通信ネットワークに接続して,エネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。
正しい。HEMSの説明です。
問55
ロングテールは、膨大な商品を低コストで扱うことができるインターネットを使った商品販売において、
実店舗では陳列されにくい販売機会の少ない商品でも、
それらを数多く取りそろえることによって十分な売上を確保できることを説明した経済理論です。
一般的に商品の売上は
「全体の2割の優良顧客が全体の売上の8割を占め、
全商品の上位2割が8割の売上を占める」というパレートの法則に従うので、実店舗では売場面積や物流などの問題から上位20%の商品を優先的に販売することになります。
しかし、インターネット販売では従来の小売店販売面積の制約に縛られず、商品をデータベースに登録するだけで膨大な商品点数を揃えることが可能です。この商品点数の多さを活かし、小さいけれども確かにある販売機会を大量に集めることで、実店舗では実現不可能部分で大きな売上が生じるという現象が起こります。このようなビジネスモデルを説明するときに使われるのがロングテール理論です。
名前の由来ですが、
販売数を縦軸、商品を横軸にして、売上額が多い商品順に並べたパレート図を作成すると、販売数の少ない商品群の部分が低く長い形状となります。この右に延びた部分が恐竜の尻尾(tail)のように見えることから「ロングテール」と呼ばれています。
メーカや卸売業者から商品を直接発送することによって,在庫リスクを負うことなく自分のWebサイトで商品が販売できることは、ドロップシッピングの説明です。
問57
線型計画法の考え方に従うと最大利益となる可能性のある生産方針は、
以下のの3つのどれかになります。
製品Xを優先的に限界量まで生産
製品Yを優先的に限界量まで生産
調達可能量を全て使いきる製品XとYの組合せで生産
それぞれのケースごとに得られる利益を計算し、最大利益を求めます。
原料の調達可能量の制約からXの最大生産量は50個になります。Xの1個当たりの販売利益は100円なので、得られる利益は5,000円です。
原料の調達可能量の制約からYの最大生産量は40個になります。Yの1個当たりの販売利益は150円なので、得られる利益は6,000円です。
原料A、Bの両方を調達可能量まで使いきるときの、XとYの生産量の組合せを連立方程式で求めます。
{2X+Y=100 …①
{X+2Y=80 …②
①の式を変形
Y=100-2X …③
③の式を②の式に代入してXを求める
X+2(100-2X)=80
X+200-4X=80
-3X=120
X=40 …④
④の式を②の式に代入してYを求める。
40+2Y=80
2Y=40
Y=20
調達可能量まで原料A・Bを使った場合、Xを40個、Yを20個を生産することができます。このときに得られる利益は「100円×40個+150円×20個=7,000円」です。
以上より、
最大利益は3つのケースのうち最大となる「7,000円」となります。
問58
固定資産売却損益は、
固定資産を売却したときの譲渡額と売却時の帳簿価額の差によって
生じる損益です。
まず最初に売却時点での帳簿価額を計算します。
減価償却は償却率0.250の定額法で行うので、1年ごとの償却額は、
30万円×0.250=7.5万円
売却は購入からちょうど3年後に行われたので、売却時点での帳簿価額は、
30万円-(7.5万円×3年)=7.5万円
帳簿価額7.5万円の物を1万円で売ったので損をしていることになります。このため、両社の差額を固定資産売却損として計上することになります。
7.5万円-1万円=6.5万円
したがって「イ」が適切です。
問59
売上高、固定費、変動費および利益の間には次の関係があります。
利益=売上高-変動費-固定費
このうち、変動費は売上高に比例して増減する費用であるため、
売上高に対する変動費の割合(変動費率)を用いて
「変動費=売上高×変動費率」と表すことができます。
よって、 利益=売上高-変動費-固定費は、
利益=売上高 -(売上高×変動費率)- 固定費となります。
本問では、固定費が30百万円、変動費率が「60÷100=0.6」なので、18百万円の利益を上げるための売上高N は、上記の式に各値を代入して以下のように算出できます。
18=N-(N×0.6)-30
18=N-0.6N-30
0.4N=48
N=120
したがって必要な売上高は120百万円です。
News
勉強勉強だとほんとに嫌気がさしてきます。なんか今日、全く動いてないな、とか、気分が落ち込んだ時には、必ずやっていることがあります。それは、筋トレです。私は、いつも貯金じゃなくて貯筋しています。
たまにあるんです。どうしてかわからないけど、不安になる。
この先、自分は生きていけるんだろうか・・とか。
でも、そんなことを深く考えたところで、何も先に進まないことは十分理解したのと、これまでの経験上それが役に立ったことはありませんでした。
結果が変わらないなら、自分の好きなことをします。
自分のやりたいことをします。
最近、陰で、自分の悪口(とまではいかないのですが)陰口を言っているというのを、別の友人から教えてもらいました。(言わなくていいよって思うけど笑ありがとう。)
なんだかな〜・・。そんなことを思っていたんだなぁ。と思ったのと同時に、実は自分が過去にそういうことをしたこともあったことを思い出しました。今だから、絶対人の嫌がることはしないと決めています。だって、悪気がなくても、色々な人に迷惑をかけるから・・。
な〜んて、ずっとダラダラ考えてしまうんですよね。
そういう時には、筋トレです。
もう、辛くなったら、苦しくなったら、
そんなこと、どうでもよくなる。
ものすごく、悔しくて、辛くて、苦しくて、、、、
そんな時、息を止めてみてください。
そんなことどうでもよくなると思います。息しなきゃ!!って。
筋トレはそれに近いです。自分のボディメイクをすることが、
目にみえる自分磨きにつながるだけでなく、今の現状がどーでもよくなるんです。
結果的に、自信もみなぎってくる。というか、身についてくる。
辛くなったら、筋トレ。
疲れたら、筋トレ。
楽しいなら、筋トレ。
マラソンは、走る前が一番緊張する。
走り始めたら、もう緊張とかどーでもいい。
ただ、走り続けるだけ。
そんな感じです。
高校時代、ザバスのプロテインをずっと飲んでいました。
バニラ、ヨーグルト、バナナ色々試しました。味はまずいけど、組み合わせてうまいものもあります。
自分は、初手はビターショコラが安定だと考えます。ザバスの組み合わせで、バニラ✖️ココアとか、ジュースを変えて、オレンジジュース✖️バニラとかにしても楽しいし、うまいんですが安定なのはビターショコラでした。
一日2食、がっつり決めたいのであれば3食でいいです。ただ、必ず1食は寝る前の2時間前くらいに飲むのがベストです。
寝るって、結構体力使いますし、1日運動したことが、筋肉アップになりますしね。もちろん、食生活はとても大事なんですが、とりあえずこちらは筋力アップをサポートしてくれるので、是非是非。
Index
過去Indexです。基本情報技術者対策として勉強を続けています。
よろしくお願いします。
少しずつですが、投稿をしております。 noteで誰かのためになる記事を書いています。 よろしくおねがいします。
