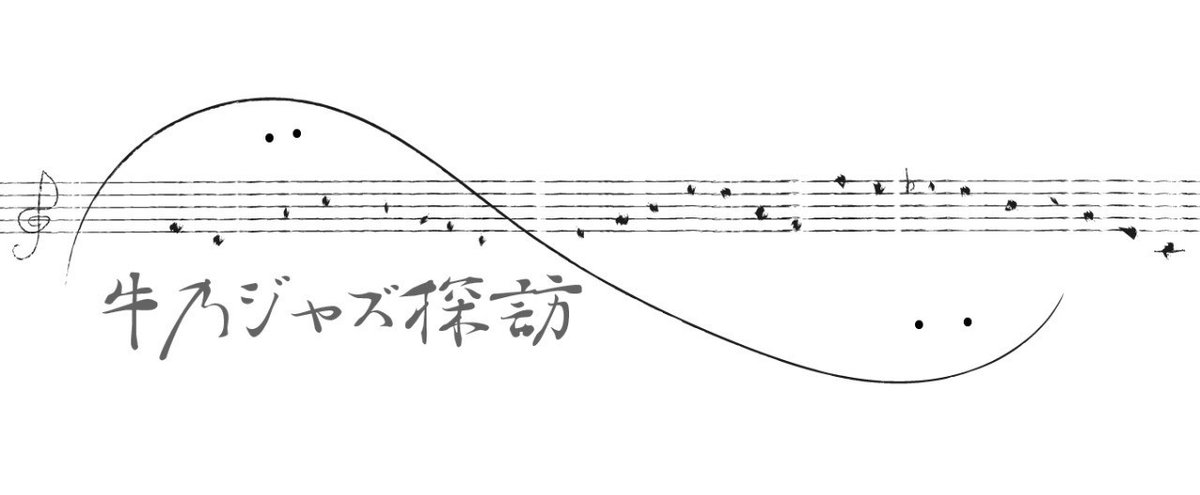
牛乃ジャズ探訪(14) ラリー・グレナディア
高知の音楽家・ギタリストの牛心。です、梅雨入りしたら晴れて来たみたいな爽やかなジャズ記事を目指しています。いま決めました。
みなさんベーシストってどんな印象ですか?バンドや吹奏楽などの経験者にとっては、音楽の要的存在という認識があると思います。
一般のリスナーはベーシストなんて気にしてないのではないでしょうか。ライブを見に行ってもせいぜい「かっこいい(小並感)」みたいな感想なのが一般リスナーの平均値なんじゃないかと思います。
ジャズの界隈はベーシストの社会的地位が高い。
ラリー・グレナディア(Ba)
Larry Grenadierは1966年サンフランシスコ生まれのベーシストです。トランペット奏者の父を持ち、その影響か10歳でトランペットを始めます。ちょうどその頃、兄の影響でジャズを聴き始め、特にジャズベースに興味を持ち、12歳になったことアコースティック・ベースに手をつけます。
既にジャズベーシストの若手として頭角を現していたラリーは、スタンフォード大学を卒業後にボストンへ拠点を移し、ゲイリー・バートンとギグを重ねボストン界隈のミュージシャンと交流を深め、1991年にニューヨークへ。カート・ローゼンウィンケルやジョシュア・レッドマンらのサイドマンとして安定感を示していきました。
僕が彼の名前を知ったのは(多くの人がそうだと思われますが)、パット・メセニー・トリオとの共演からです。
当然、最初はメセニーすげえ!と思いながらアルバムを楽しむのですが、何年か経って改めてこのトリオを聴くとベースがとてもメロディアスであることに気がつきました。
1曲目の(Go)Get it はヘッドのメロディこそ複雑ですがソロは12小節のブルースです。すごく複雑に聴こえますが、ミュージシャンレベルが上がってくるとシンプルに聞こえてくるという不思議な曲です。今度ライブでやってみようかな。
二十歳頃にこのメセニートリオを聴き込んでから、他のジャズのアルバムを聴くと「なんか物足りないな」という気持ちになったのをよく覚えています。
ラリーのベースはちょっと他のジャズベースとは違うフレイバーが隠されていました。
脱ウォーキングベース
このアルバムも何回聴いたか分からん(笑)
ベーシストの大きな役割は2つあります。
①リズムパターンのキープ
②最低音程を維持しハーモニーを支える
他にもやるべきことはあるにせよ、この2つが重要です。異論はないと思います。
そしてジャズの場合は②のハーモニーを支える方法としてウォーキング・ベースという手法があります。
このイントロみたいな4拍ずっと弾き続けるスタイルです。よくジャズで聴きますよね。
ずっと同じビートをキープする①の要素をクリアしつつ、ハーモニーを分散和音にして繋げていくのがウォーキング・ベースのシステムです。
いかにもジャズって感じがします。
このいかにもジャズが、ちょっと小っ恥ずかしというか、こそばゆい感じがするジャズプレイヤーが少なからずいます。
その理由は、ウォーキング・ベースはコードが決まれば自動的に生成できる合理的なシステムだから誰がやってもだいたい一緒になる点にあると思います。
素晴らしいシステムだし、美しいのですけど、ジャズのメンタリティは「新しさ」を求めているので、こういった伝統的なものがあると壊したくなる。そうやってジャズは進歩してきたのでした。
ウォーキング・ベースの理論を踏襲しつつ枠を外したりハーモニーを自分勝手に変えたり、そういう試行錯誤を感じるレコーディングも紹介してみます。有名どころですけど、スコット・ラファロなんかはそんな感じです。
あまりに有名なAutumn Leavesですが、このベーシストであるスコット・ラファロはウォーキング・ベースが全盛の1960年にあってアコースティックベースの旨味である中高音域のポジションを積極的に使っています。
それでもちゃんと楽曲のハーモニーは成立しています。
ハーモニーはオクターブが違っても同じと解釈
どうして低い音でなくてもOKなのかというと、バークリーシステムでは、
コード構成音のオクターブが変化してもハーモニーに大差ない
という前提、というかこれは経験則なんですが、つまりコード構成音=スケールなので「ハーモニーの枠内でなら何やってもいいよ」という考え方なんですよね。
詳しくはそのうち別記事でも書きたいですが、要するに「ベース=低音域の楽器」という枠を突破する理屈がちゃんとそこにある、ということです。
ある程度以上に習熟したベーシストにとっては当然のことですが、案外ベーシスト自身が「ベース=低音域の楽器」と思い込んでたり執着したりして、練習メソッドに中音域以上のポジションが含まれていない教本もたくさんあります。けど、やっぱり使える音域は、使えた方がいいに決まってますよね。
話題は外れましたが、ラリー・グレナディアのプレイスタイルはこういったジャズ・ベースの歴史を学んでいる雰囲気があります。ジャズのメンタリティである「新しさ」を探求する姿勢とでも言いますか。
面白い曲であれ、シンプルなジャズであれ、自分の感じているハーモニーの中で自在に泳ぐ。それが彼のベースの魅力だと思います。
サイドマンとして優秀
音楽家一家に育ったラリーは、様々な音楽に対して柔軟に対応できるミュージシャンです。
こういったヨーロピアンな音楽もやるし、
こういう8ビートっぽいのもこなす。そうそう、僕はブラッド・メルドーのトリオはメセニートリオより先に知ってたんですが、ラリー・グレナディアだって意識は無かったですね。
そういえばメルドートリオのベーシストだったやん!みたいな驚きはありました。
この、ちょっと隠れて活躍してる、表立ってはあんまり知られてないサイドマンとしての格好良さはジャズに限らずベーシストの魅力だと思います。
牛心。
高知在住の音楽家・ギタリスト。4月からの作家稼業も無事〆切を過ぎ6月冒頭デスマーチが始まるぞ、という段取りがあんまりよくないローカルミュージシャン。
サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!
