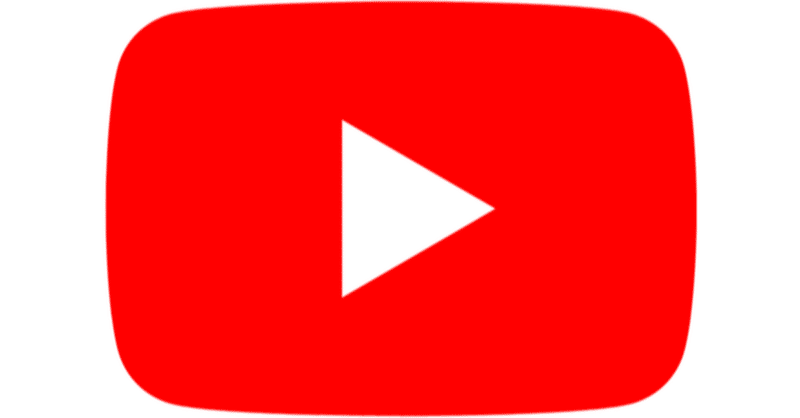
YouTubeのビジネスについて勉強④
こんにちは! ばなおです。
前回は、大きく以下のポイントを勉強しました。
・YouTubeから広告収入を得る仕組み
・広告で稼ぐポイント
・コンテンツ販売の仕組み
・独自コンテンツについて
・独自コンテンツ販売におけるYouTube活用法
前回に続き、今回も取り扱うのは、KYOKO『世界一やさしい YouTube ビジネスの教科書 1年生』です。
5時限目 ユーチューブアフィリエイト
01 ユーチューブアフィリエイトの仕組みと全体像
アフィリエイトとは、広告主が販売する商品を自分の媒体(YouTubeやブログなども含む)で紹介して宣伝し、販売の手伝いをすることを指します。
商品を紹介する人をアフィリエイターと呼び、アフィリエイターが紹介した商品をユーザーが購入したら紹介料がもらえる仕組みです。
アフィリエイト商品は広告主との仲介をするASP(Affiliate Service Provider)に登録されており、アフィリエイターは登録された商品の中から紹介するものを選びます。
具体的には、「紹介する商品の広告リンクを自身が運営する媒体に貼り付けて商品を紹介する」という流れです。
直接広告主と交渉をするよりもASPを通した方が楽に始められる点や、ASPを通してさまざまな情報が得られる点がアフィリエイターにとっても大きなメリットとなります。
アフィリエイターはASPに登録することで、そのASP会社が契約している広告主のサービスを扱うことができるのが大きな特徴です。
広告主の定めた成果条件を満たすと、それに応じた報酬が支払われる仕組みとなっています。
ちなみに、前職は広報をしていたので主なASPの表の中に知っている企業もちらほらありました。
アフィリエイトを構成する要素
・アフィリエイター
・ASP
・広告主
・ユーザー
アフィリエイター
インターネット上で企業の代わりに商品を宣伝する仕事で、個人でもできる広告代理業です。
ASP
アフィリエイターと広告主との間を取り持つ仲介役のような存在です。
広告主
商品の販売を促進したい企業やメーカー。
ユーザー
WebサイトやYouTubeを訪れる人です。
海外アフィリエイトの場合はASPが省かれていることもあるそうですが、国内に関してはASPが大きな力を持っており、この4要素がなくてはアフィリエイトビジネスは成立しません。
4つの役割は大きく、以下のように振り分けられています。
各要素の役割
・アフィリエイター:ASPを経由して広告主の広告を自分のサイトでユーザーに紹介する
・ASP:広告主から広告を募集し、アフィリエイターにその広告を紹介する
・広告主:売りたい商材の広告をASPに依頼し、アフィリエイターに自分のWebサイトで商品を紹介してもらう
・ユーザー:アフィリエイターのサイトを経由して、公式サイトへ行き広告主と契約または商品の購入をする
アフィリエイトできる広告は、成果報酬の仕組みによって大きく分類されます。
1. クリック型広告
2. 成果報酬型広告
前回のnoteで触れたとおりYouTubeの広告収入はクリック型広告ですが、ここでは成果報酬型のYouTubeアフィリエイトについて解説します。
成果報酬型とは、広告リンクを通して何かしらの商品を購入したり、サービスの契約が成立するアクションをユーザーが行った場合に報酬が発生するアフィリエイトです。
メリットは、クリック型広告に比べて報酬単価が高いこと。
デメリットは、広告にマッチしたコンテンツ(動画)が必要なことです。
YouTubeで使える成果報酬型広告は大きく3種類あります。
・ASP広告
・楽天アフィリエイト
・Amazonアソシエイト
ASP広告は、YouTube外部のASPが提供するアフィリエイトリンクを動画の概要欄に記載するタイプの広告です。
案件の形態も様々で、無料会員登録の件数で見るサービス系や来店案件、物販案件などがあります。
特に物販案件は、比較的紹介しやすいスキンケア商品などでも1件で3000円くらい稼げるものがあるため、まとまった金額が手に入りやすいです。
続いて、楽天アフィリエイトは楽天市場で取り扱う商品を紹介するアフィリエイトです。
楽天の中にある商品なら無審査で広告として取り扱うことができ、YouTubeで利用する場合はASP広告と同じく、概要欄にアフィリエイトリンクを記載します。
一般的な商品が多く、動画を作り込む必要があまりないため、普段使っている愛用品を概要欄で簡単にアフィリエイトできるメリットがあります。
ただし、ASP広告よりも報酬単価は低めなようです。
AmazonアソシエイトはAmazonで販売されているすべての商品を対象にアフィリエイトできる広告システムです。
こちらを利用する場合は事前にチャンネルを審査にかける必要があります。
それ以外の部分については基本的に楽天アフィリエイトと同じ仕組みで、動画の概要欄にAmazon商品のアフィリエイトリンクを貼り付けて紹介するだけです。
ジャンルによって紹介料率はまちまちみたいなので、こちらのページで確認しましょう。
生活に密着した商品が多くてハードルが低いので、初心者向けかもしれません。
02 ユーチューブアフィリエイトの始め方
YouTubeでアフィリエイトを始める際、実行しなければならないことが2点あります。
1. ASPに登録する
2. ユーチューブチャンネルの登録申請をする
まずは先ほど紹介した成果報酬型広告の概要について説明します。
楽天アフィリエイトの場合は、楽天アカウントの作成が必要です。
アカウント作成後、楽天アフィリエイトにログインし、任意の商品を選んだら広告リンクを取得すればOKです。
Amazonの商品をアフィリエイトする場合は、Amazonアソシエイトに登録しなければなりません。
前述しましたが、Amazonアソシエイトは登録申請の際に、アフィリエイト広告を貼る媒体を審査にかける必要があります。
自分のYouTubeチャンネルURLを記載して登録申請をする際、既に何本か動画が投稿されている状態が望ましいです。
広告と異なり、申請時点での登録者数や再生時間の条件は特に記載されていませんが、新規開設したばかりのチャンネルでは審査が難しいですからね。
審査に通れば「承認メール」が届き、Amazon商品を紹介できるようになります。
Amazonアソシエイトは利用規約が比較的厳しめなので、注意しましょう。
・登録申請した際の媒体でのみ商品紹介が可能(変更・追加する際は都度申請が必要)
・Amazonアソシエイト参加者であることを明記すること(ユーチューブであれば概要欄にその旨記載すること)
次に、ASP広告をYouTubeで利用するための手順について説明します。
まずはASPへの会員登録が必要です。
ASPは種類がたくさんあり、ASPごとに紹介できる商品が異なる場合がありますので、複数登録することが推奨されています。
YouTubeのアフィリエイトでASPを利用する際の会員登録方法は基本的にどれも同じです。
Amazonアソシエイトと同様、広告動画であることが分かるように概要欄やハッシュタグで「PR動画」「広告投稿」「#PR」などと記載する必要があります。
事前準備が整ったら、紹介する商品を選びます。
推奨される基準は以下の通りです。
1. 使用したことがある商品やサービス
2. 動画にすることによって魅力が伝わる商品やサービス
3. 自分のチャンネルテーマにマッチしている商品やサービス
中でも「使用したことがある商品やサービス」については、必須条件とも言えるかもしれません。
ASPにはセルフバックという自己アフィリエイトシステムがあり、ものによっては無料入手できますので、手元にない場合はこのシステムで購入することも可能です。
次に「動画にすることによって魅力が伝わる商品やサービス」について説明します。
前提としてYouTubeで商品を紹介する最大のメリットは、リアリティですので、その特性を活かせる商品を選ぶことがポイントになります。
視聴者は動画で、「実際に手に取って試したらどうなるのか」を求めています。
・実際の大きさ・重さは?
・使用感や効果は?
・細かな性能は?
・不便な点や逆に良かった点は?
こうした点を押さえつつ、視聴者が疑似体験できるような内容の動画だと、より魅力的に見えるのではないでしょうか。
商品購入前に動画などで詳細を確認してから購入する人が全体の40%に上り、その中でもユーチューブで動画を視聴してから購入する人の割合は、59.9%にもなります。
私自身、高額な買い物であればあるほどインターネットで事前に詳細を調べてから購入しています。
そんな人たちの約6割がYouTubeを視聴しているので、YouTubeの動画がいかに購入の判断基準として信頼されているかが分かります。
最後に「自分のチャンネルテーマにマッチしている商品やサービス」についてです。
こちらは何となく想像がつくのではないかと思いますが、適当に選んだ商品を紹介するだけだと権威性や専門性がなく、情報の信憑性にも欠けるため、購入どころかチャンネル登録などにもつながりにくいですよね。
押さえておくべき基本的なポイントですが、SNSは宣伝を嫌います。
YouTubeも同じなので、アフィリエイト動画ばかり出すことは避けた方が良いです。
ただし、目的をチャンネルの成長ではなく、検索結果からの流入にフォーカスするのであれば、その限りではありません。
商品が決まったら、紹介用の動画を作成します。
広告リンクのみを概要欄に貼ることも可能ですが、本気でアフィリエイトをするのであれば、商品・サービスを動画内で紹介することは必須です。
紹介する方法は大きく2つあります。
1. 動画1本まるまるアフィリエイト動画にする
2. 動画内でテーマに関連した商品に軽く触れる
前者は、YouTube検索結果に動画を表示させて集客したい場合におすすめのスタイルです。
動画の宣伝色は強くなりますが、商品・サービスについてユーザーが求めている情報をたっぷり伝えられるので、成約につながりやすいです。
一方後者は、動画のテーマ自体はアフィリエイトと直接関係ないものの、動画内でさりげなく商品を紹介するタイプです。
動画内でさらっと商品について触れて「詳細は概要欄にリンクがあります」などと誘導すればシンプルかつ親切な構成で商品・サービスを紹介できます。
またこのスタイルは、商品よりも動画テーマや演者が目立つので宣伝色が弱くなります。
商品を紹介する際は、表現に気をつけなくてはいけません。
主に薬機法に関連するものですが、化粧品などの商品を紹介する際、効果効能に対しての絶対的な表現は法に抵触しますのでやめましょう。
03 ユーチューブアフィリエイトのコツ
GoogleやYouTubeの検索結果からアフィリエイト用の動画集客を狙う場合、動画のテーマを検索キーワードベースで考えるのが効率的です。
その際、YouTubeで商品情報を確認してから購入する層が、どのように検索しているのかを類推します。
・「商品名+効果」
・「商品名+使い方」
・「商品名+やり方」
・「商品名+経過」
想定したキーワードを動画のタイトルに含ませることによって、検索にヒットする可能性を高めることができます。
キーワードの選択方法については、以下2つが簡単です。
・YouTubeサジェストから選ぶ
・ツールを使う
どちらも以前のnoteで触れましたが、YouTubeサジェストはYouTubeの検索窓にキーワードを入力した際、補足として表示される言葉です。
ツールについてはラッコキーワードが代表的です。
ラッコキーワードは様々なサービスのサジェスト情報を収集しているのですが、画面上で絞り込みができるようなので、YouTubeのサジェストキーワードだけに絞って確認することもできます。
目標キーワードをタイトルに含めてそのテーマで動画を作成すれば、検索結果の上位に必ず表示されるのかといえば、必ずしもそうでもありません。
YouTube検索対策は一般的なSEO対策と共通点があるのですが、SEO対策においては「キーワードへの関連性」と「情報の網羅性」が重要と考えられています。
例えば、本で挙げられていた「黒ずみ」などの目標キーワード単体では、複数の需要が含まれています。
Google検索とYouTube検索両方で検索結果の上位表示を目指す場合、目標キーワードに包括されるあらゆる検索意図を網羅する必要があります。
意味合いの広いキーワードは月間検索ボリュームも高く、検索意図が多くあるため、意図ごとに関連動画を複数作成した方が良いと言えます。
そうすることでチャンネルの専門性も高まりますので、手間はかかりますが悪いことばかりではありません。
一方商品名など、狭いキーワードの場合は検索意図がかなり絞られます。
検索ユーザーの知りたいことが限定されている場合は、1本の動画で求められている情報が網羅できる可能性が高まり、作らなければならない動画の数が少なくて済みます。
ユーチューブを使ったアフィリエイトで稼ぐためのコツとしては「高単価案件を選ぶ」というものもあります。
動画作成に費やした労力と金額は必ずしも比例しないので、効率良く稼ぐためには当然とも言えます。
ただ単価が高いからと言って、綺麗な言葉を並び立てて粗悪なサービスをアフィリエイトするのは信用問題に関わりますので良くないですよね。
・売りたい気持ちを前面に出したPRでは物は売れない
・売上を上げたければデメリットを開示せよ
まだ使ったことのない商品・サービスを紹介したいと思ったのであれば、まずは自分で体験しましょう。
そして良かったところだけでなく、悪かったところもあれば、一緒に動画で紹介しましょう。
売りたいがためにデメリットを隠して紹介したり、実際にサービスを使わず適当に静止画を流すようなアフィリエイト動画を作っても売れません。
6時限目 ユーチューブで挫折しないための心構え
01 最大の苦難は「続けられない」こと
YouTubeなどのインターネット上でお金を稼ぐ場合、大きく分けて2つの稼ぎ方があります。
・スキルを販売するスタイル
→WebライターやWebデザイナー、動画編集など
・仕組み構築スタイル
→アフィリエイトやブログ、ユーチューブなど
前者は即金性があるので、継続についてはさほど関係ない一方で、後者は仕組みづくりが必要な稼ぎ方となっています。
稼ぐためには何より継続することが重要です。
何度も言いますが、私の場合は趣味の延長なので本格的にお金を稼ごうとは思っていません。
ただ、せっかく作った動画を多くの人に見てもらいたい気持ちはあります。
そうなると、インプレッションやエンゲージメントを伸ばした方が良く、やはり継続して動画をアップする必要がありますね。
ユーチューブでビジネスをするためには、稼ぎたい金額に関係なく、E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を向上させ、チャンネルステータスを上げていく必要があります。
継続して投稿することで、こうしたステータスを上げることができ、チャンネルが信頼されるようになります。
前回のnoteでも説明しましたが、更新頻度を保つと視聴者のチャンネル視聴が習慣化し、再生回数も安定的に増えます。
さらに言うと、更新頻度が高いチャンネルは登録者の増え方が大きいです。
趣味でユーチューブをやるならいいのですが、ビジネスとしてお金を稼ぎたいのなら、このような理由から「継続」は最重要事項だということを心得ておきましょう!
冷静に考えると、私のような趣味でYouTubeをやろうとしている人間がここまでYouTubeビジネスについて真面目に勉強しているのも変な話ですが、ここまで来てしまったので最後まで走り抜けたいと思います。
次は、投稿を継続できない理由について見てみましょう。
挫折してしまう原因は大きく2つあると考えられます。
・ユーチューブ投稿のハードルが高すぎる
・理想と現実のギャップ
動画投稿する際の労力が大きければ大きいほど、継続は困難になります。
ほとんどの人は私と同じように、本業がありながらも動画を投稿しようと考えているのではないでしょうか。
私自身も懸念していることですが、撮影や編集など、動画投稿のためにリソースをなかなか割けないんですよね。
また「理想と現実のギャップ」について、筆者が以下のように分析していました。
ユーチューブを続けられない人は「割と楽に稼げる」「楽しみながら稼げる」「好きなことで生きてく」……と、このようなイメージで始めているように思います。
もちろん、私のように趣味でやる人は良いのですが、本気でYouTubeで稼ごうと思っているのであれば、生半可な気持ちで取り組んでも成果は出にくいのではないでしょうか。
これまで勉強してきた内容も、本の方では約230ページ、私の書いたnoteでは3記事分の注意事項やポイントがありますし、それらの内容を意識しながらチャンネルを運営するのってかなり大変だと思います。
本にも書いてありますが、「私頑張ってます!」という方が1週間に1本しか動画を投稿していなかったり、数ヶ月しか投稿を続けていないと、想定違いということみたいです。
なかなか大変な世界ですね……。
YouTubeを継続するために気を付けるべきポイントは3つです。
1. 目標を高く持ちすぎないこと
2. ベビーステップを踏むこと
3. 最初は質より量を意識
高すぎる目標は挫折の原因になりますが「1年後に月収益5万円稼げるようになる」くらいであれば現実的な目標になるみたいです。
会社勤めの方は想像しやすいと思うのですが、1年間で給料を5万円アップさせるのって結構ハードじゃありませんか?
そう考えると、なかなか十分な金額のようにも思えます。
ユーチューブをやる目的を、最初の頃は「稼ぐ」ではなく「楽しむ」にフォーカスを合わせると、目標達成しやすいでしょう。
「楽しんでやっているうちに、いつの間にか稼げてしまった」これが苦しまずに稼ぐ唯一の近道だからです。
また、継続するためには細かな達成感を味わうことも欠かせません。
そのために必要なのが「ベビーステップを踏むこと」なのです。
初めのうちは再生回数1桁が当たり前ですし、短期間で収益化条件をクリアできるのはもともと知名度がある人くらいです。
段階を踏んで継続につなげましょう。
・撮影できた!
・アップロードできた!
・10回再生された!
・登録者が10人になった!
こんな小さな達成感を重ねていくことで、継続力が上がっていきます。
さらに押さえておいた方が良い考え方ですが、初めのうちは稼ぎたいのであれば「量」をこなすことを意識するべきです。
その理由としては以下の通りです。
1. 撮影に慣れるため
2. ユーチューブを習慣化するため
3. ユーザーに認知してもらうため
慣れていないがゆえに継続できないということは、よくあります。
初めから稼ぐことは求めず、ベビーステップを踏んで負担の少ないところから量をこなしていきましょう。
02 ネタが見つからないときの対策
これから動画を作る予定かつ、撮りだめた動画が大量にある私にとってはまだまだ先の話ですが、見ていきましょう。
ネタ切れを起こさないためには、最初のチャンネル設計の時点で、テーマの広がりがあるジャンルであるかを見極める必要があります。
最初はニッチはジャンルから! ということは前のnoteで触れましたが、とは言っても広げる余地がないと意味がありません。
自分の参入ジャンルで、どれぐらいまでチャンネル登録者数を伸ばせるかは、そのジャンル内のライバルたちを見れば大体わかります
YouTube検索でジャンル名を入力し、「チャンネル」をフィルタして検索すると、そのジャンルのチャンネルが出てきます。
私のチャンネルのライバル(というのもおこがましいですが……)の登録者数をチェックしてみました。
・Vlog…19万人のチャンネルもあるが、1~2万人くらいが多そう
・ディズニー…多くて10万人くらい
・旅行…多くて1~5万人くらい、1000人満たないチャンネルがかなり多い
・日記…多くて40万人のチャンネルあり
最後の「日記」は私のチャンネル名が「ばなおさんの日記」なので念のため調べてみました。
正直、どのジャンルももっと登録者数が多いものだと思っていたので、意外と少なくてびっくりしました。
こうやってジャンルで検索すると、上位層・中間層・下位層のチャンネルで規則性が見いだせると思います。
それぞれの層がどんな動画をアップしているのかを研究すると、自分のチャンネルでネタが切れた時の打開策のヒントが見つけやすくなります。
また、広がりのあるジャンルの選び方として、以下のような方法も挙げられています。
「最終着地点から逆算して、最小のジャンルから取り組む」という方法が有効だと考えています。
ちなみに私の場合は、過去のnoteですでにこのような例を考えています。
・(初期)ディズニーグルメ系Vlog
↓
・(テーマ変更後)ディズニー前日の夜からの過ごし方
↓
・(テーマ変更後2)20代OL 休日の過ごし方
チャンネル設計の段階で先々の展開計画を練る人はなかなかいないと思いますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
5時限目で解説があったように、キーワードベースで動画のネタを選ぶのも良いです。
キーワードベースで選ぶメリットとしては、「自分の話したいことしか話さない自己中心的な内容になる」ことを避けられることが挙げられます。
動画のネタを選ぶ際の基準として「人気のテーマに寄せて作る」というものがあります。
一般的なSEOは順位の奪い合いですが、YouTubeにおいては同じテーマ同士で関連動画に載りあうことで、お互いの再生数を伸ばすことができます。
自分が参入しようとしているジャンルの動画を日ごろからチェックして、旬なネタを取り込むのも大いに有効だと思います。
この時、注意点があります。
1. 同レベルのチャンネルに照準を合わせる
2. 別ジャンルの動画テーマはやらない
過去のnoteでも説明しましたが、アルゴリズム上、チャンネル格差が激しい動画は関連に載りにくいようです。
テーマを寄せるのであれば、自チャンネルと同じかそれ以下のチャンネル内で人気の動画に寄せる方が関連枠に載る確率は高いと考えられます。
もちろん畑違いのテーマの動画は避けるべきです。
ネタ切れ対策の1つに過去の人気動画のリメイクがあります。
チャンネル登録者数が増えるにつれて、「ヒットした動画」の基準も変わるはずです。
当時はヒットしたと思っていても、今見てみると再生数自体はそうでもない……というような動画があった場合は、リメイクをすることで「今基準の数字でのヒット」を生み出せる可能性があります。
「ネタがない」と困ったときは、動画に寄せられるコメントに回答する動画を作ってみましょう。実は、これはすごく視聴者の反応が高い方法です。
双方向コミュニケーションの重要性は以前のnoteで説明した通りですが、まさにそれを実践するということですね。
視聴者目線で考えても、自分のコメントが読まれたり動画のテーマとして取り扱ってもらえたら、きっと嬉しいですよね。
「視聴者のコメントに動画で答えるのはメリットしかない」と筆者も力強く書いています。
エンゲージメントを高められるだけでなく、視聴者とコミュニケーションも取れる、一石二鳥なやり方です。
ちなみに動画にコメントがなかなかつかない場合は、以下の方法もあります。
・質問箱を概要等に設置する
・ツイッターなどのSNSで意見を求める
・YouTubeコミュニティのアンケート機能を使ってみる
質問箱はPeingのサービスが有名だと思います。
視聴者からのレスポンスをもとに動画を作れる、フレンドリーなチャンネルを目指したいですね。
03 批判やアンチの対象になる覚悟も必要
YouTubeのようなインターネット上で何かを発信すれば、不特定多数の人の目に留まり、評価されることになります。
チャンネル登録者数が少ないうちは、さほどコメントされることもないかもしれませんが、人気が上がってくると批判的なコメントが付く可能性があることは覚悟しましょう。
どんなに良い動画を作っても、すべての人を満足させることは不可能ですもんね。
ここでは、誹謗中傷やアンチの対策について勉強したことを記載します。
コメントで書かれる悪い評価について、シンプルな誹謗中傷パターンが想像しやすいですが、きちんと受け止める価値のあるアドバイスの場合もあります。
誹謗中傷する人の特徴4つを順番に押さえていきましょう。
まず、アドバイスと誹謗中傷は全くの別物です。
全て無視することもできますが、アドバイスも無視してしまうと自分の成長機会を逃すことになります。
KYOKOさんが考える誹謗中傷とアドバイスの線引きは以下の通りです。
・誹謗中傷は自分(コメント投稿者)のため
・アドバイスは相手(チャンネル運営者)のため
後者の方は、コメントに具体的な指摘内容や改善方法が書かれているはずです。
ただ単に「面白くない」とか、「キモい」とか書かれているだけコメントは、コメント投稿者が満足するだけで生産性がないので誹謗中傷ですね。
今時SNSの誹謗中傷で自殺する方が出るなど、センシティブで大きな問題になっているはずなのに、なぜ未だにこういう方がいらっしゃるのか、はなはだ疑問です。
ネットリテラシーを高めること、ネチケットをきちんと守ること、この2つは必ず気を付けたいですね。
誹謗中傷する人の2つ目の特徴としては、嫉妬が根本の動機にあることが挙げられます。
ある程度チャンネル登録者数が多くなってきた頃にアンチコメントが付きやすいことからも分かりますよね。
また、アンチコメントをすることで相手の反応を見たい人もいるようです。
インターネット上で、批判コメントに対して反論コメントが付いているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。
そしてさらに、その反論コメントに反論する批判コメントが付き……と地獄絵図になるパターンもありますよね。
内容はともあれ、ネット上で会話のキャッチボールをするのが楽しいのでしょうか。
最後の特徴として、承認欲求を満たしたいというパターンもあるようです。
動画投稿者本人に直接DMすれば良いものを、わざわざ不特定多数が見える場所で不愉快なコメントをする方は、確かに承認欲求を満たしたがっているのかもしれません。
公の場所でコメントするのは、自分の意見に賛同してくれる仲間が欲しかったり、論破する自分を誰かに見てほしかったりするのでしょう。
余談ですが、この引用の中で「欲しい(ほしい)」の表記が揺れていますね。
職業柄こういうのが気になってしまいまして……
話を戻しますが、こういう方はネチケットがなくネットリテラシーが低いと言えます。
このような特徴を持つアンチについて、対処法があります。
対処法は簡単です。「気にしないこと」です。
前述しましたが、すべての人が満足できる動画を投稿することは不可能です。
極めて悪質なコメントが投稿されたら、非表示にすることも選択肢の一つだと思います。
もちろん悪質なコメントをする方が悪いのですが、自衛として自分のチャンネルは自分で守る努力をしましょう。
「割れ窓」という考え方があります。
悪質なコメントが残っていると「こういうコメントをしている人がいるんだから、自分もちょっとくらいストレス発散しても良いかな」と勘違いして、同じ動画に悪質なコメントをする人がさらに発生する可能性があるのです。
その意味でも、悪質なコメントを非表示にすることは有効な対策と言えます。
ただし、まっとうなアドバイスには真摯に対応しましょう。
前述の通り、自分の成長機会につながります。
5時限目と6時限目はここまでです。
続きは「YouTubeのビジネスについて勉強⑤」に書きますので、引き続きよろしくお願いします。
分量的に次回が最終回になります!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
