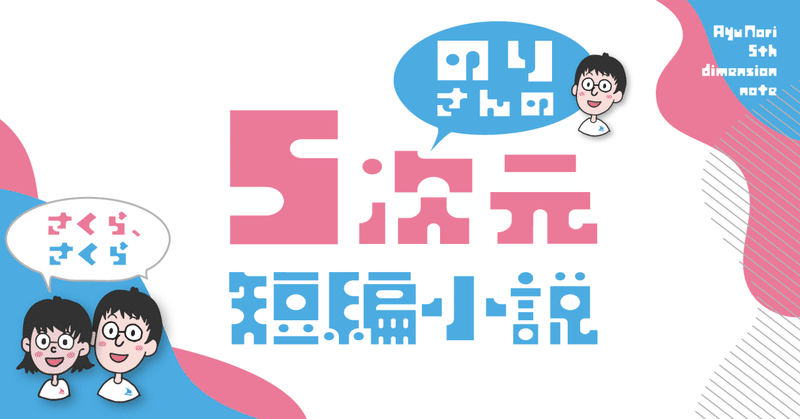
5次元短編小説『さくら、さくら』
俺が料理だなんて、いったい何十年ぶりだろうーー。
定年を迎えて今日で一週間。いつまでも外食や店屋物ばかりという訳にもいかない。
何より今日は妻の誕生日だ。ここはひとつ、あいつを驚かせてやろう。
一念発起した俺はこうして台所でひとり、ちらし寿司を作っている。
久しぶりに握った包丁はずしりと重かった。汁気を切った酢レンコンをいちょう切りにしていく。
包丁を受けたまな板がトントントンと小気味の良い音を立てる。このまな板はたしかヒノキだっただろうか。
こうしてあらためて見てみると、とてもよく使い込まれている。しかもよく手入れされていて清潔そのものに保たれている。
一家の食卓を長らく支えてきた功労者として、まな板はどこか誇らしげな表情を受けべているようにさえ見えた。
そのまな板は、妻が毎日の暮らしを大切にしてきた何よりの証のように思えた。
それに引きかえ俺はどうだろう。家庭を顧みない男だっただろうか?
もちろん自分なりに家族を大切にしてきたつもりだ。一家の大黒柱として俺にやれることをやってきた自負はある。
だが日々の仕事に打ち込みすぎるあまり、家のことはほとんど妻に任せっきりだった。
ひとりで台所にいると、どうしてこんなにも内省的な気持ちになるのか、自分でもよく分からなかった。
俺の中にいる「別の誰か」が突然おしゃべりになったのかもしれない。
◯
「もし私が先に逝ったら、あなたはきっと独りでは生きていけないわね」と妻はよく晩酌の席で俺をからかった。
「だいいち料理のひとつもできないんだから」
「俺だって学生時分はよく自炊したものさ。料理くらいできる」と言って、俺は妻がお酌してくれたビールを飲む。
「昔取った杵柄ってやつだ」
「自炊って言ったってもう四十年も前のことでしょう。ふふふっ」
俺の強がりなんてお見通しの妻は、嘲りとも同情ともつかない笑みを浮かべる。
自信たっぷりで悪戯っぽい妻の表情は、皺こそ増えたが、出会った頃のままとても魅力的に見えた。
「それに――」強がりついでに俺が続ける。
「先に逝くのはきっと俺さ」
これが俺たち夫婦のお決まりのやり取りだった。
◯
ゆでた絹さやを斜めに切っていく。包丁さばきは相変わらずぎこちなく、スライスの幅もバラバラだった。
お世辞にも上手いとは言えないかもしれないけれど、それでも自分ではなかなか悪くないように思えた。
団扇をあおぎ、桶に平たく盛った酢飯を冷ます。ツンとした香りが台所に立ち込め、鼻の奥を刺す。
開け放した縁側の窓からは、気持ちのいい四月の温かい風が吹き込んでいた。季節はもう春なのだ。
「あなたが無事に定年を迎えたらお花見にでも行きましょうよ」という妻の言葉が思い出された。
(俺の鼻の奥には何か映写機のスイッチのようなものがあって、過去の記憶が勝手に脳裡に上映されるしくみなのかもしれない。)
「そうだな。時間ができたら二人でゆっくり過ごそう」と、スクリーンの中の俺が言った。
「定年まであともう少しだ。頑張るよ」
◯
ちらし寿司はやっと仕上げの段階に差し掛かっていた。
細切りにした錦糸卵(少し焦げてしまったのはご愛嬌だ)をできるだけふんわりと散らし、その上にでんぶをふりかける。
黄色と薄ピンクの鮮やかなコントラスト。俺にしてはよくできている。これを見せたらきっとあいつは驚くに違いない。
「ふうん、あなたもやればできるじゃない」きっとそんなふうに言うかもしれない。
◯
妻が突然倒れたのは、俺が定年を目前に控えた冬のことだった。
「まだ老け込むような歳ではないと思っていたけど、身体のことは分からないものね」と妻は病室のベッドで言った。
あのときのあいつの精一杯の苦笑いをよく覚えている。
「大丈夫。もうすぐ桜も咲き始めるころだ」と記憶のスクリーンの中の俺が言った。
「早く退院して二人で見にいくぞ」
叶わないことだと知っていたが、それでもそのときの俺にはそれしか言えなかった。
妻は自分と同じ名を持つその花のことをとても好んでいた。その花が咲き誇るのは、春の盛りのほんの短い間にすぎない。
どうして人はその花のことをこんなにも刹那く、美しいと感じるのだろう?
どうして俺はその花のことを思うだけで、こんなにも鼻の奥がツンとするのだろう?
俺の中にいる「別の誰か」が俺に何かを伝えたがっているような気がしたが、まだよく分からなかった。
だが焦る必要はないように思えた。彼とはきっとこの先、長い付き合いになるのだろうから。
◯
ひし形にカットされた絹さやを散りばめて、ちらし寿司はようやく完成した。
出来上がったちらし寿司をあらためて見てみると、悪くない仕上がりのように思えた。
それぞれの具材の形はいびつでも、一つ一つが何か大切な意味を持ってそこに存在しているように見える。
うん、悪くない。
完成したちらし寿司を、俺は妻の元に運んだ。
「ほら、さくら。美味そうだろう?」と言って俺は仏壇に手を合わせる。
「言っただろう? 俺だって料理くらいやればできるんだ。誕生日おめでとう」
くゆる線香のむこう、遺影の妻が悪戯っぽく微笑んだような気がした。
(了)

ここまでお読みくださり、ありがとうございます❣️
ご感想もお待ちしております❤️
応援がとても励みになります。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。
