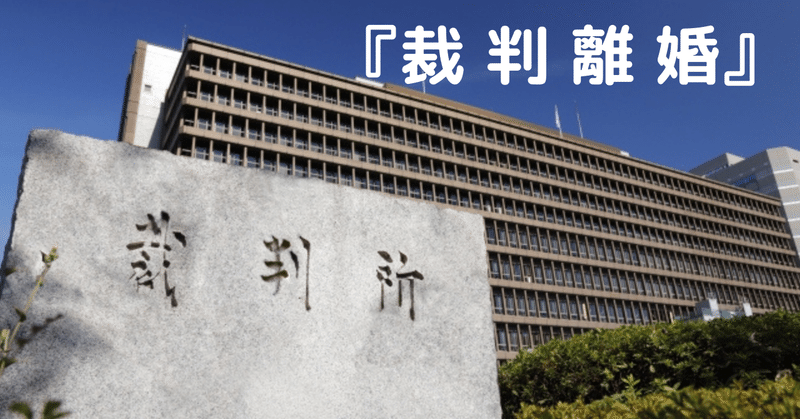
『裁判離婚』(離婚訴訟)で「勝訴」するためのポイント。
こんにちは、あやねです。
今回は、『裁判離婚』(離婚訴訟)について書いていきますね。
『裁判離婚』と聞いただけでも精神的な負担になりますよね。
裁判は経験をしたことがなく緊張してしまいますね。
落ち着いて裁判を受けらるように詳しく書いていきますね。
離婚裁判は多額の費用と時間が必要で、心理的負担も大きく、判決には必ず従わなければなりません。
裁判を冷静に対応するためにも、裁判期間を落ち着いて生活するためにも離婚裁判の流れを知ることで精神面の負担は少なくなります。
裁判は、公平さを保つために基本的には公開され誰にでも傍聴ができますが裁判に集中して行って頂きたいと思います。
【結果】
・裁判離婚について知り不安を取り除き負担が軽減できますよ。
・裁判離婚を冷静に対応できます。
・裁判離婚で勝訴することができます。
【このようなあなたに読んで頂きたい】
・裁判離婚を考えているあなた。
・裁判離婚が決まっているあなた。
・裁判離婚について知らないあなた。
【得られる成果】
・離婚裁判のポイントを知り優位に立ち勝訴することができます。
・裁判離婚について知り裁判中の生活を不安なく過ごすことができます。
・離婚後に、養育費等取り決めたことが守られない場合は、裁判所に申し立てを行い、強制執行による財産の差し押さえができて支払いを受けられ安心できます。



・収入印紙 (請求により異なりますので訴状をだす家庭裁判所に確認してくだい。(郵便局などで購入できます)
・切手 (訴状を提出する家庭裁判所に確認してください)
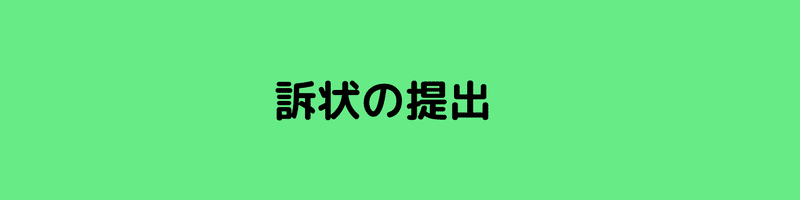
夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所か離婚調停を行った家庭裁判 所に提出をします。

【必要な書類】
・訴状(2部)訴状書式は裁判所ウエーブペ
ージのこちらから入手できます
➡2019_rikonsojou_743kb.pdf (courts.go.jp)
訴状書式の記入方法はこちらからご覧になれます
➡2019_rikonsojou_rei_899kb.pdf (courts.go.jp)
・夫婦の戸籍謄本(原本とコピー)
(本籍地の市区町村役所で入手してくださ
い)
【訴状記載内容について】
・訴状に記載する内容は訴訟戦略上とても重要になりますので弁護士に相談することも考えた方がいいと思います。
・裁判所で訴状の確認を行い、補正を求められることもあります。
【訴訟を行う条件】
民法770条で規定されている法定離婚事由は以下となります
・配偶者の不貞行為
(不倫行為)
・配偶者から悪意で遺棄
(見捨てる、物理的、経済的、精神的の意味も含まれます)
・配偶者の生死が3年以上明らかでない
(音信、消息が3年経過、生死不明の
客観的証拠がある場合)
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
(医師の見立てなど慎重に行われます)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(証拠などを用いて判断されます)
これらに該当しても必ず離婚が認められるということではありませんので注意してくださいね。
婚姻の継続が相当であると認める場合は離婚の請求を認められないないこともあります。
※【無料】LINE講座 受付中!
詳細は下記をご参照ください。
無料プレゼントも用意しています。

【訴状を提出してから】
裁判所で裁判の期日が決められ相手方に(被告)に口頭弁論期日呼び出し状、原告が提出した訴状の写しが届く。
⇩
被告は原告の作成した訴状をみて、反論の答弁書を作成し第1回期日の1週間前までに裁判所と相手方に提出します。
(当日でも提出できますが期日までには提出しましょう。
⇩
間に合わない場合は争う旨だけでも記載した答弁書を提出し詳しい反論はあとから準備書面として提出できます

【裁判が始まる目安と流れ】
・訴状提出日から1~1ヶ月半後くらいに行われます。
・期日呼び出し上に記載された法廷に出頭し口頭弁論が行われます。
・訴状(原告作成)、答弁書(被告作成)の内容を裁判所が確認し、問題点を整理して原告と被告それぞれの反論を準備書面にまとめて提出するよう指導されます。
・準備書面は、期日の1週間前までに裁判所と相手方に提出します。
・次回の日程を決め、次回期日までに準備することの確認が行われます。

【2回目以降の裁判は】
・約1ヶ月の間隔で行われます。
・2回目以降は第1回期日のような法廷での口頭弁論ではなく準備手続き室で「弁論準備手続き」が行われることが多いようです。
・弁論準備手続きでは準備書面により争点と証拠を整理します。
・弁論準備期日での話し合いの結果で和解が成立し、和解期日が開かれ和解が成立すれば裁判は終了となります。
・弁論準備期日で和解の見込みがないとなると、証拠調べをおこなっていきます。
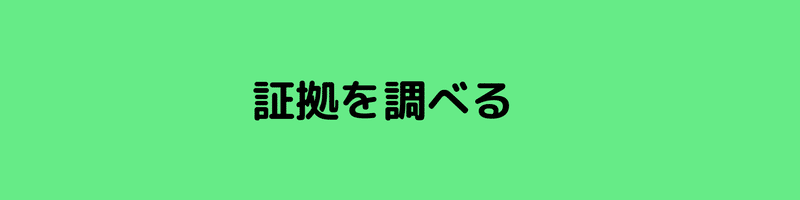
【証拠になるもの】
・書類や資料
・本人尋問、証人尋問
・証拠はとても重要な資料となるので、小さなことでも準備しましょう。
・証拠を持っている場合は有利であり、判決には強い強制力があります。
・離婚訴訟では、この段階で本人尋問が行われることが多いようです。
・証拠調べが終わった段階で和解の見込みがなく裁判官が提出書類や尋問の内容に納得したうえで判決が出ます。


【本人尋問の流れ】
・尋問を受ける本人の言い分をまとめた
陳述書を提出します。
1. 人定質問
氏名、住所を聞かれ、本人であることを確認されます。
2. 宣誓
「真実だけをありのままに話す」という誓約書に記名押印し宣誓書を朗読します。
3. 尋問は、原告(主尋問)、被告(反対尋
問)の順で行われます。
訴訟代理人がいない場合は、主尋問は陳述書を基に裁判官が行い、相手方への反対尋問は本人が行うこととなります。
また、裁判官から「補充尋問」があることがあり、さらに再主尋問、再反対尋問が行われることもあります。
【本人尋問を成功させるポイント】
・これまでの書類を見直す
これまでの書類と尋問での回答が食い違わないようにすることが重要です。
記憶違いや矛盾は誰にでもありますが、食い違いがあると「嘘をついているのでは?」と思われてしまいますので注意して下さいね。
書類を確認することは重要ですね。
・本番のシュミレーションをする
経験がないため緊張してしまいますのでシュミレーションすることでイメージがついて緊張をある程度おさえることができますよ。
イメージトレーニングを行い自信を持ちましょう。
・聞かれたことだけを端的に答える
ながながと説明することや理由を付け足すことなどにより主張に論理的な一貫性がなく説得力がなくなり裁判官に伝わりませずん。
落ち着いて対応することが大切ですね。

・嘘をつかない
「ちょっとした嘘」でも矛盾が生じ不利な立場を招いてしまう危険性があります。
嘘をつかないと宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは裁判所の決定で過料に処されることがあります。(民法209条)
真実が大切です。
嘘はつかないようにしましょう。
・わからないことを無理やり答えようとしない
「質問されたことに答えなければ」と思う気持ちはわかります。
質問の意味がわからなかったり、記憶が曖昧なこともあると思いますが無理やり答えようとすると、信用を無くし不利な証拠となってしまう危険性があります。
無理に答えずに「わかりません」「覚えていません」「質問の内容がわかりません」などと素直に回答しましょう。
言葉に気をつけないと不利になってしまいますので注意がひつようです。
・冷静さを保つ
相手側からの質問に気分を害することもあると思います。
わざとの場合があり、冷静さを失わさせて不利となる回答を引き出そうという意図があると考えられます。
感情的にならず冷静に答えるようにしてください。
発言する前に深呼吸をして落ち着きましょう。

・弁護士との打ち合わせを綿密に行う
本人尋問の時は緊張してしまいますので一人で何とかしようと思わずに弁護士に頼りましょう。
綿密な打ち合わせをすることで準備もしっかりとでき落ち着いて対応できるますよ。
不安なことは確認しておきましょうね。


【裁判の終了は2つあります】
裁判の終了には以下の2つがあります。
・判決
・原告の離婚請求を認めるか、棄却するか。
・和解
・原告と被告が、判決を行わず、話し合い
で解決するという結論に至った場合
・裁判官が話し合いで解決すべきとの結論
に至った場合
・裁判官が仲介役となって話し合いをすす
め、双方が納得できる解決策が見つかったら和解成立となります。
※判決に不服がある場合は、判決書が送達された日から2週間以内に高等裁判所へ控訴すると裁判が行われます。


【判決後の控訴】
判決で決着した場合は、判決書が送達された日から2週間以内に控訴しなければ判決が確定し同時に離婚も成立します。
原告が判決確定証明申請書を提出し判決書と判決確定証明書を受け取ります。
和解で決着した場合は、裁判所によって「和解調書」が作成されると同時に離婚が成立します。


【判決で成立した離婚届けについて】
判決で決着した場合、判決確定後10日以内に、「判決書謄本」「判決確定証明書」「離婚届」を市区町村役所に提出することとなっています。
この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
【和解で成立した離婚届について】
和解で決着した場合、和解成立後10日以内に、「和解調書謄本」「離婚届」を市区町村役所に提出してください。
この場合も、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
期日を過ぎないように気を付けてくださいね。

【終わりに】
①訴状の提出から提出後の流れ
②訴訟を行う条件
③重要となる証拠について
④裁判離婚の流れ
⑤尋問を成功させるポイント
⑥離婚成立、不成立について
⑦判決は2つある
⑧控訴する期日
⑨離婚届の方法、提出期限
などについて書いてきました。
ご理解いただけたでしょうか?
長い期間になると思いますので、普段の生活では気分転換しながら精神面を落ち着けて冷静に過ごしていただきたいと思います。
「役に立ったよ!」という方は、私の”継続の力”となりますのでスキ♡をお願いいたします。
※【無料】LINE講座の登録はこちらから!
『子供に辛い思いをさせたくない』
『離婚をしたいけど誰にも相談ができない』
『ひとりで子育てができるのか不安』
『先のことが不安』
など悩まれているシンママが子供と笑顔で生活ができるようになる講座となっています。
ご質問や悩み相談も対応いたします。
登録簡単で無料ですのでどしどしご登録お待ちいたしております。
無料プレゼント! 20名様限定
【無料】LINE講座ご登録の方に2つのプレゼントを差し上げます。
詳細はクリックでご確認をしてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
