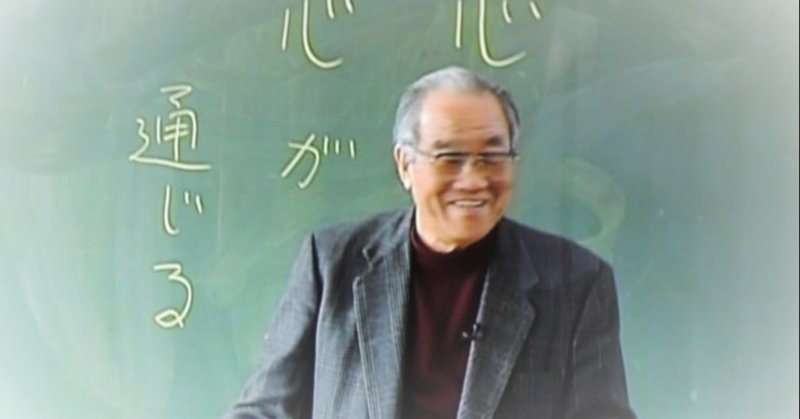
河合隼雄を学ぶ・8「母性社会日本の病理③」
(前号の続きです)
ところで、この本の第二章として、【ユングと出会う】という章が挟まっている。日本社会の原理を、ユング派の視点から考察するための前提として必要な章である。ユング派の心理療法家である河合隼雄には、ユングに関する著書が多数あり、今後紹介している機会も多いと思われるので、今回は、この本の中で印象的な部分を抜粋するにとどめたいと思う。
【第二章:ユングと出会う】
・夢こそは、人間の内界に至る王道であり、ユングはその心理療法の技法として、夢分析をもっとも重視した。
・不可知なものを信じて、それに身を捧げようとするときに味わう畏れ・畏怖の感情こそ、現代人がほとんど忘れ去ってしまったものではなかったろうか。
・ユングは意識と無意識の「相補性」ということを強調する。人間の自我の意識体系があまりに一面的なものとなるとき、無意識内には、それを補償するような心的内容が集まってひとつの布置(コンステレーション)を形成し、その補償性によって自我がより高次の統合へと向かうような働きをする。その無意識の動きをキャッチできるのが夢分析である。
・無意識の心の働きの中に、より高次な全体性へと志向する傾向を見出そうとしたのである。その考えは、人間の無意識内に、人間の意識・無意識を含めた心の中心性=「自己」が存在することを仮定することとなった。
・確かに、我々の知っている「私」というものが、もっと深い心全体の中心へと結び付けられ、根付いていき、「私は私だ」と確信をもって言えるような体験が存在するものである。そのような心の中心をユングは「自己」と呼び、我々の意識の中心である「自我」と区別したのである。その「自己」の働きが、シンボルとして顕現されたもののひとつとして、曼荼羅が存在すると考えることができる。
・東洋は、自我よりも自己(あるいは意識よりも無意識)の重要性を強調してきたとユングは考える。
・ユングは無意識の破壊的な性質をもちろんよく知っているが、その創造的な側面をも協調する。
・ユングによれば、退行とは心的エネルギーが自我から無意識のほうへ流れる現象である。一般的に退行現象は、病的現象を指すものと考えられているが、ユングはこのような退行がいつも病的なものとは限らず、むしろ創造的な心的過程には必要なものであることを早くから指摘している。退行によって自我が無意識と接触したときに得るものは、病的なもの、邪悪なものもあるが、未来への発展の可能性や新しい生命の萌芽であることも考えられる。ただし、退行が「創造的退行」となるためには、そこに新しい要素が出現し、主人公はそれに対して、相応の努力を払わねばならない。
・章の最後に、ユング研究所での河合隼雄の体験が紹介される。最終の資格取得試験まで、トントンと順調に学問を進めてきた河合隼雄が、最後の最後、先生たちと徹底的に戦うのである。「自己の象徴としてはどんなものがありますか」という口頭試問に対し、「曼荼羅」とでも答えればよいとわかっていながら、河合隼雄は「世界中のもの、すべてのものです」と答える。そこから試験は対決の様相を呈し、途中、何度も互いに軌道修正しようと努力するものの、雪道でスリップをはじめた車のように、衝突を避けることができなかったという。河合隼雄は、何年も必死に努力してきたあげく、ユング派の資格が与えられないかもしれないと悔恨の気持ちを覚えつつも、すっきりとすがすがしい気持ち、「ごまかし」をせずに貫いた自分が嬉しかった、と語っている。結果的に、研究所は激論の末に免状をくれるのだが、すべてが丸く収まったあと、先生のひとりが、河合隼雄にこんなことを言う。
「まったくうまくできているね」「ところで、そのすべてをアレンジしたのは誰だろう」
大切なことは、このようなアレンジメントが存在すること、そして、それに関わった人たちがアレンジするものとしてではなく、渦中において精一杯自己を主張し、正直に行動することによってのみ、そこにひとつのアレンジメントが構成され、その「意味」を行為を通じて把握し得るということであろう、と河合隼雄は振り返っている。
そして、そのことを体験に根ざして知ることが、分析家になるための条件のひとつでもあったと、河合隼雄はいっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
