
かわさき市民アカデミー(24前期)自由民権運動講座 第3回R6.5.29を受講して
今回は、講師のコレクションである私物を惜しげもなく回覧してくださりながらの講義でした。
自由民権運動における結社と政党 その1(結社編) 大正大学名誉教授・特遇教授 全国自由民権研究顕彰連絡協議会代表 福井淳(ふくいあつし)
講義がはじまるとすぐ、2本のYouTube動画をご紹介された。
両シンポジウムで、福井先生がご登壇され、講義されている。
2人の自由民権家シンポジウム動画
河野広中
河野広中、は福島県で石陽社を立ち上げた人物。福島県三春町から石川町に移り住んだことから、没後百年シンポジウムは両町で二日間行われた。(福井先生が登壇されたのはin石川のほう。)
この動画で、一点気になったのは、高校生が作文を読むのだが、河野広中「さん」とさん付けしていることだった。最近は、学校でもポリコレで、呼び捨てはNGという話をきくので、そのせいかな?と。
河野広中は、杉田定一(自郷社)と同様、農村部の運動からできた結社を作った人物と分類。(在地民権)
鶴松利光
もう一人、利光鶴松(としみつつるまつ)は、小田急電鉄の創始者として有名だが、実は自由民権運動の資金調達のため、明大で法律を学び、弁護士業務の傍ら、五日市憲法草案に関わっていたという。
渡瀬裕哉氏がスポットライトを当てたいタイプ、産業を興した自由民権家の一人、なのでなないだろうか。
日本初の結社は埼玉県熊谷で
福井先生第1回目の講義は「結社」についてのお話。私もよく分かっていなかったので興味深く聞いた。
日本で最初にできた結社は、先生の調査によれば、1975年2月埼玉県熊谷の七名社に間違いない、とのこと。これが上記で紹介した、石陽社、自郷社、そして高知の愛国社と合流して「自由党」結成に繋がった。
都市民権の結社はシンクタンク的存在?!
都市民権は全国に
都市民権とはいわゆる、都市の知識人たちの運動である。
現在(令和6年6月)は来月の都知事選を控えて立候補者の批評が飛び交っているが、「都市」とは、人口密度が高く、非農業地帯で、地域のセンター的、結び目的役割を担う場所、というのが社会学の古典的な定義だ。
東京以外の都市、は大阪、京都、横浜、神戸、名古屋、水戸、仙台、新潟、岡山。。とそれぞれに運動が起こり、結社が結成されている。
東京で有名な結社は、福沢諭吉の三田演説会、と沼間守一(ぬまもりかず)の嚶鳴社(おうめいしゃ)である。
東京の双璧 三田演説会と嚶鳴社
講義の中で、いくつかトリビアがあって面白かった。
嚶鳴社の「嚶」は「鳥が友を求めて鳴くときの声」という意味の字。
嚶鳴亭、という建物が那須の御用邸内にある。
三田演説会の拠点だった慶應義塾は英語学校だった。
Speechを「演説」と訳して広めたのは福沢諭吉。
知識人の会だからか、入会するのには「精選制」という厳しい入会条件を満たす必要があった。その点、誰でもウエルカムな在地結社(農村部の石陽社など)とは対照的だった。
そのときの会則集を福井先生がコレクションされていて、回覧していただいた。



沼間守一の嚶鳴社
驚いたのは、1979年に規制ができるまで、政府の役人も自由民権運動に加わっていたことだった。
沼間自身が大変優秀な人物だったので、旧旗本として板垣官軍と戦ったが、維新後は逆に板垣土佐藩の改革指導者として招かれた。その後新政府に入り、法律を収め、政府役人のまま自由民権運動に加入した。77年には嚶鳴社を設立し、『嚶鳴雑誌』『東京横浜毎日新聞』を発行。当時の主要メディアを自前で持ち、発信力が凄かったそうだ。


その後、全国に支社を展開。
沼間自身は東京府会にも進出。
演説が素晴らしく、「政界の団十郎」の異名まであったそうだ。
ぜひ、聞いてみたいものだ。
当時、私も生きていたらきっとファン♡になっていたに違いない笑
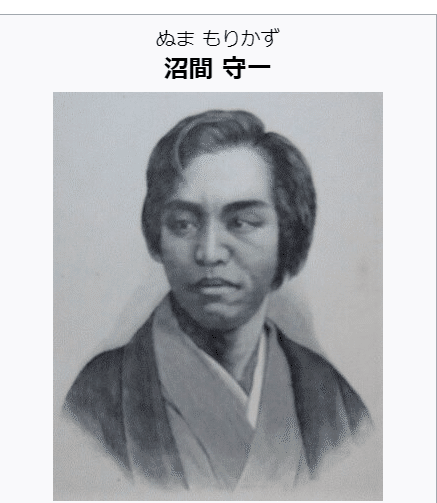
嚶鳴社の思想
沼間は、憲法制定を政府と民権派で「連合」して「国会憲法調査委員」を設置しておこなうことを提唱したところが特色、と福井先生の論。
政府の国会開設、憲法制定の遅れを批判する民権論もあったが、上記のような建設的な提案をした、大変柔軟な思想でリーダーシップをとったということである。
ほか、大変興味深かった沼間の主張を要約する。
・府知事・県令は自由民権運動を規制するのではなく、全国に高揚する民権運動の実情を奏聞する(天皇陛下に伝える)ことが役割だ、と主張。府知事・県令は国民の立場に立て、というメッセージを新聞で主張した。
・イギリスの自治制度「コーポレーション」※にならい、
東京15区、横浜、神戸などは他と区別し、「独立自治」の権限を与えるべきだ、という都市制度論を主張した。これは、88年(明治21)の市制町村制の先取りだった。
※イギリスの自治制度「コーポレーション」 p25参照
https://www.jlgc.org.uk/jp/information/img/pdf/J2011.pdf
現在、川崎市が特別市法制化を主張しているが、この時代にも「独立自治」が主張されていたことは大変興味深い。
このように、役人や政治家、知識人の顔をもつリーダーが、定期的なメディアの発行、演説会の企画、政治への提言など行った「嚶鳴社」の役割は、
救国シンクタンクの活動と重なるところも多々あるなぁと感じた。
今度、倉山満理事長や、渡瀬裕哉研究員に質問する機会があれば、
ぜひ伺ってみたいと思った。
おわりに
今まで、結社、のイメージがいまひとつつかめずにいたのだが、今回の講義でだいぶ理解が進んだ。一国民の会の自由民権運動動画講座での、民権運動の分類と、福井先生の分類、用語が少し違う点もあった(視点の違いにより、分類も異なる)ので次の機会に確認したい。憲法制定、地方自治など、いまだ継続中の課題であるが、このような歴史を経て今に至ることを知り、あらためて先人の努力に感謝し、その思いを引き継いでいきたいと思った。
減税あやさん
よろしければサポートをお願いいたします!行政研究、地域の活動へ生かして参ります💕
