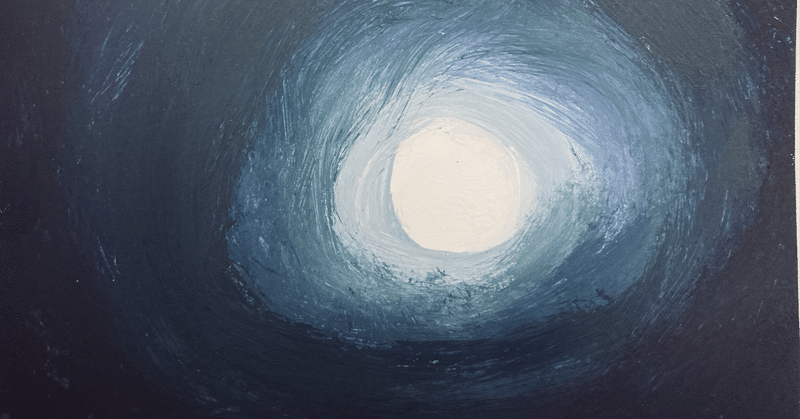
『せめて先にしんでくれ』
登場人物
・葛葉(くずは)アミ
・清村(きよむら)サヤカ
【本編】
100万年後には、みんな死ぬ。100万年後には、この地上の人類がみんな死んでいく。そんな果てしない数値の物差しは、実感がなくて、使い勝手が悪い。
あたし、葛葉アミは、手に取りやすい100均で買ったようなやすい物差しで、今日も線を引く。
✳︎
彼女の、白い砂浜のような背中をそっと指でなぞる。骨ばった肩甲骨の間に水を流すように、指をまっすぐ下ろしていく。触れた指先の感触は冷たい。サヤカは背中を向け、小さな寝息を立てている。少し体を起こして顔をのぞくと、そこには穏やかに眠る綺麗な顔立ちがあった。
「……まつげ、長いな」
瞑っている目元。強調されたまつ毛に思わず感想が溢れる。人の気も知らないですやすやと眠るサヤカに、すこし冷たい目線を送る。……いけない感情だ。忘れよう。速やかに自分の寝場所に戻り、きゅっと毛布に肩を埋めた。
「ん……アミさん、まだ、起きてるの?」
すこし強く引っ張りすぎたせいか、サヤカが起きてしまった。ゆっくり寝返ると、サヤカは、あたしの顔を覗き込んでくる。半目の瞳が、暗闇の中で、猫の瞳孔のように光る。
「起こしちゃってごめん。なんだか、寒くて……」
「ああ、もしかして、取っちゃってました? 毛布」
「いや、そんなことないよ。大丈夫」
「…二人で寝るにはちょっと小さいですよね、このベッド」
「そういうムード作りもあるんじゃない 小さい方が肌と肌が密着して燃える、みたいな?」
「アミさん、ちょっとおじさんくさい」
「歳を重ねて、生き遅れた女の戯言だよ」
「……その発言、なんか嫌です」
サヤカは目線を落として、そのままあたしの胸元に顔を埋めた。表情は見えない、でもわかる。サヤカの拗ねた態度。あたしは彼女の髪を撫でる。
「……安いホテル選びすぎましたかね。私、そういうの、全然わからなくて」
「そんなことないよ。どこに入っても同じだよ。目的が一緒なら」
「……私、今日、アミさんに迷惑かけてばっかりですね」
「迷惑じゃない」
「ほんとうに?」
「本当」
「一緒にきて、よかったですか?」
「もちろん。こんなに可愛い子といられるなんて、生きてみるもんだね」
「そうですよ?アミさんは、生き遅れてなんかないです」
「そこ、引っかかってたんだ」
「アミさんが、生き遅れているんだとしたら、この世界の方が間違ってるんです。こんな素敵な人を置き去りにするなんて、どうかしてます」
「ロマンチストだね、きみは」
「夢見る少女と言ってください」
サヤカからは、陽だまりの匂いがする。サヤカといる世界は、青々とした草原の中にいるみたいで、現実の喧騒を忘れさせてくれる。だからこそ、無性に乱される。内側から抑えきれない淀みにえぐられそうになる。サヤカの目が、あたしを捉えた。
「……ねえ、アミさん、何か考え事してました?」
不意に言葉の針が刺さる。動揺を隠すように、悟られないように、落ち着いた声色でその針を引き抜いていく。
「…いいや、なにも」
「……アミさんは、大人だね」
サヤカに他意はなさそうだった。その証拠に、サヤカはそっとあたしを抱きしめ、優しい眼差しを向けた。あたしもまた、返すように微笑む。
(……ねえ、サヤカ。大人になるってね、もう戻れない、ってことなんだよ)
サヤカの鼓膜に届かぬように、胸の内で呪うように、そう唱える。使い慣れた物差しは変えられない。たとえそれで引く線が、頼りないものだったとしても。夜は、行き先のみえないあたしたちを乗せて、走り続ける。
✳︎
「ねえ、アミさん」
「なに?」
「今日はいっぱい歩いたね」
「歩いたね」
「足、痛くない? 私は、痛い」
「ヒールが高いんだよ。スニーカーは楽だぞー」
「まさか今日、こんなことになるとは思ってなかったから」
「物語は突然だよ。悪者にお姫様が攫われるのだってそうじゃん。予告なんかしないでしょ?」
「まあ、そうかもしれないですけど」
「だからいつ、何が起こってもいいように、準備しておかないと」
「攫われる準備を、ですか?」
「そこはいいの」
「なんか、目、覚めてきちゃいました。アミさんのせいですよ?」
「足が痛いから、でしょ?」
「ちがいます、もう…」
サヤカは、ぐいぐいと体を寄せて来る。肌の柔らかさが、生命の温度を伝える。夢のようなぬくもりが、彼女とふたり、見知らぬ大地で共にしていることを実感させる。
「……ここ、どこなんでしょうね?」
「……さあ。あたしもきたことないから」
「神奈川……静岡……もしかして、伊豆とか?」
「ばか。そうだったらホテル探すのに苦労したりしないでしょ」
「スマホ、会社に忘れてこなければなあ」
「財布さえあれば、なんとかなるって」
「そうやって、お金に物を言わせて」
「派手に使っても死にはしない。そのための社会人だよ、サヤカくん」
「社会人かあ……。アミさんは、普段、旅行とかいったりします?」
「ずっと東京。生まれも育ちも。暮らしも仕事も。旅に出たのは、学生時代の修学旅行か、出張だけ」
「えー。飽きたりしないんですか? 同じ場所にいて」
「その感覚はないかな。むしろ、遠い場所にいくほうが怖いよ」
「どうして?」
「自分の生きている場所には、匂いというか、記憶が染み付くんだよ。時間を重ねていくと、ここが自分の居場所なんだって思える。だから」
「よくわからないです。居場所があるから旅にでられるんじゃないですか。私は好きですよ、旅。普段とちがうものに触れることで、刺激も生まれるし、知識も経験も増える」
「でもさ、ずっとその場所にいるわけじゃないでしょ? いずれ帰らなくちゃいけない。…一瞬で過ぎ去ってしまうものなんて、信じられないよ。あたしは」
「心配性なんだ?」
「よく言えばね」
「……じゃあ、どうして私と、ここに来たんですか?」
安全地帯を望むのは生物の性だ。誰だって危険を冒したくない。だからこそあたしは、拙いながらも、一般的な社会人という線を引いて、それを辿ってきた。
「ねえ、アミさん」
サヤカは、あたしの手を取る。心音にまで響くような熱。この温度に、あたしはきっと、ほだされてしまっている。
「さあ、どうしてだろうね」
曖昧な返事でごまかしながら、嘘の指先で、サヤカの指を絡め取った。サヤカは、それ以上言葉を求めることはなかった。
✳︎
「喋ってたら、喉乾いちゃいました」
サヤカは、ベッド横のライトをすこしつけると、毛布の外へ出て、備え付け冷蔵庫を物色し始めた。ベッドに取り残されたあたしもまた、上体を起こして軽く伸びをする。
「あ、結構充実してるんですね、ここの冷蔵庫。アミさんも、何か飲みます? 」
「水でいいよ」
「別に遠慮しなくてもいいんですよ。ここは、私が払いますから」
「いや、水が飲みたいな。あとで歯磨くの面倒だし」
「そうですか。じゃあ私はどうしようかな……コーラ? あ、でもミニッツメイドもいいなあ」
「……ねえ、ひとつ聞いてもいい?」
サヤカの、無邪気な背中を眺めるのに耐えられなくなったあたしは、吐き出すように言った。
「明日には、戻るんだよね? 会社 」
「…ふふっ、どうして疑問形なんですか?」
「いや、確認したくて」
「……アミさん次第ですよ。だって、私から誘ったんですから。私の気持ちは……わかるでしょ?」
サヤカは、あたしを見つめる。ベッドの中にいるあたしと、外にいる彼女。色のない時間が流れる。
「…………」
「…………」
「…………」
「…………だんまりなんですね。ちょっと寂しいな」
「…………帰ろう」
「それでいいんですね?」
「…………帰らなきゃ。部長に謝ろう。仕事、サボってごめんなさいって」
「……やっぱり私も、水にしようかな」
「……ごめん」
「意気地なし」
清村サヤカは会社の後輩で、とても優秀だった。社内での成績も常に上位をキープし続けており、このまま行けば、それなりのポストが約束されている。一方あたしは、ルーティンワーク以上のことはしない、窓際手前の位置で仕事しているような人間だった。そんな彼女とあたしが、恋に落ちていいはずがない。
これはハッピーエンドだ。あたしはあたしのまま、サヤカはサヤカのままでいられる。互いの身の丈にあった物差しで線を引ける。その線はまっすぐで、交わらなくていい。
✳︎
明け方。ふたりで見知らぬ街を歩く。まだ夜から目覚めたばかりの風景は、燻んだ青色の世界だ。前を歩くサヤカの後ろを、あたしは適切な距離をとってついていく。
「……あ、海だ」
サヤカが、ぼそっとつぶやく。見るとたしかに、そこに海はあった。しかしその場所は、あたしたちが向かっている駅とは反対方向の、道の果てにみえたものだった。
「行きたかったな、海」
目を細めてそう言ったサヤカの横顔を、あたしは生涯忘れることはないのだろう。
100万年後には、みんな死ぬ。100万年後には、この風景も思い出も消える。サヤカと会社で過ごした日常も、休日にデートしたことも、一緒に映画を見たことも、二人で過ごしたすべて。100万年後という物差しなら一瞬だ。なんてことはない。すぐに過ぎ去っていくだろう。
……でも。もし叶うなら、この惨めさがカケラも残らないように。
せめて、君より先にしんでくれ。あたし。
※2019年4月初出/2023年8月更新
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
