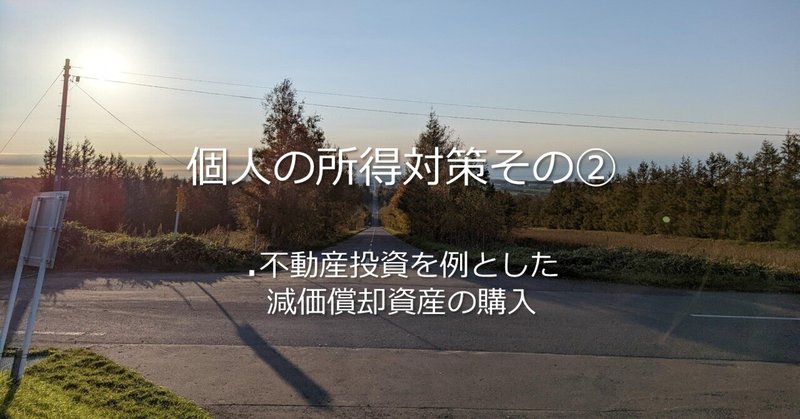
個人の所得対策その②
前回に続きまして、個人の所得対策について続けてお話します。
前回では所得対策の意義は節税ではなく手元キャッシュの安定だというお話をさせていただきました。↓前回の話
今回から、具体的に所得対策の原理と方法をお話ししていきたいと思います。まずは、最もポピュラーな考え方から。
減価償却資産を購入して減価償却費を計上する
法人では当たり前に行われていることですが、個人の場合は工場や工作機械などの設備を持つ法人ほどの規模にならなかったり、そもそも設備と呼べる設備が少なかったりしますので、そこまで計算づくで減価償却資産を購入しよう、という方は少ないように思います。
建物の建築・購入や、その付属設備、また大規模修繕の内容などは、個人における減価償却資産の代表格です。
まずは減価償却を理解しましょう
減価償却の仕方は2種類。定率法と定額法での減価償却が許されています。ざっくり、使い始めに大きく減価償却するのが定率法。一定期間一定価格減価償却するのが定額法です。
設備には適用すべき耐用年数が定められており(※1)、その耐用年数に応じて、定額法・定率法の償却率もまた定められています(※2)。
※1 設備の耐用年数
※2 減価償却資産の償却率表

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf
流行りの不動産投資のケースを用いて、耐用年数が違うとどうなの?という話をしてみます。
こんな前提でシミュレーションしてみましょうか。
ファンタジーですから現実的な数字では無いのはご容赦いただいて。
<前提>
・2億円の賃貸アパート(共同住宅)を購入
・内訳は土地代1億円、建物代1億円
・A=木造(耐用年数22年)、B=RC(耐用年数47年)
・年間家賃1,000万円
・年間費用諸々で15%
・借入金額1.8億円
・金利0%
・借入期間30年
・所得税+住民税=50%
まずA=木造の場合
金額単位=千円

B=RCの場合
金額単位=千円

同じ金額を投資したはずですが、Aは22年目まで黒字。Bはずっと赤字ですね。違いは減価償却費、ということになります。
実際は大規模修繕あり・細かな修繕あり・それもまた減価償却費として計上する期間あり・家賃も一定ではない為、上のシミュレーションはファンタジーです。どっちが良いという話ではなく、「耐用年数で減価償却費が変わる」ことと「減価償却費でキャッシュフローが変わる」ことを掴んでいただけましたら、OKです。
不動産の話をしましたので、ついでに中古だったらどうなるのか?ということを話しておきましょう。
国税庁のHPに考え方が載っていますのでご覧ください。
※資本的支出というのは、イメージ建物の改良工事をして建物の寿命を延ばした、とか。その際の工事費用などが資本的支出と言います。固定資産の耐久性を高めて価値を高める支出、と説明されるようです。
中古の試算を購入するというと、シンプルに簡便法を使わせてもらえそうです。実際には、一回一回税理士に相談して下さいね。
上の考えでいくと、例えば築23年の木造アパートは法定耐用年数の全部を経過した資産ですので、その法定耐用年数22年の20%に相当する年数=4.4年。1年未満の端数は切り捨てですので、4年ということになります。
前述のシミュレーションに当てはめると、4年間だけキャッシュフローがすごく良くなりますね。所得がマイナスになってますから、4年間だけ今までよりも税負担が軽くなります。

ただ、5年目以降は償却しきってますから、キャッシュフローは一気に悪くなります。キャッシュフロー悪くなったから売却するか…という時には建物の簿価は備忘価格の1になってますから、建物部分はほとんど売却益になりますから、譲渡税がしっかりかかります。長期譲渡で20.315%、短期で39.63%ですから、まあ痛そうですね。
この期間だけ所得が上がるから所得を下げたいとか、この期間だけキャッシュフローが悪いけれども5年目から良くなるというような場合に、使えるかもしれません。
事情、状況に応じてふさわしい条件があるでしょうから、そういう目線で不動産を選ぶのも面白いんじゃないでしょうか。
一応、そこまで考えている人を今まで見たことはありませんが。
一例として、流れで中古不動産を取り上げてましたが、次のその③では航空機リースを取り上げていきたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
