
お問い合わせメールをビジネスチャットに転送することで向上する対応効率
企業間で行われるコミュニケーションは、今もなお、圧倒的に電子メールの利用が多く、ホームページ等のお問い合わせを受け付ける方法も、フォームの入力内容を電子メールで受け取るといった利用方法が多いと思います。
このように受け取ったお問い合わせメールを、一人の社員が返信対応している場合は、そのまま回答を返信すれば良いかもしれません。また、カスタマーサービス等、事象毎に回答状況や回答履歴を厳密に管理しなければいけない場合は、事象毎に管理が可能なチケット管理システムを導入した方が良いかもしれません。
しかし、大半は、複数の社員が内容を確認し、担当者が返信するといったように、コラボレーション要素を含んだ社内やりとりを経て回答される場合が多いと思います。このコラボレーションの部分をビジネスチャット上で行うことによって、お問い合わせ対応に関する業務フローの効率性が大きく向上する可能性があります。
お問い合わせメールをビジネスチャットに転送することによる利点
議論内容が埋もれない
電子メールでは、署名をつけることが一般的になっています。よって、電子メールの場合、一言だけコメントを送った場合、メールの半分以上が署名になってしまい、本文であるコメントが埋もれてしまうことも多くあります。また、引用を繰り返すことで、議論の内容よりも、メールの返信におけるヘッダーの内容で本文が占められてしまい、議論の内容を一目で把握しづらいといった問題も発生してしまいます。ビジネスチャットでは、細かいメッセージのやりとりでも時系列でわかりやすく表示されるため、議論内容に集中することができます。
スタンプ機能活用で内容確認
回答内容を作成し、他の同僚に問題ないことを確認したい場合、メールでは、問題ありません等、コメントを返信しなければいけませんが、ビジネスチャットの場合、スタンプ機能を利用し、ポジティブなスタンプを付けることで、内容に問題ないことを確認したという意思表示になります。そして、問題を発見した場合のみコメントを行うという運用を行うことで、無駄を省いた効率的なコミュニケーションが可能です。
議論中のメール誤送信の心配がない
例えば、取引先から送信されたメールについて対応等を協議する場合、そのままメール上で議論を開始してしまうと、取引先のメールアドレスが返信先に入っているにも関わらず、メールを送信し、社内向けのメールを外部に漏らしてしまうといったリスクが発生してしまいます。議論の場を、ビジネスチャットという外部の人がアクセスできない場所に移動することによって、社外の人に誤って社内向けのメールを送ってしまうという、メール誤送信リスクを回避することができます。
議論の場所を明確に分けることができる
上記と同様ではありますが、ビジネスチャット上を、メールの対応に関する議論の場、メール上を、お客様や取引先とのやり取りの場と、明確に分けることにより、後から、内容を見直す際に、外部とのやり取りと内部でのやり取りの切り分け作業に手間をかける必要がなくなります。
議論に必要な人をいつでも招待
メーリングリストを利用している場合、メンバーをメーリングリストに加えるためには、管理者にいちいち依頼をしなければいけないといったケースも多いかと思います。ビジネスチャットのパブリックチャネルであれば、必要だと思った人をいつでも招待できるので、より多くの人を巻き込んで、業務を遂行することもできるようになります。
Slackにてメールを転送する方法
Slackを利用している場合、Slackのチャネルに電子メールを転送する方法が複数あります。一つは「Email」というアプリを利用する場合です。ただし、これは、有料版のSlackを利用していなければ利用できません。この「Email」Slackアプリは、転送したいチャネルに送信できる電子メールアドレスを発行します。この電子メールアドレスを例えば、お問い合わせフォームのメール送信先に設定しますと、メールが届く度に自動的に、指定したチャネルにメールの内容が送信されます。ただし、メールの容量に制限がありますので、お問い合わせフォームの転送先としてというように、メールの容量の上限が予想できるような場合での利用が良いと考えます。
このアプリを利用した場合、メールが届くと即対象のチャネルに転送されるため、その内容についての議論をSlack上ですぐに開始できます。
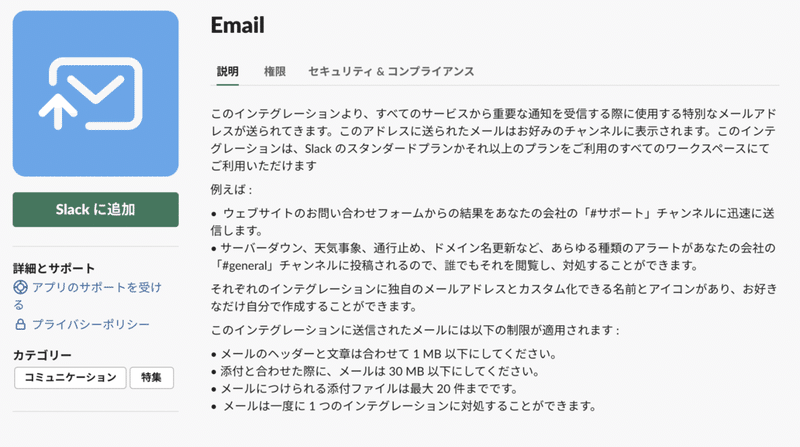
もう一つの方法は、メールクライアントとして、GmailもしくはOutlookを利用している場合に限られますが、「Slack for Gmail」および「Slack for Outlook」というアプリを利用する方法があります。これは、それぞれのメールクライアントのアドオンのツールとなっており、受信したメールをメールクライアントより、指定したSlackのチャネルに転送することができます。ただし、転送は自動ではないため、転送したいメールに対し、転送作業を人の手で実施する必要があります。
よって、お問い合わせ対応として利用する場合は、誰か担当者が転送しなければなりません。しかし、転送する労力は最低限で済みます。それ以上に、このアプリの良いところは、個人宛のみに受信された電子メールをチャネルに共有したい場合に便利である点です。メールのやり取りをしている中で、中には、送信時にはついていたCCがすべて外れ、個人宛に直接メールが返信されるということもあります。そういった際に、このアプリを利用することで、簡単に社内のメンバーと共有することができます。
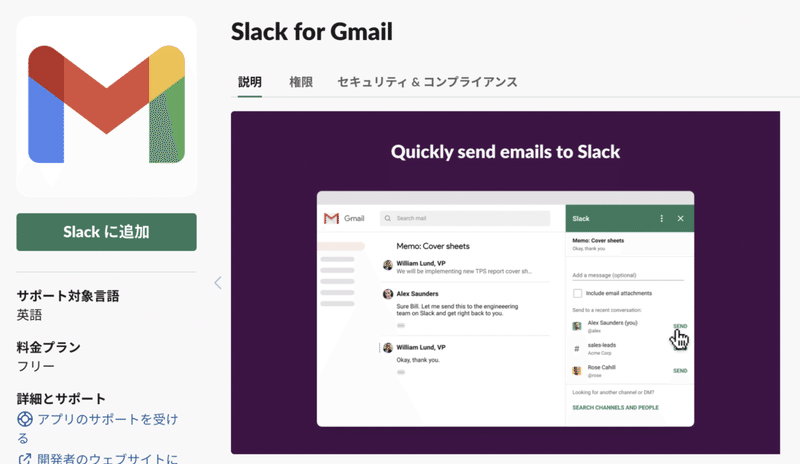
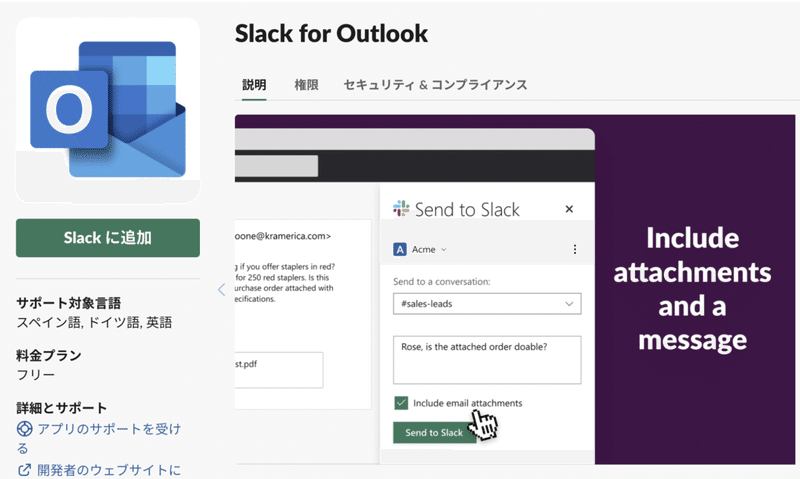
業務の流れを見直すきっかけとして
ビジネスを行っている以上、お客様や取引先とのコミュニケーションは不可欠です。さらに、一人でビジネスを回すことはできませんので、必ずチームで情報を共有し、コラボレーションしながら物事を進めていくことになります。その際に、情報共有や手順確認にかける労力が少なければ少ない程、業務効率は向上することになります。今までは、電子メール以外に有効なソリューションはありませんでしたが、今では、ビジネスチャットといったソリューションの選択肢が生まれています。よって、このような新しいテクノロジーを積極的に試し、業務効率が向上する可能性があるのかどうかについて検証するという姿勢は、限られた人的リソースの中、最大限の結果を出すために必要なことだと感じます。
※本記事に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社、各団体の商標もしくは登録商標です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
