
小説版「旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」第四章・第五章
<はじめに>
先週から掲載を始めた「小説版 旭川青春グラフィティ ザ・ゴールデンエイジ」。今回は前半の終わり、第四章と第五章です。
第四章では、主人公の一人、義雄、そして彼が一目惚れした後の歌人、齋藤史が、それぞれ心を痛める「ダブル失恋」の場面が登場します。
手前味噌になりますが、詩人、小熊秀雄がからむこの場面は、この物語の中でワタクシが一番好きなシーンです。
そして第五章では、その史と父親の瀏が旭川を去ります。
四章と五章の間には、大正から昭和の改元があります。天皇崩御の日の様子については、実在の史が書いた手記の一節を引用しています。散文でも才能を発揮した彼女の名文の一つです(この小説では、各章の冒頭に、旭川とゆかりのある文学者らの作品の一部をエピグラフとして引用させてもらっています)。
それでは今回も最後までお付き合いください。
第四章 大正十五年十二月 上川神社頓宮
霧華(きばな)とは、一般には霧氷又は樹氷などとかかれて居る「きばな」に私が宛てた文字である。霧氷、樹氷では硬すぎ、大きすぎて、ここ(注=旭川のこと)のきばなを表現するには不適当だし、又「木花」では誤解を生じるから、この文字にしたのである。
(齋藤瀏「自然と短歌」)
石狩川と牛朱別(うしゅべつ)川に挟まれた中島(なかじま)地区は、旭川の中心部と陸軍第七師団のある近文(ちかぶみ)地区の接点に当たる場所である。そこには石狩川に架かる旭橋、そして牛朱別川に架かる常盤橋(ときわばし)の二つの主要橋があり、交通の要にもなっている。
その中島地区で旭川初の都市公園の造成が始まったのは、十五年前、大正元年のことである。五年後には堀池や築山が完成して開園した。公園には、その後、ボート乗り場や茶屋なども設けられ、今では市民の憩いの場として定着している。当初は中島公園と呼ばれたが、まもなく常磐(ときわ)公園と称されるようになった。「なかじま」、「ときわ」、ともにこの一帯を示す古い呼び名である
この中島地区の一角は、川の中洲に当たることから、もともと中心部には近いが具体的な利用計画はなかった土地である。そこが公園となったのは、造成開始の二年余り前に表面化した当時の旭川町と七師団の確執があった。
発端は、師団側が持ち出した衛戍地(えいじゅち)、つまり駐屯地の町からの分離独立案である。師団の中で、一般町民と同率の町税が軍関係者に課せられるのは不当であるとの意見が高まったのだ。
衛戍地では、土木、衛生、教育などさまざまな公的事業をすべて自前で賄っている。施策の恩恵を受けていない町の税を、住民と同様に負担する必然性はないというのが理由である。是正されなければ、旭川町から離れ、別の一村を設立することも辞さない、それが師団の主張だった。
これに対し町は、制度上、特例は認められないと拒否した。しかし師団を失っては、当時目論んでいた、町から、市に準じる区への昇格に影響が出るのは必死と思われた。このため紆余曲折はあったが、結局は町が折れざるを得なかった。そして明治四十三年、軍関係者に対する実質的な税の軽減に加え、近文地区の利便性の向上を図る各種の施策の実施など、師団側の要求を全面的に飲んだ八項目の協定書が交わされる。その八項目の一つが、近文地区に隣接する中島地区に公園を設けることだった。
こうして誕生した常磐公園の堀池には、大小二つの島がある。そのうち大きい方の千鳥が島には小ぢんまりとした社が建っている。県社上川神社頓宮(とんぐう)である。
上川神社は、上川地方開拓の守護、旭川鎮守の神社として、明治二十六年に創設された。長年、中心部にあって信仰を集めたが、二年前、市南部の高台である神楽岡(かぐらおか)に遷移した。
これに合わせて造営された頓宮は、神輿渡御の際の御旅所(おたびしょ)としての役割を担っている。毎年七月の例大祭では、神楽岡を出発して市内を巡った神輿が頓宮で一夜を過ごし、翌日、また市内を巡って本社に帰る。
その頓宮では、二時間前に始まった旭川歌話会の歌会が少し前に終了したところである。控室に、会の幹事である三人が戻ってきた。
第七師団参謀長でもある齋藤瀏(りゅう)、地元信用組合の総代を務める酒井廣治(ひろじ)、そして小熊秀雄である。部屋には鋳物製の石炭ストーブがあって、薬缶から白い湯気が立っている。
「いや、いや、お疲れ様でした。おかげで、今回もいい会になりました」
五歳ほど年長の瀏に椅子を勧めながらそう話しかけたのは、酒井である。まだ四十代そこそこだが、薄い茶色の絣の袷と羽織を着こんだ姿は、年よりも落ち着いて見える。
「これも名幹事のたまものだな。小熊君。本当にご苦労さま」
休日とあって、瀏も軍服ではなく和装である。かっぷくの良い体躯を、焦げ茶の御召と黒の羽織で包んでいる。頭は丸刈りだが、目元がやさしいため、軍人特有の威圧感はない。
「いえいえ、皆さんに手伝ってもらってるんで、なんとか役目を果たせてるんですよ」
書生姿の小熊は、そばに立ったままである。
「でも旭川歌話会、本当に結成して良かった。毎回、やるたびに作品の質が上がっている。君もそう思うだろう」
そう瀏が向けると、小熊はうなずいた。
「やっぱり創作は、切磋琢磨が必要なんでしょうね。周りの刺激が、こんなにも大切なものかと僕も再認識しました」
旭川歌話会は、この夏に酒井や瀏が呼びかけて結成された旭川初の本格的な短歌の勉強会である。市内や近郊の四十人余りが参加し、この日を含め、これまでに四回の歌会が開かれている。
「ま、そういう意味では、旭川の短歌界も大きな刺激を受けて飛躍したということでしょう。軍人歌人として知られる齋藤参謀長が旭川勤務になり、去年は白秋先生、今年は牧水先生が来てくれた。こうしたことがなかったら、歌話会結成の話など持ち上がりませんでした」
「白秋の弟子である酒井会長が旭川に戻っていたことも大きかったと思いますぞ。やはり地元で中心になる方がいないとね」
「いえいえ。それはそうと、きょうの歌話会で言うと、やはり史嬢ですな。前回は最高点だったが、きょうは別の意味で驚かされました」
酒井は、そう言うと、会場から持ち帰った短冊を探り始めた。瀏は苦笑している。
これこれ、と言って酒井が作品を取り出した。
「長髪の小熊秀雄が加わりて歌評はずみきストーブ燃えき。長髪の小熊秀雄が加わりて歌評はずみきストーブ燃えき。……うん、やはりこりゃ短歌を始めたばかりの人が作る歌ではありません」
小熊は、困ったなという表情である。
「また当の本人を目の前にして、こうした歌を出すというのは……。や、父君を前にしてこれは失言でした」
「いやいや、わたしは一向に。ただなりは大きいが、まだ子供ですから。含みは、やはりないのでしょう」
「もちろんですよ。幹事の立場を忘れて、私があれこれ批評を言うので、印象に残ったのだと思います」
「まあ、ここはそういうことにしておきますか」
酒井がこう言って破顔すると、師範学校の制服姿の義雄と武志が部屋に入ってきた。会の出席簿や筆、硯などが入った箱を抱えている。
「小熊さん。これはこっちでいいんですか?」
「ああ初参加の君に手伝わしてしまって悪いな。武志君も会員でもないのに使ってしまって」
「僕は一番下っ端なんですから当然です。こいつは、どうせ暇なんで」
「暇とはなにさ。お前が付いて来てくれって言ったんだろ」
義雄と武志がいつものようにやりあっていると、遅れて史が部屋に入ってきた。黒白の千鳥格子の袷に、大柄の牡丹を配った紫の羽織。歌会という場所を意識したのか、洋服好きの史には珍しい装いである。
「親父様。迎えの車が着きました。酒井先生もごいっしょにどうぞ」
「うん、お送りしましょう。どうせ師団の差し向けの車なんだから、遠慮せずに」「そうですか。それは助かりますが。でも史さんは?」
「わたくしはもう少しやることがありますから」
「申し訳ないねえ。本当はあなたにお手伝いしてもらうのは気が引けるんだ」
「いやいやそれは私が命じたんだ。もう女学校も出てしまったんだし、家でぶらぶらしているんだから」
ちらりと娘を見やりながら瀏がそう言うと、史がわざと不満げに応える。
「あら、ぶらぶらとは失礼だわ。でも会のなかでは年少者ですから、当然のことです。親父様、あまりお待たせすると……」
「ああそうだな。さ、会長」
瀏がそう言って立ち上がると、小熊も酒井を促した。
「あとは会場をもとに戻す程度ですから、気にせんでください」
「そうかい。それじゃ。お先させてもらいますか」
瀏と酒井が皆にねぎらいの言葉をかけて出ていくと、部屋にはほっとしたような空気が流れた。師団の参謀長と信用組合の総代。その立場で出席しているのではないとしても、やはり同席する若者に緊張は隠せない。
「義雄さん」
二人が片付けを始めようとしたときに史が声をかけた。
「あ、はい!」
「始まる前は、時間がなくて失礼しました。やっと来てくださったんですね。ありがとうございます」
お辞儀をすると、義雄も慌てたように返す。
「あ、いえいえ、なんもです」
「なかなかお見えにならないので、やはり短歌には興味がないのかなって」
「いえ、そんなことはないんですが、その……」
「ああ、こいつ、行きたくてしょうがなかったんですけど、いい作品持ってかなきゃ史さんに恥ずかしいって」
そう言う武志の腕を義雄が引っ張る。
「よけいなこと言わなくていいの。小熊さん、会場もとに戻すって言ってましたよね。僕らでやりますから。おい、行くぞ」
「あ、ざっとでいいからね。……ふっ、何あわててるんだ」
二人が部屋を出て、歌会の会場となっていた拝殿に行くと、しばらく部屋は沈黙に包まれた。史が何か言いたそうなそぶりをしているのを察した小熊は、椅子を勧めた。
「史さんに会計をしてもらえると助かりますな。金の計算とか、全く苦手でね」
そう言いながら、小熊も少し離れた椅子に座る。
「詩人さんで、お金の計算が得意な人って……。やっぱり似合いません」
「そりゃそうだ。史さんの言うとおり」
「……あの、迷惑でしたか?」
居住まいを正した史がそう問うと、小熊は、え、という顔をした。
「きょうのわたくしの歌」
「ああ。……突然自分の名前が出てきたんで、少し驚きました」
「それだけ?」
「うん。……斬新で、とても良かった」
史は、ほっとしたように微笑むと、小熊の顔を覗き込むようにして聞いた。
「わたくしが最初に小熊さんとお会いした日のこと、覚えていらっしゃいます?」
「もちろん。旭川に来られてすぐ、父君に会いに官舎にお邪魔した。その時ですよね」
「親父様が新聞記者の方がいらっしゃると言うから、てっきり師団担当の方かと」
「父君は軍人でありながら、歌集も出して、絵も描かれると聞いたんで、どんな人か会ってみたくなったんですよ」
「でも親父様の前で、いきなり軍の悪口を言い出して。わたくし、なんて人なのと思いました」
「いやー、思ったことは口に出してしまうたちなんで。……でも、父君は度量が広い。だから歌話会の幹事も引き受けたんです。ただこれだけは、お嫌いのようですな。会うたびに、その黒珊瑚はどうにかならんかと言われる」
小熊はトレードマークの長髪を自ら指した。
「わたくしは、新聞に『黒珊瑚』という署名記事を見つけて吹き出しました。すぐ貴方だとわかりましたから。それと、わたくし、小熊さんのこと、ずっと独身だと思ってたんですよ。最初に来られた時、男やもめなのでと、おっしゃってたから」「ああ、でもその時は確かに」
「ええ、その後にご結婚されたんですよね。旭ビルディングの美術展に来られた小学校の先生が今の奥様」
「はい、その通りです。よくご存じで」
小熊の意外そうな顔を見て、史はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「ええ、いろいろと探らせていただきましたから」
「……そうか、じゃ僕の素行の悪いところは、みんな知られているんだ」
「そうですわ。いろんな女性に声をかけている事とか、お腹の大きな奥さまを、樺太の実家に一人残して旭川に戻ってきた事とか。奥さま、なんてお気の毒」
「いやあれは……。話せば長くなるんだが、継母(はは)と僕の折り合いが悪いので、いないほうが良いと本人も言い出して……」
「勘弁してあげます」
そう言うと、こらえ切れず吹き出した。
「そんなに言い訳なさらなくても」
「……いや。これは失敬」
社(やしろ)の外はもうかなり暗くなってきている。冬の間も頓宮に参拝に訪れる人はいるが、夕方以降はまず人気はない。
「……わたくし、そろそろ旭川を去ることになりそうですの」
しばらくの沈黙の後、史がそう切り出した。
「え? それはもしかして父君の異動で?」
「ごめんなさい。それ以上詳しくは……」
「なるほど、失礼しました」
「父もわたくしも旭川が好きなんです。だからとっても残念」
「うーん、それはびっくりですね」
小熊が続く言葉を探しているのを、史は待っている。
「そうですか…。せっかく歌話会もできたばかりなのに、惜しいことです」
ストーブの上の薬缶がシューシューとわずかに音を立てている。
「……でも史さんは歌を続けてください。僕は、短歌は古い芸術だと思っていたが、あなたの歌を見て思い直した。牧水が歌をやるべきだと言ったそうだが、史さんはぜひ歌を作り続けてください」
史は小さく息を吐くと、伏せぎみにしていた顔を上げた。
「……ありがとうございます。小熊さん、ひとつお尋ねしていいですか?」
「……何でしょう?」
「小熊さんは、いずれまた東京に行かれるおつもりなんでしょう?」
「……うーん、ま、そうなるでしょうなあ」
「どうしてわざわざ東京に行かれるのですか? 旭川には、良いお仲間とお仕事があって、とてもいきいきしているように見えますのに」
「……確かにそうですね。いい仲間がいて、大好きな姉もいるし、なにより妻子を養うことのできる職場もある」
「なら」
「でも、心の奥のもう一人の自分がそれじゃいかんと言うんですよ。それじゃ本物の詩は書けないって。……僕はね、弱い人間です。だから温かい所にいると、ちゃんと自分と向き合えなくなる」
「創作って、そんなに不自由なものなのですの? だったら、わたくしはやりたくない」
「いやいや、それはね、自分がそうなんです。私という人間の業であり、それが使命なんですよ。あなたには、あなたの使命があるように」
「……使命って、変えることはできないんでしょうか?」
史はそう言うと、立ち上がって窓に近づいた。いつの間にか、雪が降り始めている。気温の低い旭川ならではの乾いた粉雪である。
「……申し訳ありません。師団通まで送っていただけませんでしょうか」
「わかりました。お送りします。……ええと、義雄君たちはどこにいるのかな」
と、小熊が立ち上がった時、入り口の扉の脇から若者二人が顔を出した。
「ああ、そこにいたのか。会場の片づけは?」
「はい。終わりました。……というか、とっくに終わってたんですけど」
武志が頭をかきながらそう言うと、小熊はたちまち恐縮した。
「ああ、それは申し訳なかった。で、もう一つ悪いんだが、僕は史さんを送ってゆくので……」
「はい。社務所に声をかければいいんですよね。どうぞ、遅くなりますから」
「そう? 悪いね。じゃ史さん」
史は窓から離れると、入口近くにいた義雄と武志に近づいた。
「義雄さん、きょうは来てくれて本当にありがとうございました。じゃ、武志さん、お言葉に甘えて、お先しますね。御機嫌よう」
史は、お辞儀をすると、小熊の後について部屋を出た。ストーブの石炭が切れかかってきたのか、時折カン、カンという金属が収縮するときの音がしている。
「……いやいやいや、まいったんでないかい」
押し黙ったままの義雄の様子を伺っていた武志が、おどけたように言った。
「……全くさ。部屋に入るったって、あの雰囲気じゃ入れないべさ」
義雄の表情は変わらない。
「……あのさ。知ってる? ここの、常磐公園のボートってさ、アベックで乗ると、別れちゃうんだって。あ、いっけね……」
「……そう、気ぃつかわないでいいべさ」
立ったままだった義雄が椅子にかけながら言った。
「何よ」
「いくら鈍感な俺だって分かるっしょ。あの会話聴いてりゃさ。……史さん、小熊さんのこと好きだったんだな。ものすごーく」
「……うん。まあな」
武志も腰を掛けた。
「しかもかなり前からさ、ずっと好きだったんだわ」
「……そうかもね」
「で、せめて自分の気持ち、伝えておこうってさ」
「……そだねえ」
「もしかしたら、二人きりになることって、もうないかもしれないしさ」
「……うん、ま、そういうことなんだべな。……あれ、お前……」
武志はうつむいている義雄の顔を下から覗き込んだ。
「泣いてるんかい?」
目が赤くなっている。
「……したってさ。史さんの気持ち考えたらさ。可哀想だべさ」
「……うん。……ま、俺はお前の方が可哀想だけどね」
「……うん、俺も史さんと同じくらい悲しい」
再び下を向いてしまった義雄の横で、武志は思案顔である。すると、あのさと言って立ち上がった。
「俺、歌作ったんだけど、聞いてくれる?」
「え、なに、歌ってなにさ。短歌のこと? なんでお前が?」
「いいじゃん。浮かんだのよ。歌。武志作」
いいかと言うと、武志は一言一言確かめるようにして自作の歌を披露し始めた。
「慰めの……言葉探すも見つからず……。ここまでいいか?」
「うん」
「……初恋やぶれし……友よ許せよ」
「え?」
「だから。慰めの 言葉探すも見つからず 初恋やぶれし 友よ許せよ」
とたんに義雄が吹き出した。
「なんなのよそれ、全然歌じゃねーべ」
「え、歌じゃん」
「歌じゃねーって。普通の会話、五七五七七にしてるだけだべさ。ほんとお前って」
「何よ」
「初恋やぶれし友よ許せよ、って、なんだよそれ。ククク」
義雄が笑い出したのを見て、武志は少し安心したようだ。
「……腹減ったな。どっか食いに行こうか」
「お、いいね。どこ行く? お前の好きなとこでいいよ」
「……ヤマニでライスカレーかな」
「おお、こないだ大将が始めた奴な。うん、じゃ行くべ」
二人は、社務所に声をかけに行く途中もじゃれ合っている。
「ライスカレー、武志のおごりな」
「え、なんでよ」
「当然だろ。友よ許せよって謝ってんだから」
「なによそれ、意味わかんねーし」
第五章
十二月に入ると、いよいよ北海道らしい激しい吹雪がつづいた。土地に生れ育った人々が、落ち付きはらって冬に籠り、当り前の事として毎日の雪を眺め、平気に凌いで行くのが羨ましかった。
折から、大正天皇御不例(ごふれい)の報が、しきりにきこえて、伝導の仕どころの無い毎日の屈(くぐ)んだ心の中に、かなしく積っていくのであった。
神去りました知らせを受けた夜は、殊に寒く、絶えず父の勤めさきからかかる電話を待って、誰も寝るどころではなく、黙りあって座って居た。馬橇の鈴の音ひとつ聞えない、くらい夜であった。
(齋藤史 散文集「春寒記」から「師走の思い出」)
そしてわずか一週間の昭和元年が過ぎ、年が明け、昭和二年となった。
昭和二年三月 カフェー・ヤマニ
カフェー・ヤマニのある師団道路は、旭川一の目抜き通りである。北北西の方向に伸びる通りは途中でさらに西方向に折れ、常盤橋と旭橋を経て第七師団のある近文地区に至る。
旭川の街の始まりのころ、この道は村外れの田舎道の一つに過ぎなかった。それが賑わいを見せるようになったのは、明治三十一年、通りの起点の位置に道央と結ぶ鉄道の拠点、旭川停車場が設けられたためである。
その後、稚内や網走、富良野方面にも鉄路が伸びると、旭川の商圏は一気に拡大する。札幌や小樽、さらには本州からも大勢の商人が流入し、通りにはさまざまな商店が軒を構えた。衣類から日用品、薬や食品、書籍、時計、眼鏡など、ここに来れば大概のものは手に入る。最近では、東京銀座の銀ブラに倣い、師団道路をブラブラ、団ブラという言葉も使われ出した。
そうした人出の増加を見込み、中心部には各種の飲食店も急増した。ただこちらは二条から五条辺りの条通りやその仲通りに多く、師団道路にある店は意外に少ない。ヤマニは、先代の食堂時代から、この数少ない目抜き通りに面した飲食店の代表格である。
そのヤマニ。今は、昼の喫茶営業の時間で、カウンターでは店主の速田が手持ちぶたさにしている。少し離れたテーブルには、制服姿の義雄が新聞を読んでいる。その義雄をせかすように声をかけたのはボーイ姿の武志である。
「あのさ、駅いかないの?」
「……うん」
「うんじゃねーよ。史さんの出発、そろそろだべさ?」
「……うん」
「あのさ!」
武志がじれったそうに声を上げた時、義雄が新聞の記事を指差した。
「『熊本第六師団旅団長に栄転の齋藤参謀長御一家、きょう旭川を出発』。新聞にまで書いてあるんだもの。どうせ行ったって物凄い人なんだろ。おれなんか行ってもしょうがないべさ」
「でもさ。気持ち伝えておいた方がいいんじゃない? 後悔するよ」
「いいのよ。もう俺は踏ん切りがついたんだから」
そう言いながらも浮かない顔の義雄の様子が武志には気に入らない。
「踏ん切りって何よ」
「踏ん切りは踏ん切りっしょ。だいたいさ、思うんだよね、どうかしてたんじゃないかって。よく考えたら、そんなすげえいい女かなーとか、思ってさ」
「お前だよ。ここで。天使が舞い降りた、とか言ってたやつ。まさに、この場所で」
思わず身振り手振りが伴う。
「いやいや、天使って。ついそういう言葉が浮かんだだけなんだわ。俺、いちおう詩も書いてるしさ。まあ普通に考えたら、言い過ぎだよな。そうそう天使って言える人、いないしさ。ま、どうにかすることって、あるじゃない。誰でもさ。それによく考えたら、史さん、結構、気が強い感じだし……」
義雄の話の途中で、速田と武志がクスクスと笑い出した。
「……え、何笑ってるの。なにさ大将まで」
当惑している義雄に、後ろから声をかけたのは史である。
「気が強いって、どなたの事ですの?」
細かな花模様の紺のワンピース。ボーカラーの長い襟をリボンのように胸の前で蝶結びしているのが、大柄な史によく似合っている。義雄がなにやら弁明をしている間に店に入ってきたらしい。
「いやいや気が強いっては、そういう意味ではなくて。あの、あれでして。……いや、そ、それより、どうしたんですか、だ、だ、だって、きょうは……」
また北修のようになっている。
「ええ、でも最後にヤマニの美味しいコーヒーを飲んでおかなくちゃと思って。そしたら親父様まで」
史が涼しい顔で答えると、遅れて瀏が店に入ってきた。軍服姿。外に車を待たせているらしい。
「……ああ、わかっとる。すぐに戻るから、少し待っていてくれ。……おお、義雄君。それに……」
「あ、武志です」
「ああ、そうだ武志君。君らにも世話になった。ここでは、酒はよく飲んだが、コーヒーは飲んだことがなくってね」
「大将、お願いできるかしら。わたくしと親父様と」
史は速田に声をかけると、瀏とともにカウンター前のテーブルについた。
「よござんすよ。お二人に最後に飲んでいただけるなんて、光栄の限りです」
武志が運んできた水を飲むと、父娘(ふたり)はそれぞれ名残惜しそうに店内を眺めた。史が店に入ってきた段階でもう察したのか、速田はいち早くコーヒーの準備を始めていたようだ。すぐにドリップされたコーヒーがほろ苦い香りを立て始めた。
「来ていただいたのはうれしいんですが、お時間は大丈夫なんですか? 駅で皆さん待っておられるのでは」
淹れたてのコーヒーをカップに移しながら速田が尋ねた。
「いやいや、どうせ固い挨拶ばかりだから、あまり早くいきたくないというのが本音なんだ」
「歌話会の皆さんには、先日、送別の歌会を開いてもらったんです。その時に御挨拶させていただきました」
ともに肩幅のあるがっしりとした体躯に丸顔。こうして並ぶと父娘(ふたり)はよく似ている。さっぱりとした性格も含め、史は父親から多くを受け継いでいる。速田はそういうことなんですねと返すと、近づいてきた武志に手で大丈夫と合図をし、自らコーヒーをテーブルに運んだ。
「大将に、自ら運んでいただくなんて」
「光栄だな。ではいただこう」
瀏はカップを持ち上げて香りを確かめると、ゆっくりと口に近づけ、コーヒーを味わい始めた。時折うんうんと頷いている。
史は、スプーンで一つ砂糖を入れてかき回した後、やはり一口一口確かめるようにしながら飲んでいる。
「……ああ、やっぱりおいしい。わたくし、ここのコーヒーの味は忘れません」「うん。こんなうまいコーヒーがヤマニにあったとは。知らないでいて損をした気分だな。ますます旭川に思いが残る」
「熊本へは直接行かれるのですか?」
テーブルから少し離れたところで二人を見守るようにしていた速田が尋ねた。
「はい。親父様は直接。わたくしと母は、東京の親戚のところに寄ってから向かうことにしています」
「向こうはもう暖かいんでしょうね」
「そうですね。もう桜が始まっているんじゃないかしら。着いたときは、もう見られないかも」
「そうか。九州はもう経験済なんですね」
「はい。ここと同じで二度目です」
黙ってコーヒーを味わっていた瀏が、奥のテーブルにいる義雄に目を向けた。
「……そうだ、義雄君」
義雄は、はいと言って居住まいを正す。
「小熊君といっしょで、君も専門は詩らしいが、ぜひ短歌も続けてほしい。特に歌話会に君のような若い人が加わっていることはよいことだ。期待しているよ」
「はい。ありがとうございます」
「それじゃ、あわただしいが、そろそろ行かねば」
コーヒーを飲み終えた瀏が立ち上がった。釣りはいらないと言って速田に札を渡し、おいと史に声をかける。
「申し訳ありません。先に車に乗ってらしてください。すぐ行きますから」
なにかやり残したことでもあるのだろう、そう察した瀏は軽くうなずくと、ゆっくりと外に向かった。
「では御一同、お世話になりました。お達者で」
敬礼をした瀏は、義雄らが立ち上がって見送る中を去っていく。
瀏が外に出ると、一緒に立ち上がっていた史が義雄の方を向いた。
「義雄さん。短い間でしたけど、本当にありがとうございました」
「いえ、とんでもないです」
「わたくし、この三か月、自分の使命って何なんだろうって考えていたんです」「使命……ですか?」
「ええ。小熊さんに言われたんです。『あなたには、あなたの使命がある』って」
史は少しうつむくと、言葉を選びながら続けた。
「そうしたら、わたくしにとって大切なのは、毎日のなにげない暮らしや周りの方々との関わりのように思えてきました。ですから、これからはそうした日常や周りの人たちとの関わりの中で生まれてくる言葉とともに生きていこうと思います」
史はそう言うと、再び義雄に顔を向けた。
「生意気な言い方ですが、義雄さんは、人にはない感性をお持ちの方と思います。創作がそうなのかはわかりませんが、義雄さんもきっとご自分の使命を全うされていくんだろうなって思います」
義雄は溢れそうになる思いを抑えながら応えた。
「……ありがとうございます。僕の方こそお世話になりました。史さんもお元気でいて下さい」
義雄が頭を下げると、史もならった。
「……行かなくては」
史はテーブルに置いてあった上着とハンドバッグを手に取ると、店にいる三人の方を向いた。
「それでは皆さま、御機嫌よう」
史は少し早足で入口のドアに向かうと、レジの横で足を止めた。そして名残惜しそうに店内を見渡すと、外に出た。
見上げると、いつの間にか、厚く黒い雲が空を覆っている。
***
(夢の続き、あるいはその後の物語・・・・実在の人物その一)
齋藤瀏…
昭和四年、第二歌集「霧華(きばな)」を出版。翌年、予備役となり、軍務から離れ東京に住む。昭和十一年、二・二六事件で決起した青年将校を支援したとして拘束され、禁固五年の判決を受けて下獄する。終戦間際に故郷である長野に疎開。戦後もそのまま居住した。昭和二十八年、七十四歳で死去。
齋藤史…
二・二六事件では、旭川の北鎮小学校で幼なじみだった二人の青年将校が処刑され、父、瀏も禁固刑を受ける。以来、事件は、史の創作上の大きなテーマとなった。昭和十五年、第一歌集「魚歌(ぎょか)」を上梓。以来、歌壇の中心として活躍。現代短歌大賞など多くの文学賞を受賞した。平成十四年、九十三才で死去。
(後半に続く)
<注釈・第四章>
* 常磐公園(ときわこうえん)
・ 1916(大正5)年に開園した旭川初の都市公園。今も市民の憩いの場として親しまれている。地名は「盤」、公園名は「磐」の字を使う。
* 上川神社頓宮(とんぐう)
・ 今のような手頃なイベントスペースが街中になかった時代には、この頓宮や寺院などがさまざまな団体の会合に使われた。旭川歌話会が頓宮で開催されたことはないが、そうした事実を伝えたく、あえて開催場所とした。

* 霧華(きばな)
・ 凍てついた朝、霧が草や木に付いて凍った姿を指す齋藤瀏による造語。旭川歌話会の合同歌集および瀏の第2歌集のタイトルでもある。旭川の銘菓「き花」のネーミングは、この言葉を元にしている。
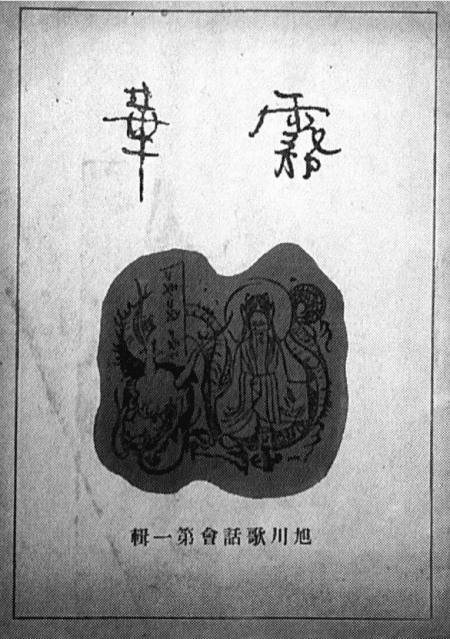
* 牛朱別川(うしゅべつがわ)
・ 旭川と、旭川の北隣りの当麻町を流れる石狩川支流の一級河川。昭和初期、洪水対策として、旭川中心部で流路を変える大規模な切り替え工事が行われた。
* 旭橋
・川の街、旭川を象徴する橋。初代は1904(明治37)年、北海道で2つ目の鋼鉄橋として誕生。1932(昭和7)年架橋の2代目旭橋は、北海道3大名橋の一つで、美しいアーチで知られる。

* 常盤橋(ときわばし)
・ 昭和初期に行われた牛朱別川(うしゅべつがわ)の流れを変える切替工事の前、今の常盤ロータリーの場所にあった橋。旭橋と並び、中心部と師団のある近文地区を結ぶ重要な橋だった。

* 衛戍地(えいじゅち)分離独立案
・ 旭川町からの分離独立も辞さないという陸軍第七師団の強硬姿勢を示したプラン。新しい遊郭の設置計画に対する強硬な反対姿勢など、当時の旭川町の町政運営に対し、不満を募らせていた師団が嫌がらせ的に無理難題を持ちかけたという側面もある。
* 区
・ 本州の市に準じる当時の北海道独自の行政単位。北海道で市が誕生するのは1922年(大正11)年まで待たねばならなかった。
* 上川神社
・ 上川地方および旭川の鎮守として、1893(明治26)年に創設された。
* 軍人歌人
・ 陸軍将校であり、歌人でもあった齋藤瀏を指して言った言葉。
* 酒井会長
・ 実際の旭川歌話会は、発足時、会長は置かなかった。酒井廣治(さかいひろじ)は齋藤瀏らとともに顧問を務めた。
* 長髪の小熊秀雄が加わりて・・・
・ 齋藤史の作品だが、作ったのはゴールデンエイジ期ではなく晩年。旭川時代を振り返っての歌。
* 美術展に来られた小学校の先生
・ 当時、神居小学校の音楽教師だった崎本(さきもと)つね子のこと。会場で知り合った小熊とつね子は、翌1925(大正14)年2月に結婚する。

* わたくし、そろそろ旭川を
・ 実際には軍人である父の異動を匂わすことはないと思われるが、あえてこうしたやり取りとした。ただし瀏の異動については、この場面の前年である1925(大正14)年11月、小樽新聞に少将への昇進が内定したという記事が掲載されている。このため、異動先は不明なものの、周囲には翌春には旭川から去ると受け止められたはずである。
* 常磐公園のボート
・ いつの頃から言われたかは定かではないが、筆者が小学生〜高校生の頃、常磐公園でボート乗りを楽しんだアベックはその後別れる、といった趣旨の話をよく耳にした。

<注釈・第五章>
* 旭川停車場
・1898(明治31)年、北海道官設鉄道上川線の駅として開業した旭川の玄関口。現在の駅舎は4代目。
* 熊本第六師団
・ 旧陸軍の師団の一つ。熊本、大分、宮崎、鹿児島の南九州の出身兵士で編成された。司令部は熊本市に置かれた。
* 旅団長
・ 旅団は日本陸軍の編成の一つで、師団より小さく、連隊より大きい(旅団には2つの歩兵連隊が属し、師団には2つの旅団が属した)。旅団長はその指揮官。
* 送別の歌会
・ 1927(昭和2)年3月に開催された旭川歌話会の歌会のこと。会の立ち上げに参加した齋藤瀏の熊本への異動が決まったため開かれた。

* 予備役
・軍隊の構成員のうち、現役を終えたり、退いたりした要員。一定期間、有事には現役招集される。
* 二・二六事件
・ 1936(昭和11)年に起きた陸軍青年将校によるクーデター未遂事件。旭川は、陸軍第七師団の本拠地であったことから襲撃した側、された側ともに多くの関係者がいる。
* 栗原安秀・坂井直 くりはらやすひで・さかいなおし
・ 旭川の北鎮小学校で史の幼馴染みだった陸軍将校。二・二六事件で決起し、ともに事件後、銃殺刑に処された。
* 「魚歌(ぎょか)」
・ 1940(昭和15)年8月に刊行された齋藤史の第1歌集。装丁は版画家の棟方志功(むなかたしこう)。新進歌人としての史の評価を定めた。「魚歌」とはつたない歌という意味。
* 現代短歌大賞
・ 現代歌人協会が主催する短歌賞。1年間に刊行された歌集や短歌に関する著作のなかからもっとも優れたものを選ぶ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
