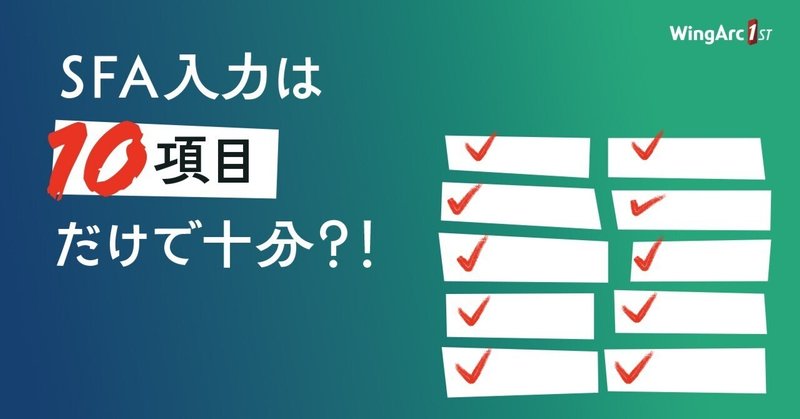
SFA入力は10項目だけで十分?!
先月の記事では、日本企業にとってRevOps(Revenue Operations)が必要な理由を、大上段から解説しました。コンパクトにまとめると、RevOpsとはデータやテクノロジーを使い、社内のプロセスを横断的に管理することで、顧客に対して最高の価値を提供するための取り組みであること。一方で、日本企業はSFAツールなどを導入しながら、いまだに“鉛筆なめなめ”なケースが多く、非常に大きな経営損失を招いていることなどを解説しました。
今回からは、より細かい実務的な内容にも踏み込んでいきたいと考えています。テーマは、RevOpsの一丁目一番地である現状把握のために必要な「KPI」です。
KPIとは結局何なのか?
一口にKPIといっても、難しいのは会社によって見るべきデータが異なることです。なぜならば、組織体も違えば、直面している状況も千差万別だからです。とはいえ、私なりにKPIの定義は持っています。KPIとは「最もパフォーマンスに影響する、各メンバーに一番見てほしい指標」です。
よくあるケースが、とにかく何でもかんでもKPIに設定してしまい、現場が嫌になってしまうケースです。特に、SFAツールの導入時などに多いのではないでしょうか。まだ現場メンバーがデータ入力を習慣的にできていないフェーズで、何でもかんでも入力を迫るのは避けるべきです。
KPIや管理指標が不必要に多い場合、結局どれがパフォーマンスに直結するか分かりにくくなり、現場の意識が分散し本来集中すべき活動に馬力をかけられなくなってしまいます。達成すべき目標に対して、なぜその指標がKPIになるのか。この因果律をしっかりと示せないと、単に画餅になってしまうので注意しましょう。
KPI変更で、人数が減っても売り上げは2ケタ成長
一例として、私の経験をご紹介しましょう。かつて、私の部署では退職者が相次ぎ、3分の2ほどに減少してしまったことがありました。当然現場に残ったメンバーは不安になりますよね。ただ、私はそこまで悲観していませんでした。なぜなら「人数が減っても、生産性を高められれば十分戦える」と考えていたからです。
営業部署の生産性を向上させるためにボトルネックだったのが「ピュアセールスタイム」、つまり顧客と向き合う時間です。メンバーの話を聞くと、同じクライアントのところにばかり足を運んでいたり、移動時間や社内業務が異常に長くて訪問社数がかなり少なかったりと、ピュアセールスタイムが非常に少ない状況でした。
そこで、ピュアセールスタイムを増加させるために、KPIを単に訪問した件数ではなく、重複なしでターゲットしている企業に対して訪問した件数や、実際の訪問に関わらず電話やメールでの顧客対応についても件数をカウントするよう変更しました。
すると、不必要な移動時間が大幅に減り、本質的な営業に時間をかけられるようになりました。その結果、メンバーは3分の2ほどまで減ったにもかかわらず、売り上げは2ケタ成長。この「タイムマネジメント」の視点でKPIを考えたことがないという読者の皆さんは、試してみると良いのではないでしょうか。
RevOpsとミニマリストは好相性(かも)
また、当時は週報に日報、さらに数値の細かい報告作業などで、1人当たり週当たりで4時間ほどをロスしていた点も課題でした。そもそもSFAツールに入力すべき項目が70個ほどもあったのです。メンバーが面倒くさがって、データの入力を躊躇ったため、習慣的に入力できていませんでした。
そこで、SFAツールに入力すべき項目を10個ほどに絞ることにしました。ルールも非常に簡素化して、
(1)現在持っている商談があれば入力する
(2)商談金額は現実的なものを入力する
(3)受注予定日が当期であれば想定月を記載、当期以外は大体でOK
程度の緩やかなものにしました。
ここでのポイントは、(2)だと考えています。当時よくあったのが、商談金額が1万円など、当社の商談金額としては極端に少ないケースでした。これではまともな予測は立てられません。そこで、扱っている商品の最低価格から、考えうる最大金額までのレンジに限定することで、現実的なデータにしました。
こうしたルールを基にして、SFAツールに入力すべき具体的な項目としては、商談日と先方担当者、さらに商談フェーズと商談金額、クライアント名、商品名、受注予定日くらいに減りました。「少ないな」と思いませんでしたか? そもそも目標を達成するためのパイプラインがしっかり見えるようにすることが重要になるので、一旦はこれで十分なので、入力すべきデータはこれくらい少なくても良いのです。
重要なのは、これらのデータから「どのタイミングでどの程度のパイプラインがあれば、目的を達成できるか」の推論を立てて、結果を基にいかに推論を精緻化していくかです。
まず本当に達成したい目的(ここではパイプラインを把握できるようにする)、そのために必要なデータのみを収集し(あったらいいなはやらない)、登録されたデータは必ずマネジメントする(PDCAサイクルをしっかりと回す)、途中で挫けないよう強い意志と社内合意を取り付ける SFAの定着に関して言えば一旦登録の習慣化が出来てしまえば、必要に応じて少しずつ入力項目が増えても組織は適応することが出来ます。
また入力工数が増えることに対して、相応の営業業務時間を減らすことを実現しなければ業務時間は単純に増え、メンバーの負担は増えてしまいます。数値報告の廃止や集計業務の自動化、タイムマネジメントにより業務工数を緩和する施策を同時に走らせることが効果的でした。
さて、今回は私自身の経験を基に、KPIの考え方や実例を解説しました。皆さんの会社でも、SFAツールに膨大なデータを入力する必要がありながら、実際に使っている項目はわずか――ということはありませんか。いったいどの指標がパフォーマンスに直結しているのかをしっかりと考え、不必要なものは、勇気を持って切り捨てる。これまでの部署単位ではなく、全社単位でデータを一元管理するRevOpsでは、そうしたミニマリスト的な考えも重要です。空文虚字な理想論を振りかざす組織変革は避けたいところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
