やっと少し復活。
元旦、家族が被災したことによるダメージは思ったよりも大きかった。もちろん当人たちは自分なんかより遥かにダメージ大きかったと思うが、1月4日、つれと次女が直江津から東京に戻ってこれてからというものの、自分はなんか虚脱状態になり。
しかし、本当に震災の直撃をくらった主に石川県の方々、心中お察しします。一刻も早く少しでも状況がよくなることを祈ります。
確実にコロナ後遺症も新年から悪化している。自分の場合、2年前に発症したときは、とにかくブレインフォグと全身倦怠感に悩まされた。ブレインフォグの方は1年くらいでなんとか改善したような気がするが、全身倦怠感は一向によくなる気配がない。起床したての午前中はなんとかもつものの、午後、特に3時か4時くらいになると急激に鉛が体中に詰まったようになる。当然気分は最悪で、頭も働かなくなる。酷いときはブレインフォグの再発を思わせるときもある。
しかし、ブレインフォグについていえば、後遺症はじめの頃よりは格段にまだ耐えられるレベルにはなった。四六時中頭に霧がかかって働かない状態のとき。そんなときはもう、焦りばかりが果てしなく空転する感じで、死ぬことしか考えられなかった。「死にたい」というより脳が死にたがっている、というような、なんか自分の臓器が自分の意思を離れて勝手に暴走している、まあそんなイメージだろうか。地獄と言えば、今も地獄であるが、ブレインフォグの酷いときの地獄ほど、地獄なことはない。とりあえず、そのピークに比較すればマシにはなったのだろう。
一方、全身倦怠感は基本的にメンタルより肉体的な苦痛なんであるが、一日のうち、これが襲ってくると、この苦痛により事後的にメンタルはやられる。ブレインフォグの焦燥感とは異なる、底に沈むようなダウナー感というか。地球の重力に肉体だけでなく精神も引き込まれるような。
で、元旦の震災も結構その倦怠感に影響を与えていただろう。テレビで被災地の場面を見ると胸が苦しくなる。それが全身倦怠感がやってくる時間になると脳内で増幅される。
そういう状態になると、noteなんかも端的に書けなくなるな…。
文字を書くという作業もエネルギーあってできること。だからあまりいいコンディションや境遇にない人が、例えば闘病記とか、書いているのは本当に敬服する。コロナ後遺症、メンタル疾患、そういう状態でSNSとかでつぶやいてくれる人がいるおかげで自分は少し安堵できたりする。贈与されている。
文字というのは人を癒す機能をもっている。誰にも見ていられなくても、少なくとも書く自分が見ることによって癒されることがある。
その効用はいろいろなところで言われたりするのだけれども。特に認知行動療法では、「とりあえず書いてみること」が治癒の一つの手がかりになっているのだと思う。
ただ、自分はあまり認知行動療法をきちんと理解していると言えないかもしれない。確かに文字化すると、自分の「考え方の歪み」を可視化できるのかもしれないが、それをフィードバックさせて、補正して、というのは、結局どこまでも歪みの範囲内でなされるのではないか? というとあまり正確な表現ではないかもしれないけれども、なんとなく、きちんとした主体が、きちんと主体に向き合う、そういう信念を支えるだけのエネルギーが必要になってくるのではないかしらん? やっぱりちゃんと理解してないかも。
ただ、ひょっとして文字化するということは、「現実の解釈」を変えるところに肝があるのではないか。こうしたことを考えたのは今年1月4日、高橋 和巳『人は変われる: [大人のこころ]のターニングポイント 』(ちくま文庫) を読了して。
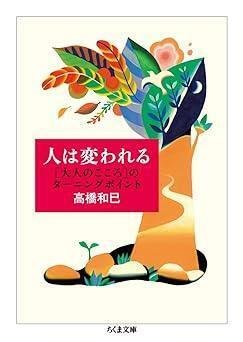
前々から読みたいと思いつつ、機会を逃していたのだけれども、年初、色々動揺している中でこの本を棚から手にとって読んでみた。色々本書については書きたいことがたまっているけれども…。やはり強く印象に残ったのは、「現実とはどうしようもならない」ことと、それを受容しつつ、「解釈を変えていく」主体性を保持する在り方である。文字を書くということは、その「主体性の保持」の一階梯ではあるのだろう。それなりにエネルギーや技術を要するものではあるけれども。
…今日は気怠いながらも、ちょっと書きたいというエネルギーが復活してきた感じで。明日の体調はどうなるかわからない。けれど書けるときはボチボチ書いていこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
