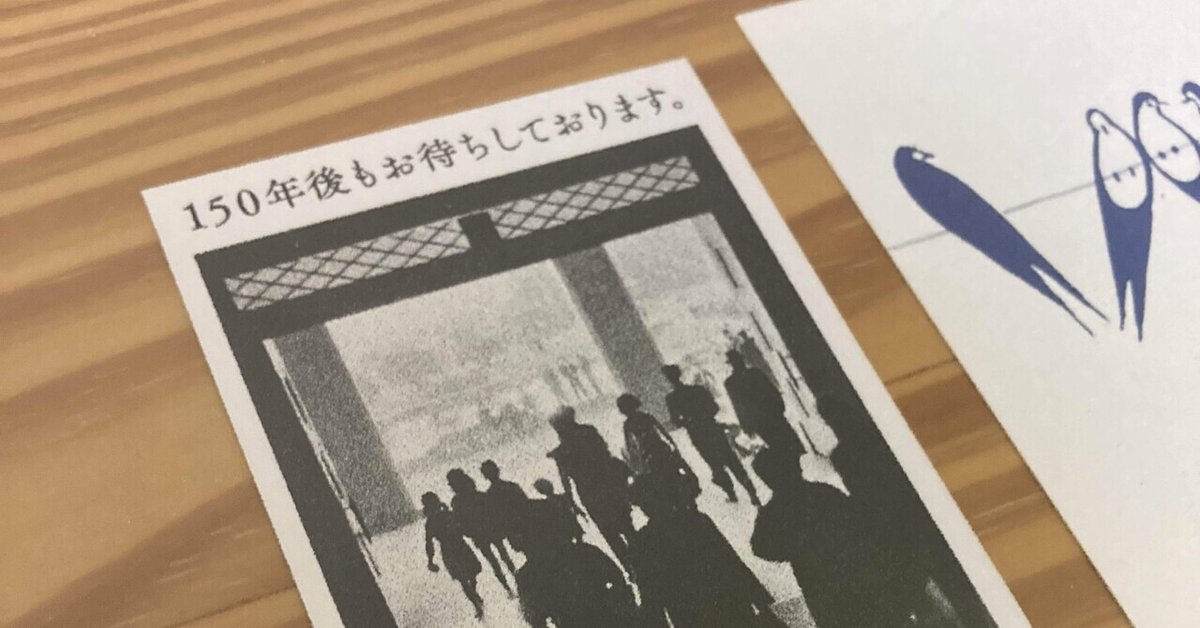
展示替えのススメ
展示替えとは。美術館や博物館において、展示してある作品を入れ替えることである。例えば会期の長い企画展において、保存などの観点から会期を前期と後期に分けて作品の一部を入れ替えるといった形で行われている。ではここに展示替えのススメとして文章を書き始めたのは何故か。ここでいう展示替えとは、自分の部屋における展示替えのことである。
展示替えとは何か。意外なことに、ジャパンナレッジでこの言葉を引いてみても見出しは一件もヒットしない。代わりに「模様替え」の語を引いてみる。
もよう‐がえ〔モヤウがへ〕【模様替え】
[名](スル)
1 建物などの設計、室内の装飾、家具の配置などを変えること。「部屋を―する」
2 物事の仕組み・方法・順序などを変えること。「組織の―」
私の部屋の壁には、美術館や博物館で買ってきたものをはじめとして、いろんなポストカードやフライヤーや絵が飾ってある。飾りきれずに眠っているものも含めると相当な数である。このたくさんの"展示物"たちを抱えながら、また新たにコレクションに追加するものを手に入れて帰ってきては、どれを新たに飾り、また飾ってあるうちのどれをしまうかということを考えるのである。気に入っているからといってずっと飾っておくと、太陽光によって赤い色からみるみる褪色していくので、そういったことも考えなくてはならない。こうして色々と考えながら壁面に飾ってあるものを入れ替えていく作業のことを、自室を博物館や美術館の展示室に見立てて「展示替え」と呼んでいるのである。
春先などはこの季節特有の薄紅に溢れた企画展のフライヤーをたくさん持ち帰ってきて、どれを飾ろうかと壁に当てて思案する時間が楽しい。行きたいと思っている展示の会期を知らず知らずのうちに逃すことも多いため、リマインドの意味でフライヤーを飾ることもある。展示で惹かれた作品のポストカードを買って帰れば、たちまちそれはあのときに見た展示室の一角のイメージとなり、それに伴って得た感情まで含めて一連の記憶を想起させるものとなる。
これまでに飾ったフライヤーの中で一番気に入っているのが2019年に横浜のそごう美術館で開催されていた「ウィリアム・モリスと英国の壁紙展」のものである。これはその展示テーマとなっているウィリアム・モリスの壁紙が全面に印刷されたものになっているが、これを壁に飾るとフライヤーのデザインが文字通り「壁紙」として機能するようになり、そこまで制作者が意図していたかどうかは別としても、なるほどなと思わされたものである。

私が熱心に集めているこうした展示のフライヤーやパンフレットなどは、図書用語では一般的な書籍と区別した非図書資料として「エフェメラ」と呼ばれているらしい。昆虫のカゲロウのように儚い存在、というところからきているという話など、エフェメラの収集については東京都現代美術館の美術図書室司書の方がアートスケープのインタビュー記事の中で語られているのでそちらも参照されたい。初めは将来自分が学芸員になった時の参考として集め始めたフライヤーであったが、次第に印刷物としてのグラフィックそのものに惹かれるようになり、今では私のコレクションの大部分を占めている。自分の好きなものを扱う仕事を新しく知り、なぜ学部時代に図書館司書の資格もとっておかなかったのかと後悔するばかりである……。
さて、ここから私の部屋、もとい展示室を少し紹介しておきたい。現在ある展示ゾーン(少し大袈裟か、)は大まかに5つ。基本的に展示替えのない常設ゾーン(実際の美術館博物館では常設でも展示替えが行われる。)2つと、比較的入れ替わりの激しい企画ゾーン2つに、最近新設した日本人作家のゾーンである。
常設ゾーンの一つは、東京国立博物館の分館である黒田記念館で手に入れた黒田清輝の6枚組の作品《雲》のポストカードである。長い額縁に6枚が横並びで収められているのを見て、なんとかしてこれを自室に飾りたいと思ったのをよく覚えている。額縁こそないが、実物のように6枚横並びで飾ってある。

もう一つは車ゾーンである。これは私がフォルクスワーゲンのビートルが好きでそのミニチュアやカタログを飾り始めたという、美術館や博物館とはまた別の趣味がきっかけになっているゾーンである。だが、最近は目黒区美術館で行われていた木村伊兵衛の展示で手に入れたポストカードのうちに1950年代のパリの車を写したものなど、雰囲気が合致するものはこちらのゾーンに加えられている。ここのゾーンのメインは、フォルクスワーゲンのディーラーが毎年配布してくれる、ワーゲン車をテーマにしたカレンダーである。

企画ゾーンは基本的にテーマはなく、新しく手に入れたものやその時の気分、季節など、自由に入れ替えをしている場所である。ポストカードとフライヤーのそれぞれに1つずつ、計2つのゾーンである。フライヤーの企画ゾーンにはついこの間までアーティゾン美術館の企画展である「写真と絵画ーセザンヌより 柴田敏雄と鈴木理策」のフライヤーが飾ってあった。この展示には先日足を運んだので、こちらは訪問済みの展示のフライヤーを整理したファイルへと場所を移し、今は新たに「ハマスホイとデンマーク絵画」という一昨年に東京都美術館で開催されていた展示のフライヤーが飾ってある。ヴィルヘルム・ハマスホイの《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》という作品が全面に切り抜かれたデザインであるが、これは先日国立西洋美術館の常設を見に行った際に見かけてこのフライヤーのことを思い出したので、コレクションの中から引っ張り出してきたものである。
新設の日本人画家ゾーンは、私の好きな二つの作品、黒田清輝の《昔語り下絵(舞妓)》と鏑木清方の《築地明石町》をどうしても飾りたいという想いから始まったところである。前者はマット台紙付きポストカード、後者は大判ポストカードに額付き、と他のコレクションに比べて明らかに待遇が良い。ここに雰囲気の合う吉田博の《神楽坂通 雨後の夜》を額付きで飾り、日本人画家ゾーンとした。本当は《昔語り下絵(舞妓)》と似ている木村伊兵衛の《ロンシャン競馬場》を飾りたかったのだが、ゾーンとして系統をまとめたい気持ちの方が優ってしまった。

このほかにも以前の記事で書いたケルトの組紐紋の絵や、それ以外の写真やカードを飾ってあったりもするのだが、これ以上エゴを語るのは誰も興味がないだろうからやめておくことにする。
美術は所有と切り離せないものである。今日の美術館博物館は紛れもなく先人のコレクション、つまり所有の欲求を源流の一つとしている。展示室で作品と向き合う時、そこから何かを読み取ったり感じ取ったりしようとするだけではなく、それが欲しいか欲しくないか、所有に値するかどうかという現実的な視点も肯定されて然るべきなのである。事実、自分は「これはウチに欲しい」とか「これはない」とか、基本的にIKEAのノリで展示を回っている節がある。私と同じようにエフェメラを相手にするもよし、ポストカードを集めるもよし、立体物のミニチュアを集めるもよし、各々のお気に入りを集めたコレクションを形成して、自室という展示室に展示するという作業を、美術の根幹に関わる所有の問題の当事者になれる簡単な方法として他の人々にススメたいのである。
追記:企画展のフライヤーは美術館や博物館などで手に入れることができるが、アドレスを登録するだけで無料で自宅に隔月でフライヤーが届くおちらしさんというサービスも存在する。気になる方は以下を参照。※回し者ではありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
