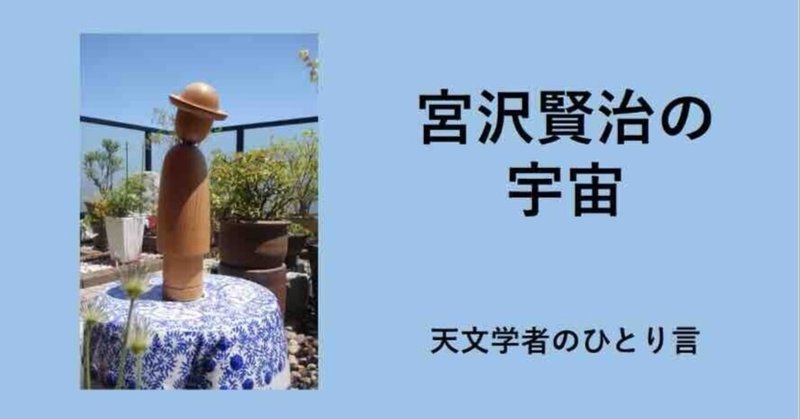
宮沢賢治の宇宙(13) 賢治さん、今夜も薄明穹(はくめいきゅう)を行きますか?
薄明穹(はくめいきゅう)
宮沢賢治の作品には聞いたことのない言葉がよく出てくる。その中には賢治が造った言葉、造語も含まれている。ここで話題にする「薄明穹」もそのひとつだ。
この言葉に出会ったのは今から4年前のことだ。それは小沢俊郎(1921-1982)による『薄明穹を行く 賢治詩私読』(学藝書林、1976年)という本のタイトルにあった(図1)。小沢は賢治研究の分野では有名な人で『校本 宮澤賢治全集』(筑摩書房、1973-1977年)の編集委員も務めた人だ。

ただ、この本に惹かれて購入したわけではない。この本は『宮澤賢治研究叢書』シリーズ全八巻の第八巻になっている(図2)。実は、私が読みたかったのはこのシリーズの第一巻、科学評論家の草下英明(1924-1991)による『宮澤賢治と星』であった。しかし、神保町の古書店で、全八巻セットで販売されていたので、まとめ買いした。そのおかげで、偶然だが、小沢の本も手に入れることができた。
ところで、小沢はこの本のタイトルを考えていたとき、「薄明穹」だけでは物足りないので、何かアレンジをしたいと考えたそうだ。そのとき、知人から「動詞をつけたら」と言われ、『薄明穹を行く』にしたとのことである。素晴らしい着想だと思う。

漢字の世界は奥が深い
私は「薄明穹」という言葉を知らなかったのだが、それは当然のことであることがわかった。先にも述べたように、「薄明穹」は賢治の造語だったのだ。小沢俊郎による『薄明穹を行く 賢治詩私読』の「あとがき」に書いてあった。賢治マニアならいざ知らず、私のような素人が賢治の造語を知る由もない、何しろ、この本を買った4年前といえば、ようやく賢治関係の本を読み始めた頃だった。
「薄明穹」は「薄明」+「穹」という構造をしている。「薄明」は誰でも知っている。夕方、西の空に日が沈み、だんだん暗くなる。夜空が暗くなる前、沈んだ太陽の影響が残るうちは、空はまだほのかな明るみを持っている。これが薄明である。日が沈んでから、だいたい30分ぐらいは薄明の時間帯だ。しかし、天体観測をする際、薄明の影響がなくなるのは、日没後、一時間経過してからだ。この時間帯の薄明は「天文薄明」と呼ばれている。明け方の天文薄明は日の出の一時間前から始まる。
さて、「薄明」のことは、よしとしよう。問題は「穹」である。この漢字には「弓」が含まれているので、音読みの場合は「きゅう」だろうか? そのあたりまでは想像がつく。そういえば、浅田次郎の小説に『蒼穹(そうきゅう)の昴』というのがあったことを思い出した。しかし、訓読みはなんだろう? 『漢字ぺディア』で調べてみると、訓読みは、なんと5通りもある。おおぞら、あな、おおきい、たかい、ふかい。つまり、「穹い」と書いてあれば、「たかい」とか「ふかい」と読めるのだ。いやはや、漢字の世界は奥が深い。いや待て、漢字の世界は奥が穹い、と書いてもいいのだろうか。おおぞらのように広い世界という意味にできる。これは新発見だ。
賢治は薄明穹が好きだった?
結局、「薄明穹」は薄明の空、薄明の大空という意味だった。賢治はなぜこの言葉を創ったのだろうか? もちろん、薄明という時間帯を気に入っていたのだろう。夜の山歩きが好きだった賢治は、野宿もよくした。ということは、一晩のうちに2回も薄明を楽しめる。まず、日が沈んだ後の薄明。そして、夜が明ける前の薄明だ。
賢治の薄明好きは『【新】校本 宮澤賢治全集』の別巻(筑摩書房、2009年)についている索引で調べてみてわかった。本文篇だけに限っても、「薄明」が29回、「薄明穹」が25回、「薄明どき」が1回、作品に使われている。
実際に「薄明穹」がどのように使われているか見てみよう。
まず、短歌(『【新】校本 宮澤賢治全集』第二巻、筑摩書房、1995年)。
いまいちど空はまつかに燃えにけり薄明穹のいのりのなかに (392番)
薄明穹まつたく落ちて燐光の雁もはるかの西にうつりぬ (762番)
また、不気味な歌もある。
屋根に来ればそらも疾みたりうろこ雲薄明穹の発疹チブス (122番)
雲みだれ薄明穹も落ちんとて毒ケ森より奇しき声あり (512番)
賢治の心象や、いかに? という感じだ。しかし、賢治の心象スケッチは、そのときどきの正直な心象が反映されているのだろう。私たちができることは、それを単に受け入れることだけだ。
函館山から見た薄明穹
実は、「薄明穹」の意味を理解したとき、荘厳とまでは言わないが、何か神秘的な蒼の世界をイメージした。それに似たイメージは賢治の作品『泉ある家』に見つけることができた。
山の上では薄明穹の頂が水色に光った。(『【新】校本 宮澤賢治全集』第十二巻、筑摩書房、1995年、292頁)。
このような景色を見ることは難しいと思っていた。ところが、幸運にも、こんな景色に出会うことができた。
昨年の秋、ふと思い立って、北海道の函館を訪れた。函館といえば夜景だ。それは函館山の頂上から見るものだ。夕方、観光タクシーで函館山に登った。幸い好天に恵まれ、夜景を眺めるときが来た。ふと、函館市街の反対側に目をやったときだ。今まで見たことのない景色が夕空にあった。それは幾つもの美しい筋だ(図3)。

それがなんだかわからないまま、しばし見とれていた。あとで知ったのだが、これは薄明光線と呼ばれるものだった。
賢治は岩手山や早池峰山など、イーハトーブの野山で薄明穹を眺めた。きっと、こんな美しい薄明光線を幾度も見たことだろう。
賢治さん、今夜も「薄明穹」を行きますか?
註:薄明光線について、『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』(荒木健太郎、ダイヤモンド社、2023年、169頁)に、次のように説明がある。
大気中のエアロゾルに光が当たって散乱し(ミー散乱)その経路が見えるチンダル現象(エアロゾル:大気中の微小な液滴粒子、ミー散乱:光が光の波長程度のサイズの粒子に散乱される現象、チンダル現象:光の通路が斜めや横から見える現象)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
