
「宮沢賢治の宇宙」(25) 宇宙塵は美味しいですか?
『春と修羅』に出てくる宇宙塵
宮沢賢治にとって『春と修羅』は記念すべき最初の心象スケッチ集である。その「序」に宇宙塵という言葉が出てくるのをご存知だろうか? その部分を見てみよう。
・・・人や銀河や修羅や海胆(ウニ)は
宇宙塵をたべ または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です (『【新】校本 宮澤賢治全集』第二巻、筑摩書房、1995年、7-8頁))
ここに出てくる「人や銀河や修羅や海胆は 宇宙塵をたべ」とはなんのことだろう? なぜ、宇宙塵を食べるのか? 宇宙塵は食べられるものなのか? 謎だらけだ。
賢治にはたくさんの作品があるが、宇宙塵が出てくるのは、この一箇所だけである。
宇宙塵は食べ物か?
宇宙塵。この言葉を知っている人はあまりいないと思う。天文学では「塵」はコズミック・ダストを意味する。岩石を細かく砕いたような微粒子のことだ。しかし、「塵」と聞くと、多くの人は「ゴミ」を思い浮かべるのではないだろうか。厄介なことに、「宇宙ゴミ」というのも実はちゃんとした科学用語である。英語ではスペース・デブリ。地球の周りを回る人工衛星の壊れた残骸のことを意味する。ただ、最初の人工衛星スプートニクの打ち上げは1956年のことだったので、「宇宙ゴミ」が生まれたのはそれ以降のことだ。現在では深刻な汚染状況になってしまったが、賢治の時代には存在しなかった。
宇宙塵は平たくいえば固体微粒子だ。主な成分はケイ酸塩鉱物(シリケイト)や炭素(グラファイト)だが、鉄やアルミニウムなどの金属も含まれている。鉄分補給にはよいかもしれないが、食べ物とは言えない。
宇宙塵の大きさはおおむね0.1ミリメートル以下である。天の川銀河(銀河系)の中にあるガス雲の中や、太陽系の中にたくさん漂っている。地球に落ちてくると大気を刺激し、流れ星として見える。大気との摩擦で溶けてしまうこともあれば、溶けずに地表に落ちてくることもある(図1)。賢治は地表に落ちてきた宇宙塵を食べなさいと言っているのだろうか? ちょっと、遠慮したいところだ。

〔生徒諸君に寄せる〕にヒントがあった!
『春と修羅』の「序」に唐突に出てきた宇宙塵。賢治はどこでこの言葉を知ったのか? なぜ、この言葉に関心を持ったのか? 『春と修羅』の「序」で、宇宙塵という言葉に出会ってから、ずっとこれらの疑問が心に引っかかっていた。
そして、あるとき、ヒントを見つけた。そのヒントは『詩ノート』付録にある〔生徒諸君に寄せる〕〔断章六〕にあった。
新らしい時代のダーウヰンよ
更に東洋風静観のキャレンヂャーに載って
銀河系空間の外にも至って
更にも透明に深く正しい地史と
増訂された生物学をわれらに示せ (『【新】校本 宮澤賢治全集』第四巻、筑摩書房、1995年、298 - 299頁)
ここに出てくる「キャレンヂャー」は、今風にいえば「チャレンジャー」である。私たちの頭の中に浮かぶのは、スペースシャトルのチャレンジャー号だろう(図2)。
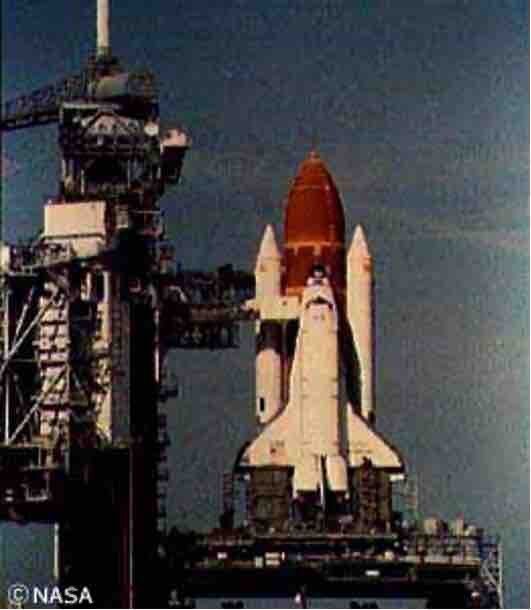
チャレンジャー号の大発見
賢治の時代にはスペースシャトルはない。したがって、「キャレンヂャー」は19世紀に活躍した「船」の方のチャレンジャー号のことを指している(図3)。
英国の海洋生物学者であるチャールズ・ワイヴィル・トムソン(1830-1882)の発案で、ロンドン王立協会はなんと海軍から軍艦であるHMSチャレンジャー号を借り受け、それを使って海洋探査を行った。チャレンジャー号探検航海と呼ばれるものだ。この航海は1872年から1876年にかけて遂行され、海洋学の発展に大きな貢献をした。その成果は1869年に創刊された英国の科学雑誌 「nature」 に大々的に発表され話題を集めた。

実はチャレンジャー号の活躍は日本でも早くから注目を集めた。公開の途中、2ヶ月間、日本に立ち寄ったからだ。その間、明治天皇との拝謁も行ったので、チャレンジャー号の名前は広く日本国民に浸透しただろう。
チャレンジャー号はマリアナ海溝の発見など、海洋の神秘を探究した。しかし、成果はそれだけではない。実は、海底から大量の宇宙塵を発見したのだ。
宇宙塵は北極圏の雪の中から発見されていたが(1874年)、チャレンジャー号による大量発見が宇宙塵の研究を大きく発展させたのである。
海底に宇宙塵がたくさんあるなら、海胆(ウニ)は宇宙塵を食べたかもしれない。賢治はそんなことに思いを馳せて『春と修羅』の「序」を描いていたのだろうか。
銀河系空間の外にも至って
賢治はスペースシャトルに姿を変えたチャレンジャー号が宇宙に飛び出すことを予測していたのだろうか。さすがに、天の川の外に出るのは難しいが。賢治の壮大な発想を見習いたいものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
