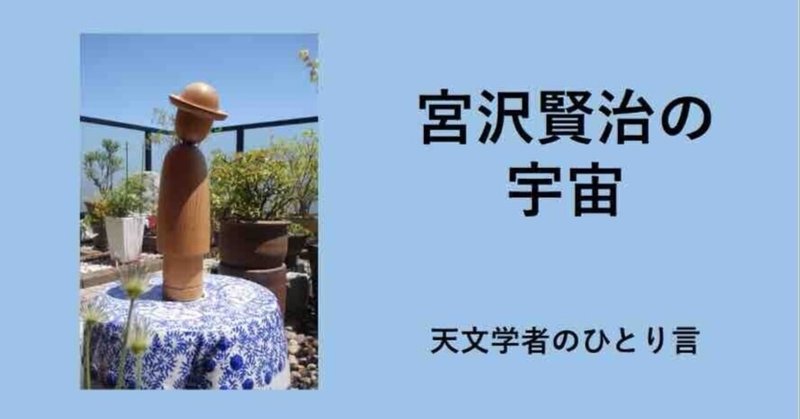
「宮沢賢治の宇宙」(54) 宮沢賢治は科学者だったのか?
科学者としての宮沢賢治
前回のnote「宮沢賢治の宇宙」(53)で「宮沢賢治は科学者に向いていたのか?」という話をした。 https://note.com/astro_dialog/n/nf2d6f89d924a
「科学者に向いているのか?」という話をする前に、本来は、「科学者とは何か?」を明らかにしておく必要がある。
前回のnoteで斉藤文一の次の文章を紹介した。
賢治はまた、優れた科学者であったが、その根っこのところには、自然の神秘に対する畏敬の念があった。空に浮かぶ雲であれ、さざめきながら流れゆく水であれ、そのずっと奥深くに息づいているものがあるのではないだろうか。 ・・・ 賢治が描く世界が、われわれの誰もが内にいだく自然への懐かしさを誘うのは、そのためでもあろう。・・・ (『科学者としての宮沢賢治』(斎藤文一 著、平凡社新書、2010年、10頁)
この文章で斉藤は「賢治は優れた科学者であった」と結論している。似たような議論は以下の本でもされている。
『宮沢賢治とその展開 — 氷窒素の世界 — 』斎藤文一 著、国文社、1976年
『宮沢賢治と銀河体験』斎藤文一 著、国文社、1980年
『宮沢賢治 — 四次元論の展開』斎藤文一 著、国文社、1991年
『銀河系と宮澤賢治』斎藤文一 著、国文社、1996年
『宮澤賢治をめぐる冒険 水や光や風のエコロージー』高木仁三郎 著、社会思想社、1995年
『宮沢賢治と化学』板谷栄城 著、裳華房、1988年
これらの本を読むと「宮沢賢治=科学者」ということが広く受け入れられているように感じた。
科学者とは何か?
では、科学者とは何か? WIKIPEDIAによると「科学を専門とする人、学者のこと」と書いてある。これだと、かなり曖昧な定義になる。例えば、「私は宮沢賢治を専門としています」と宣言すれば、宮沢賢治を研究する学者とみなされることにある。ありがたいことだが、「研究する」ことに対して、なんらかの定義がある方がわかりやすい。
そもそも18世紀までは、科学者という言葉はなく、自然哲学者と呼ばれていた。ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)も自然哲学者であった。19世紀になると科学、サイエンスという言葉が使われるようになった。そして科学に携わる人は科学者、サイエンティストと呼ばれるようになったのである。英国の科学者ウイリアム・ヒューウエル(1794-1866)が1834年に提案した。
「科学に携わる人は科学者」
科学者は「科学に携わる人」と定義されたわけだが、これでスッキリしただろうか? 「携わる」の意味が問題になるだろう。例えば、賢治は「石っこ賢さん」と呼ばれるほど、石に興味を持っていた。これを持ってして、賢治は石に携わる科学者としてよいか? 「鉱物学者」、あるいは分野を広げれば「化学者」だろうか。「携わる」を「研究する」と理解すると、賢治は「鉱物学者」でも「化学者」でもないような気がする。やはり、「科学者=研究する人」とした方が、納得できる。
研究とは何か?
「科学者=研究する人」と定義する場合、どういう人が科学者になるだろうか? 現状を見てみると、研究者には次のような人たちが多い。
[1] 大学・研究所で研究職に就いている
[2] 博士号を持っている(理学博士、工学博士など)
[3] オリジナル研究成果を査読付きのジャーナル(専門誌)に出版している
実際のところ、天文学者(科学者)をやっている私は、これら三つの条件を満たしている。なお、研究職に採用されるとき、博士号を持っていなくても大丈夫なこともある。ただし、修士号を持っていることは要求される。
これら三つの条件で一番重要な条件はどれだろう? それは、[3]である。やはり、オリジナルな研究成果の公表が研究者(科学者)には要求される。公表したことで、その成果が次の新たな研究に引き継がれるからだ。
これらの条件を課すと、賢治は科学者ではないことになる。科学者のスピリットを持って、自然現象に対峙していた人。科学との関係という意味では、これが正しい賢治像かもしれない。
キャベンディッシュはどうするんだ!
英国の自然哲学者ヘンリー・キャベンディッシュ(1731-1810)をご存知だろうか?キャベンディッシュは人嫌いが顕著な人で、そもそも人と会話をしないような人だった(図1)。

幸い、貴族の生まれで、莫大な遺産を使うことができたので、自由に物理や化学の実験を行うことができた。水素を分離して検出、また水が化合物であることも突き止めた(水はH2Oなので水素と酸素の化合物)。さらには電磁気学の重要な法則であるクーロンの法則やオームの法則も見出していた。さらには、地球の密度を測定する実験も行った(図2)。実は、これらの大発見は彼の死後、明らかにされたものだ。彼は研究成果を一切公表しなかったのだ。先ほど挙げた研究者の三つの条件は、どれも満たされていない。

キャベンディッシュのスタイルをまとめると次のようになる。
[1] 日宅に篭り、オリジナルな思索や実験的研究を行った。
[2] 学位は取ろうと思えば取れたが、取らなかった。
[3] 研究成果は一切公表しなかった。
キャベンディッシュは、死後、偉大な科学者の仲間入りをしたのだ。
ちなみに、彼の死後、研究成果をまとめたのは電磁気学の統一モデルであるマクスウエル方程式を完成させたジェームズ・クラーク・マックスウエル(1831-1879)だった。
「一個のサイエンティストと認めていただきたい」とは思わなかったのか?
キャベンディッシュは自分のことを、どう思っていたのだろう?
私がキャベンディッシュの偉大さに気がついたのは、イギリス・ケンブリッジで研究員生活を送っていた時のことだ。次のnoteを参照されたい。「バルコニアン」(11)番外編-イングリッシュ・ガーデン https://note.com/astro_dialog/n/n89bc2ea46a11
友人に「キャベンディッシュ研究所で天文関係の研究会があるから行ってみよう」と誘われた。その研究所は私の勤務していた王立グリニッジ天文台から歩いて15分ぐらいの場所にあった(図3)。研究所の名前になるぐらいだから、キャベンディッシュはすごい人なんだろうな」実は、その程度の知識しかなかった。あとで調べて、キャベンディッシュの偉大さを知った次第だ。

前回のnoteで、賢治は科学者に拘っていたことを話した。
私は詩人としては自信がありませんけれども、一個のサイエンティストと認めていただきたいと思います。
賢治が詩人の草野心平に宛てた手紙の中にある文章だ。
キャベンディッシュには「一個のサイエンティストと認めていただきたい」という気持ちはなかったのだろうか? 自己満足の日々を送るだけでよかったのだろうか? クーロンの法則やオームの法則を先駆けて発見したのだ。大声で「大発見だあ!」と叫んでもよいぐらいの業績だ。自己顕示欲を抑え込むほど、人嫌いだったということか。
それにしても、世の中には規格外の科学者がいるものだ。
キャベンディッシュがそれを教えてくれた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
