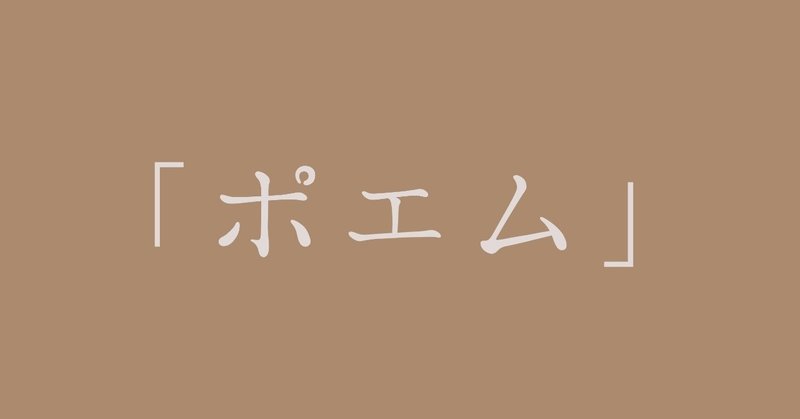
「ポエム」という語が使われるとき
「ポエム」という言葉が蔑称のように使われることがある。普段聞き慣れない比喩を使ったりした人に対して、「ポエマーだね」なんて言うあれだ。ある大臣の発言をして「ポエムだ」と揶揄したりするのも同じだろう。
ぼく自身、詩を書く身だけれども、確かに蔑称として人の書いたものや発言を「ポエム」と言ったり、その人を指して「ポエマー」だと言ってみたりする気持ちもわからなくはない。
ツイッターのタイムラインで明らかに違う言葉遣いをしている人を見たら、気持ちが悪いというのは納得する。そのようなとき、嫌悪感を自覚するかしないかのうちにスクロールするか、それともミュートにするか、あるいは……。
言葉には共有財産だというような漠とした共通認識があるのだと思う。たとえば近代国家の形成においては国民語を制定するのが常だし、似たような言葉を用いることで、仲間意識を育てたりする。聞き慣れない方言に疎遠さを感じたり、インターネットスラングに親密さを感じたり。
では、詩は、というと、そもそもの言葉の成り立ち自体を問いに付すところがあるのではないだろうか。つまり、この語にはこういう意味があって、この言葉にはこういう組み合わせの語を連ねて、というような暗黙のルールを一度宙吊りにしてしまうところがあるのではないだろうか。
もちろん、詩と言ってもいろいろな詩があるし、詩とは何か、というところまで考え出したらキリがないけれども、日常的に使う言葉遣いと対比されるものとしての詩は、日常的な言葉を、そして言葉が思考の同義語だとすれば、私たちの日常自体を問いただすものなのだと思う。
だから、詩を恐れるのは当然だ。笑いに回収してその怖さを乗り越えようとするのは当然のことだ。「ポエマー(笑)」だとして仲間外れにしないと自分が不安定になってしまう。
だから、詩ばかり読む人も逆にぼくは少し怪しむ。もしそんなに読んでたら気でも狂ってしまう(実際に「読んで」はいないから気が狂いはしない)。
「ポエマー」同士がかたまることはない。「ポエマー」たちは、差異ゆえに疎外されているからだ。それぞれの「ポエマー」がそれぞれに異質なものとして、異なる言語を用いる人として、弾かれている。
わたしは、ここに男たちのホモソーシャルな絆が女たちを排除する動きとしてのミソジニーと近いものがあるように感じる。
詩人とは概念を創造する存在でもあろうが、その概念(concept)とは、conceive、つまり孕まれたものであるということ。男たちは女たちを、男らしくない男たちを除く。日常言語の信奉者が詩人を除く。
産み出すものたちが除かれる。
詩を恐れるものたちは、それが呪力を持ちうるものだということを知り抜いている。だからこそ詩を嗤おうとする。
「ポエマー」という語を使い始めた人は詩人(ポエット)だ。概念の創出者だ。今やこの言葉は人口に膾炙している。
どうやったら、かの人たちに読ませることができるだろうか。もちろんそれが暴力であることを理解した上で。
100円でも投げ銭をしていただけますと、大変励みになります。よろしければ応援よろしくお願いします。
