
藤田和日郎『からくりサーカス』における「顔」についての一考察。
--しかしこれは周知のことですが、宗教が魂の救済を語りかけるときにはまずだいいちに地獄のことを、救済に反逆する魂の落ちていくべき地獄のことを思い浮かべているのです--イヨネスコ『ノート/反ノート』P112
■矛盾する欲望
『からくりサーカス』という作品には、たくさんの忘れがたいシーンがあるけれども、ぼくの頭の中には、忘れたくなってしまうシーンがひとつだけある。それは物語の展開上、必要すぎるほどに必要でありながら、作品の根底を揺るがす、あるシーンだ。
「ミンシア…私が、香港に役者をめざしてゆくおまえを許さなかったのは、私にとって「何かを真似し演じる」という行為がどうしても嫌だったからだ」
『からくりサーカス』16巻P106
武道家の「梁師父」が、香港で俳優として暮らす娘に遺したことばだ。彼は作中で「四年に一度しか年をとらず」「不死身に近い体を持つ」しろがねと呼ばれる生き物へも、似たような言葉を投げかける。
「偽りの「永遠の人生」など要らないのだよ」
先に引用した、娘に遺したことばと合わせると、どうやら「演技者」すべてに対して、そのことばは向けられているらしい。
しかしだ、しかしだよ、よく考えてみたまえ。彼はどう重く見積もっても、ひとつの作品、そう『からくりサーカス』というフィクションの登場人物なのだよ君。もしかして、彼が否定しているのは、このマンガの中の登場人物たちを描いている(演じている)作者そのものじゃないのか。
そんな矛盾を抱えれば、人はやがて当然のようにその見返りとして罰を受ける。彼は望みどおりに真実の死を選び、その死の行為によって読者の心に残り続けることになった。いつわりの永遠の人生を否定した彼は、最高の演技者として読者の心、とくにぼくの頭の中で永遠の生を得る羽目に陥ったのだ。
そんな梁先生には、黒目が描かれない。なぜ梁先生には黒目がないのか?
ここで、藤田和日郎の描く「黒目」に注目してみよう。
黒目の変形は情動の圧力を表す。
藤田和日郎の絵を真似するときに、もっとも簡単なのは変形した黒目を描くことだ。己の正義に燃え過ぎたか、喪失の悲しみに潤み溶けたか、はたまた邪悪なたくらみに隠せぬ笑みを漏らしたか、彼らは決まって歪んだ黒目を読者に向ける。(図1模写)
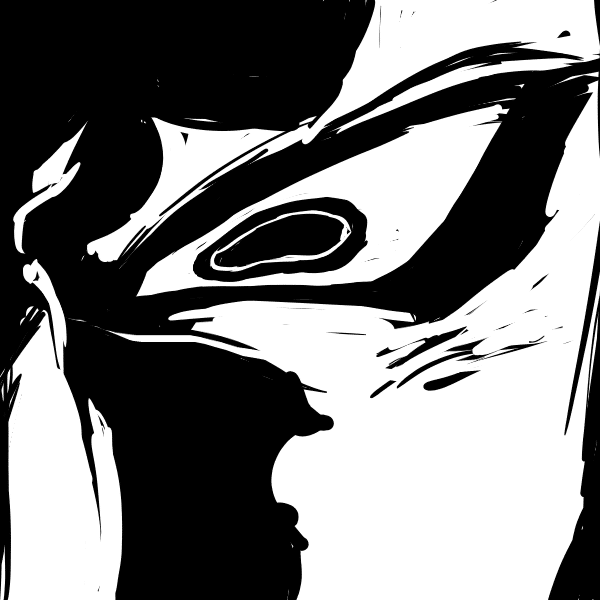
逆に正直でまっすぐな瞳は正円で、環境光がしっかりと反射する。(図2模写)
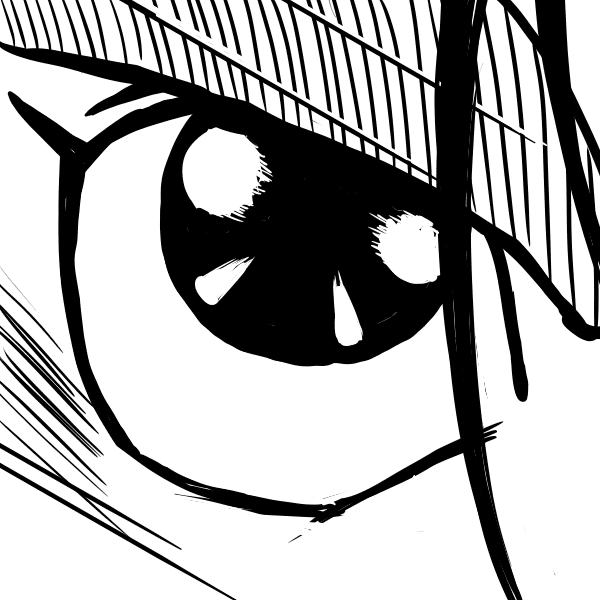
梁先生には、これらの表現を媒介するための「黒目」がもとから存在しない。つまり、彼には何の内面表現も許されてはいなかったということだ。梁先生自身が言うところの「自分の人生」を、なぜ彼が生きさせてもらえなかったか。
実のところ、彼にはもともとそんなものはなかったのだ。彼には主人公を目覚めさせ、作者のメッセージを伝えるという役割しかなかった。だから「物語の中の登場人物でありながら、物語の中の登場人物であることを否定する」という矛盾する欲望を抱えさせられた梁先生は、邪悪さや正しさを表現するための黒目を、はじめから与えてもらえなかったのだ。なんと残酷な作者であろうか。
そしてここに、本心を表現する装置「黒目」を、隠すことで使用不能にした登場人物が、二人現れる。道化の面をかぶった鳴海、そしてフェイスレスだ。特にフェイスレスはその登場時から、決してサングラスをはずさなかった。主人公を騙していたことを明かす、そのときまでは。
◾︎無自覚な虚言に恐怖する
ここで少し目線を変えて、とあるマンガの話をしよう。 カラスヤサトシ氏の描く四コマだ。「野菜の端っことかにはスーパーK細胞が入っている可能性が高くて、食べると超人になれるかもしれないからつい食べてしまう」と書いたすぐあとに「スーパーK細胞ってなに!? オレが考えたの!?」と恐怖を覚える。
こういう「意図せぬ虚言」はあまりに唐突すぎて、どこをどう笑ったらいいものかわからない気持ちになる(もちろん面白いと思いながら)。作者が作中で冷や汗をかいたように、読者であるぼくもまた、うすら寒い恐怖に身を震わせた。三秒前に言った自分のことばが、もしも自分でも気づかないような「うそ」だとしたら?
いま本当だと思っている自分の言動や気持ちが、どうして「うそ」じゃないと言えるだろうか。G=ヒコロウの「どーもッ!G=ヒコロウです! アメリカ行ってきました!!」って星条旗のシルクハットかぶって紙袋持ったまま登場した次のコマで「って行ってねえよ!! 何コレ!?」と自分の扮装を投げ捨て恐怖するやつもそれだ。ギャグマンガにもいろいろ種類はあるが、ツッコミを描く場合は常に客観的に自分の間違いを指摘しなければならない。
なぜぼくたちは、それを見て恐怖を感じたり、笑ったりするのだろうか。
答えは簡単だ。ぼくたちはいつだって、自分は自分だと思い込んでいる。
自分の考えや、自分の生き方や、自分の好き嫌いや、自分のあれやこれやが、まさか人の作ったまがいものだなんて思いもしない。だからそれが突然目の前に差し出されて、実はお前の考えは、まるでお前のものではないのだよ、などと言われてしまうことに恐れを抱く。
お前の見ている景色や、お前の聞いている音、お前の頭に浮かぶ過去の記憶などは、なんと誰か別の人間のものなのだ。とすればいま、この文章を読んでいるお前さんはもしや……よくできた「にせもの」ではないのかね。
「不気味の谷」ということばがある。これは人間によく似せたロボットを見ると、かえって人間との違いを強く感じとるのではないか、という予想を表したことばだ。これによく似た認知現象は、ロボット以外でもよく起こる。たとえばアライグマは人間によく似た動きをするかわいい人気者だ。模様のある毛皮で彩られた愛くるしい表情、サイズの小ささ、ふさふさの尻尾などに、ぼくたちは安心感すら抱いてしまうだろう。
彼らがもし毛のない人間サイズの生き物だとしたら、同じ愛くるしさを感じられるだろうか?
人が恐怖を感じるのは、少しだけ人と違う、にせものだ。
たとえば目鼻の位置が少しだけずれた人物画。動作に奇妙なところのある顔を隠した人物は、実は昆虫の擬態したものかもしれない。確かにいつもと同じように見えるが、少しだけ違う風景も、ぼくたちの神経を逆撫でする。いつもの帰り道を逆向きに歩いてみよう、暗闇で見る町の風景は、ただ進行方向を逆にしただけで、見たこともない不気味な影を色濃く見せるだろう。
偽の記憶や意図せぬ虚言は、こんな不気味さをぼくたちに感じさせてくれる。さっきまでのぼくが、ぼくではないような感覚。だからぼくたちはなるべく、うそをつかないように生きている(はずだ)。そしてうそをつくときは、それをうそだと自覚してつくだろう、それならば自分は自分でいつづけられる、過去の自分に裏切られることもないし、未来の自分が今の自分を見捨てることもない。
ところが、この境界を侵犯し、恐怖を感じてはいけない職業が、この世にひとつだけある。俳優だ。俳優はときに自覚的に、そしてときに無自覚にうそをつく。舞台上で泣いているとき演技者の心にあるのは次の場面転換時における小道具の片付け方かもしれない。けれどあるとき演技者は舞台上で本当に泣き、笑い、恥ずかしがり、誇らしく思い、そして何も思わない。観客は言うだろう、とても良い演技だった、特にあのソファの前を横切る動きは最高だったよ。すると演技者は決まってこう応えるのだ。「ほんとうに? おぼえてないよ?」
彼らはそのとき、漆黒の太陽へと変貌していたのだ。
◾︎おぼえていないこともある
「なんで、みんなしあわせになれないのさあ?!」27巻P139(図4)
複数人の記憶が次々と重なっていくことで『からくりサーカス』という物語は、次第に性質の悪いブラックジョークと化していく。主人公を取り巻く登場人物たちは、誰もがどこかで見たような顔をしていて、どこまでが真実なのかがわからない。あの感動はうそで、この憎さは間違いで、その怒りはにせものなんだよ。だって藤田は約束を破るんだ、うそをついているときに、本当に感動させる絵を描くのはズルいじゃないか。もちろんページをまたげば怪しげな描写をいくつもやっているのだから、ミスディレクションのテクニックと言われたらそれまでだ。だけどやっぱりぼくたちは、何ページも裂いて語られたフェイスレスの過去話にぐっと来たし、そのことばを受け取った鳴海の心意気にガッツポーズをしたはずなんだ。 そんな気持ちをぐちゃぐちゃに踏みにじるのが、顔の近似性だ。
フェイスレス、貞義、とうさん! ディーン! 勝! 同じ顔、同じ顔、また同じ顔だ!
どうやらまずぼくたちは、自分の目がどれだけちゃんと、ものを見ているのかということに気を配らなきゃいけないらしい。たとえば有名な視覚実験で、こういうのがある。youtubeなんかでも見ることができるから、知っている人も多いだろう。ボールを投げあっている複数の人が映っている。黒い服を着た人たちと、白い服を着た人たちの映像がオーバーラップし、画面には指示がでる。「白か黒の人に注目し、ボールが何回やりとりされたかをおぼえてください」。きみは素直に画面を見て、ボールの軌跡を追いかける。1、2、3……やがて映像は終わり、答えが出る。 あなたは画面を横切った○○に気づきましたか?……答えは自分の目で確かめてほしい(Visual illusion- Attention Experimentで検索すると良い)が、少しだけ補足すると、この実験は認知心理学者であるナイサーの研究グループが作った映像で、おもに「非注意による見落とし」を題材としている。
非注意による見落とし、そう、ぼくたちの見えているこの世界は、そのほとんどが欠けている。はっきりと、細かいところまで見えている場所は、きみたちが思うよりも、驚くほど狭い。たとえば目に入る映像の幅は、上下左右でおよそ120度ほど。でもこれは見えているというだけにすぎない。網膜に映った情報の中から、脳がちゃーんと処理できる、つまり何があるかを細かいところまで理解分析できるのは、この視線の先にある真ん中、手をぐっとのばして親指を立ててみよう。その親指の先に隠れるぐらいの幅、それだけが見えている世界のほとんどなんだ。たとえばね、今きみが見ているこの紙面をぐっと離して、親指、という文字だけ見てごらん、その文字から親指の幅以上に離れた文字たちは、眼球をくいっと動かさなきゃ読めないはずだ。そしてひとつの文字だけに集中して眼球を動かさないでいると、だんだんまわりの文字が、見えいているのに見えていない文字たちが、反乱を始める。似た形を抽出し、似ていない形を消し始める。漢字の数が減った気がしないか? 「け」と「こ」だけがやたらと目立たないか? 本当にきみが見ているのは意味のある文字列なんだろうか?
でも、普段のように無意識に眼球をふるふる動かすと、なんとなくボンヤリと見えているものを、ぼくたちは「あーこれは多分意味のある文字だな」と勝手に決め付けることができる。さっきのは思い過ごしさ、意味のない文字列を勝手に読んでいるなんてそんな馬鹿なことがあるもんか。意識して止めなければ、サッケード運動やらなんやらかんやら、眼球は微妙に動き続けているから常に新しい情報を得て「おっとこいつは……うん、文字に違いない」なんて確認をしてくれる。でもきみは体験したはずだ、眼球を少し動かさないだけでもやもやしてくる、この世界ってやつの不気味さに。
幻覚を見る仕組みというのも、脳に標準装備されている。といってもそれは普段はありえない風景や空を飛ぶドラゴンなんかを見せてはくれない。代わりに盲点を埋める作業をしてくれている。そう、目の中にある盲点には、まったく映像が映らない、でもぼくたちの前にある風景には穴なんて空いてない。脳は穴のまわりの風景を引っ張ってきて埋めているらしい。そこにはない風景を勝手に脳の中で作って見ているんだから、これだって立派な幻覚だろう。
ちなみに盲点を確かめる簡単な方法はこうだ。A4くらいの白い紙に二つ、横並びの点を打つ。できれば目の幅くらいが好ましい。その紙を手に持って、片目をつぶってひとつの点に、近づいたり遠ざかったりする。それだけだ。何度か往復していると、注視しているのと反対側の点がふっと消える。そら、そこに盲点があるってわけさ。脳はまわりの白い部分を勝手に持ってきて、視野の中にある不思議な穴を埋めたってこと。さらに強く「勝手な幅寄せ」を体感したい人は、中心に空白のある十字を書いてみるといい。その十字が盲点に重なると、なんと中央の空白は消えて、なんとなくつながった十字模様がそこにあらわれる。本当は何もない空間に、ありえないものが出てくるというわけだ。
この「あまりよく見ていないものは、見えないけど見えているフリをする」という脳の特性は、ぼくたちに恐ろしい感覚を与えた。見えているものは、常にそこにあるものは、きっと変わらないはずだ、という感覚だ。 だから騙される、白い紙の上にのたくる線を見て、そこに人間を見出した気になってしまう。自分の理想や夢を投影して、癒されて、楽になる。単なる線、単なる影、単なる闇なのに。ぼくたちはそこを安住の地と思う。だって顔があるから、ぼくらを見つめてくれるから、それが敵でも味方でも、ぼくたちに背を向けて去ってはいかない。マンガはいつでも正面を向いているからだ。
■マンガの正面性(フロンタリティ)
そもそも絵画の技法であった正面性が、なぜマンガと相性が良かったのかは、わからない。でもぼくたちが読んでいるマンガのキャラクターたちは、とくに『からくりサーカス』のキャラクターたちは、ことさらに前を向く。フェイスレスと勝の戦う場面など、二人の顔、顔、顔、に眩暈をおこしそうになるくらいだ。 ぼくはたぶん、人間の視野の狭さが原因だろうと予測をたてた。見開きの大きなアクション画面を見ているときでも、注視しているぼくたちの目は、正面を向いたキャラクターの顔を追いかけている(おれは顔なんて追いかけないぜって人は、まあ優雅な集中線でも見て楽しんでいてくれたまえ、ぼくたちは先へ行く)。常に前を向くキャラクターたちの顔は、豊かな表情を持って画面上を駆け巡る。それはともすれば作者による情動の押し付けになってしまうところだけど、静かな暴力とでも言うべきマンガの特性が、その力を和らげてくれる。
先ほど中心視野についての話を書いたが、周辺視野、つまり120度の範疇にだって視界は存在する。そこには何が見えているか。
動くものが見えている。
中心視野が解像度中心の能力を持っているのにくらべ、周辺視野は動体視力に優れているのだ。この視野内における能力の違いが、他の映像メディアとマンガから受ける印象を大きく隔てる原因だ。舞台や映画では、観客は画面の中から、見るべきものを探す必要があまりない。なぜならそれは多くの場合動いている、もしくは動いていないからだ。その区別を脳は勝手につけてくれる、動いているものを「動いていない」とは思わないし、その逆もない。
マンガは、賢明なる読者諸君におかれてはご存知のとおり、はじめっから動きゃしない。画面の中で動いているものを、動いているように見せるための技術は数多くあるけれども、やっぱりどこからどう見ても動いているように見えるそれは、動いてはいない。この動かない画面の中で、流線や集中線の中で、キャラクターの顔は待っている。信管をむき出しにした爆弾のように、読者がハンマーでぶったたくのを待っている。これが静かな暴力性ってやつだ、読者と出会い、読者がそこに何かを見出すまで、マンガは静かに黙つだけだ。
どんなに押し付けがましい主張があっても、読者の中心視野がそこに至らなければいい、なにしろ人間は見たいものだけ見ることに慣れているのだから。ほら、もうすぐだ、あの子が見てくれる、キラキラ光る雷管を、その小さなハンマーでコツンとやっておくれ! 爆発! 感動! 怒り! 悲しみ! 苦痛! 快感! 流れ込む情動! 爆弾は炸裂し、メッセージはなだれうち、読者はそれをごくごくと飲み干す。からりと乾いた紙面の上で、フェイスレスが笑ってる。
ぜんぶうそだよ~ん。
■こりゃいい、乗り物が運転手に逆らってどうするんだ!?28巻P78
梁先生が黒目を持たないのも、鳴海の道化面が黒目を持たないのも、ここはそれこそが藤田の贖罪意識であると断じよう。 何から何までうそだらけの世界で、ほんとうのことを言いたいときに、なんの表現もそこに含ませたくはなかったのだ。だとすれば、そこまでにフィクションに追い詰められていた藤田が『からくりサーカス』を完結させたのは、もはや奇跡に近い所業だとも言える。と偉そうに語ってみても、ぼくはただ『スプリンガルド』や『月輪』に出てくる白目に、何らかの意図を勝手に読み取るだけだ。ああ楽しい。
そして新しい物語が始まる。『月光条例』の主人公月光は「本当のことを言わない」主人公だ。だがその一言、毎回繰り返される「彼はうそをつく」というただ一言が、この物語を単なる勧善懲悪から程遠い、凄まじいものへと変貌させてしまう。そして相方の「エンゲキブ」は梁先生の否定した「いつわりの永遠」なんて知らぬ顔で演じること=うそをつくことを楽しんでいる。彼らは誰だ、操り人形ではない、では何だ。
フェイスレスは言った「地獄の大きな機械」がぼくの運命を回してる。そのとおり、彼は結局最後の最後まで自分が何をしているのか気づかなかった(ほんとうに最後の時に至るまでは!)。でははじめから気づいている者は? 自分がうそつきで、みんながうそつきで、それでもやっぱり地獄の大きな機械がぐるぐる自分を巻き込もうとダンスしているとしたら? 月光は応える。真っ白な濁りない瞳で。
「正さねーよ」
運命の機械を軽やかに乗り回す、彼らは新たに生まれたフェイスレス。月光とエンゲキブの物語に幸あらんことを。
了
初稿 2010年
改稿2019年
あとがき
10年ぶりに読み返してみると、いやはや論旨は曖昧だわ話はあっちゃこっちゃに飛ぶわ、よくぞユリイカさんも載せてくださったことである(初稿は『ユリイカ 』誌 2010年2月号 特集=藤田和日郎、掲載)。というわけで前段中段をごっそりと改稿した。が、これも10年後にはまた書き直すのかもしれない。
ともあれ、読んでもらえて本当に嬉しい、ありがとうございます。
ここから先は
¥ 200
サポートしていただけると更新頻度とクォリティが上がります。
