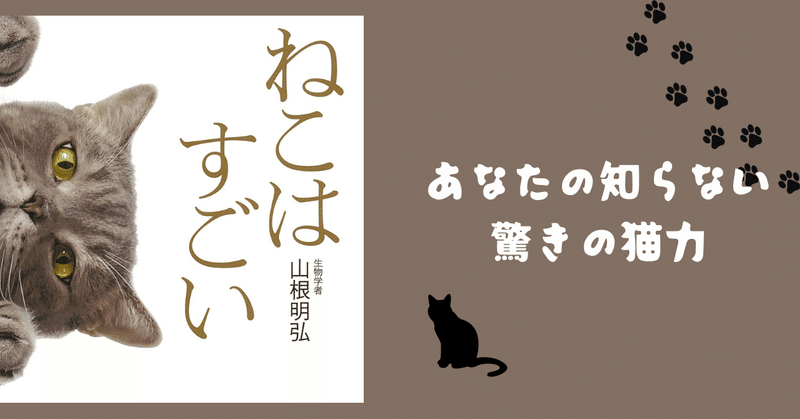
あなたの知らない驚きの猫力 『ねこはすごい』を立ち読み
身近な存在なのに謎がいっぱいの「ねこ」。長年一緒に暮らしても、その行動や感情表現など、不思議に思うこともたくさんある。朝日文庫『ねこはすごい』(2022年2月)は、ねこの調査研究を行っている動物学者である山根明弘さんが、優れた身体能力や感覚器の鋭さから人間の治癒力まで「すごい」生態を解明する、ねこ好き必読の一冊だ。加えて、全国各地の招き猫、猫碑、猫道祖神などのフィールドワークから、古来から続く日本人と猫との温かな交流の歴史を辿り、日本人の猫との関係性に迫る。本書の「はじめに」と「目次」を特別に公開する。まずは立ち読み気分で、あなたの知らないねこのすごさを知ってほしい。

■はじめに
日本人は世界有数の「ねこ好き」国民といわれています。街のなかで、ごくあたり前のように「ねこのキャラクター」や「ねこグッズ」を目にするのは、どうやら日本特有の光景のようです。外国人から見ると多くの驚きがあるそうです。
わたしが昔、ノラねこの研究をしていた福岡県の相島へは、最近の「ねこブーム」の影響もあって、たくさんの人がノラねこに会いに訪れます。若い女性のグループもいれば、カップルもいます。ねこ大好き家族や、動物カメラマンまで。そのなかで、近年よく見るのは外国人です。日本への観光の目的のひとつが国内に点在する「猫島めぐり」という人もいました。
2014年、わたしのもとを訪ねてきたドイツ人の若い男女は、日本に数カ月滞在しながら、全国の「ねこスポット」をめぐっているとのことでした。彼らの来日の目的は、日本人とねことの深い関係、そして日本の「ねこ文化」をテーマとした映画の撮影でした。作品はドイツの映画祭に出品するそうです。
ねこ好きの外国人が口をそろえていうのは、日本は「ねこ文化大国」で、日本人ほどねこ好きな民族は他に存在しないということです。具体的には、日本のどんな大都市でも、路地に足を一歩踏み入れれば、そこにはあたり前のようにノラねこが暮らしている。さらに、街には「ねこ」がデザインされた服や小物を身につけた子供や女性があふれ、店に入れば何かしらの「ねこグッズ」が売られていて、書店などではねこの写真集のコーナーまである。このような光景に、海外からの旅行者は驚き、特にねこ好きの外国人は興奮するそうです。少なくとも、こんなねこまみれの光景は、ヨーロッパではあり得ないことなのだと。
日本人にとっては、ごくごく日常的でありふれたことであっても、海外の人の目には、とてもユニークで、そしてクールに(カッコよく)映るものがあります。彼らの熱狂的な反応によって、わたしたちは少し戸惑いながらも、自国の文化や習慣のユニークさや素晴らしさに、あらためて気づかされることも珍しくありません。たとえば、寿司や蕎麦などの和食、日本の伝統文化や職人の技、最近のものではマンガやアニメ、ファッションなどがそれにあたります。そして、日本人とねことの深い関係も間違いなくそのひとつのようです。恥ずかしながらわたし自身も、外国人の熱狂ぶりによって、そのことを再認識させられました。
日本人とねことの関係の始まりは、いまから1400年ほど前の飛鳥時代(最近の研究からは弥生時代の可能性も)の頃までさかのぼるといわれています。中国からの、ありがたい仏教の教典をネズミから守るため、教典とセットでねこが持ち込まれたとの説もあります。農耕民族である日本人にとって、ねこはとても役に立つ動物でした。いうまでもなく、瑞穂の国の日本では、米は食と生活、そして文化の原点です。その大切な米を食い荒らすネズミは、日本人の天敵といっても過言ではないでしょう。そんなネズミを次々と退治してくれるねこの登場は、当時の人々にとっては、少しおおげさかもしれませんが、救世主(メシア)が現れたようなものだったのかもしれません。米だけでなく、絹糸を生産する養蚕業にとっても、ねこは必要不可欠な存在でした。絹を吐くカイコやカイコがつくる繭をネズミから守るために、一昔前までは、養蚕の盛んな土地ではたくさんのねこが飼われていました。ねこが足りなくて、ねこを描いた絵を壁に貼って、ネズミ除けにした時代もあったくらいです。
さらに、四方を海に囲まれた島国日本は、古より漁業が盛んな国でもあります。昔の船は、「板子一枚下は地獄」といわれる木造船でした。船をかじるネズミは、漁師の生活どころか、命さえも奪いかねません。漁村においても、ネズミを退治するねこは、当然のことながら重宝され、船の守り神として大切にされてきました。わたしたちがねこを特別な動物として大切にする習慣は、農業や漁業を生業とする日本人の生活特性と深く結びついています。日本人がねこ好き民族である理由は、第一にこのあたりにあるように思います。
ねこにとっても、日本人とともに暮らす生活は、十分に快適なものでした。湿気の多い気候にあわせてつくられた、昔の日本の木造家屋には、ねこが自由に出入りできる隙間がたくさんあり、軒下や天井裏など、ねこが出産したり、身を隠したりする場所もたくさんあります。さらに、食べ物に関しても、海辺の漁師町では魚のアラや雑魚などのエサが豊富にあります。海が近くになくとも、農村地帯の家屋のまわりには自然がたくさん残っており、野ネズミや野鳥、トカゲなどの天然のエサも豊富にあります。ねこにとってほとんど栄養にもならない、麦飯にみそ汁をかけただけの「ねこまんま」しか飼い主から与えられないとしても、家のなかにはネズミもいますし、外に出ればエサとなる小動物たちがたくさんいました。自然に恵まれた日本の環境は、ねこにとっても随分と暮らしやすいものであったようです。
このような双方の利益の一致から、ねことわたしたち日本人は、お互いにかけがえのないパートナーとして長年一緒に暮らしてきました。この蜜月関係は、ねこがネズミを捕るという役割をほぼ終えてしまった現在も、少しずつ形を変えながら続いています。
しかし、これほどまで身近な動物でありながら、わたしたちはねこに秘められた素晴らしい能力について、つまり「ねこのすごさ」について、知っているようで、実はあまり知らないことも多いのではないでしょうか。それもそのはず、家のなかにいるねこは、ご飯を食べている時と、遊んでいる時以外は、ほとんど一日中寝て過ごしています。普段の生活態度を見ている限りでは、ねこは、なんとも気ままで、お気楽な生き物なのだろうと思われても仕方がありません(そこがまた、ねこの魅力ではありますが)。しかし、遊びに興じている飼いねこのちょっとしたしぐさのなかに、あるいは街のなかで、高い塀に軽々と登ってしまうノラねこの姿を目撃して、さらにはネットで話題になった、身を挺して大型犬から飼い主の子供を守る勇ましい行動に、ねこの底知れぬ能力を、「ねこのすごさ」のほんの一部を見て、びっくりすることはないでしょうか?
実は、ねこの身体能力や感覚器の鋭さは、いまから約1万年前の、野生のヤマネコだった時代から、ほとんど失われていません。獲物に音も立てずに忍び寄り、射程圏内に入れば、一気に飛びかかって瞬時に獲物の息の根を止めてしまう。そんな凄まじい野生のハンターの身体能力をそのまま持ち続けた動物と、わたしたちはひとつ屋根の下で一緒に暮らしています。いわば、ねこの大きさにした獰猛なトラやライオンと、一緒に暮らしているようなものです。
しかし、一緒に暮らしていても、そのようなすごい身体能力を、ねこたちはなかなかわたしたちに見せてはくれません。それは、人間に知られないようにわざと「ツメを隠している」のではなく、人間と暮らす快適な生活のなかではそんな能力を使う必要がないからです。日々、自分に正直に生きているねこは、生きていくうえで不必要なことは決してしません。この本では、このように秘められた、ねこの潜在能力について、紹介してゆくつもりです。みなさんは、ねこのすごい能力を知って、きっと驚かれることでしょう。そして、そんなすごい動物と、同じ家のなかに、あるいは同じ街のなかで、一緒に暮らしていることを知って、興奮し、そして嬉しくなってくるかもしれません。
この本は私の前著『ねこの秘密』(文春新書)と内容が少し重なる部分もありますが、新たなトピックスを加えるなどして、前著とはまた少し違った視点から「ねこのすごさ」をみなさんに知っていただこうと思っております。
ねこは本来、ネズミを捕るという能力が高く評価されて、人間に大切にされてきました。しかし、日本をはじめ多くの先進国では、次第にその役割を終えようとしています。それでもなお、人はねこと暮らし続けています。その理由は、ねこを飼ったことのある方にはいわずもがなですが、ねこと一緒にいることで、人々は心が癒され、日々の生活に潤いや張り合いが生まれるからです。特にストレスの多いといわれる現代社会では、心を癒してくれるねこの役割が、今後もますます注目されると思います。「ねこカフェ」が、都市部を中心に人気を集めるのもそのような理由からなのでしょう。さらに、この癒しの効果は、ねこを家で飼ったり、「ねこカフェ」などで、かわいいねことのふれ合いによって得られるにとどまりません。漁師町や山里、そして都会で、たくましく生きるノラねこの素の姿をとらえた写真集がよく売れていることからも明らかなように、気ままなねこの生き方を眺めるだけでも、人々は癒しを得ています。何物にも縛られない、自由気ままなノラねこの姿を見て、なにかと集団で行動することの多いわたしたちは、そんな生き方に憧れ、つかの間の自由な生き方を疑似体験しているのではないでしょうか。この本では、現在のストレス社会に疲れた人々の心を癒し、元気にしてくれるねこの「すごい」力についても紹介したいと思います。
昔からわたしたちは、ねこと深い関係を持ち続けている一方で、最近では、この関係も現代社会の持つ負の影響を受けつつあることも確かです。具体的には、ねこの殺処分です。日本では、年間に2万7000匹超のねこが、人間の手によって殺処分されている事実(環境省ウェブサイトによる、2021年)を、みなさんはご存知でしょうか? それに加えて、ブリーダーやペットショップなどの販売業者の流通過程で、6486匹(2018年度)ものねこが死亡しています(『朝日新聞』2020年6月25日夕刊)。世界有数のねこ好き民族、ねこの文化大国と、海外の人たちからもてはやされているわたしたちが、このような問題を抱えたままでは、やはりよくないと思います。この本の第4章では、日本人とねこの蜜月関係を、江戸時代の招き猫や浮世絵などのねこ文化についても振り返りながら、もう一度見直してみようと思います。これをヒントに、今後わたしたちは、同じ社会のなかで、ねことどのように共存し、ともに暮らしてゆけばよいのか、さまざまな新しい試みについても紹介しながら、考えてゆこうと思います。
■ねこはすごい 目次
はじめに
第1章 ねこはつよい
ねこは「つよい」生き物
ねこは最強にして究極のハンター
「ネコ科」動物としての狩りの能力
飼いねこも「ハンティング行動」をする?
驚くべき身体能力
ねこは時速50キロメートルで走る
ねこは1.5メートル跳ぶ
ねこが木に登れる理由は?
ねこの牙
ねこの歯はどんな構造?
ねこの歯はナイフとハサミ
ねこのツメ
ねこのツメはカッターナイフ
ノラねこのツメ痕はコミュニケーションの手段
母ねこは最強?
母ねこに見る動物の普遍的な「つよさ」
オスも子ねこの面倒を見る?
第2章 ねこの「感覚力」
ねこは暗闇なんてへっちゃら
ねこの目はなぜ光るのか?
夜行性動物として進化したねこの目
ねこの視力
ねこはなぜ色をあまり認識できないのか?
ねこのすごい動体視力
ねこは動く物体を「コマ送り」で見ることができる?
ねこの瞳
ねこはなぜ明るさによって瞳孔の形を変えるのか?
遺伝子によって決まる目の色
ねこの聴力はすごい!
ねこの聴力は人間の5倍?
人間の生活音はねこにとってストレス?
耳で知るねこの気持ち
ねこの耳は喜怒哀楽を表す
ねこは、ねこや人の声の聞き分けができるのか?
個体によって異なる、ねこの鳴き声
瀕死の状態でも娘ねこの鳴き声に反応した母ねこ
ねこの嗅覚は人間の約10万倍
ねこの嗅覚は「嗅細胞」が多くあるため
ねこのニオイ情報の世界
ねこが自分のニオイをなすりつけたがる理由
cauxin旺盛なオスねこの尿
強いオスの尿は特に臭い?
ねこのヒゲ
ねこのヒゲはセンサーの役割を果たす
ヒゲの向きでわかる? ねこの気持ち
ねこの味覚
第3章 ねこの「治癒力」
ねこは健康によい?
ねこを飼うと健康になる?
ねこは心の病も癒してくれる?
ねこはうつ病を治す?
社会のなかで活躍するねこたち
ねこカフェの効能
さまざまな場で活躍するねこといぬ
第4章 日本がほこる「ねこ文化」
そもそもねこはいつ、日本にやってきたのか?
約3500年前、ねこは古代エジプトで完成した
ねこはいつ頃日本に渡ってきたのか?
招き猫文化
招き猫はいつ生まれた?
招き猫は現在も進化する日本のねこ文化の象徴
ねこブームは、昔からあった!
江戸時代にも現在のような「ねこブーム」があった?
ねこの着せ替え人形
現代の「ねこ事師たち」
招き猫、浮世絵、猫本、猫雑貨……ねこ文化を伝える人たち
絵画、イラスト、新聞……ねこ文化に貢献する人たち
第5章 人とねことの共存社会に向けて
不幸な飼いねこをどうやって減らすのか
ねこを飼うには「覚悟」が必要
高齢者がねこを飼うためにしておくこと
殺処分されるノラねこを減らすには
安易なエサやりはやめよう
高齢者のノラねこへのエサやりを防ぐには
各地に広がる地域猫活動
ネットワークで強まる各地の地域猫団体
ノラねこの生き方を尊重する方法を模索して
ねこも人も幸せに暮らせる社会とは
相島の人たちに学ぶ、ねことの共存社会
相島のノラねこたち
おわりに
文庫版あとがき
参考/引用文献
