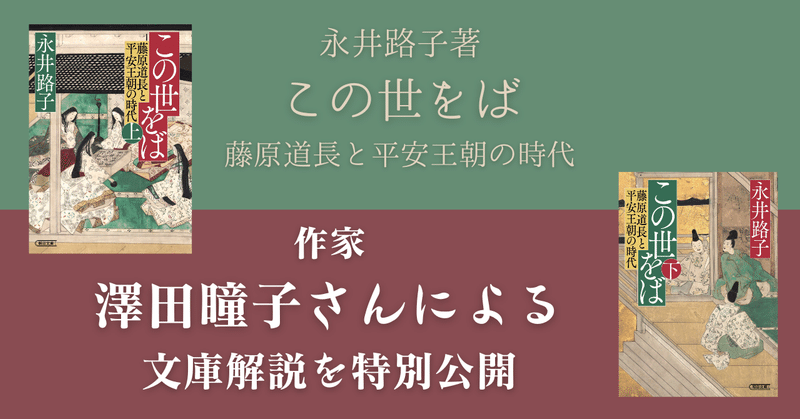
NHK大河「光る君へ」をより深く楽しめる一冊!永井路子著『この世をば 藤原道長と平安王朝の時代 上・下』澤田瞳子さんによる文庫解説を特別公開!
永井路子さんの『この世をば 藤原道長と平安王朝の時代』(朝日文庫)が刊行されました。平安時代の寵児・藤原道長の生涯を描いた王朝歴史小説です。藤原兼家の末っ子に生まれ、優秀な兄たちに比べて「平凡児」だった道長が、多くの賢女たちに恵まれ、いかにして頂点を極めていったのか――。王朝の貴族社会が鮮やかに描かれ、NHK大河ドラマ「光る君へ」をより深く楽しめる一冊です。本書の刊行にあたって作家の澤田瞳子さんがご執筆くださった解説を掲載します。

英雄を一点非の打ちどころのない人物として描くことは、非常にたやすい。なぜなら英雄とは凡人の予想もつかぬ人間であるがゆえに英雄たりえ、突飛な行動も非論理的な言説も「英雄」という設定の前には、すべて許されてしまうからだ。
難しいのはむしろ、英雄をただの平凡な生身の人間として描くこと。超人であれば遭わぬであろう悩み苦しみ、ただ人であるがゆえの苦悶……生身の人間を余さず文章を以て捉えるには、残酷なまでにひたむきな観察と精緻な描写が必須となる。
本作において永井路子は、平安中期の寵児たる藤原道長を、時代の覇者ではなく、徹底的に幸運に恵まれた平凡児として描いた。とはいえ従一位摂政太政大臣、娘を三人も天皇の后とし、三人の天皇の外祖父となった彼は、一説には『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルとの説もある男。それだけに『大鏡』や『栄花物語』といった平安後期に記された歴史物語は、道長を並々ならぬ才能の持ち主と評価する。「権者」、つまり神仏の権化であると誉めそやす記述すら見られるほどだ。
それだけに本作の道長像――すなわち、容貌は残念ながら人並。美貌にはほど遠い顔立ち同様に、性格も平々凡々。末っ子ならではのおっとりしたところだけが取り柄で、ついでにいえば舞や管絃といった素養にも欠けるという描写に、読者の中には肩透かしを食らった気分になる方もおいでかもしれない。しかしながらそもそも道長は摂関家の正室腹の御曹司ではあるが、所詮は五男坊。同母の兄たちが相次いで病没したため、たまたま幸運に恵まれたという史実に接すれば、なるほど永井の描く人物像も決して不自然ではないと得心できるはずだ。
この物語は、そんな道長の正室となる源倫子の婿取りから幕を開ける。左大臣の長女であり、宇多天皇の曽孫に当たる倫子は、年頃さえ釣り合えば天皇の妃として入内しても不思議ではない高貴な姫君。それだけに『栄花物語』によれば、倫子の父は実のところ道長を「口わき黄ばみたるぬし(青二才)」と評し、彼の婚姻の申し出も「あなもの狂ほし(馬鹿馬鹿しい)」と言って、まったく取り合わなかったらしい。真摯な歴史研究を基盤に作品を発表し続けてきた永井は、こういった史料の記述を積み重ねることで、英雄視されがちな道長観を取り払い、彼を生身の人間として描き出すことに成功している。
道長の同母の二人の兄のうち、長男は苦労知らずの独断専行型の人物、次兄は人を陥れることにためらいのない峻烈な男。本作はそんな兄たちに頭を押さえられてきた末っ子が、気の小さい自分自身を見つめ直しながら時代を泳ぎ渡る物語とも言い得るであろう。
だが本作において何より注目すべきは、これが藤原道長という一人の男の生涯であるとともに、彼を支える女たちの物語としても構築されている点だ。前述の通り、本作は倫子の婿取りから始まり、倫子の介添えを受けつつ彼岸へ赴く道長の姿によって幕を下ろす。だがそもそも「出世の見込はまずないな」と倫子の父にこき下ろされていた道長が婿取りに成功したのは、倫子の母の強い推薦と、姉である詮子の励ましあればこそ。道長自身はうまく行きそうにないなら仕方がない、と早くから諦めモードであるのが実に情けない。
すでに幾人もの妃が天皇に侍る後宮に17歳で上がった詮子は、時に道長をたじろがせるほどの強い闘志の持ち主。そして女たちの戦を勝ち抜き、一条天皇の母として君臨する彼女は、決してその栄光に溺れる愚かな人物ではない。かつて恨みを呑んで亡くなった藤原氏の政敵の娘・明子を道長に娶せ、彼女を幸せにすることで怨霊の憎しみから一族や我が子を守ろうと奮闘したり、甥・伊周を取り巻く高階一族を警戒し、それゆえに道長を引き立てんと策を巡らす。いわば藤原氏一族の守護者とも呼ぶべき女傑である。
永井はこの詮子の動向を、各人の個性ではなく、「古代から連綿と続いた母后の発言力のなせるわざ」と喝破する。当時の人々の中には女系中心の考え方が根強く残っており、それが詮子の一条帝に対する発言力の大きさとなったのだ、と。
――この時代、官位の昇進に関しては父親の七光が大いに効果があるので、母系、女系の連帯感はつい見おとされがちだが、いわば水面下にたゆたうこの意識が、いざというときには案外力を発揮するのである。
という永井の指摘は、女性史研究が端緒についたばかりの1980年代の作とは思えぬほどに先進的である。この眼差しは道長の長女であり、後に後一条天皇を産むことになる彰子にも向けられており、道長はまだ幼いと思っていた娘の堂々とした態度に、幾度となく驚かされることとなる。
ところで平安女性史研究の第一人者である服藤早苗らを編者とし、2020年に刊行された『藤原道長を創った女たち――〈望月の世〉を読み直す』(明石書店)は、源倫子や明子、彰子といった道長の親族や婚族、更に側仕えの女房など多くの女性の分析を通じ、道長の栄光の新たな側面に光を当てた研究書である。第一章「道長を創った女たち ジェンダー分析の提唱」において、服藤は以下のように記し、この論集の射程を明らかにしている。
――作家の永井路子『この世をば』は、一九八四年に出版されたが、道長の正室源倫子の視点で道長の生涯が描かれていた。平安時代の研究を始めたばかりの駆け出し研究者の筆者は、女性たちが多く登場し、何とも新鮮な印象を受けた。多くの女性たちの登場のみならず、婚姻の最初は妻方で同居し生活の扶養を得る妻方居住婚、すなわち「婿取婚」からはじまる当時の家族婚姻実態がきちんと反映されているのも嬉しかった。(中略)しかし、小説刊行から三十五年、道長を取り巻く女性たちの史料に即した実像は明らかになったのだろうか。
ここからは本作刊行当時、永井が描いた道長と彼を「創った女たち」の姿が如何に斬新かつ正鵠を得ていたかが明確に分かる。ただ一方で、永井が本作において、道長を取り巻く女たちをただ彼に権力を与えるための道具のみとしては扱っておらぬことにも、我々は注意せねばならない。
長女・彰子の入内前夜、一条天皇の最愛の女性・定子が懐妊したと知った倫子は、娘の入内中止を夫に請願する。まだ12歳とあどけない娘を、熾烈な女たちの戦に加わらせたくない。そう涙ながらに夫をかき口説く倫子の姿には、左大臣の正室たる威厳はない。そこにはただ、娘を案ずる一人の母親の狼狽があるのみだ。そしてそんな妻に対し、もはや自分たちに逃げ場はないと言い聞かせる道長の姿もまた、倫子同様、およそ幸運に恵まれた男らしからぬ脆さをあらわにしている。徹底的な歴史考証があればこそ描き出せる、生身の人々の哀歓がここにはある。
ちなみに来年2024年は、NHK大河ドラマとして紫式部を主人公とする『光る君へ』が放映される。歴代NHK大河ドラマの中では1976年放送の『風と雲と虹と』に次ぐ古い時代を扱う注目作であるが、先日、『光る君へ』の時代考証を担当なさる倉本一宏・国際日本文化研究センター教授から興味深いお話をうかがった。
倉本氏はまだ駆け出しの研究者でいらした頃、永井の夫――すなわち古代史研究者であった元・清泉女子大学教授・黒板伸夫に電話をかける機会が幾度となくおありだった。倉本氏は電話を取る永井とやがて雑談を交わすようになり、「いつか『この世をば』がドラマ化された際には、ぜひ考証をさせてくださいよ」と永井に仰った折もあったという。それに対する永井の返答は、「『この世をば』が大河ドラマになることはないでしょうが、そうなった際にはよろしくお願いします」だったそうだ。
無論、本作は『光る君へ』の原作ではない。だが『御堂関白記』『小右記』といった歴史上の当事者の日記に始まり、『大鏡』や『栄花物語』などの歴史物語まで多くの古典を読み込み、数々の逸話の中から生身の人間をすくい上げ、今日でも色褪せぬ史観で以て彼らを描いた本作が、今日の平安時代を舞台とする創作物に与えた影響は大きい。その意味からすれば、倉本氏は40年の歳月を経て、永井との約束を間接的に果たしたとも言えるであろう。
作中、道長は半ば諦めを抱きながら、「王朝社会には転職はない」と心の中で呟く。平凡であるがゆえに激しい転変を泳ぎ切った一人の男とそれを取り巻く女たちの物語は、偉大なる英雄の成功譚よりもなお強く、我々の胸を打つ。刊行から40年を経てもなお色褪せぬ王朝絵巻を、存分にお楽しみいただきたい。
