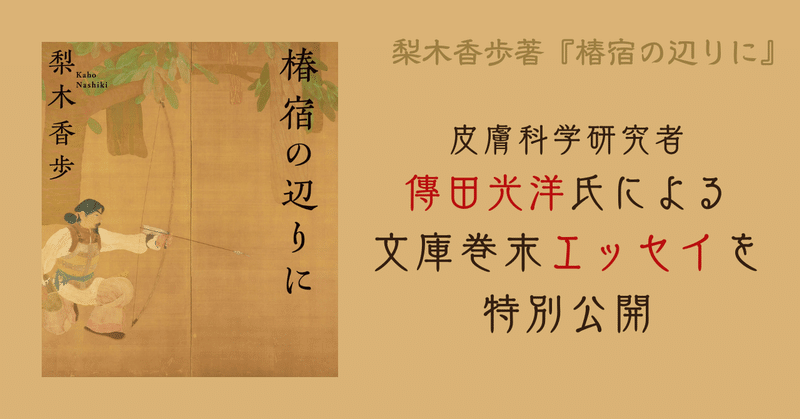
梨木香歩が描く痛みから始まる“物語”『椿宿の辺りに』皮膚科学研究者・傳田光洋氏による文庫巻末エッセイを特別公開!
梨木香歩さんの『椿宿の辺りに』(朝日文庫)が7月7日に刊行されました。三十肩と鬱の山幸彦は、治療で訪れたふたごの鍼灸師のすすめで祖先の地・椿宿に向かいます。山幸彦は、そこで屋敷と土地の歴史、自らの名前の由来を知ることになりますが……。自然、人間の体、こころ――入りくんだ痛みとは何かを問いかける、深淵でコミカル、重くて軽快な傑作長編小説。2012年6月に文庫版が発売された『f植物園の巣穴』(朝日文庫)の姉妹編になります。発売に合わせて、皮膚科学研究者・傳田光洋氏による文庫巻末エッセイを特別に公開いたします。
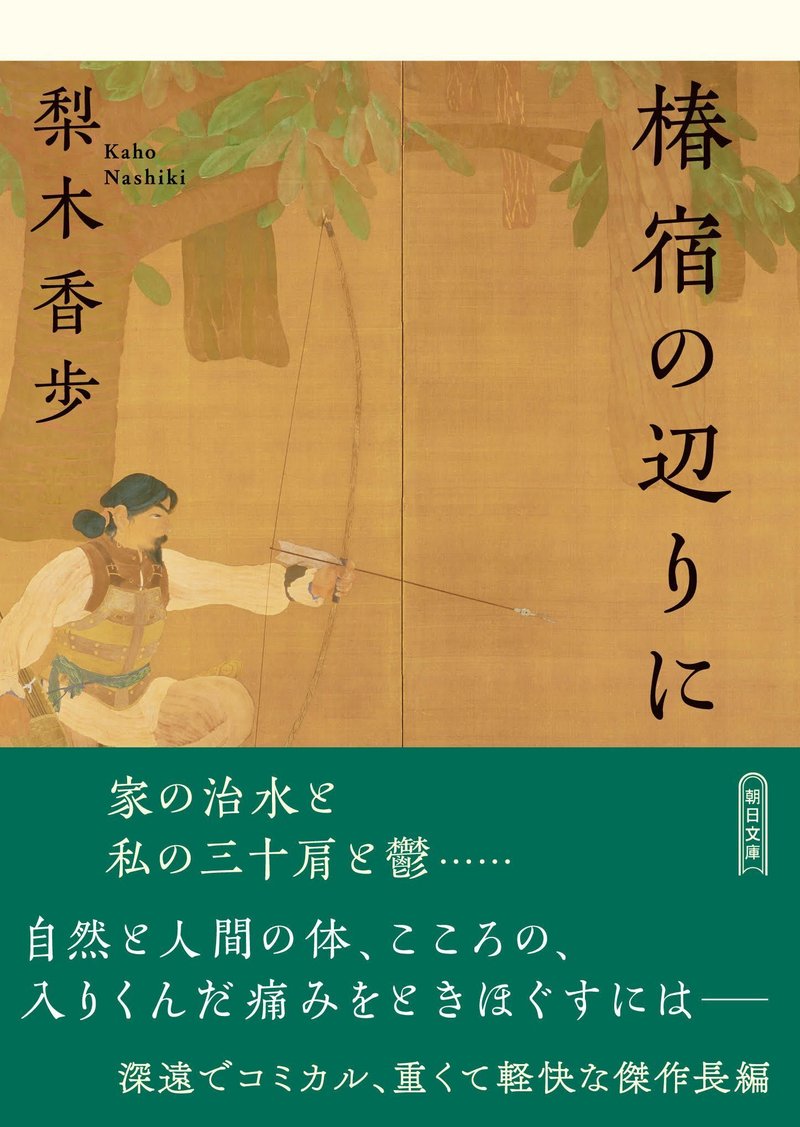
痛みから始まる「物語」の発見
痛みは孤独だ。
あるいは、痛みは自分が孤独であることに気づくきっかけになる。そして、それは自分だけの物語を見つける道を示す。
現代社会では会社員、公務員はもちろん、フリーランスの人でも、何かの組織に属したり関わったりしている場合が多い。そんなぼくたちの日常生活は、組織やマスメディア、インターネットなどが提供する「常識」に支えられている。その「常識」に逆らってばかりでは生活に不便が生じるし、むしろその「常識」に全てを委ねていた方が、大抵、楽である。楽なような気がする。
そんなある日、突然痛みが起きる。運がよければ家族や同僚が同情してくれるかもしれない。しかし自分の痛みは自分にしか感じられない。心優しい隣人が「あなたの痛みはわかる」と言ってくれるのは、正確にいえば「あなたの痛みは想像できる」ということに過ぎない。そして痛みが長く続けば親切な隣人もつきあってくれなくなる。もとより組織やマスメディアやインターネットは個人の痛みに冷淡だ。それまで身を委ねてきた「常識」が、自分の痛みに無関心であることを思い知り、やがては一人で痛みに向き合わなければならなくなる。
本書の主人公の佐田山幸彦(山彦)も右肩から腕への痛みに襲われる。そこに頸椎ヘルニアの痛みまで加わる。鬱病でもある。そして「存在の基盤が崩れ落ちそうな不安」を覚える。
現代医学でも、痛みのメカニズムがすべて解明されているわけではない。前世紀末、痛みの受容体が発見され、2021年のノーベル医学・生理学賞を受賞したが、一方で、脳科学の分野で古くから知られている幻肢痛という症状がある。事故などで手や足を失った人が、無いはずの手足に痛みを覚える。これは多分、脳が、失われた手足があると誤解した結果だろうが、そうなると、痛みは、それを感じる部位にあるのか脳にあるのかわからなくなる。
山幸彦は大学で遺伝子工学を学ぶが、なしくずし的に化粧品メーカーに勤め、ファンデーションの開発をやらされている。まあ理系、科学技術系の人の特徴だろうが、なにかと論理的に考えようと自分に言い聞かせるタイプである。彼は従妹や実の母親にまで敬語を使う。「人間関係に適切な距離を保つために敬語を使うようになった」という自覚もあるらしい。あるいは、初対面の人にやたら「すみません」と頭を下げ、「どうしてそうすぐ謝るのかね」と言われる。
彼は孤独に陥りやすい現代人の典型のようだ。
かくいうぼくも「理系、科学技術系」のハシクレであり、それに関わる場所では「論理的であろう」と考えている。しかし「論理」では、ぼくや世界のほんの一部、うわべだけしか語れない。それにもかかわらず、なぜそんな「論理」が重宝されるかというと、言葉で語られる「論理」は他人との共有が容易だからだ。あるいは民族や国を越えて考えを共有しうる道具として、人間は「論理」を発明したのだと思う。
現代の社会の常識も言語で表現される「論理」が主体になっている。論理を使えば、より多くの人たちの間で「常識」を共有できるからだ。その「常識」に沿って生き続けていると、だんだん「常識外れ」になることが怖くなる。そして言葉にしにくい自分の気分を主張すると、非難されるのではないかという懸念が生まれる。山幸彦も、だから次第に他人と距離をおくようになる。
人間の歴史を振り返っても、様々な悲劇は異なる「常識」がぶつかりあって起きた出来事のように感じる。「誰にとっても正しい常識」というものは実は存在しない。それをあるように考えることが、苦悩や争いを引き起こす。
痛みは山幸彦を「常識」から引き離し、不安と孤独に追いやる。彼は考える。「不安を耐え忍ぶ方法として痛みが生まれてくるのか――痛みと不安の関係は、もしかするともっと複雑なものなのかもしれない」。山幸彦は、ここで「常識」から離れて、本当の痛みの原因、自分の存在の根源を探し始める。
途方に暮れる山幸彦は従妹の海幸比子(海子)の勧めで、風変わりな鍼灸師(「仮縫」という象徴的な苗字)に出会う。仮縫鍼灸師が山幸彦の痛みの原因を「世代を重ねて深まってきたややこしさ」だと示唆すると、山幸彦は、先祖とは切り離して、痛みだけなんとかしてほしい、と頼む。しかし仮縫鍼灸師は「複数の意識されない痛みが絡み合い、どうにも無視のできぬ規模になり、仕方なく『そこ』に、本人にも自覚できる痛みとして顕われるものです」と諭す。
科学的論理で考えても、一人の人間は、あるいは、その痛みは、その人個人だけが責任を負わねばならないものではない。受精卵の遺伝子は過去40億年ほどの天変地異の歴史を負っている。受精卵が新生児になる過程では母体を通して世界の影響を受ける。誕生してからの成長では言うまでもない。長い歴史を経て築き上げられた多様な風土や社会のありようが個人のなりたちに関わっている。近年の脳科学、認知科学もそれを肯定している。個人とその命は、時空を超えた無数の出来事からなる現象だ。その痛みや苦しみは個人だけで担えるものではないだろう。
山幸彦は仮縫鍼灸師の妹、どうやら“時空を超えた”世界を感じ取れるらしい亀シ(亀子)に出会う。海幸比子によれば「どういう『物語』がそのひとに一番『効く』か」わかる能力があるという。その亀シに導かれ、山幸彦は先祖が住んでいた椿宿を訪ねる。そこには、江戸時代に御家騒動が起き、古代から山や川が移動し、キツネ使いの伝説や日本神話につながる物語が幾重にも重なる世界があった。その中で山幸彦は自らの痛みの原因を見つけ出してゆく。
どんな人間も、自分を支える物語が必要だ。「常識」は手軽な物語を提供してくれる。しかし、そこでは誰も主役にはなれない。人間にとって本当に必要な物語は、自分が主人公である物語でなければならない。
山幸彦は椿宿で先祖が住んでいた旧家で過ごしながら、初めて自らの意志で、長年淀んでいた家の空気が流れるように工夫する。すると「重く滞留していた何か」が外へ流れ出した。そして「未だかつて味わったことのない達成感、というのは、すなわち、『主人公』感覚、といってもいいもの」を感じる。自らの「痛み」をきっかけに、山幸彦は自分の物語への入り口を見つけたのだ。
人間個人の物語は、創造の基点でもある。科学的な発見、芸術的な表現、ビジネスモデルの提案、それらの中で本当に新しいものは、「常識」を超えたものである。誰も知らなかった、考えもしなかったことを創造する人は、「常識」の外にいなければならない。その視点を可能にする足場になるのが、その人、個人の物語なのだ。
時代を超えて生き続けてきた創造には、いつでも際立った個人がいた。その個人は、同時代同地域の最大公約数的な「常識」にはとらわれず、生命の起源や人間の歴史と深い場所でつながる物語を持っているのだ。そんな個人の物語だけが未来を拓く力を持っている。
先年、パリとニューヨークの脳の研究者たちが興味深い報告をしている。異なる場所にいる人でも同じ小説を読んでいると、心拍数が同期するというのだ。この結果から想像できることは、例えば『源氏物語』を読むことで、千年前の紫式部個人の物語を今のぼくたちが文字通り身体で感じることができるということだ。小説という表現方法が長く広く世界で親しまれてきたのは、それが一時代の「常識」のしがらみから個人を解放し、自身の物語を見出すきっかけを提供するからではないだろうか。
梨木香歩さんの小説の魅力の一つは、本書がそうであるように、時間や空間を超えた世界と現実世界とがなめらかにつながっていることを体験できることだ。その体験を通じて、読者は「常識」を超えた大きな世界があることを実感できる。また、本書の最後の方で発見された古い文章の束「f植物園の巣穴に入りて」は『f植物園の巣穴』(朝日文庫)として刊行されている。そこでは現実が、異なる時間と重なりながら、より豊かで優しい異界へと溶けてゆく。未読の方はそちらもぜひ体験してほしい。
(でんだ みつひろ/皮膚科学研究者)
