
Artist Note vol.2 川谷光平
「Art Squiggle Yokoyama 2024」では、「アーティスト・ノート」というコンセプトを掲げ、各参加作家に本フェスティバルの準備段階で、まだ頭のなかにしか存在していなかった展示についてのインタビューを行いました。作品に込める思い、悩みや葛藤、インスピレーション源についてなど、まさに「Squiggle」の最中にいたアーティストの声がここには綴られています。
誰でも写真が撮れる時代の、写真家の作家性 写真作品のゴールを曖昧に考える

川谷さんの今の写真観は、どういった経緯で培われてきたのでしょうか?
私はこれまでに写真の専門的な教育を受けたことはなくて、ファッションの専門学校を経て、その後撮影スタジオのアシスタントになりました。 そこでは撮影技術は学べますが、いわゆる写真史や写真論については教えてくれません。 基本的に写真を独学で学んできたので、例えば、 作品の希少性を担保するために販売枚数を制限する「エディション・ナンバー」という仕組みも、実際に自分が展示を行ってから知りました。 そういうことがいくつかあって、特に写真が作品になることの違和感には素朴に向き合ってきた経緯があります。 だからこそ、ことデジタルイメージに関して言えばいわゆる「作品」とは額装されてエディションが付けられることがすなわちゴールではないのではないかと考えています。 制作から完成までの流れがスムーズな直線であるよりも、展示など発表のたびにサイズやメディア、そして組み合わせが変わり、意味が組み替えられていく、それぞれの写真を起点に制作的なプロセスは何度も繰り返されうる、という方がしっくりきます。
本フェスティバルのテーマである「SQUIGGLE」とも響き合うところです。
今回の展示ではそうしたテーマも踏まえて、数枚の新作のほかに、普段見返すことのない過去の膨大な撮影データのなかからテストとして撮影していたものやリファレンス、何かの過程で偶然に撮った写真も選んでいます。 普段であれば選ばない少し不完全に感じるものも「SQUIGGLE」というテーマにのっとり、視点を変えることで作品になり得ることにおもしろみを感じています。

Photo: 市川森一
—見、スタジオの背景紙のように見える写真や、アドバルーンから吊られている写真など、アウトプットの手法はさまざまですね。
撮影と発表という、写真の入口と出口をひとつの空間で見せる展示方法を通じて写真のプロセスにフォーカスしてもらいたいと思っています。 展示空間のなかで、来場者が写真のプロセスのなかに入っていくような経験が生み出せないかなと。 展示された作品だけが作品なのか、空間全体も作品なのか、背景紙のように匿かれた写真は背景なのか、もしくは作品なのか、それとも、いくつかの写真やオブジェクトが重なり合う状態で成立する作品なのか。 そうした枠組みに含みを持たせるようにしています。来場者が私の展示空間を撮影したら、その写真すら作品として機能するかもしれない。作品とそうじゃないものを言い切らないことで、ぐるぐると思考してほしい。
どこを作品として切り取るのが正解なのか、曖昧であることが楽しいです。
今回展示している写真のなかには、ある撮影のリファレンス画像をつくるためにAlで生成したものもあります。リファレンスを元に撮影した作品も別の機会に発表しているのですが、そちらではなくリファレンスを展示することにしました。 初めからここを目指してはつくれない、そもそもつくろうと思わないけと、とても魅力あるものがリファレンスをつくる過程で生まれてしまった。一度完結した制作プロセスを別の角度から見直す、今回の展示ではそうしたことに取り組みました。制作のゴールをフレキシブルなものとして考えています。

ゴールをフレキシブルにとらえ、決めきらないというのは撮影のときもそうでしょうか?
撮影では明確な終わりを決める必要があるため、確かな1枚が撮れたと判断した段階で終わりとしますが、選んだり編集する段階では撮影時の自分を信用せずに全く別の観点から見るようにしています。 さらに言えば、一度選んだ後であっても、次の機会には選び直しても良い。 同じモチーフが 別の形で発表されても、そこに新しい意味が生まれるのが面白いです。 無数のアーカイブがあって、何度でもそれらを取り出して再編集できる、そういった写真の特徴を楽しみたいですね。
生成画像も作品として扱う一方、シャッターを切ることはどのくらい意識していますか?
そうですね…。 必ずしもカメラで撮影されたものだけが写真作品だとは思わないし、古典的な意味での「写真らしさ」ということも特に気にしませんが、撮影することをキッカケにしてしか自分は作品をつくれない気がします。
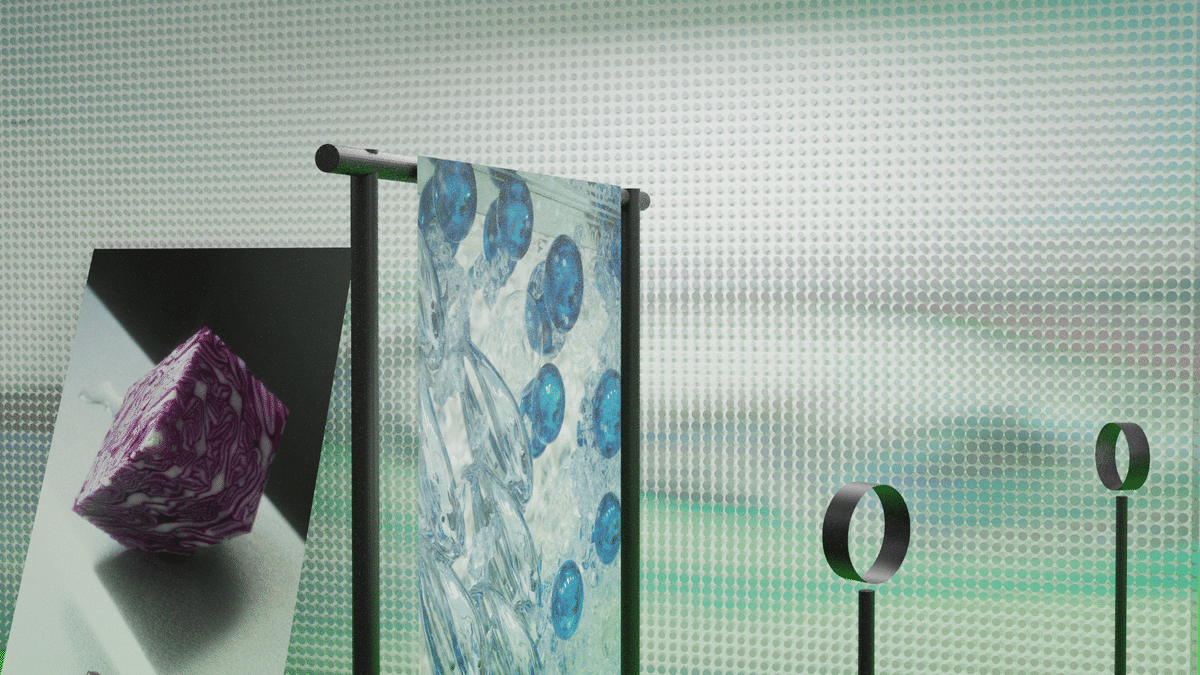
撮影行為それ自体、現代の写真家におけるひとつの共通のテーマでしょうか?
私には、写真の先鋭的な技術や複雑な撮影方法によって作品性を担保させるという考えはフィットしないんです。 今日の写真の良いところは誰もが日常的に写真を撮っていることだと思います。 私の作品は一見そう見えないかもしれないですが、技術的には鑑賞者の延長線上にあるものでありたい。 つまり誰でも撮れるようなアイデアやモチーフで作品をつくりたい。 見たことのなさや作品の複雑さを強度とする作品も魅力的ですが、そうしてしまうと私の思う写真の魅力が失われるのではないか、とも。 ある種の絵画や彫刻作品から鑑賞者が受ける、自分にはつくれないと感じるがゆえの魅力と距離に対して、写真は基本的には誰でも撮れる身近なメディアです。 それが今日の写真の良いところであり、そんな時代に作品としての写真はどうあるべきなんだろうかと現代の写真家として試行錯誤しています。
Interview Date: 2024/06/26
Text by Jun Asami
PROFILE
1992年島根県生まれ。 東京を拠点に活動する写真家。近い距離感から色鮮やかに被写体を捉える独自の作風が国内外から注目を集める。2019年、JAPAN PHOTO AWARD シャーロット・コットン賞受賞。2021年、Kassel Dummy Award 2020で日本人初の最優秀賞を受賞した作品『Tofu-Knife』を出版。グループ展「BOOK_SPACES、2023」(Museum für Photographie Braunschweig、ドイツ)に参加。
https://koheikawatani.com/
About "ARTIST NOTE"
会場では、それぞれの作家ごとに用意されたテーブルの上に普段制作に使用している道具やアトリエにあるもの、影響を受けた書籍などが並ぶほか、インタビューや制作プロセスが垣間見れる写真などが掲載された「アーティスト・ノート」が2枚置かれています。会場を巡りながらそれらを集め、最後にはご自身で綴じ、自分だけの一冊をお持ち帰りいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
