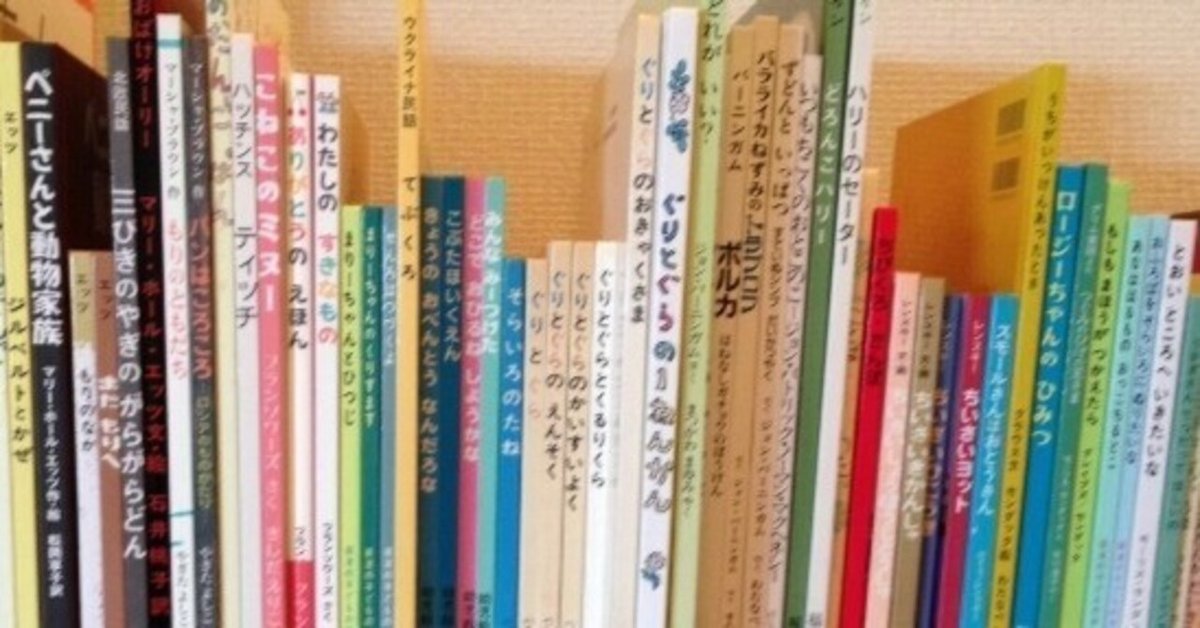
★『氷の花たば』アリソン・アトリー
自然の生命力と、夢のような世界を信じることのできる、
小さな人たちに向けて語られた素敵な物語
この本は「グレイ・ラビット」シリーズや、長篇ファンタジー『時の旅人』で知られるイギリスの作家、アリソン・アトリーが1948年に発表した短篇集
『John Barleycorn:Twelve Tales of Fairy and Magic』の中から翻訳された、6篇の物語からなる作品集です。

訳者は日本を代表する二人の児童文学作家、石井桃子と中川李枝子。
6篇の作品は原題通り、どれも自然の生み出す不思議な力と、そこに生きるものたちのもつ生命の力が出会い、不思議な結末──奇跡を生み出す物語です。
アリソン・アトリーの作品については、巻末の解説で石井桃子さんが以下のように短い言葉で的確に述べておられます。
アリソン・アトリーの作品を読んでいると、児童文学というものが、伝承
文学から独立して、自我をもつ個人の創作となっていく道すじを目の前に
さし示されたような思いがします。
それは、彼女より先に、アンデルセンが通ってきた道でもあります。
(訳者あとがきp211)
個人的には、アンデルセンの作品に比べて、アリソン・アトリーの作品には、その結末に含まれる悲劇性が少ない分、より童話として安心して小さな子どもが楽しめる物語であるように思います。
しかし、悲劇性が少ないからといって、そこに描かれる自然や人間の姿の真実性が損なわれているわけではありません。
その点こそが実は、アリソン・アトリーの物語の凄いところだと、私には思えます。
例えば、この本の表題にもなっている「氷の花たば」という作品は、吹雪の中、道に迷って遭難寸前の男が、擬人化された自然の力(霜の王)に助けられて無事帰宅するのですが、命を助けることと引き換えに、男は自分の最も大切なものを霜の王に差し出すことになります。
たしかに、悲劇といえば悲劇なのですが、そこにはこの世に生きている限り、誰もが受け入れざるをえない自然の摂理というものが描かれ、それに直面し、悩み苦しみそれでも受け入れる人間の姿にもまた、真実さが感じられるのです。
その真実性とは、必ずしも絶対的な存在からの恩寵として与えられる奇跡でもなければ、逆に、この世の摂理を司る自然からの一方的な戒めや教訓でもありません。
それは厳しくも豊かな自然の中で生きる生き物に与えられた運命であると同時に、約束された恵みでもあるのです。
そしてこの、自然と共に生きることの中に有る人間の本当の姿、そのあり様は、現実の自然の中で生きた経験のある作者にしか描けない真実の物語なのではないでしょうか。
アトリーの物語には、現実には起こりえないと思われるような不思議な出来事や、奇跡としか思えないような現象が描かれる点では、訳者が指摘している通り、伝承文学を受け継ぐものであることに間違いありません。
しかしこれもまた訳者が指摘している通り、自然の一部として生きる人間の生命は、その摂理の前では無力であり、はかないものだとしながらも、その力に直面した人間の中に生まれる生命力(それは個々の人間の中に宿る力=自我とも言い換えられるかもしれません)は、微細ではあるけれどもそれ自体が「Fairy and Magic」なのだと、いえるのかもしれません。
この本の中に描かれているのは、私たちが普通に考えるこの世の幸せではなく、自然の摂理とともに生き、その厳しさと恩恵をともに受け入れて生きることの静かな安らぎのように思います。
作者はきっと自らの経験から、そんな人間のあり方に、確固とした肯定感を抱いていたのでしょう。
ここに収められたお話を読むと、大人の私でも、遠い昔、私たちの祖先は、本当に自然の精とお話できたのかもしれない、と想像してしまいます。
現代人は、ただそのことを忘れ去ってしまい、ほんの少しだけ伝わったことが奇跡として語り継がれているのかもしれません。
それを「本当のこと」と感じられるのは、今では、昔と変わらず自然の中で生きるほんの一握りの人々、そしてこうして語り継がれるお話の中に人間の真実を感じ取ることのできる、小さな子どもたちだけのように思います。
6つのお話の中には、「七面鳥とガチョウ」のような、伝承文学の香りを色濃く残した、勧善懲悪的なスカっとする滑稽譚や、「妖精の船」のように、小さな子どもの夢がぎっしりつまった作品もあります。
この物語は、そんな夢のような世界を信じることのできる、小さな人たちに向けて語られた素敵な物語です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
