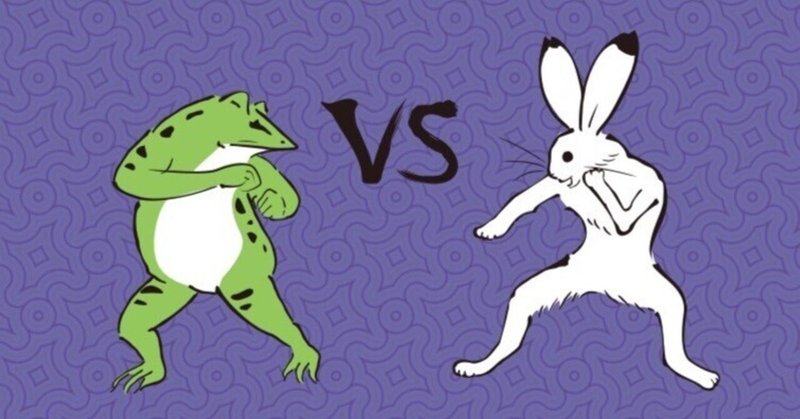
御匣殿騒動 その一 行成と繁子のバトル
藤原行成といえば、その勤勉さ、誠実さで一条天皇や道長の信頼も厚い能吏・能書家。「枕草子」では意外に茶目っ気のあるところも描かれ、その日記「権記」は「小右記」と並んでこの時代の貴族の多忙な日常が伺える貴重な資料だ。
「権記」長保2(1000)年8月20日条に面白い記述がある。
故ニ条殿(藤原道兼)の女君が着袴の儀を行なった。旧意を思ったので、参り向かったのである。また、尊者の御膳について、春宮属(錦)信理に命じて、調達させたのである。家君の丞相(顕光)・藤中納言<時(藤原時光)。>・左大弁・殿上人二、三人が座にいた。雑役の諸大夫も何人かいた。故相府(道兼)の門人である。深夜に帰宅した。
この日、御匣殿別当(尊子)を女御とするという事について、朝餉間において勅命を承った。退出する頃、女御の母氏(藤原繁子)が暗戸屋曹司にいて、私に纏頭を行なおうとした。私はその様子を見て、直ぐに退いて陣座に向かった。「この事を伝えていた頃、あの曹司から従女を遣わした。苔雄丸を介して、私を招かせようとした。苔雄丸は進み向かわなかった。従女はただ、女装束を持って空しく曹司に帰った。見た者は嘲笑の様子が有った」と云うことだ。右府の許に参った頃<時に夜に入っていた。>私の宅から書状を送って云ったことには、「予想外の下人が来ました。女装束を包んで、侍所に置きました。侍所の人は取らずに、咎めました。下人は更に東面の高欄干に置きました。理由も無いので、取り入れませんでした。使の下人は、すぐに遁れ去ました。この事は甚だ奇怪です」と云うことだ。推量するに、女御の曹司の人が行なったものである。そこで事情を説孝弁に伝えて、女装束を遣わし取らせ、その車に入れさせた。この尚書(説孝)は、あの女御と交流のある家の者である。そこで、この贈物は理由が無いということを告げさせて、返却させたのである。私の家女(藤原行成室)は、この物を取り入れず、書状を馳せ送った。時の人はこれを賞賛した。後に聞いたところでは、「女御の母氏は、この事によって怨気が有った。院、及び左府に訴え申した」と云うことだ。甚だ愚かなことである。
長保2年は七日関白と言われた道兼の没後6年目。
この日は、藤原道兼と正妻との遺児が着袴を迎えた日であり、また奇しくも繁子との間に儲けた尊子が一条天皇からめでたく女御宣下を受けた日でもあった。
おもな登場人物と語句を整理しておこう。
・故二条殿/故相府=藤原道兼
・女君=道兼と藤原遠量の娘である正妻との女児(道兼の死後に誕生している)
・家君の丞相/右府=右大臣 藤原顕光(後家となった道兼妻の再婚相手)
・藤中納言=中納言 藤原時光(顕光の弟)
・御匣殿別当、女御=藤原尊子(道兼と繁子との娘)
・女御の母氏=藤原繁子(長保2年時点では平 惟仲と再婚している)
・纏頭=儀式・行事における功労者・使者に対して、褒賞・慰労の意味で「女装束」などを被けること。
・暗戸屋曹司=尊子の局。内裏のどこかは不明。
・苔雄丸=行成の従者、小舎人童
・説孝弁=権左中弁 藤原説孝(繁子家と昵懇、行成の推薦で右中弁→蔵人に昇進)
・家女=行成の妻(源 泰清の娘)
・院、及び左府=東三条院(藤原詮子)、その弟 藤原道長
冒頭、行成は、道兼の死後に誕生した女児の着袴の儀のために顕光邸を訪問し、深夜に帰宅したことを書いている。
夕刻、忙しい蔵人頭の仕事をやりくりして駆けつけたのだろう。
「旧意を思ったので」とあるのは、行成は後年、実資に道長の「恪勤上達部」などとレッテルを貼られるが、若き日は道兼から目をかけられていた。道兼の大饗の裏方を務めたり、道隆、道長時代には見られない春日社への随行もしている。律儀な彼はこの恩顧を忘れず、道兼の死後も未亡人となった妻への拝謁を怠らなかった。
彼女はこの時、顕光と再婚していた。
さて話はこの日の朝に遡る。宮中、清涼殿の朝餉間。
行成は一条天皇から御匣殿別当(尊子)を女御にすべしとの命を承り、退出した。
道兼のもう一人の娘・尊子は、2年前の長徳4年に一条天皇に入内していた。母・繁子はこの頃は平 惟仲と再婚しており、一条天皇の乳母であり詮子や道長とも近く、従三位の典侍としてかなりの力を持っていたらしい。尊子の入内、女御宣下にもそんな“力”が働いていたと思われる(もちろん義父 惟仲の“運動”も)。
さて、退出した行成を待っていたのは…!?
次に続きます。
イラスト:ダ鳥獣ギ画より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
