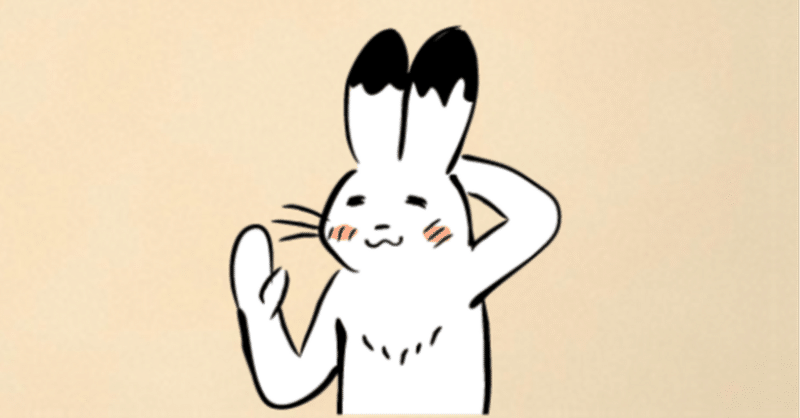
番外編 「枕草子周辺論」より
ここのところ「枕草子周辺論」(下玉利百合子先生)からの話が多い。
この本、本当に面白くて、今のところ取り上げたのは「御匣殿騒動」だけだけど、いずれまた別の記事について書きたいと思ってる。
出来事を時系列に並べての詳細な検証や解説はすごいボリュームで自分にはちょっと手に余るんだけど、理解半分にしてもパラパラ斜め読みしてるだけで楽しい。
(こんな読み方でいいのか…?😅)。
先生の執筆意図とは軽薄にかけ離れてしまうけど、ここではお気に入りの箇所を少しだけ切り取ってみたい。
行成を形容する言葉
ざっと拾ってもこの量!
「能吏」とか「誠実」「有能」あたりのよく見る表現が物足りなく感じるw
らうらうじき男(=気がきいている。 才たけている。 洗練されている)
きわめて多感なソフトマインドの持ち主たるこの青年
俊秀にしてしかも秘められたるやさしさの持主たる彼
この能吏の智謀と才幹
愛妻との仲むつまじく、幾多の人の子の親としてのこの青年
官界において常に颯爽、生気に満ちた敏腕能吏
生来心やさしきこの青年
頑なまでに潔癖な
公正な姿勢と明晰な頭脳を以て
器量抜群、さらには絶大な左府の信頼の上にあぐらをかく
生来極めて長高い彼の性格の基盤には
傲岸かつ慧敏な頭弁
これを眺めただけで、行成がどういう人物であったかが想像出来るというもの。
特に「きわめて多感なソフトマインドの持ち主」が気に入ってるw
今回の大河の行成像とぴったりな気も?(まだ性格がわかるほど出番ないけど)
行成と妻との描写
行成にとって更に不幸なことは、(その実至福というべきであろうが)気むずかしい彼が心を開いた親しい女性達が、揃って繁子とは全く逆の範疇に属するタイプであったことである。まず「御匣殿騒動」の処置が、世の称賛を博したその妻の場合を考えよう。言言句々繁子の愚を笑い非を糾弾しながら、
家女不取入件物、馳送消息、時人称之、
と書き綴る行成の筆致の何と甘いことか。彼はこの妻の適切敏速を極めた処置の切れ味に、その美意識を満足させている。世の評価も当然至極と目を細めている。行成の如き俊才をかかる形で喜ばせたというのは、まことにおどろくべきことである。この人の才気はなみなみのものではない。しかも一方このようなエピソードもある。
今夜室女夢与余共見明月
(長保四年二月九日条)(行成三十一歳、妻 二十七歳)
闇の寝ざめに彼女は夫に語った。
「あなた……今夢でご一緒にお月見をしました。覚えていらっしゃるでしょ、きれいなお月さま……」
行成が渾身の力をこめてこのいとしい妻を専び両腕に抱きしめたとしても少しも不思議はない。才気と可憐さが異和なく共存するまことに佳き人の肖像がそこにある。…
////////である(本数多!)。
この日の権記はわずか2行。うち1行がこのことだ。
嬉しさから書き留めたんだろうか。それとも…
話が悲しい方に逸れるけど、以前、倉本一宏先生はラジオで「何か予感めいたことがあったのかも」と言われていたが、妻はこの時懐妊中で約8カ月後の10月16日に2日前に出産した女児と共に死去してしまう。
「悲慟の極まりは、何事がこのようであろうか。…去る永延三年八月十一日以後、今まで十四年。」(権記 全現代語訳/倉本一宏)
これはなんと結婚した日!記念日!
行成17歳、妻13歳(源 泰清女)※ 泰清は花山期に参議だった忠清(大河第7回で台詞あった!)の兄
現存はしていないが、当時すでに日記を書いていたとしたら間違いなく結婚の日のことを記していただろう。
それを見返して結婚記念日がわかった?
いや、行成のことだから、ちゃんと覚えていたに違いない。
(ちなみに行成は権記10月23日条で弔問がなかった者4人を名指ししその中には「あの」実資がいる…。)
それにしても「揃って繁子とは全く逆の範疇」ってところに笑ってしまう。
ちなみに引用文中「気むずかしい彼が心を開いた親しい女性達」のもう一人として下玉利先生は清少納言を挙げている。
もちろん、この本では行成を誉めそやすばかりではなく、帝や定子に誠実に仕えつつも、一方で彰子入内・立后や敦成立坊の場面で道長・詮子のためにも尽くした彼の両面(「板ばさみの苦衷」)についても詳しく分析している。
ずっと探していた続編も無事手に入った!
今日は目次の紹介だけにしておくけど、この章タイトルの強さよ…。
一条天皇と定子の遺児のその後については興味があるのでいずれまとめてみたい。
枕草子周辺論」続編
試論 枕草子の周辺をめぐって=先導主題=
一 第一皇子敦康親王(正)
I 〔持ち駒の時期〕
Ⅱ〜Ⅳ〔使い捨ての時期〕(上、中、下)
V〔孤絶の時期〕
二 第一皇子敦康親王(続)
I〜Ⅲ〔香かなるその晩年〕(上、中、下)
Ⅳ〔薨逝とその前後〕
三 第一皇子敦康親王(正・続)終章
その生涯の政治史的展望と、『枕草子』・『紫式部日記』への投影
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
