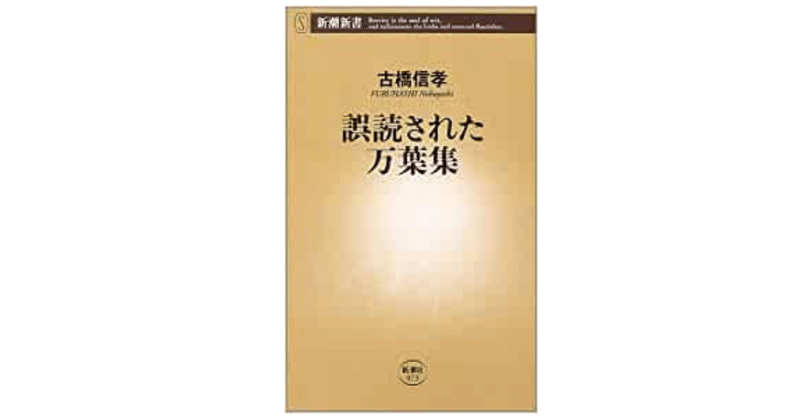
呪術から余興としての和歌の流れがある「万葉集」
『誤読された万葉集』古橋信孝
万葉集は誤って理解されてきた――。庶民の素朴な生活感情を素直に表現した国民歌集などではない。山上憶良は家族思いで大伴旅人は大酒飲みというイメージには問題がある。性の歌もある。都市生活が営まれ、郊外も誕生していた。平安文学とのあいだに断絶はない。……従来の万葉観を大胆にくつがえし、最古の古典に新たな輝きを与える。
目次
1 人麻呂は妻の死に泣いたのか
2 額田王と天武天皇は不倫の関係か
3 山上憶良は家族思いだったか
4 大伴旅人は大酒飲みか
5 逢引の夜には月が出ている
6 妹が妻や恋人の意となるわけは
7 枕詞にも意味がある
8 序詞の不思議を解く
9 挽歌は異常死の死者を悼む歌である
10 旅の歌には美意識がある
11 斎藤茂吉の解釈にも問題はある
12 方言はなぜ東歌と防人歌にかぎられるのか
13 性の笑いもある
14 日本には古代から郊外があった
15 万葉集から平安文学へ
図書館本。『芭蕉・蕪村 春夏秋冬を詠む 秋冬編』の推薦図書だったのか?気になったので読んでみた。和歌の成り立ちが呪術にあるということ。それが色濃く現れているのが『万葉集』で徐々に呪術性が消えて行くのが『古今和歌集』であるのだ。それは突然変わったというより、徐々に、例えば呪術が恋占となり、相聞歌が恋の歌となっていくように。
旅の歌がその土地を称えること(天皇の国見もその一部かもしれない)と残してきた妻を想う気持ちだったのだが、最初は旅の安全を祈る父母の祈り的なものが、防人のうたにあるという。
枕詞の意味も呪術的な言祝から来ているということだった。斎藤茂吉の解釈も呪術性が足りないということだった。そのへんは文学者と学者の読みの違いにあるのだろう。
挽歌も不幸な死に目にあった人の呪いを解くために和歌を捧げるということだ。まあすべて呪術で解釈してしまうのも味気ないものになってしまうが、和歌の言葉が言霊というのはそういうことだ。例えば大来皇女が巫女として大津皇子の悪霊を鎮める為に和歌を読んだというより、巫女という立場を離れて私情の感情を読んだとするほうがドラマチックだ。
東歌の方言が収められているのは、都を中心とする洗練された文化とは別の後進性と取ったようだ。ただ東歌もその土地のものばかりではなく官僚的な人が詠んだということだ(そもそも歌を詠むぐらいだから文化度は高いのだ)。日本の都が支配する境界が東地方にあったということ。それ以外には方言は採用されていないのだという。防人のうたも東地方の人が多く駆り出されたということらしい。
第16巻はセクハラオヤジの宴会歌集のようだ。このへんになると呪術性も薄くなって宴会としての和歌が余興としての言葉遊び的なものになるのだろう。それは父母を敬う呪術性が妻を選び核家族化していく流れが個人としての物語としての和歌を作ったという。それは豪族社会から天皇を中心とする中央集権的な社会になって、都市型の官僚化構造になった(単身赴任もあれば左遷もある)。そうして郊外は未だ神々がいる世界として自然という謎を残していたのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
