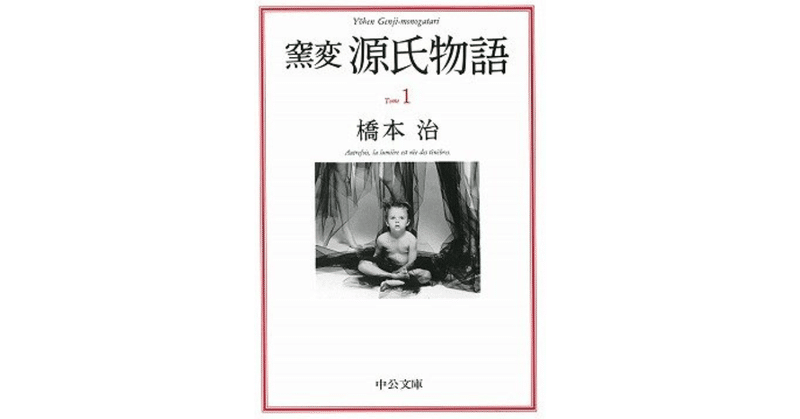
「窯変 源氏物語」はジャニタレ源氏か?
『窯変 源氏物語 1』橋本治(中央公論)
千年の時の窯で色を変え、光源氏が一人称で語り始めた――原作の行間に秘められた心理的葛藤を読み込み壮大な人間ドラマを構築した画期的現代語訳の誕生。
『源氏物語』は二回目なので、最初はウェイリー版のイギリス王室かと思わせるシャイニング・プリンス=光源氏の世界に浸っていたのだが、図書館本だったので返却しなければならずその代わりに借りてきたのが『窯変 源氏物語 1』橋本治だったのだ。ウェイリー版もぶっ飛んでいるけど、この橋本版も負けてはいなかった。なんせ『源氏物語』が光源氏の一人称になっているのだ。それによって、多くの翻訳源氏が女たちの物語に成っているのに対して、男源氏というか政治色が濃い、光り輝くジャニタレのスター物語みたいな(喩えだから)。
「窯変(ようへん)」とは焼き物で人工的に付けた色模様なんですが、それがどう変わるかはなかなかわからない。そんな陶器の美を日本文化・社会に喩えて、光源氏という一人の男がどう変化していくかを語った「源氏物語」でこれまでの「源氏物語」が多様な女を描いていたとすれば、橋本治の源氏は光源氏の一人称にすることで、一人の男の人生を描いているのだった。その根源に『源氏供養』で明らかにしたのは、光源氏が一番愛していたのは桐壺帝という父でもあり日本の頂点でもある男だったというのがある。
もう一人称の翻訳からして異様な光を放つ光源氏になっているのだ。それがよく出ているのが、母の更衣(女は名前がないから部屋の名前で呼ばれるそれは源氏名という元になっているのかな。)が亡くなって、光源氏も実家に引き取られていたのだが、桐壺帝がみすぼらしい家よりも宮廷で育てた方がよいと引き取りにくるのだが、祖母はなかなか手放さい。それは娘の更衣が宮廷で惨めな目に合ったからで、孫もそのような環境に置きたくないとしたのだが、光源氏は祖母の悪あがきと捉えている。そこが客観的なのかクールなのか末恐ろしい子供の片鱗を伺わせる。
それで父の元へと引き取られていくのだが、彼は母に面影があり桐壷帝からも愛される。それを妬むのが弘徽殿女御で母をいじめ抜いたも正妻である弘徽殿方の左大臣の権力(藤原氏のような?)基盤があり、光源氏が天皇になることを快く思わないから宮殿内でも対立構図になっている。そこが政治色の強い「源氏物語」で権力の話でもあるのだ。
ただ不覚にも光源氏は藤壺に恋してしまう。それは父の愛人を奪うことでもあり、タブーなのだが、その禁を犯すことで、分裂したアイデンティティを持った一人の男としてのドラマが始まるのだ。それは倒錯した愛でもあるのだ。光源氏の中にある天皇の血と母更衣である血がドロドロのドラマを展開していくのだと思うとこれからの物語に期待が持てる。
それで最初にやってくる「夕顔」の悲劇が待っているのだ。
「夕顔」(ここから、かなり脚色が入ってます)は地方で引っ掛けた女子タレ(スターの素質があったかもしれない「あまちゃん」を連想した)を呪われた旧帝國ホテルのような場所で少女である夕顔を死なせてしまうのだ。これはかなりヤバい!光源氏は17歳なんだよな。
死んだ少女(夕顔)もそのぐらい。お付きのマネージャー右近(夕顔とは姉妹のように育った)もおろおろ泣いてばかりいるし、辛うじて源氏側の惟光(スターにはしっかり者のマネージャーが付いている)マネージャーがしっかりしていたので、どうにかその場をスキャンダルにならずにすんだのだが、光源氏は落ち込みようったら、ストレスで病になるほどだった。みんな若いんだよな。最初に読んだ『源氏物語』ではもう老成された光源氏だと思っていた。やんちゃ時代の源氏の行動は天皇になれない鬱憤を晴らすようなところがあるのだが、その分精神は内省的な帝王道を身に着けていくのかなと思わせる。ただそれでも恋に落ちってしまうのが、光源氏の欠点といえば欠点なのだ(もてすぎるというのもあるな)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
