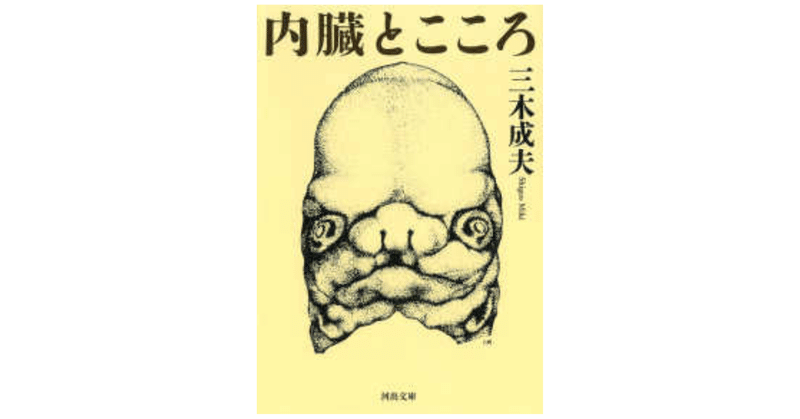
こころを鍛えるには内蔵から
『内臓とこころ』三木成夫
内容説明
「こころ」とは、内蔵された宇宙のリズムである―おねしょ、おっぱい、空腹感といった子どもの発育過程をなぞりながら、人間の中に「こころ」がかたちづくられるまでを解き明かす解剖学者のデビュー作にして伝説的名著。四億年かけて進化してきた生命の記憶は、毎日の生活の中で秘めやかに再生されている!育児・教育・保育・医療の意味を根源から問いなおす。
目次
1 内臓感覚のなりたち(膀胱感覚;口腔感覚 ほか)
2 内臓とこころ(内臓波動―食と性の宇宙リズム;内臓系と心臓 ほか)
3 こころの形成(指差し・呼称音・直立―満一歳;言葉の獲得―象徴思考 ほか)
4 質問に答えて(夜型の問題―かくされた潮汐リズム;再現について―形態学の実習)
5 補論(胎内にみる四億年前の世界;忘れられた二五時―バイオリズムと眠りのメカニズム)
この表紙を見たときに『胎児の世界―人類の生命記憶』 (中公新書 )を思い出した。同じ著者だったのか?と今になって気づく。胎児の世界が辿る道は、古生代の卵から魚類、爬虫類、さらに哺乳類と進化を遂げているというもの。
そうだ、最初に奇書、夢野久作『ドグラ・マグラ』について触れていたのだ。精神病院の体操についてだったか。ここでも内蔵を鍛える体操を紹介していた。
人間の(というか魚類から進化過程で)鰓(エラ)が手に変化したというのがある。赤ん坊はまだ手の連帯が不十分らしく、ものを認識するのに舌を使うという。幼子が何でも口に持っていくのはものを認識する為で、毒素に対しても耐性を養っていくのだという。昨今のコロナ禍のウィルスもいたちごっこの様相でワクチンを作ってはそれが効かないウィルスがでてくる。無菌状態で育ってしまった我々はそうした病原菌やウィルスの耐性が欠けてしまった。それはある部分人間が文明化の過程で被らなければならない試練なのだろう。
そうしてものの認識も文明人よりも未開部族の方が自然との共生に優れていることはわかるだろう。彼らの確かな距離感や気配を察知する能力はそうした訓練によって培われたものである。ちなみに舌使いが上手くなるのは、母乳の訓練だとか。そうした者はキスを上手くなるとか。それはどうかと思うが、自然の波長を感じるのは頭ではなく心(内蔵)なんだという身体論を解説した本である。
ただ時に過剰に解説しだすのでカルトっぽく思える部分もある(こういう話は哲学よりも宗教になりやすい)のだが、身体論については納得する話が多い。四季を敏感に感じるとか季節の変わり目に体調を崩すとか。朝型や夜型人間の時間周期は、太陽暦に上手く馴染めたか、未だに陰陽歴(月の周期)の影響にあるのだとか。興味深い本ではある。俳句や短歌をやっている人は、そうした内蔵感覚は大切なのだと思う。論理的な部分、例えば理性は否定することから始まるとか、身体論と精神論の駆引きはあるのだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
