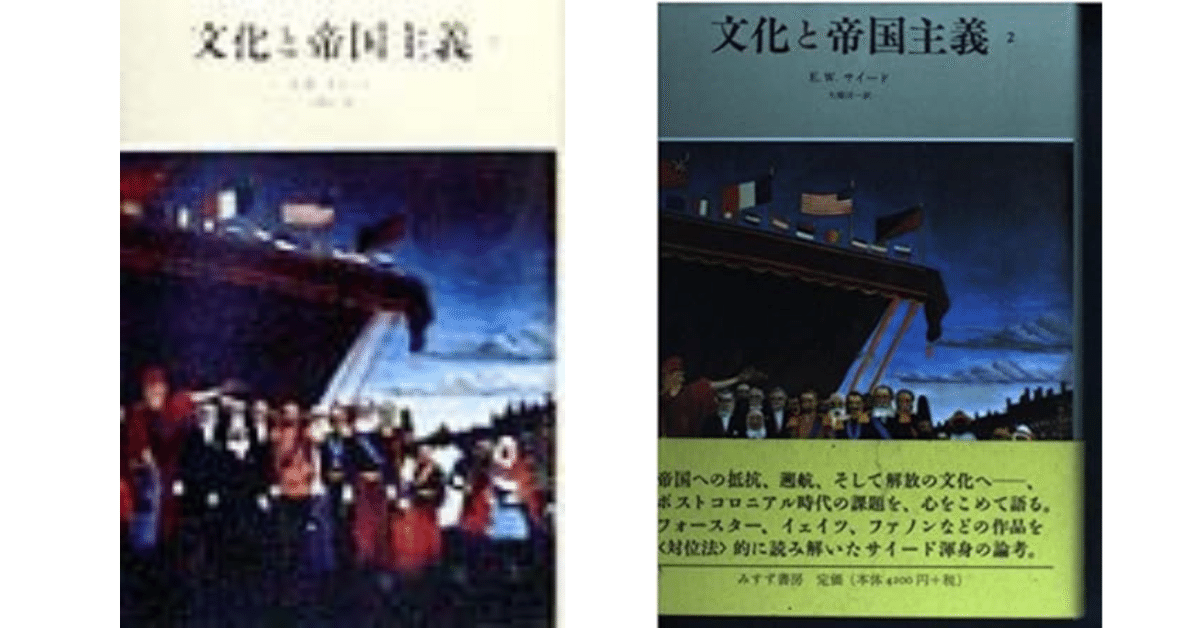
ポストコロニアルの書
『文化と帝国主義』サイード,エドワード・W.【著】/大橋 洋一【訳】
『オリエンタリズム』以後の著者の思索と活動のすべてを集成。ポストコロニアル批評のバイブル。
書評など:
9・11以降、サイードの本が注目を受けています。
2002年2月12日から4日間連続で、朝日新聞紙上でサイードと大江健三郎との往復書簡が掲載されました。そのなかで、大江健三郎さんは「自分への疑いを持たぬ雄弁な若者に、メディアの宣伝の本だけでなく、サイードの本を読むように、…緊急かつ本質的な文章『戦争とプロパガンダ』、あわせて、昨年見事な翻訳の完成した『文化と帝国主義』が読まれることを私は望みます」と語っている。
「いまあらためて母国語で『文化と帝国主義』を読み、ほぼ十年前のこの本が、まさに現在の日本、日本人についての分析であるのを痛感」と。(大江健三郎/2002.2.13 朝日新聞)
内容説明
19世紀と20世紀を通して破竹の勢いで進展してきた帝国主義。イギリスやフランスをはじめとした西洋諸国は、世界地図のアジアやアフリカの部分を「われら」の土地として塗りつぶしていった。宗主国の国民は、また植民地化された「原住民」は、それぞれこの事態をどうとらえていたのだろう。そして文化は、帝国主義とどのような関係にあるのか。とりわけ、ルカーチによれば「近代」の形式である小説、それもその最高の芸術的成果が帝国主義とどう絡みあってくるのか。サイードは、歴史意識を前提としつつも、文学の地政学ともいうべき方法論を駆使して、両者の関係を考察する。
目次
第1章 重なりあう領土、からまりあう歴史(帝国、地理、文化;過去のイメージ、純粋なものと混淆的なもの;ふたつのヴィジョン―『闇の奥』における;乖離する経験 ほか)
第2章 強化されたヴィジョン(物語と社会空間;ジェイン・オースティンと帝国;帝国の文化的統合;帝国の作用―ヴェルディの『アイーダ』 ほか)
ウェイリー訳『源氏物語』はオリエンタリズムではないのか?とふと疑問に思い、この本を手にした。一番わかり易いのはコンラッドの『闇の奥』でこの小説が斬新なのは支配する側の不安も描かれているからということだった。オースティン『マンスフィールド・パーク』はイギリスがインドを植民地化することによって「マンスフィールド・パーク」の豊かさがあるということ、植民地側の小説・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』を読むことを勧めている。またカミュ『異邦人』もコロニアル小説なのは理解できるが帝国側というのが良くわからない。
モダニズム小説が帝国主義の小説であるというのはなんとなく理解出来たが、それだけではないのはヴァージニア・ウルフとかはフェミニズムに繋がっていく。ウェイリー訳『源氏物語』はやはりコロニアル文学であるというのは、天皇制が受領階級の荘園から成り立っているのであり、女性は男尊女卑の中で搾取される身体ということかもしれない。それがアトウッドの『侍女の物語』として現代性と繋がっていくのだろう。
全2巻完結
-第2巻-
「今日、誰もが、純粋にひとつのものではない。インド人あるいは女性あるいはムスリムあるいはアメリカ人といったレッテルは、せいぜい出発点にすぎなくて、ほんの一瞬でも実際の経験に足を踏み入れるなら、すぐにも忘れ去られてしまうものなのだ。帝国主義は文化とアイデンティティとの混合を地球規模で強化した。しかし、そこからもたらされた最悪の、もっとも逆説的な贈り物とは、人びとに、自分たちがただひたすら、おおむね、もっぱら白人あるいは黒人あるいは西洋人あるいは東洋人であると信じこませたことだ。しかも人類が自分自身の歴史を築いてきたように、人類はまた自分の文化なり民族的アイデンティティをつくりあげる。執拗に連綿とつづくところのいにしえよりの伝統や継続的な居住や民族言語や文化地理を否定できる者は誰もいない。けれどもそのような他者との分離点や相違点に、これこそが人間生活の本質であるかのごとく、こだわりつづける理由は、恐怖と偏見以外にどこにもないように思われる。事実、生存とは、さまざまなものを結びつけることを中心にして達成される。エリオットの言葉を借りれば、現実は「バラ園にいる木霊たち」から切り離して考えることはできない。より実りあるのは――そしてより難しいのは――「わたしたち」についてだけではなく、他者について、具体的に、共感をこめて、対位法的に考えることなのだ。しかし、だからといって、他者を支配したり、他者を分類したり、他者を階層秩序のなかに位置づけたり、またとりわけ、「わたしたちの」文化なり国がいかにナンバー・ワンか(もしくはこの件に関しては、なぜナンバー・ワンでないのか)について、何度もくりかえしていればいいということではない。そうしないことが、知識人にとって、じゅうぶんに価値あることなのである。」
『文化と帝国主義』末尾の、みごとな一節を、ここに引用した。これは故郷喪失者としての知識人のメッセージである。故郷を喪失すること――これは、この節の少し前にサイード自身が引用し、またかつてサイードの敬愛するエーリヒ・アウエルバッハが「世界文学としての文献学」の末尾で引用もした、12世紀ザクセン出身の修道士サン・ヴィクトルのフーゴーの美しい一節「故郷を愛おしむ者は、まだ未熟な初心者にすぎない……完璧な人間は、彼自身の場所を抹消するのである」から採られている。
訳者の大橋洋一氏もまた、「あとがき」にこう書きつける。「故郷は、本来的な異種混淆性を忘却させて、排他的・攻撃的な姿勢の温床になるがゆえに、危険きわまりないものであり、故郷をなくすことのほうが、望ましいこともあるし、そもそも故郷などなかったのではないかと思い知ることのほうが重要ではないか。サイードがいま読まれるべき理由もここにあるだろう。サイードは西洋が、あるいは西洋に端を発した帝国主義が、諸悪の根元だとは思っていない。ただ故郷が、利用のされ方次第で、諸悪の根元になりうることを示してくれたのである――豊富な事例と多彩な語り口によって。」
読者の皆さんは、まずは本書の「豊富な事例と多彩な語り口」を、エメ・セゼール『帰郷ノート』の引用ではじまる1ページ目から読み進められて、先に引用した末尾の一節に辿りついていただきたい。第2巻の本文は246ページ。すばらしい体験になることは、保証いたします。
目次
第3章 抵抗と対立(ふたつの側がある;抵抗文化の諸テーマ;イェイツと脱植民地化;遡航そして抵抗の台頭;協力、独立、解放)
第4章 支配から自由な未来(アメリカの優勢―公共空間の闘争;正統思想と権威に挑戦する;移動と移住)
サイードのわかりにくさはそれまでの帝国主義がアメリカ型の多国籍正義として存在する在り方でナショナリズムに陥らない道を模索するからだろうか?それはサイードのパレスチナとして生き方がアラブにあるのではなくアメリカ帝国主義の中で共存していかなければ成り立たないポスト・コロニアルだからなのか?植民地主義でもアラブでは不可能なパレスチナという生き方。それはかつて離散したユダヤ人のようにその土地で生存することだ。専門書の羅列で読むのに苦労する。後半は植民地主義からの抵抗を模索する文学を読んでみたいと思った。
映画『エドワード・サイード OUT OF PLACE』というドキュメンタリーで描かれていたのはサイードがイスラム教徒ではなくパレスチナでも裕福なキリスト教徒である家庭に育ったこと(資本家の家)は、アラファートのPLOとは一線を画すものであり、根無し草としての故郷喪失者なのだ(そこはユダヤ人的なのだが)。一つには国家としての幻想があるのかもしれない。サイードの墓がパレスチナに建てられずに妻の出身国であるヨルダンに墓を建てるしかなかった在り方は考えてしまう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
