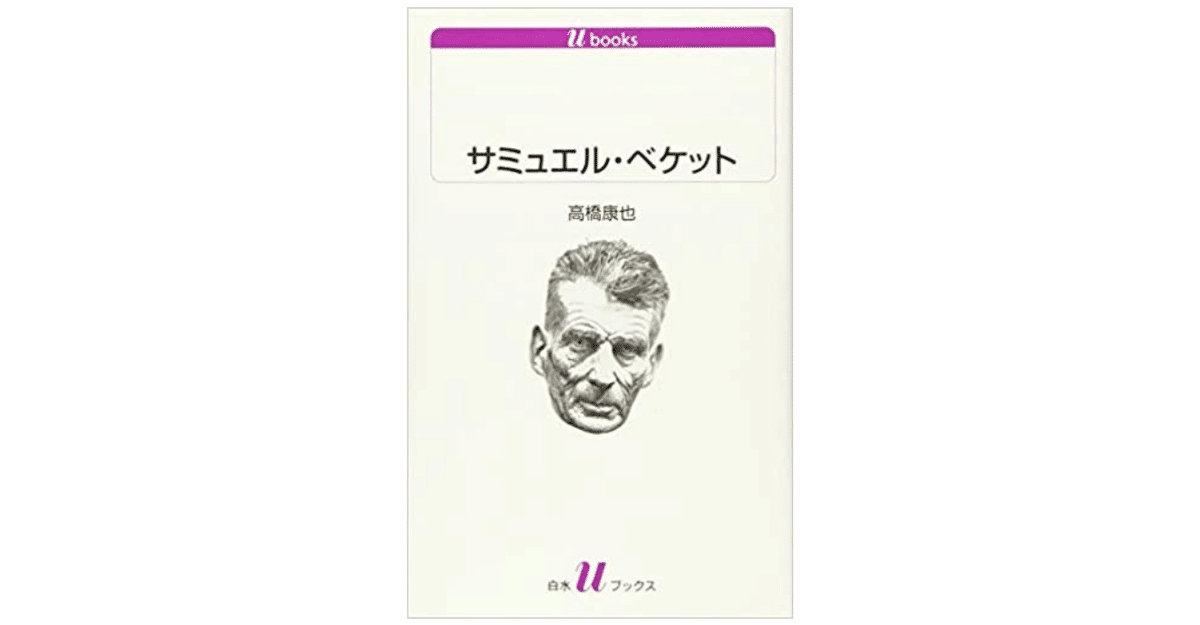
道化師のソネット
高橋康也『サミュエル・ベケット』 (白水Uブックス)
《第一人者によるベケット入門》
「ぼくは『道化』に視点を定めて、ベケットの世界を見つめようとした。
恐ろしさと滑稽さがいわくいいがたく一つに重なっている。
そこにベケット文学の要諦があると信じたからだった」(本書より)
いつの時代にも、新しい読者を獲得し続ける稀有な作家、サミュエル・ベケット。ゴドーとは何者なのか。ベケットの半生とその時代を辿りつつ、〈道化〉の誕生から終末までを代表作を中心に読み解く。
祖国喪失や使用言語の問題、第二次世界大戦時に参加した抵抗運動の影響について、チャップリンの道化やデカルトとの違いなど、要点を押さえられている。『ゴドーを待ちながら』の着想と小説三部作(『モロイ』『マロウンは死ぬ』『名づけえぬもの』)との関連も詳述され、ベケットの全体像がよくわかる。
後期三部作と『ゴドーを待ちながら』のベケット解説本。カフカに於いて書くことが最後に残された尊厳だとしたら、ベケットはそれを強制されているわけだった。書くことを強制されている存在、それは精神病院の分析医と患者の関係かなとも思う。それは外部の神的位置にいる権力構造だという。ベッドに括り付けられていつまでも死ねないベケットの登場人物。
ベケットの登場人物は声を失っている。声が届かない。例えばこんな光景。病気でベッドで寝ていて苦しくなった。緊急ボタンを押すが看護婦が来てくれない。その絶望感。これは今の日本のシステムなんだと思う。看護婦は頑張っているのだ。自己犠牲的に。それでもボタンを押し続け応答のない世界で演じる続ける道化の姿。
ヴィドゲンシュタインの問い。語り得ぬものには沈黙せねばならない。ベケットは声を失ったが書くことを強いられた。それを止めることもできたのだ。強制されたにしても。でも止めなかった。賭けがあっるのだ。マラルメ的な賭け。物語は道化でもそれを読み取る人がいる。そういう賭けとしての書くこと。
ベケットは突然刺されたことがあって、その狂人になんで刺したのか聞きに行ったそうである。「わからない」と言われたのがベケットの書くことの元にあった。想像力を想像できない世界。今、読まれるべきはベケットなのかもしれない。
ベケットの道化は、シェイクスピアや「ドン・キホーテ」の時代にあったものだが、ちょうど彼らの道化がまだ道化でいられた時代よりは、すでに道化をも排除していく時代になっていた。フーコーの『監獄の誕生』。それでも模倣することしか出来ない者たち。
『ゴドーを待ちながら』でウラディミールとエストラゴンが最悪な神かもしれないものを待ち受けながら、最後に模倣したのが一本の木の枯葉や木の姿だった。そのときに音楽的なものが生まれる。調和性か?その仕草の尊さ。不条理劇の中の光なのかもしれない。
しかし小説の方では、動くことを禁じられ声を封じられる。その中で書くこと。模倣する道化は、デカルトだったという話(心の中の声を相手にしていたわけだ)。『名づけえぬもの』は神を求めたキリストに近づく。それも道化としてなのだが。
