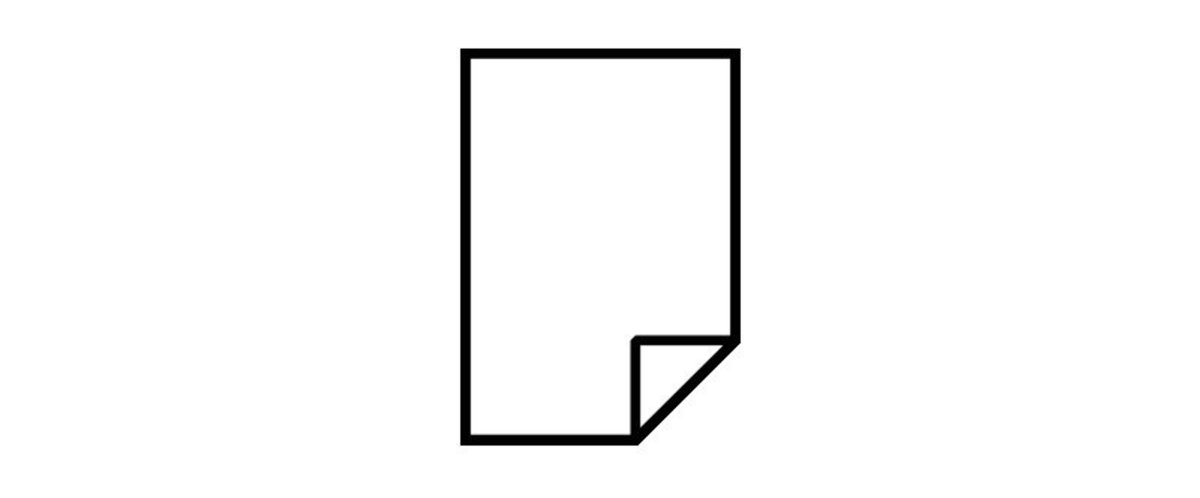
「コピー数多型」からみる世界人類の遺伝的多様性
人類学,生物学に関心のある諸氏は,ヒトの遺伝的多様性について既によく知っているだろう.ご存知の通り,血液型や身長,薬の効きやすさには遺伝子の個人差というものが深くかかわっている(ところでサルにもABOの血液型があり,長年研究されてきている.機会があればこれについて解説するかもしれない).本noteでも,今まで幾つかの遺伝子の個人差についての記事を公開している:
新たに注目される「コピー数多型」とはどんな個人差?
遺伝的な個人差には大まかに分けて「一塩基多型」と「コピー数多型」がある.一塩基多型は,「文字の書き間違い」のようなものであり,連綿と続く遺伝子配列のうちの一文字(一塩基)に突然変異が入ることによって起きる.従来精力的に研究されてきたのはもっぱら一塩基多型である.これは変異の範囲が狭いため,検出や解析がやさしいからである.対してコピー数多型はもっと範囲の広い変異だ.親が子にDNAを受け渡すとき,染色体を複製しなければならないが,その際染色体の一部がずれてしまい,部分的に重複したり欠失したりしてしまうことが起きる.この「一部」の中に遺伝子が含まれていると,遺伝子の数(コピー数)が他の人より増えたり減ったりする.すると,ある病気へのかかりやすさや薬の効き方に違いが現れる場合がある.これが「コピー数多型」である.旧来のシーケンサーで解読できるのはせいぜい500塩基程度だったが,この「コピー数多型」の範囲は1000塩基から数万塩基にも及ぶため技術的に解析が難しく,今まであまり研究が進んでこなかった.次世代シーケンサーの登場といった技術革新によって,近年盛んになりつつある分野の一つでもある.
世界人類のコピー数多型
ではこのコピー数多型,人類の多様性や進化にどのように影響してきたのか.2015年9月にサイエンス誌に発表された論文(文献1)で,研究者らはアフリカ,ヨーロッパ,オセアニア,東アジア,シベリア,南アジア,アメリカの125集団236人のゲノムを解析し,15000余りのコピー数多型を発見した.一塩基多型がゲノム中の1.1%を占めるのに対し,コピー数多型はゲノム中の7.01%を占めていた.それぞれの人類集団について解析すると,自閉症や,「眠り病」と称されるトリパノソーマ病へのかかりやすさに関連するとされる遺伝子,血糖値や不安に関係するとされる遺伝子のコピー数多型がどれだけ観察されるかは,集団ごとの違いが大きかった.これらは風土病への適応進化の結果である可能性がある。さらに,4万年前にロシアで暮らしていた化石人類であるデニソワ人(英語サイト)が持っているコピー数多型が,現在のオセアニアの人にも共有されていることが明らかになった.デニソワ人とオセアニア人の遺伝的類縁性は,過去に一塩基多型の研究によって示唆されてきたが(文献2),今回のコピー数多型の研究もそれを支持する結果となった.コピー数多型は一塩基多型と共に,人類の進化史や病気の原因を究明していく重要な手掛かりとなりそうだ.
(執筆者 James)
文献
1. Sudmant et al. (2015). Global diversity, population stratification, and selection of human copy-number variation. Science, Vol. 349, No. 6253, aab3761, DOI: 10.1126/science.aab3761
2. Meyer et al. (2012). A high-coverage genome sequence from an archaic Denisovan individual. Science, Vol. 338, No. 6104, 222-226, DOI: 10.1126/science.1224344
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
