
募集企画「イラスト業界」への質問を各社に聞いてみた
冬コミ3日目(南リ32b)に新刊を出します。
『イラスト業界の解像度を上げる100の回答』
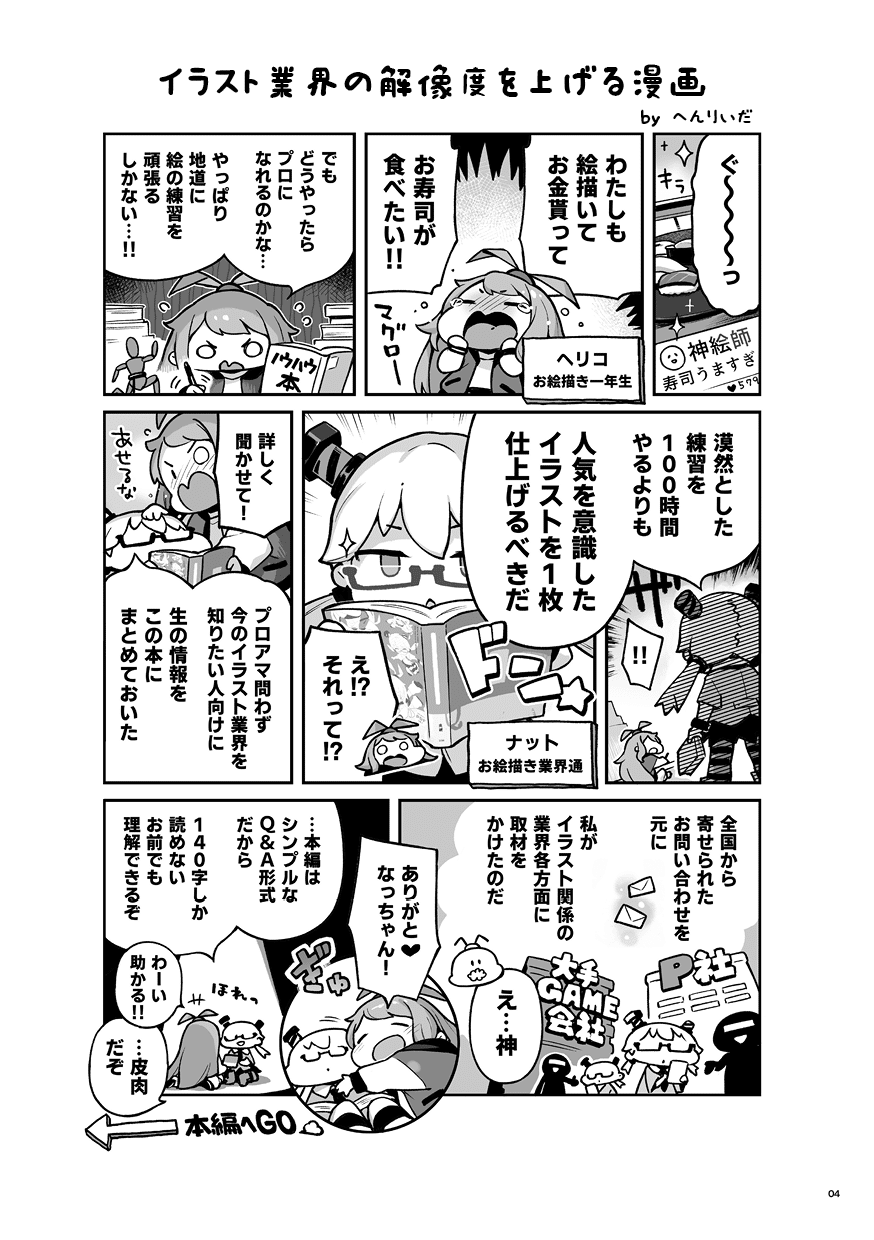

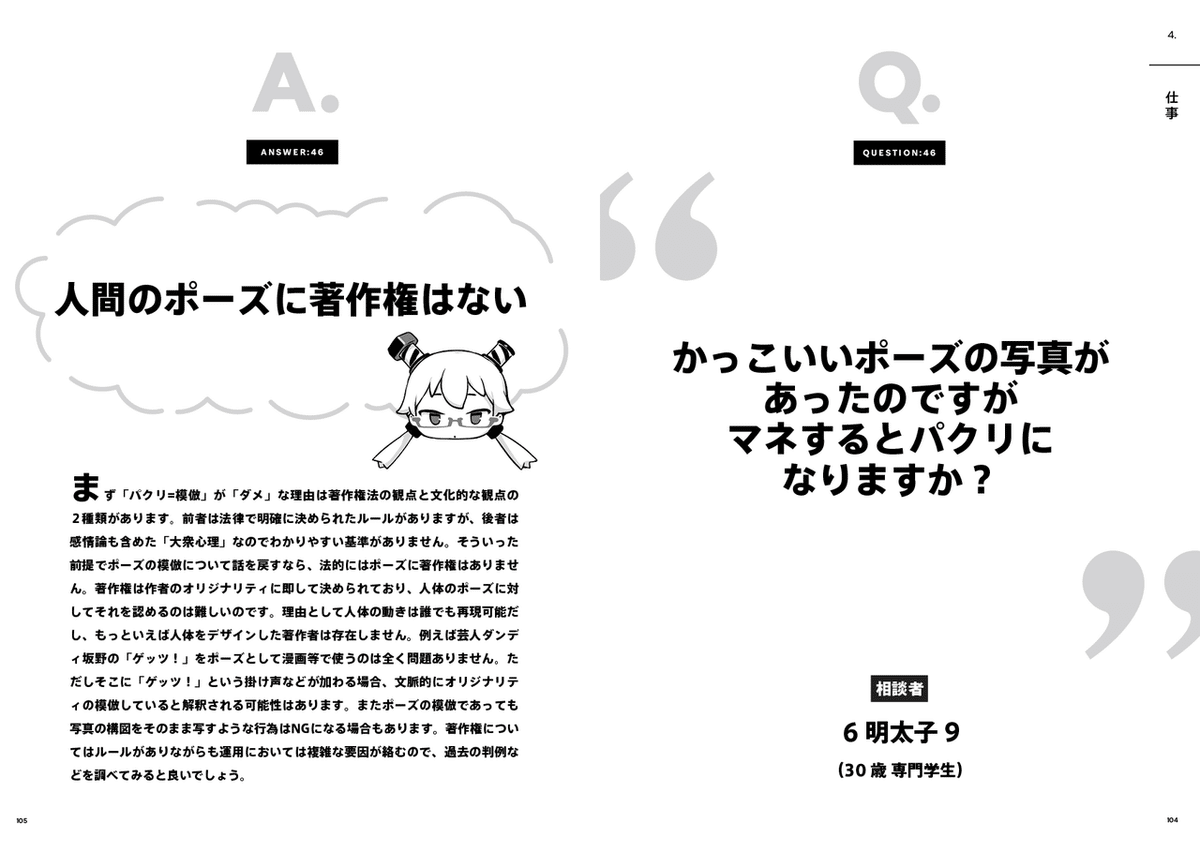
▲リンク先にDL販売あり▲
内容は昨今大きな注目を集めている「イラスト業界」への解説本になります。Twitterや学生などから募集した質問を元に、著者である私が各社に取材。出てきた内容を元に編集し、テキスト化しています。今回の記事では本に載せられなかったQ&Aをこの場を借りて公開しようと思います。
【募集】イラスト業界(企業、クリエイターなど)に関して知りたいことがあれば、このツイートにリプライください。私から取材して結果を記事や同人誌で公開します。お気軽にコメントください〜
— ネット絵学@C97_3日目/南リ32b (@netegaku) November 11, 2019
みんなからの質問に回答!
ちなみに取材した企業の具体名は伏せているので「怪文章!」と言われるとそれまでですが、幅広い業界から話を聞けたと思うので楽しんで頂けると幸いです。ちなみに質問文はそのままではなく、こちらで編集させていただいています(重複する質問が多かったので)。
Q1:企業がイラストレーターを採用する場合、学歴を基準にしていますか?
一般的に言われる難関大学のような武蔵美、多摩美、東京藝術以外にも美術大学には需要はあるのか気になります。また専門学校や高卒だと不利になる、などはあるでしょうか?
A:以前ほどではないが美大卒もニーズがある
学校関係の質問はとても多かったです。ちなみにTwitterなどで人気クリエイターに聞くと十中八九「学歴は意味ない」と応えます。私自身も同様のツイートを過去にしました。しかし実際に調べる中では学歴を重視する企業はそれなりの割合でいることもわかりました。

簡単にモデル化すると上の図の様になります。学歴以外の質問もしてます。これが、フリーランスとしての単発契約か、正社員としての長期雇用かによってさらに変数は増えます。要するに答えは一元化しないし業種や人それぞれという結論です。
美大を重要視する理由として、入学難易度の高さがあり、少なくともそのハードルを超えている人は優秀であろうという判断があります。しかし近年は美大人気にも翳りが出ており、このあたりのレベルが下がっていて、昔ほど評価対象になっていないという意見も同社からありました。
Q2:現在のイラスト系サービスの主力を教えてください!
大学生です。イラストレーター業界のサービスと今後の業界の動きについて調べています。ただ、自分がイラストレーターなど創作活動をしていないためピクシブ各種サービス・TwitterなどSNS・SUZURIなどを初めとするグッズ代行サービス 以外の主力サービスなどがいまいち把握出来ていません。自分の研究不足ももちろんあるのですが、是非知りたいです。
A:投稿数は(おそらく)pixivが上、Twitterの方がPRに強い
質問範囲がかなり広いので「イラストSNS」に限定して回答します。まず、なにをもって「主力」と考えるかの定義をするなら、一つに「イラスト投稿数」が挙げられると思います。しかしTwitterのイラスト投稿数を調べるのはかなり難しい。マクロなデータからTwitterに投稿している画像をイラストか写真かを見分ける術がないし、仮にスクレイピング(規約違反)で判別できたとしてもそれが本人が描いたものか無断転載なのかを調べづらいです。pixivの場合、イラスト作者による投稿であることを規約で縛っているので内部データを持っていなくてもidから投稿数を判別できます。ちなみに2019年12月25日のイラスト投稿数は1日で約25,000件でした。クリスマスで多いという説はありますが、概ね2〜3万件/日の間で推移しているようです。ちなみに世界のサイトのアクセス数を可視化できるSimilarWEBによると国内18位でニコ動やInstagramよりも上です。トップ5はGoogle、Yahoo!、YouTube、Twitter、Amazonの順となります。これはあくまでもウェブ版のランキングですが、媒体資料をみるとpixivはアプリの方がアクセスが多いので、いずれにせよ上位といえるでしょう。

他社だとニコ静、Skebもランキング圏内に入っていないようなので、イラスト投稿サイトとしてはpixiv一強の状態が続いてます。(本筋とは関係ないですが、以前は上位にいたニコ動が急落しててびっくりしました。そして「小説家になろう」の躍進がすごい!)
一方でSNSとしてはTwitterの人気が加速してます。拡散力が強いのでプロも積極的に利用し、自身の付加価値を高めるツールになってます。pixivはあくまでもイラストに興味がある人がユーザーになりますが、Twitterはその分母を広められるのが強みですね。
ちなみに個人系ECサイトだと、ピクシブが運営するBOOTHが国内669位、、SUZURIが3,774位、BASEが803位だそうです。メルカリが8,541位ですが、あくまでもWEBなので、アプリはダントツでトップでしょう。
Q3:人気作家はどれくらい仕事オファーが来るのですか?
イラスト関係会社で仕事をしています。人気クリエイターさんに絵を発注する場合の温度感が知りたく、彼らがどれくらいオファーが受けているのが教えて欲しいです。あと制作実績数、オファーメールの返信に要する日数なども知りたいです。
A:聞いた中だと月50〜100件オファーが最多
これもケースバイケースなので「〇〇さんはn件来ている」という回答しかできません。プライベートな情報なので実名で公開できず、あまり意味の無いデータでしょう。という前提のもと、私が取材した人の中でpixivランキングトップかつTwitterフォロワー数十万、コミケ壁というセグメントで見ると月あたり50〜100件という方が最多でした。一方で月1〜2本程度の新規発注だけど、長期案件にコミットしているのでほぼ仕事を受けられないという人もいるのでオファー件数の量で受注できるかどうかは直接関係ないともいえます。
月あたりのイラスト制作数は、ソシャゲで絵柄が複雑でないなら1日で2〜3件(月産50〜80件)こなす方もいます。ただしフィードバックが少ない(=要件に対して的確なアウトプットができるor発注者が妥協するくらいネームバリューがある)ことが条件です。
オファーメールの返信も本当に人によりけりという感じで、私の経験上、トップか若手かでこの辺の差は少ないです。もちろんメールが一日に何通も来る人は律儀に返信するよりも「無視」した方が効率良いというのもありますが、人気だからルーズ、駆け出しだからちゃんとしているという括りは全く無いです。むしろ全く仕事実績のない学生ほどルーズなケースが多いように思います。いずれにせよ連絡まめな人がレア人材というのは間違いないです。しばらく連絡できてたのに納品間際になって突然音信不通になるのも業界あるあるですね。
Q4:需要が大きいのに描き手の少ないジャンルはなんですか?
絵仕事の中で、需要が大きいのに描き手(供給)が少ないジャンルはありますか?イラストだと女の子を描く人は多いけど、モンスターや背景を描く人は少ないと聞きます。調べても企業からの意見は見つからず、事実や詳細はどうなんだろうと気になりました。
A:絵合わせできる人は貴重
ジャンルというよりも「モチーフ」として考えると、モンスターや背景が描ける事そのものでは仕事につながりません。絵柄の要素が大きいので単にニーズの大きいモチーフが描けたとしてもタイトルの世界観に合わなければ採用されません。なので質問に直接応える形ではないのですが、絵柄を柔軟に合わせられる人のニーズが高まってます。SNSでは個性的な作画が尊重される傾向もありますが、現場では逆です。没個性だけど絵柄の再現が得意で、デッサン力があるクリエイターが歓迎されます。このあたりの話は『イラスト業界の解像度を上げる100の回答』にも書いたので興味があればどうぞ。
Q5:イラスト単価の決め方を教えてください。
絵のお仕事の報酬計算方法を知りたいです。いわゆるなんとなく相場に合わせる・または言い値ではなく、根拠をもって計算する方法を知りたいと思っています。「人それぞれ」だとは思いますが、いくつかの例を教えてもらえると嬉しいです。
A:最も分かりやすいのは時給計算
案件から工数を見積もってかかる時間×〇千円と出すのが一般的です。もちろん面白そうな仕事やトレンド、友達付き合いなどがあれば単価は下がるだろうし、非常に変数の大きい部分です。そもそも「金額には根拠がある」という前提に誤りがあり、ほとんどの人は具体的な根拠を持って計算していないのが実情かと思います。いわゆる「時価」的な考え方が重要になります。同じ工数でもあるタイミングなら10万円だけど、別のタイミングなら30万円になる、というようなものです。また発注経路によっても設定金額は変わります。そう考えると以下の計算方式の様になるかもしれません。
イラスト単価=
かかる時間×設定時給(〇千円)×キャリア×関係値×モチベーション×スケジュール×etc…例えば「書籍の表紙を描いて欲しい」というオーダーがあった場合はこういう思考になります。
イラスト単価=10万円(小計:87,480円+バッファ)
かかる時間:25時間×
時給:2,000円×
キャリア:初の単行本表紙(0.9)×
関係値:知り合いからの紹介(0.9)×
モチベーション:好きなデザインが描けそう(0.9)×
スケジュール:結構忙しい(1.2)×
品質保証:×:表紙になるのでハンパなのは出せない!(2.0)これは感覚を具体化したモデルなので、実際はここまで数値化されて計算しているわけではないはずです。仮に明細を出すならこういう感じかなという実験ですね。
まとめ
そんな感じです。Twitter経由できた質問は上にまとめた感じでだいたい網羅できたか、変数が大きすぎて回答できないというパターンのいずれかです。「人それぞれ」というケースが非常に多いのでまず、業界やニーズごとにカテゴライズした上で解説を載っけるがベストだと思い、本はそのあたりをメインにフォローしてます。書籍化にあたってはTwitter以外からの質問を自分で8割以上作ったので、バリエーションは増えてます。
オマケの宣伝
書籍版は装丁結構頑張りました。特色銀刷り+カバー&帯付きです。イベントだと1000円で入手できてめっちゃ安いので、コミケ3日目来る方は是非ゲットしてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
