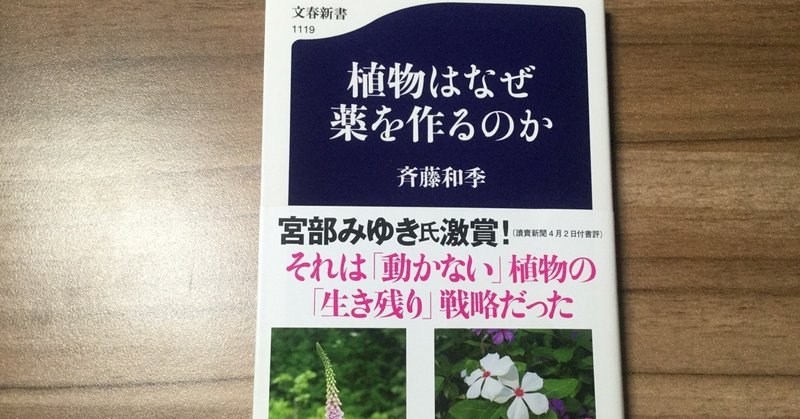
[書評] 『植物はなぜ薬を作るのか』

『植物はなぜ薬を作るのか』齊藤和季著
文春新書(2017年2月20日初刷発行 2018年5月5日 第7刷)
株式会社文藝春秋
「植物成分を使った薬や健康食品は、人工合成じゃないから毒じゃなくて、体に優しいでしょう」というような質問を著者はよく受けるそうだ。植物は体にいい、体に優しいというイメージは、昨今の”ボタニカル”ブームを見ればどれだけ浸透しているかわかる。著者は薬学の専門研究者だが、このような質問に少し苦笑いをしながらも、丁寧に対応していたという。
植物は我々人間に「優しくするために」、我々の「体に良いもの」をつくっているわけでは決してない。植物は生存競争の中で生き延びるために進化をして、多様な化学成分を製造する機能を持っただけであって、その中のある物質がたまたま人間にとって薬になり、あるいは猛毒や麻薬になったというだけのことである。本書は、植物がこれら化学成分をつくるメカニズムや、植物自身がその物質に侵されない秘密などを平易に解き明かしてくれる。ケシからは鎮痛剤モルヒネが、ヤナギからは解熱鎮痛剤アスピリン、ニチニチソウからは抗がん薬ビンカアルカロイドが生まれたなど、数々の薬の歴史と成分について化学式を交えながら詳しく展開される。
科学的知見とエビデンスに基づいた冷静な筆致は、「植物は自然のもの、だから体にいい」というぼやっとした妄想をクールダウンするのに充分だ。似たような妄想は野菜栽培などについても見られる。たとえば「肥料は無機肥料より有機肥料」という話があるが、無機肥料の代表である「リン」は「リン鉱石」からつくられるが、リン鉱石は太古の動植物や海洋プランクトンの死骸が堆積し、それらが持つリン化合物が鉱物化したもの、つまり無機のリン肥料ももとは生物(≒有機物)であるということが、本書を読んだ後にはすんなりと頭に入ってくるのではないかと思う。
新薬の6割がいまだに植物を含む天然物の成分や生合成経路をもとにつくられているという。化学製薬工場での人工合成が足元にも及ばない植物の凄みを感じるとともに、様々な面で植物に生かされている人間は、もっと自然の前で謙虚にならなくてはならないと本書は教えてくれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
