
【赤報隊に会った男】⑩ 本命の男
鈴木邦男が「この男が赤報隊に違いない」と考えている本命の人物は、見沢知廉の奪還を持ちかけてきた〈第1の接触〉の男ではなく、中曽根総理襲撃を予告した〈第2の接触〉の男だった――――。
そのことを悟った僕は当然、この人物に質問の矛先を向けることにした。
――――この人とは1度しか会わなかったんですか?
「もう1回会ったのかな。なんか、ものすごく慎重でしたね」
そう、この〈第2の接触〉の男はものすごく慎重な人物なのだ。
繰り返しになるが、改めて説明しておこう。
鈴木が1995年(平成7年)に「SPA!」の連載コラム「夕刻のコペルニクス」につづったところによると、朝日新聞阪神支局襲撃事件の後、鈴木のもとに差出人不明の手紙が届き、ある場所に呼び出された。そこに電話がかかってきて、警察の尾行を警戒するように2度3度と場所を変えさせられた末、謎の男に会った。その男は、当時総理の座にあった中曽根康弘を「全生庵で狙う」と予告した、という。

さらに付け加えると、鈴木は2005年(平成17年)に別冊宝島に寄稿した文章でも、これとよく似た体験談、すなわち〈関西での接触〉を披露している。
朝日新聞阪神支局襲撃事件の後、鈴木のもとへ切符が送られてきた。関西のある駅で降りると、雑踏の中ですれ違った男から「後ろからついて来てください」と声をかけられた。ついてゆくとホテルの部屋が予約されていて、そこで夜を徹して話し合った。こういう会い方を何度もした、という。
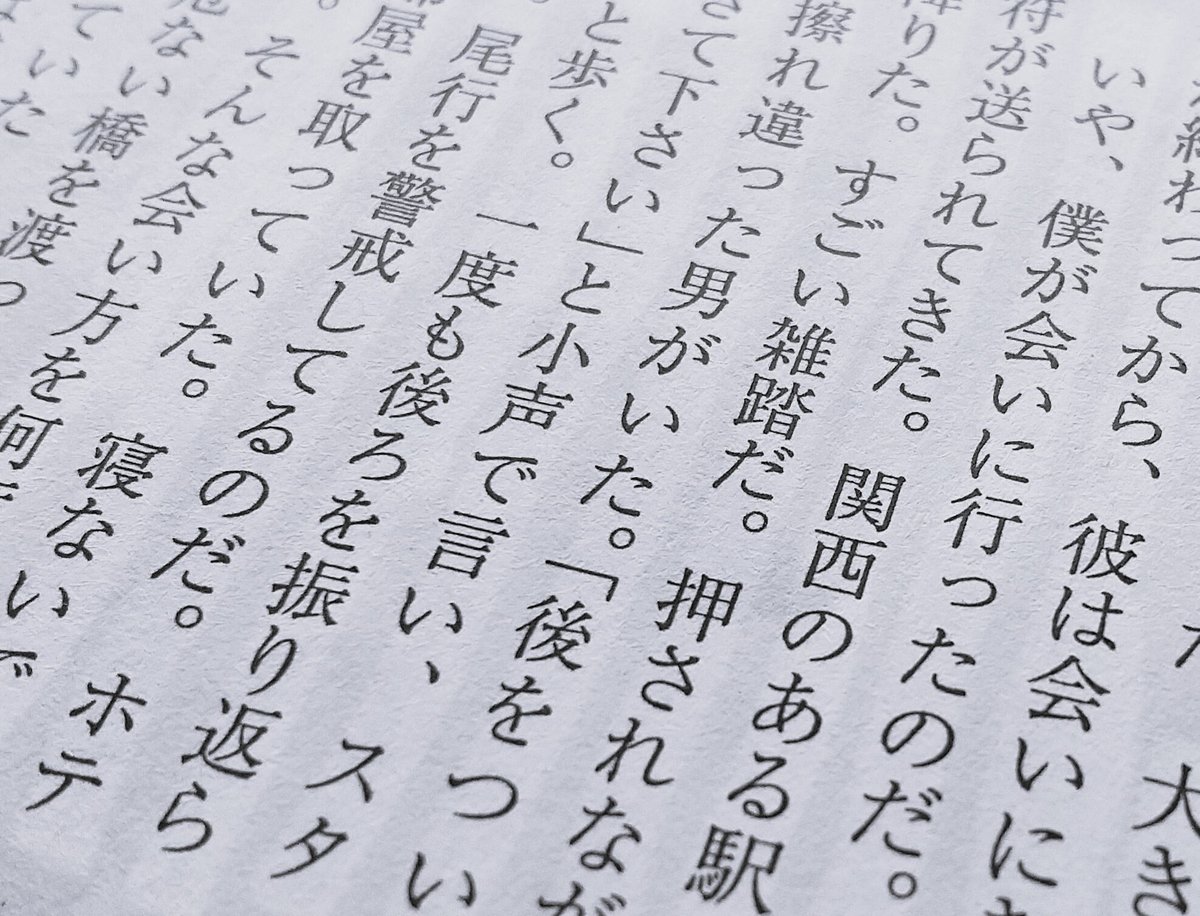
ともにスパイ映画のようなミステリアスな手順で行われた密会の物語。
恐らく、この2つのエピソードに登場する謎の男は同一人物なのだろう。念のため確認してみることにした。
〈第2の接触〉と〈関西での接触〉は同一人物
――――この別冊宝島に出てくる男は、「夕刻のコペルニクス」で「中曽根を全生庵で狙う」と言ったあの男なんですね?
「そうですねえ。その時、彼らの心情みたいなものを随分聞きましたねえ」
――――この人とは結局、2度3度と会っているんですか?
「そうですねえ」
――――いつもこういう会い方をされていた?
「そうなんですよ。雑踏の中でぼうっとしていると、パッと近づいてきて『俺の後をついてきてください』という感じで。ついていくと、そのホテルで部屋を取っていたと。それで、こういうことがあって許せないと思ったから行動したんだ、ということを言ってましたよ。そういう意味では、心情的に熱いものを持っていたんだなあ、と」
――――ということは、あれはやっぱり「文学的表現」ではなくて、鈴木さんの実体験だったんですか?
「そうなんですねえ」
鈴木は〈第2の接触〉の男と〈関西での接触〉の男が同一人物であることを肯定した。
ただ、「実体験なのか」という僕の念押しに対して発した「そうですねえ」という返答には、やや冗談めかしたような響きが含まれているように感じられなくもなかった。
こちらとしては、事実関係を地道に詰めていくしかない。
僕はとりあえず、話の内容により具体性がありそうな〈関西での接触〉のエピソードに質問を集中させることにした。
――――切符が送られてきて、関西のある駅で降りたと?
「だからホームで降りてボーッとしていたら、向こうがパッと、すれ違いざまに声をかけてきて。凄いですね、ああいうのは。映画みたいですね」
淀みない口調だった。
どうやら、フィクションの要素が濃厚な〈第1の接触〉や〈野村・赤報隊会談〉に比べると、この用心深い男のエピソードには真実味がありそうだ。
少なくとも、鈴木は老境に達した今でも、この話を「実体験」として語っている。
ただ、彼が話す内容は、あくまで過去に雑誌に書いたことをなぞっているに過ぎない。
話の真偽を見極めるためには、接触した日時や場所を特定し、より詳しく、より具体的に接触時の様子を聞き出す必要がある。
インタビューはいよいよ核心に近づいてきた。
変化した口調
――――その男と初めて接触したのはいつの話ですか?
「いつごろなんだろうな。メモ取ってないし、どんどん忘れようとしてますからね、自分の中でも」
――――関西の駅というのはどこだったか覚えてますか?
「いやあ……」
――――それを言うのはまずいんですか?
「うーん……」
鈴木の口は重い。僕は質問を変えてみる。
――――最初に会った時も、いきなり手紙で呼び出されたんですか?
「そうですねえ」
――――僕には不思議なんですが。全く見知らぬ人から手紙が来て、回りくどい方法で会いましょうと言われて、鈴木さん、会いに行ったんですか?
「会いに行ってたんですねえ」
――――殺されるかもしれないじゃないですか。
「何かわかんないけど、信頼関係というのがあったんだろうなあ」
――――だって初対面なんでしょう。
「ええ、もちろん」
――――どうやって信頼関係が? 手紙の文面からということですか?
「そうですねえ。向こうにしてみたら、赤報隊を鈴木が誹謗中傷しているわけじゃないし、また、鈴木に警察の目が向いていることで自分たちが逃げられたというのがあったんじゃないかなあ。それは僕も感じましたね。僕に対して恩義を感じているところがあったのかなと。その点、安心していたというのがありますねえ。
それに山の中で会うとかいうのではないんですよ。人がいっぱいいる雑踏の中で。そういう点で恐怖はなかったですね」
――――向こうは名前を名乗ったんですか。
「名乗りません、まったく」
――――会いましょうという手紙が来た時は、用件が書かれていたんですか? 朝日新聞の事件のことで、とか?
「なんかあったですねえ。忘れちゃったけど……」
行きつ戻りつしながら質問を繰り返したが、「暖簾に腕押し」といった感じだった。何を聞いても今一つ明確な答えが返ってこない。
この頃になると、鈴木の口調からは当初の率直さ、訥々とした語り口が消え失せ、こちらの質問に当たり障りのない言葉を返そうとしているような雰囲気が漂い始めていた。
もちろん、本当に記憶が薄れているのかもしれないが、彼の言葉にはどうも質問をはぐらかそうとしているような響きが感じられるのだ。
なぜ、言い渋るのか。密会の時期や場所を特定して話すことがそれほどまずいのだろうか。最初に会った時の経緯を語ることにそれほど支障があるのだろうか。あるいは、実体験ではないから具体的な証言ができないのか……。
今、手元のインタビュー記録を読み返していても、あの時感じた疑問、もどかしさが鮮明によみがえってくる。
埒が明かないと思った僕は、ここでさらに質問を変え、「夕刻のコペルニクス」に書かれていた〈第三の接触〉の話を振ってみることにした。
〈第3の接触〉の真偽
連載のコピーを示しながら僕は尋ねる。

――――鈴木さんの連載では、阪神支局襲撃事件の後に神田の喫茶店で本を読んでいたら、赤報隊らしき男から電話がかかってきたという話も出てきます。その男は「鈴木さんは統一教会の仕業だなんて書いているけど、僕らにとっちゃ統一教会は敵ですよ」「僕らは鈴木さんの本を読んで右翼思想に目覚めたんですよ」と言った、と書かれていますが?
「うーん……」
――――これは例の男と同じ人物なんですか?
「と思いますねえ……」
――――これは鈴木さんが例の男と1度会った後の電話ということですか?
「そうですねえ……」
この時の鈴木は「僕、そんなこと書いたっけ?」という表情をしていた。
こちらの質問に相槌を打ってはいるが、神田の喫茶店での一件をよく覚えていないという様子なのだ。
その表情を観察しながら考えた。
鈴木にとってこの件はそれほどインパクトの強い体験ではなかったのか?
それとも、この話は単なるフィクションだから忘れてしまったのか?
恐らく後者なのだろう、と僕は思った。
いくらなんでも、喫茶店でくつろいでいる時に赤報隊から抗議の電話を受けるなどという特異な体験をしたら、生涯忘れられない記憶になるはずだ。
この反応を見る限り、実体験とは考えにくい。
〈時効後の接触〉はあったのか
続いて〈時効後の接触〉についても尋ねてみることにした。
鈴木は別冊宝島に寄稿した文章の中で、赤報隊らしき男に「時効になったんだし“実は俺たちがやった”と名乗り出てはどうですか」と言ってみたと書いている。これに対して男は「そうですね」と答えたが、その気はなさそうだったという。これが事実なら、鈴木は116号事件が完全時効を迎えた2003年以降も赤報隊らしき男に会っていたということになるが、実際はどうなのか?
僕は別冊宝島の誌面コピーを示しながら質問した。

――――このやりとりはフィクションなんでしょうか?
「あんまり、そんな直接的な話はしないですね。でも、手記を発表するとか、そんな気はなかった」
――――と、その男が言ってたんですか?
「うん」
――――ということは、鈴木さんは時効後にも会っていたんですか?
「いや、時効になったら、という話をしたんじゃないかなあ……」
鈴木はこうはぐらかしたが、別冊宝島には「時効になったんだし云々」という、どうみても時効成立後の会話としか考えられないやりとりが描かれている。僕はさらに畳みかけた。
――――では、この男と最後に接触したのはいつなんですか?
「忘れちゃった、もう」
――――ホントに忘れちゃったんですか?
「忘れちゃったの。認知症なんですよ、もう」
――――そんな大事なこと忘れないでしょう?
「大事なこと忘れるんですよ」
――――メモとかは残してないんですか?
「ないない。だって、いつガサに入られるかわからないんだもん」
鈴木はそう言って屈託なく笑った。
その人懐こい笑顔につられて、思わず僕も笑ってしまう。
やはりこの人は曲者だ。
明らかにはぐらかされているのに、なぜだか会話そのものが楽しくなってくる。その人柄とユーモラスな受け答えに魅せられて、ずっとこうして面白おかしく談笑していればいいじゃないかという気分になってしまう。
ただ、笑いながらも僕は考えた。
この〈時効後の接触〉に関しては、鈴木が別冊宝島用に創作したフィクションだと判断してまず間違いないだろう、と。
少なくとも目の前にいる今の鈴木は、116号事件の時効成立後に謎の男に会ったという認識を持っていないのだから。
とすると、鈴木の中で今も実体験として認識されているエピソードは、〈第2の接触〉と〈関西での接触〉の2つ。すなわち、「スパイ映画のようなミステリアスな方法で異常に用心深い男と密会した」というエピソードに絞られるということになる。
しかし、彼はその詳細を語ろうとしない。詳細どころか、日時や場所すら特定させてもらえない。
インタビューは次第にゆきづまりの様相を見せ始めていた。(つづく)
つづきはこちら→【赤報隊に会った男】⑪ インタビューの結末
※この連載では登場人物各位の敬称を省略させていただいています。このブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しています。
