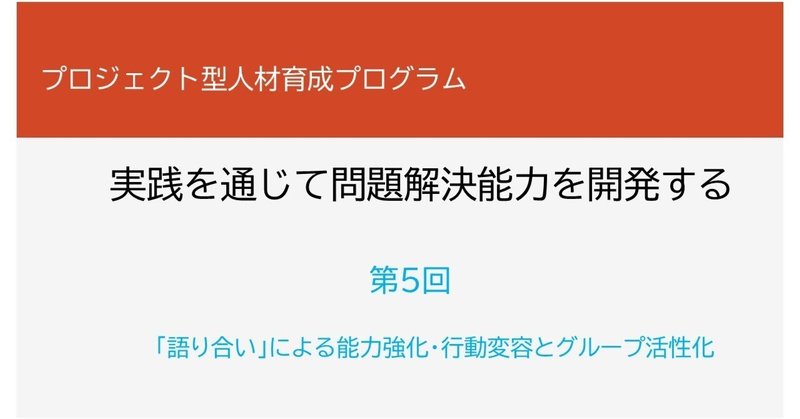
第5回 「語り合い」による能力強化・行動変容とグループ活性化
本稿の構成は、(1)「語り合い」による変化 と(2)グループ活動を活性化する「語り合い」です。
(1)「語り合い」による変化
1)成果実現による達成感と自信
「語り合い」を通じて磨き上げながら成果物を創り上げることは、自らが納得のいく内容に仕上がることに加え、その内容が第三者に伝わることや、職場での実践活動を通じて問題を解決した体験をします。その結果、プログラム参画者は、“達成感”を得るとともに、問題解決への“自信”を持ちます。この達成感と自信は、問題解決に対する“コミットメント(責任を持って成し遂げる)”を高めることにつながり、新たな職場・プロジェクトの問題解決への挑戦意欲を高めるとともに、成果の実現性が高まります。
2)「語り合い」による参画者の変化
プログラム参加メンバーが主体性を持った活動を前提した「語り合い」では、次のような問題解決能力の強化や行動変容が生じます。
まず、問題解決能力面では次の3つです。
①手段発想ではなく、目的・目標志向で取り組むこと
プログラム参画者自ら作成した成果物を眼の前に、プログラム参画者と講師が「語り合い」ながら目的・目標志向の成果物へ磨き上げていくようになります。例えば「業務改善プロジェクト」の「語り合い」を体験したプログラム参画者は、プログラム参加当初に見受けられる「問題が曖昧のままで、問題分析を飛ばし、対策をつくりはじめる。または他の事例を真似る」という手段先行発想が「問題起点の目的・目標志向」に変わります。
②問題解決に効果的な進め方を実践すること
講師との「語り合い」は問題解決の基本的な手順(プロセス)を通じて行われますが、その手順ごとに、“成果物に求められる要件(質)”の観点から改良の余地に気づき、磨き上げていくようになります。
③根拠に基づく提案・発言をすること
問題解決プロセス上の提案や自分の発言には根拠に基づくことが求められることを自覚するとともに、その適切な活用に取り組みます。例えば、問題設定では、「職場にとって〇〇は放置できない問題です。なぜならば、◇◇だからです」と結論を支える根拠とともに提案するようになります。このことは一般論的な発想ではなく、具体的・客観的にものごとを把握する能力も開発されていきます。
また、次のような問題解決の成果に影響する行動変容が主体的に行われるようになります。
④「主体的」に取り組むこと
「語り合い」は問題解決の当事者意識を高めます。当事者意識は自ら解決する動機づけになります。「語り合い」による問題解決プロセスの“良い体験”は、問題を解決する際に誰かに指示される受け身的な姿勢ではなく、主体的に活動するようになります。
⑤自分で考え、意思決定し、表現すること
「語り合い」では、「自分の意見(考え)」を求められることからも、自分で考え、意思決し、自分の言葉で表現する試みを繰り返します。その継続により意思決定の質を高め、適切な表現をするようになります。
⑥段取りを効果的・効率的に行うこと
当初は準備の面倒さややり方が分からないことから場当たり的に取り組んでいたことが、「語り合い」を通じて事前準備の重要性に気づきます。段取りをすることで、自分の担当した成果物が他のメンバーや講師に伝わるようになることやコミュニケーションがかみ合うことから段取りの重要性を実感するとともに、その継続から段取りのコツを習得し、効果的効率的に段取りを行うようになります。
上記のような能力開発・強化や行動変容は、強制されて行われるのではなく、「語り合い」を通じて、参画者が問題解決に有効であることに気づき、行動します。そして、その効果に実感することがプロアクティブな行動につながります。
(2)グループ活動を活性化する「語り合い」
「語り合い」がグループ活動の活性化に有効な点は次の2つです。
1)目的・目標からのズレに気づき、方向性を見直す機会になる
多くの問題は複雑であることから対策体制は組織横断型のプロジェクトチームで取り組む場合が多くなってきています。それに対応すべく「プロジェクト型人材開発プログラム」でもグループ単位で複数のグループ活動が行われます。グループ活動は主体性を重んずることが大切ですが放任状態にすることは避けなければなりません。グループによっては、主体的な活動が自己流、場当たり的に進めてしまうリスクがあります。そこで節目での講師との「語り合い」がリスクを回避する、または目的・目標とズレた方向に気づき、自主的に軌道修正の機会を生みます。
2)グループ活動を活性化する機会になる
正しい答えがなく、自ら答えを創り上げる問題解決活動に慣れていないメンバーで構成されるグループでは、特定のメンバーの意見で方向性が固まる場合があります。例えば、方向性を示した特定メンバーが「手段ありきの発想」や「自らの経験による判断をする」場合、この方向性がテーマとした問題についての解決策として適切でない内容となります。こうした状況のグループは、特定のメンバーだけで話し合い、例え他のメンバーが発言をしても取り上げず、自分たちの方向性で報告書を作成している傾向があります。その結果、他のメンバーはグループミーティングをしても沈黙していたり、意欲に欠けたままグループに所属している状況が発生します。
こうしたグループは一見、主体的に活動して成果物を作り上げていますが、「プロジェクト型人材育成プログラム」の目的からして放置させてはいけないグループの1つです。例えば「語り合い」において「なぜ、この対策が問題を解決するのでしょうか?」や「この提案の根拠は何でしょうか?」などの質問に応えることができないからです。「語り合い」は、それに気づき、見直すための活動を洗い出す機会です。
また、「語り合い」では、講師が全てのメンバーに対して発言機会を設けます。良く発言するメンバーでも、内容に筋道が通っていない場合や自分の経験のみを重視している場合は、その点を自覚してもらうための質問をします。一方、自ら発言しないメンバーに対しては、その発言を言い換えたり、全体を要約して言いたいことを確認します。こうしたやり取りを通じて自分の言いたかったことを他のメンバーに伝え、共有できるとともに、遠慮せずに発言することの大切さを実感する機会になります。
個別グループへのハンズオンサポートの機会であるグループ別の「語り合い」は、プログラムの目的である問題解決するために主体性を維持しながらも適時適切なサポートを通じて不足点に気づき、今後すべき活動を洗い出し、その活動を通じて成果物を改良していく過程でメンバーを動機づけ、グループとしての一体感を形成すること機会となっています。
了
