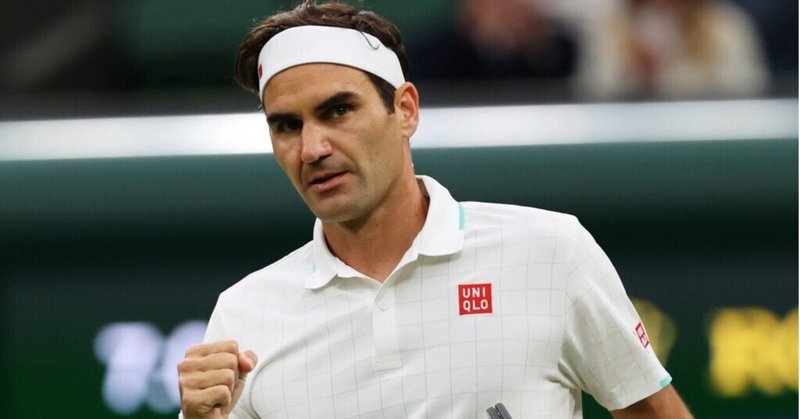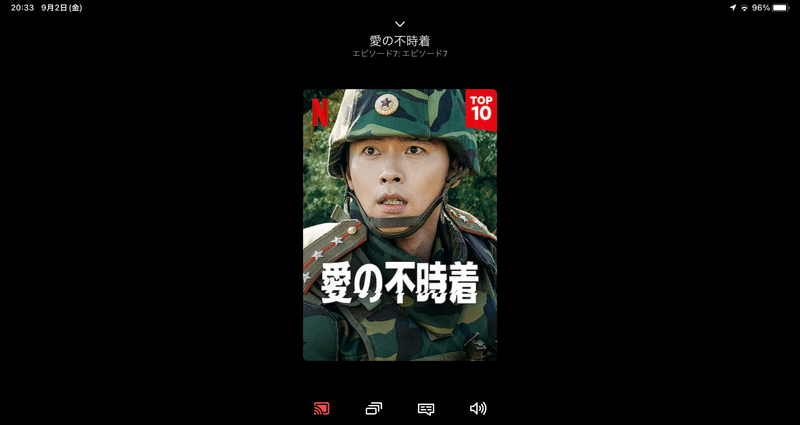
愛の不時着についての俵万智さんの記事「はにかみと思いやりのずらし話法」に触発されて、私もあのような素敵な文が書きたいと投稿を始めました。今は、韓国ドラマの他、自分の体験談や日頃思…
- 運営しているクリエイター
#今こそ学びたいこと

今日ときめいた言葉11ー「絶望を救うのは、日常そのものだけなのです。朝のコーヒーの一杯でもよい。何か人間らしいことによって、人は救われるのです」
(2023年1月1日付 朝日新聞 「誰もが孤独の時代 人間性失わないで」 スベトラーナ・アレクシエービッチさんの言葉から) 彼女は、「戦争は女の顔をしていない」で独ソ戦を戦った女性兵士の声を集めて戦場での生々しい現実を描いた作家で、ノーベル文学賞受賞者でもある。他にもアフガンに侵攻したソ連兵やその遺族、チェルノブイリの事故の遺族や被災者を取材して社会や時代の犠牲になった人々の声を作品にしてきた人でもある。 そんな絶望の淵にいる人々を見てきた彼女が、 「絶望を救うのは日常