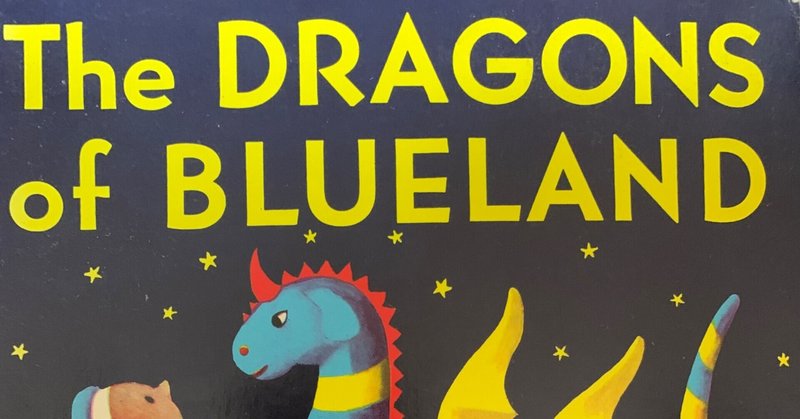- 運営しているクリエイター
2022年10月の記事一覧

今日ときめいた言葉5ー「市民たちには自由も意志もない場合は、恐れとへつらいが(投票を喝采に変えてしまい・・・)、崇拝するか、呪うかのどちらかになる😱」・・・独裁国家の行く末‼️
(タイトル写真はチェコにあるテレジン収容所墓地。アウシュビッツに送られる前の中継地。テレジンはマリア・テレジアから取られていると言う。かつてはオーストリアの要塞だったところだそうだ) (2022年10月19日付 朝日新聞「時事小言」ー共産党独裁の行く末はー藤原帰一氏の記事から) 上記の言葉は、中国の習近平国家主席の3期目就任時の演説会場を埋め尽くした大勢の参加者の光景を見ていて、藤原氏が思い出したジャン=ジャック・ルソーの言葉だそうである。 この言葉は、奴隷状態に置か