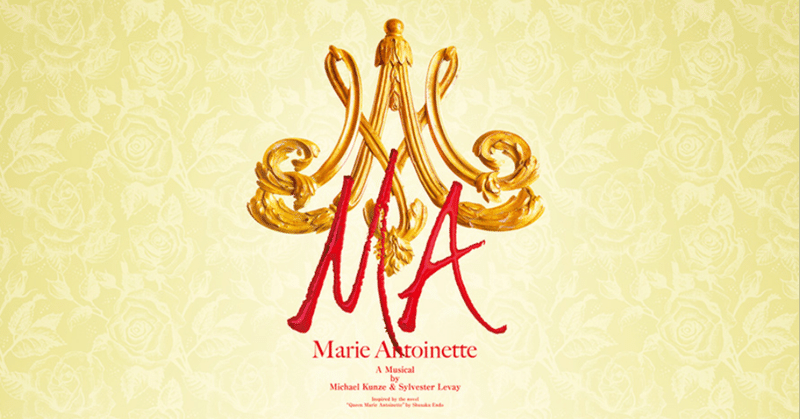
ミュージカル『マリー・アントワネット』
東急シアターオーブで上演されている『マリー・アントワネット』を観てきました。(スタッフ・観覧者は感染対策のうえ観覧しています)
本作は王族のマリー・アントワネットと市民のマルグリット・アルノーという2人の“M・A“を対比的に描く一部フィクションを含む作品となっています。とはいえ、基本的は史実をベースにしているためストーリーに安定感があり、かつ悲劇でありながら情緒的になりすぎないような演出を感じました。
『エリザベート』『モーツァルト!』を生み出したミヒャエル・クンツェ(脚本)&シルヴェスター・リーヴァイ(作曲)が日本オリジナルで作成して、2006年に上演された作品の新バージョンとして新たに準備されたそうです。
調べて知ったのですが、原作は遠藤周作の小説『王妃 マリー・アントワネット』とのこと。
私が観覧した回の主な演者さんたちは以下の通りです。
・マリー・アントワネット:花總まり
・マルグリット・アルノー:昆夏美
・フェルセン:甲斐翔真
・オルレアン:上原理生
・エベール:上山竜
(以下、ネタバレを含みます。また曲名・詞は可能な範囲で調べていますが、一部私の記憶に頼っている部分があるため誤っている恐れがあります)
◆ マリー・アントワネット 〜歴史の敗者は悪様に描かれる
マリー・アントワネットは1755年にオーストリアで生まれ、1770年に14歳でフランスへ嫁ぎ、ルイ16世と政略結婚。1789年にフランス革命で王位を追われ、1793年に37歳で処刑された。
フランス革命を、圧政に苦しむ市民が「自由・平等・友愛」の元に王政を廃止し、市民による共和国を樹立したという目線で見ると、王朝側の人間は悪者のように見える。マリー・アントワネットは結婚当時はその美貌から好意的に国民に受け入れられていたようだが、浪費家・我儘といった印象がつくにつれ、(フランス人からすると)外国人といった側面が打ち出され、より印象は悪くなっていったようで、現代に伝わる彼女の評判はあまり好意的ではない。
それは正しい面もあれば、おそらく敗者であるが故の印象操作により悪様に伝えられている面もあるのではないだろうか。(実際、「パンがなければケーキを食べればいい」という発言はマリー・アントワネットのものではない、との研究も出ている)
劇の冒頭、華やかなダンスパーティーでマリーがとてもにこやかに明るい声で歌う場面がある。
“望まれる王妃目指し、愛されるよう努めましょう。若い日の間違いを糧にして、王妃の鏡となってみせましょう“
(なんという王妃)
豪奢なドレス、華やかな音楽、満面の笑み。それだけ見ると王族・貴族の贅沢な生活が切り取られているかのように見えるが、歌詞を噛みしめてフランスへ来てからのマリーにどれだけの苦労と孤独があったのかと思いを巡らせてしまった。
母国オーストリアでは両親と16人の兄弟姉妹と過ごし、おそらく深い愛情を持って育てられてきた少女が、14歳で(おそらく言語・文化は多少学んだだろうが)異国に連れてこられて馴染むには、それは多大な苦労があっただろう。フランスの王族・貴族に馴染むべく、まさに「望まれる王妃を目指して、愛されるよう努力をして」、市民の生活などそれこそ把握する余裕もなく、ひたすら王妃としてどうあるべきかという見せ方に心を砕いてきたのではないだろうか。そしてそれを諌める人間も周囲には少なく、王妃として下にも置かない扱いだったのだろう。
だからこそ、夫であるルイ16世とは一定良い関係を築いていたと史実にはあるが、それでもなかなか世継ぎには恵まれない中で心労もあり、心の支えとして恋人フェルセンや女官長ランバルの慰めなくしては生きてこれなかったのではないかと思う。
良き王妃、良き母を目指しつつ、それでも恋に縋らざるを得ず、だからといって責任とプライドから恋だけに走ることも叶わず。そのマリーの不安定さが劇中を通して、死への覚悟を決めるまでの間、ひしひしと感じられた。
“なぜ神は彼女にすべてを与え、最期に地獄を見せたのか”
(マリー・アントワネット)
マリーの処刑を知ったフェルセンが歌うこの曲は、まさにマリーの人生を表しているようで印象深い。王族に生まれ、贅を尽くすことが許される生活をし、家族と恋人にも恵まれ、それでも最後には王宮も家族も恋人も、そして命さえも奪われた人生。
時代の変化といえば其れ迄であるし、施政者たるもの周囲の環境変化を素早く察知し、それに応じた政策展開は必要だろう。マリーは政治にも関与しないと宣言し、見せ方にばかり心を砕き、時代・市民の変化に気づくことはなかった。そして、それを諭すフェルセンの言葉に耳を傾ける思慮も足りていなかった。マリーはあくまでフェルセンに恋という名の慰めを求めていたかのようだ。(それが革命が激化する中で、マリーは思慮深く、フェルセンがマリーを救おうと躍起になる様も描かれる)
時は『法の精神』や『社会契約論』といった新思想が生まれ、それが印刷技術の発展によって市民にも広く広まり、自由を目指してアメリカ独立戦争が勃発していたにも関わらず。
“私の罪はプライドと無知。そして人の善意を信じすぎたこと。
今知りました。自分が何者か。
どうか遺された人々よ、復讐などせぬよう。
そして願う、我が子たちがあなたたちを恨まぬよう。
そして次の時代よ、真実を伝えて“
(革命裁判)
最初にあまり情緒的にはなりすぎない演出であると記載したが、それでもマリーが投獄された後、夫が処刑され、更には子供と引き離される場面は思わず喉が詰まった。それは、引き離されたルイ・シャルルの末路を知っているから尚更でもある。
◆ マルグリット・アルノー 〜民衆の狂気と自らの正義
私生児として生まれ、母は自分を残して自殺し、幼い頃から働いて、今は路上で暮らすマルグリット・アルノー。「ストラスブールで働いていた時、花嫁姿のマリーを見て、その差に愕然とした」というセリフがあるとおり、まさに同じ時代・世代で同じM・Aのイニシャルを持つ女性として、マリーの対比した人物として登場する。
勇気と知恵があり、同じく路上で暮らす人々のために盗みを働いては分けていく優しさもある。だからこそ、自分のため人々のためにと王宮に乗り込んでマリーに対峙したり、革命を扇動してゆく様は自然だ。
”100万のキャンドル煌めく世界で
この世の深い闇を見ようともしない人達
パリは泣いている。見捨てられたまま
苦しむ町を見ないふりして平気で踊るの
何故なの。それでいいの。気づいてよ、早く
変えるのはあなた、あなたたちでしょう
どうか、どうか闇に目を向けて
その目をそらすなら、許さない“
(100万のキャンドル)
けれども、マルグリットは女性であるがために男性からは「感情的でマリーに同情するだろう」「信じられない」とマリーの元へスパイとして送られる時に信頼されず、革命に声をかけた女性たちからも味方は生まれず、結局お金で動かすことに。当初は、そのように人々のために動きながらもその仲間として思想と行動を共にすることがない歯痒さが描かれる。
それでも革命が激化するにつれ、徐々に民衆は日頃の鬱憤ばらしをするかのように貴族の虐殺を始めてゆく。民衆はマリーの女官長ランバルを襲撃し首を晒し物にし、マリーの革命裁判では「ルイ・シャルルをベッドで一緒に寝た」との誹謗中傷が平然と行った。
自らが正義と信じて革命の先頭を走っていたマルグリットが、革命が拡大する中でそこに参加する民衆との温度差を徐々に感じ、戸惑いを覚える様子が痛々しく伝わってきた。加えて、フェルセンが誠実に対等な人としてマルグリットに接するからこそ、更にマルグリットは「王族 対 市民」そして「悪 対 正義」という二項対立では分けきれないことを理解したのではないだろうか。
“この世の七つの悪徳を七倍にすればいい
七つとは 金銭欲 虚栄心 愚かさ 厚かましさ 情欲 復讐心 そして憎しみ
そうすれば権力さえ倒せる“
(七つの悪徳)
革命は一方で自由・平等・友愛を掲げられつつ、他方でそれに乗じて七つの悪徳が渦巻く物であった。
それゆえ、マルグリットはマリーのスパイとして傍につく過程で、当初はお互いが「私のこと知らないくせに」と言い合う間柄でお互い憎しみあっていたが、民衆への戸惑いを抱くのと並行して、マリーへ抱く感情も変化していったように思う。
投獄されたタンプル塔で、マリーが子どもたちに「父の歌」である子守唄を歌う場面。聖母のように優しく労りを持って子どもたちに接するマリーの姿を見て、マルグリットは自らの母は自分を捨てる人間であったのと比べ、はっと何かを悟るかのような表情を浮かべていたように思う。マリーも人間なのだと。
(共に「父の歌」を知っていることから異母姉妹であることが判明するのだが、故に異母姉妹であるにも関わらず、ほんの少しの差異で全く異なる人生を歩まざるを得ない残酷さを感じる)
“遠いあの空に流れ星ひとつ 願いごとをすれば叶うきっと
昨日の悲しみも優しい夢で いつか微笑みに変わるきっと
だからおやすみ 叶うと信じて あの星の彼方 明日は幸せ“
(明日は幸せ)
マルグリットは最後に自らの正義として、革命裁判ではマリーの誹謗中傷に対抗し、またマリーの死後、オルレアンが権力欲しさに革命を企て、ジャーナリストのエベールがお金欲しさにそれに追随したことを告発するのである。
◆世界を変えられる 〜後世にいかに繋げるか
フランス革命は世界を変えた。けれども、それは血で血を洗う戦いであった。
王政下では王族・貴族が市民を「動物のように」虐げ、革命で市民が王族・貴族を「獣のように」虐殺してゆく。一方がもう一方を虐げる構図は、暴力の連鎖となって、復讐の連鎖を生む。まさに、マリーが革命裁判で訴えたように。
“どうすれば変えられる この世界を私たちで
正義と自由、掴めるか
人を許せるのか
平等とは何か
暴力の連鎖は終わるか
その答えを出せるのは我ら“
(どうすれば世界は)
印刷技術が発展し、安価に早く多くの人々に同じ情報を届けられるようになったことで、事実も悪意のある噂も、簡単に人々に知れ渡る時代になったのがマリーとマルグリットが生きた時代であった。
王族・貴族の言動はジャーナリズムという名のもとで風刺も加わり、広く市民に素早く広まる仕組みだ。同様に、市民の革命活動も。
王族・貴族の醜聞は革命を正当化させ、革命の躍進は市民に勇気を与えたことだろう。たとえ、その醜聞の一部は悪意をもって作られたものであろうと、革命の躍進は七つの悪徳と共に民衆の狂気を孕んでいたとしても。
現代においては、情報端末とSNSが普及して、個人が安価に早く多くの人々に同じ情報を届けられるようになった。有名人の一挙一動が取り沙汰され、フェイクニュースが生まれ、自分は情報(善意・悪意)を届けやすいと同時に当人にも情報が受け取られやすい仕組みだ。
マリーとマグリットの生きた時代は過去であり、革命は過去のもの、ミュージカルは娯楽だと受け止めることもできる。他方で、これは現代に通じる物語でもある。
正義 対 悪の二項対立は分かりやすい。良い・悪いも、好き・嫌いも分かりやすい。
けれどもマリーとマルグリットがお互いを「知らないくせに」と言い合うように、直接触れ合うまでは簡単に対立させられたものが、知れば知るほど簡単には対立させられなくなる。
世界は変えられる。けれども安易な決めつけと徒党は民衆の強気と狂気に変わり、暴力と復習の連鎖を生む。
『マリー・アントワネット』を通じて、知る努力を胸に刻み、民衆(群れる)の恐ろしさを忘れずにいたいと思う。
