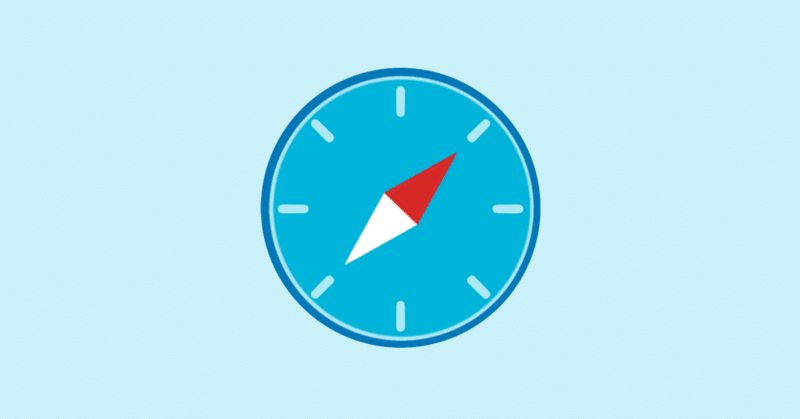
ヨーロッパの大陸の形状から、チームとしての共通目標の重要性を学べる話
このnoteは、東大野球部に学生スタッフ兼アナリストとして所属する私、齋藤周(Twitter→@Amapenpen)が、日々の練習内容や気づいたことをメモしておくためのものです。
練習再開
昨日からふたたび練習が再開しました。引退までの日数もあと百数十日しかありません。終わりを常に意識することで、わずかな時間も大切にしながら野球に向き合っていく所存です。
さて今年の東大では、「チーム全体で意識するテーマ」みたいなものがいくつかあります。
打撃の意識とか守備の考え方とか、練習や試合の中でみんなで意識してやっているのですが、今回はこうしたテーマを設定することの長所と短所について考えているところを書こうと思います。
チームテーマを設定するメリット
「銃・病原菌・鉄」という本があります。東大の書籍部の売れ行きランキングでもランキング上位の常連になっている、わりかし人気の高い本です。
この本の中におもしろい話があって、「ヨーロッパ人が世界で覇権を握ることができたのは、ヨーロッパの大陸が横に長かったからだ」と書かれているのです。
どういうことかというと、
ヨーロッパの大陸は他の大陸と比べて横に長い
→同じような気候の場所がたくさんある
→同じ穀物種をたくさんの場所で育てられるので、食糧生産に関する知見が貯まりやすい
→食糧生産技術の発展スピードが速くなる
→他の大陸よりも多くの人口を支えられるので軍事的に強くなる
→世界的な覇権を握る
みたいな感じです。めちゃくちゃざっくりですが。
で、野球においても「チーム全体として意識するテーマ」を作ると、これに似た現象が起こります。
つまり、みんなが同じテーマに取り組むので、うまくいく方法を共有したり上手にできている人をお手本にすることで、高速で知見が蓄積され、技術の向上スピードが速くなるのです。
そういう意味で、選手間の情報共有がスムーズに行われていれば、チームとしてのテーマがあることはかなりメリットがあるように感じています。
チームテーマを設定する難しさ
一方で難しいのは、チーム全員の最大公約数となるようなテーマを設定することです。
すごく極端な例で言うと、柳田選手と周東選手ではあまりにタイプが違いすぎるので共通のテーマを設定しづらいし、無理やり設定したとしても漠然としたテーマになりやすいよね、みたいな感じです。
ただ、今年の東大野球部はわりと選手のタイプが似ていて、ホームランをたくさん打つ選手とかがいるわけでもないので(いたらそれに越したことはないのですが)チーム共通のテーマを設定しやすい、みたいなところはあると思っています。
なので、特に飛び抜けた選手がいるわけではない公立高校とかでも、こうしたチーム共通のテーマみたいなものを作って練習や試合に取り組むのは、かなり有効なのではないかと思います。ぜひ試してみてほしいです!
そんなわけで、秋に向けてチーム一丸となって練習してまいります。春からの伸び率がトップだと言われるような、そんなチームにできるよう頑張ります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
