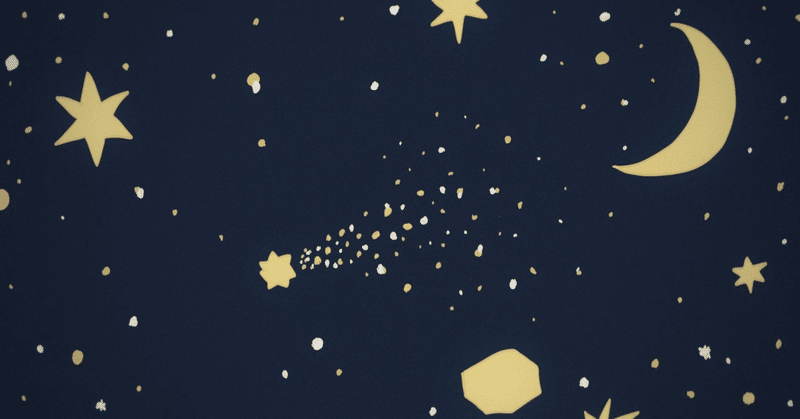
「最上階へのエレベーター」2000字小説
「はいアクション!」と監督が吠えて、僕は女優を抱きしめた。彼女が腕の中でセリフを言う。
「こんなことだめだよ、ひかるくん」
棒読みもいいところだ、そんなだからモデル出身のレッテルをいつまでも剝がせないんだ君は。このドラマは深夜枠で、源氏物語を現代版にリメイクしたという安っぽい脚本。僕が主演でなきゃ到底成り立ってない。
付き飛ばされるシーン、視界が揺れた。リハよりも力が強いな。打った尻が痛い。タイトスカートにパンプスで走りづらそうな彼女の肩を掴み、「宇津美! おれを拒まないでくれよ」夜のオフィスで陳腐なセリフを大真面目な顔して吐きながら、ちょっとさっきの仕返しがしたくなってきた。「いいじゃん、誰も見てないんだから」と付け足すと、手の中で華奢な肩が少し震える。カメラに映らない小さな動揺。急なアドリブに戸惑った訳ではないだろう、きっと、彼女も僕と同じ景色を思い出しているのだ。
「誰も見てないんだから」。これは三年前パークハイアット東京のスイートルームで、シャンパンに頬を赤らめた彼女、美優に囁いた言葉だ。いじらしく抵抗してワンピースの背中にあるジッパーをなかなか下ろさせてくれなかったが、甘い声で囁けば、瞳を潤ませて「でも、」と言いながらもこちらに身をゆだねた。
薄い体でスーツに着られた美優がこちらを振り向き、「でも、」と眉を綺麗にひそめる。あの時よりも大人になった女の香りと切実さに、三年という時の大きさを突き付けられて、僕はよろめきそうになった。交際を始めた途端、結婚ばかり迫まってくるのを煙たがらなければ、この綺麗な女が今も自分の傍にいてくれたのだろうか。「カット!」の声がかかっても、彼女の上目遣いの綺麗な表情が頭から離れなかった。
「監督があのシーンの演技を褒めてくれたんです。特に表情が良かったって」
打ち上げの場で、両手にワイングラスを持った美優がさりげなく隣にやって来て言った。
「引き出したのは誰だよ、感謝してほしいな」
こういう場で出るワインは安物なうえ、酸化していて不味いと思いながらも、彼女を見やると、「もちろん、綾人さんのおかげですよ」とグラスを煽る鼻筋の通った横顔に、きらびやかな夜景の見えるホテルでの夜を思い出す。服の下の細いくびれと柔らかい肌も。
「今、彼氏はいるの?」
「……あれ以来いないです」
含みを持たせた言い方は、つまり、僕を忘れられなかったということだろうか。子首を傾げる仕草が可愛いし、彼女の寂しさを埋めてやりたくなる。そういえば、ふたりで何度も落ち合ったスイートルームは、この打ち上げ会場のあるホテルの最上階である。お互い意識していないはずがない。彼女の左手の小指に、そっと指を絡ませると、当然、拒否は無かった。部屋は泊まるつもりでマネージャーに手配させてある。
「じゃあ、僕でいいよね?」
「えっ」
大人の恋に駆け引きはいらないんだ。酔った監督が恋愛論を大げさに語っている横を会釈だけして足早に過ぎ、美優をエレベーターの箱に押し込む。こうなる予感は再会したときから確実にあった。待てずに唇を重ねる合間に、彼女は言った。
「わたし、嬉しい。このドラマが最後って思ってたの、役者やめようって。でももっとがんばってみようかな」
それ以上は唇を塞がれて彼女は喋れなかった。エレベーターは最上階へと昇る。
翌朝、うるさい着信音で目を覚ました。早くに出たのか、ベッドには彼女のぬくもりすら残っておらず、物足りない気分になる。電話の向こうでマネージャーが声を荒げた。
「綾人さん、いい加減にしてください。売名行為に利用されたんですよ。こっちは後始末が大変なんだから!」
送られてきたURLをスマホ画面を叩くようにして見ると、ベッドに寝そべる美優と僕の白黒写真に、ネットニュースの下品な見出しがついていた。世間で名の通った俳優と寝たモデル出身女優。彼女が自分で情報を売ったのだろうか。この記事で美優が注目を浴びることは間違いなかった。
投げたスマホが耳障りな音をたてて床を転がる。彼女の笑顔、甘い再会、あれは全てうそだったのか。自分で抱いた幻想にこんなに反吐が出そうになったことはない。
僕は広いベッドにただ横たわり、心臓の音を聞きつづけていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
